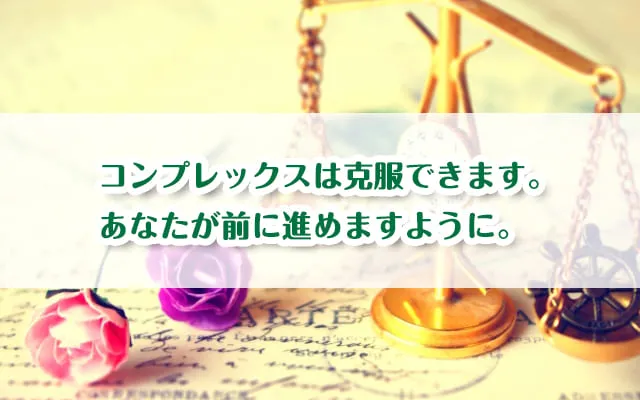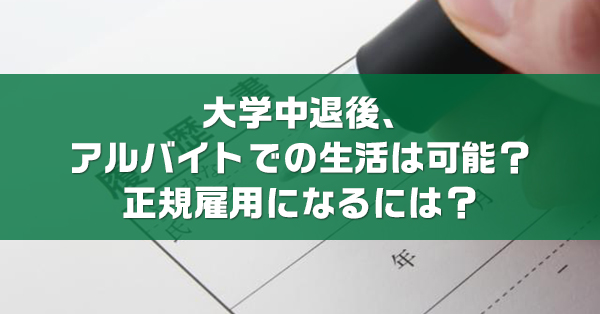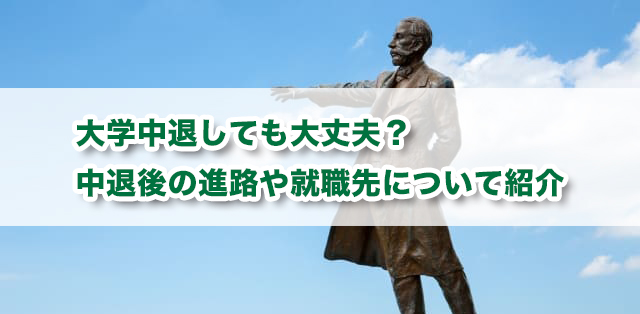大卒と高卒の違いとメリットとは? 就職できる仕事や生涯賃金、求人状況などを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
高校生になると、卒業後の進路を、就職か大学進学か迷う人が多いのではないでしょうか?
このコラムでは、大卒と高卒の違いやそれぞれのメリット・デメリットなどを解説します。
きっと、高校卒業後のあなたの将来を考える参考になると思います。
ただし、このコラムはあくまで一般論であり参考です。
「実際のあなた」の決断をどうするかは、このコラムの内容も参考にしつつ、周りの人などにも相談してからじっくり考えましょう。
また、「高卒で働き始めて、その後で大学(短大・専門学校など)に行く」「大学に進学したけれど、やっぱり中退して働き始める」といったことも可能です。
高校在学中に卒業後の進路をしっかり検討することはもちろん大事ですが、「高校在学中に決めた進路や、一度進んだ道は、その後に変更できない」というものでもありません。
しっかり考えながらも、思いつめすぎないようにしましょう。
私たちキズキ共育塾は、大卒を目指す人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
大卒と高卒の違い〜就労の観点から〜

大卒と高卒には、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
この章では、大卒と高卒の違いを、就職できる仕事や生涯賃金、求人状況など就労の観点から具体的に解説します。
違い①就職できる仕事〜高卒では就けない仕事がある〜
高卒の場合、特に新卒時点では「就職できない仕事」があります。
例えば、銀行、商社、マスコミなどの「大企業の総合職」のほとんどが、求人対象を「大卒(以上)」に限定しています。
逆に、「高卒(以上)」という求人には、大卒の人も応募できます。
他にも、例えば医者のような「資格が必要な職業」になるためには、関連する大学・学部を卒業し、国家試験に合格する必要があります。
大学教授や研究職なども、大学院の修士課程以上(の知識)が条件の場合が多いので、大卒でないと目指すことは難しくなります。
このように、大卒でないとなれない、または難しい職業があります。それらの職業を目指すのであれば、大学に進学する必要があります。
ただし、高卒で働き始めた場合でも、業界で経験を積んだ後に、「中途採用」として「新卒時には応募できなかった仕事」に就職できることはあります。
高卒で就ける仕事の具体例については、こちらをご覧ください。
違い②就職率〜景気などによって変わる〜
大卒と高卒の就職率については、景気や年度、地方などによっても変わるため、一概には言えません。
例えば、いわゆるリーマンショックの影響が大きかった2009年3月・4月では、「卒業直後の就職を希望していた人たち」の就職内定率は、次のようになっていました。(参考:厚生労働省「平成20年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成21年3月末現在)について」、厚生労働省「平成20年度大学等卒業者の就職状況調査(平成21年4月1日現在)について」)
- 大卒:約95.7%
- 高卒:約95.6%
一方で、2023年の調査では、次のとおりです。(参考:文部科学省「令和5年3月高等学校卒業者の就職状況(令和5年3月末現在)に関する調査について」、文部科学省「令和5年3月大学等卒業者の就職状況」、厚生労働省「令和4年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ(令和5年3月末現在)」、文部科学省「令和4年度大学等卒業予定者の就職状況調査(4月1日現在)」)
- 大卒:約97.3%
- 高卒:約98.0%
大卒の方が高いときも、高卒の方が高いときもある、ということです。
ただし、以上の調査は全数調査ではありません。また、「望んでいた職種に就けたか」「待遇はどうか」などというデータは、以上の数字からはわかりません。
こうしたことから、「就職率」という観点は、大卒・高卒のどちらがよいかという判断の基準にはあまりならない、と言っていいのではないでしょうか。
なお、参考までに、2022年3月の、高校の学科別の「卒業直後に就職を希望していた人たちの就職率」は、高い順に以下のとおりです。(参考:文部科学省「令和4年3月高等学校卒業者の就職状況(令和4年3月末現在)に関する調査について」)
- 工業科:約99.4%
- 水産科:約99.2%
- 商業科:約99.0%
- 看護科:約98.9%
- 農業科:約98.8%
- 福祉科:約98.1%
- 家庭科:約97.9%
- 総合学科:約97.9%
- 情報科:約97.6%
- 普通科:約95.8%
専門的な学科の場合の方が、少しだけ就職率が高くなっています。
「工業科」と「普通科」で最も差があり、工業科の方が約3.6%高い、という結果です。
同じ高校生同士でも、職業に直結する知識や技術がある方が、高卒就職に若干有利になることが多いようです。
違い③初任給〜大卒の方が高い〜
初任給(=就職してから初めてもらう給料)については、ほとんどの会社で大卒と高卒で差があり、大卒の方が高くなっています。
厚生労働省の調査によると、2019年の平均初任給は、大卒は約21万200円、高卒は約16万7400円と、約4万2800円の差が見られました。(参考:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概要:1 学歴別に見た初任給」)
違い④生涯賃金〜大卒の方が高い〜
生涯賃金とは、「新卒から定年までの間にもらう給料(・ボーナスなど)の合計」のことです。
高卒の場合は、高校卒業直後に就職するのであれば、最短で大卒より4年早く就職します。しかし、「生涯年収は大卒の方が高い」というデータがあります。
2022年に発表された統計である「ユースフル労働統計」から、就職してから定年を迎えるまでにもらえる生涯賃金と学歴の関係を紹介します。
学校を卒業後にフルタイムの正社員として勤務を続けた場合の60歳までの生涯賃金(退職金は含まない)は以下のとおりです。(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2022」)
大卒の場合
- 男性:約2億6000万円
- 女性:約2億1000万円
高卒の場合
- 男性:約2億1000万円
- 女性:約1億5000万円
大卒と高卒を比べると、男性で約5000万円、女性で約6000万円、大卒の方が高くなるのです。
高卒の方が4年早く就職しているのにもかかわらず、「生涯賃金は大卒の方が高い」ということが言えます。
ただし、これは「いろいろな職場の全体的な平均」の数字です。
職場によっては「大卒と高卒であまり給料は変わらない」「高卒の方が早く働き出した分だけ出世が早く給料が高い」というケースもありえます。
また、異なる企業の比較では、高卒の方が高いこともあります。詳しくはこちらをご覧ください。
違い⑤求人状況〜業界によって求人対象が異なる〜

大卒と高卒では、求人対象となる会社や職種にも違いがあります。
高卒の求人数のうち、2023年9月時点の上位5位までは、以下のとおりです。(参考:厚生労働省「令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ(9月末現在)」)
- 製造業:13万8642人
- 建設業:7万8092人
- 卸売業・小売業:4万8856人
- 医療・福祉:4万1815人
- 運輸業・郵便業:2万8197人
一方、大卒は以下のとおりです。(参考:リクルートワークス研究所「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」)
- 流通業:約28万3100人
- 製造業:約27万5800人
- 建設業:約11万6800人
- サービス・情報業:約8万7200人
- 金融業:約1万人
異なる調査であり、ともに「全ての求人についての調査」ではないのですが、傾向としては参考になります。
大卒・高卒ともに、「製造業」「建設業」は5位内に入っていますが、それ以外は重複していません。
「将来的に、あの業界に行きたいな」という希望があるのなら、その業界または会社が大卒・高卒に対してどのような求人を行っているのかを確認しておきましょう。
また、特に希望がない場合も、「各業界の求人状況」を調べるうちに、行きたい業界や行きたくない業界が見つかり、そこから「高卒で就職するか」「大学に進学するか」という方針も見えてくると思います。
もちろん、「今時点での求人状況」と、「あなたが実際に就職活動を行うときの求人状況」は違う可能性はあります。
ですが、調べたり、学校の先生に聞いたりすることによって、大卒と高卒の就労に対する違いの理解が深まります。また高卒で就職するか大学に進学するかの参考にもなっていきます。
違い⑥福利厚生〜学歴では変わらない〜
給料以外の待遇については、給料について差がある会社も、それ以外の待遇(=福利厚生)などに関しては、基本的に差がありません。
交通費、有給休暇の日数、住宅手当などの各種手当は、大卒も高卒も分け隔てなく、同じように与えられます。
差がある場合は、学歴ではなく、「正社員か派遣社員か」といった働き方の違いによる部分が大きいでしょう。
違い⑦出世〜大卒の方が早い〜
「出世」においては、大卒と高卒で違いがあります。
一般論としては、大卒の方が、入社後に出世するスピードが早く、昇進のチャンスも多くあります。
特に大企業にその傾向が強く、そもそも大卒の人が多いので、高卒で役職に就くのは狭き門になっています。
先ほども紹介した「ユースフル労働統計2022」によると、2021年現在、10人規模以上の会社では、課長も部長も大卒の方が多くなっています。(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2022」)
しかし、これも「一般論」です。
個別の会社によっては当然異なるでしょう。また、最近では学歴に関係なく能力で評価する会社も出てきています。
特に中小企業には柔軟な対応をする会社もあるので、高卒だと絶対に不利である、というわけではありません。
他にも、営業職や成果報酬型の仕事の場合は、出世も給料も、学歴よりも能力や結果が重視されることも珍しくありません。
そして、大企業でも、高卒で入社してその後社長になる人もいます。
例えば、大手旅行会社であるHISでは、高卒で入社した平林朗さんが、入社後に昇進を続けて40歳で社長に就任しています(現在は退任済み)。(参考:観光経済新聞「HIS社長に40歳の平林朗取締役」)
「高卒の誰もが、どんな業界や組織でも、大卒以上に出社できる」わけではないことは、残念ながらデータからも明らかです。
ただ、繰り返すとおり、あくまで一般論であり、「絶対に無理」というわけではありません。
逆に、「大卒だから」といって、高卒の人よりも絶対に待遇がよいとは限らない、ということでもあります。
違い⑧転職市場〜実績・実務経験から高卒が有利になることも〜
高卒は大卒に比べて、転職市場においては有利になる場面もあります。
なぜなら、高卒の方が大卒よりも4年早く就職し、その分多くの社会人経験を積んでいるからです。
転職の際には、主にこれまでの実績・実務経験が問われます。
高卒の方がより多くの仕事経験を積んでいる分、面接相手にその面では効果的なアピールをすることができます。
また、新卒時には大卒が必須な会社でも、転職時には実績があれば学歴を問われないこともあります。
ただし、「学歴は関係ない」「高卒の方が必ず有利」というわけではありません。転職時にも、大卒の学歴を求める求人は珍しくありません。
求人によって、求められる条件は異なるため、希望の転職先を確認しましょう。
生涯賃金についての補足〜異なる企業の比較では、高卒の方が高いことも〜
こちらでも解説したとおり、生涯賃金は、一般的には高卒よりも大卒の方が高い傾向にあります。
しかし、先ほどと同じデータのうち、企業規模による分別では、また違った結果が見られます。
高卒の人の方が大卒よりも高くなる場合もあるのです。
まず「大卒の男性」の場合、企業規模が1000人以上では「退職金を含まない60歳までの賃金」の平均は約3億1000万円に達するのに対し、企業規模10人から99人だと平均約2億円です。
同じ「大卒の男性」でも、職場によって1億円以上の開きがあるということです。
大企業には給与が高いところが多いですが、これは大卒に限ったことではありません。
高卒で大企業に就職した人は、大卒で中小企業に就職した人よりも、長いスパンで見ると給与が高い場合も珍しくないのです。
例えば、次の二つの場合はどうでしょうか?
高卒男性が1000人以上の会社規模で働き続けた場合
- 退職金を含まない60歳までの賃金の総額:約2億6000万円
- 退職金や61歳以降の賃金も含む総額:約3億1000万円
大卒男性が10から99人の会社規模で働き続けた場合
- 退職金を含まない60歳まで賃金の総額:約2億円
- 退職金や61歳以降の賃金も含む総額:約2億6000万円
60歳まででも、その後でも、高卒の方が約5000万円〜6000万円高い、という結果になります。
なお、先ほどの厚生労働省のデータでは、全ての企業規模で、「大卒の方が高卒よりも高い」というデータが現れています。(参考:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概要:1 学歴別に見た初任給」)
つまり、「大卒と高卒を全体的に見ると、初任給や生涯賃金は、一般的には大卒の方が高い」「ただし、異なる職場の生涯賃金を比較すると、必ずしも大卒の方が高収入というわけではない」ということです。
また、高卒でも高い給与を得ていくためには、最初から大企業で働くことの他にも以下のような方法があります。
- 専門的な知識や技術を身につけていく(例:資格取得、専門学校・職業訓練校で学ぶ)
- 経験を積んでスキルアップする(例:よりよい会社に転職、副業・兼業をする)
- 成果主義の企業で働く
大卒の方が職業選択の幅が広く、平均的には給与も高いのは事実です。
しかし、「大企業に就職する」「成果主義の会社で出世する」など、高卒であっても高い給与を手にする方法はあります。
大卒のメリットとデメリット・注意点
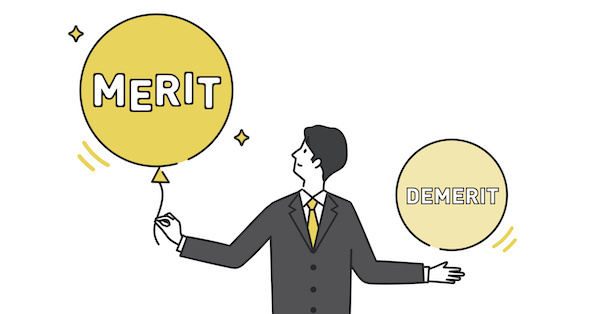
この章では、就労以外の視点から、大卒のメリットとデメリット・注意点をご紹介します。
大卒のメリット①「学術的な知識や経験」が身につく
大学に通うことで、「学術的な知識や経験」を身につけることができます。
文学、法学、政治学、工学、理学など、興味のある分野の知識が身につくことは、直接的に就職に結びつく以外にも、知的好奇心を満たし、自分を高めていくことができます。
大卒のメリット②自由な時間を活用できる
学校・学部にもよりますが、大学生には、高校生や社会人よりも自由な時間が多くあります。
「授業で学ぶ」以外にも、自由な時間を活かして、自主的に勉強を行う、サークル活動に取り組む、アルバイトやボランティアをする、交友関係を築くなどで、人生経験を積むことができるのです。
特に将来のことをゆっくり考えたい人にとっては、大学での4年間は貴重な時間になると思います。
また、こちらも学校にもよりますが、大学は、夏休みなど休暇期間が長いので、長期の旅行を楽しむこともできます。
ゴールデンウィークやお盆休みなどの「料金の高い時期」を外して計画できるので、安く済ませることができるのは学生ならではのメリットでしょう。
短期留学やワーキングホリデイもできるので、外国の生活に触れながら外国語の勉強や仕事ができるのも楽しみのひとつです。
就職以外にも「将来自分のやりたいことがわからない」という人も多いですが、以上のような大学生活を通じて見つけることもできます。
筆者自身も、高校生のときは、将来目指したいものがありませんでした。
大学進学の理由の一つには、「やりたいことを見つけるための時間がほしい」ということもありました。
そして私は、実際に大学での勉強やアルバイトを通して、自分を見つめ直す機会がたくさんありました。大学の先生や先輩方から頂いたアドバイスによって、将来の方向性を見出すこともできました。
大卒のデメリット・注意点①学費が高い
最も大きな大卒のデメリット・注意点は、高い学費を払う必要があるという点です。
国公立の大学の場合、入学金から授業料などの「大学に払う金額」の合計は、一般的には次のとおりです。
- 入学金:約28万2000円
- 1年間の授業料:約53万5800円
- 4年間に必要なおおよその費用:約242万5200円
国立大学は、文部科学省の省令によって入学金と授業料の基準額が定められていますが、国立大の法人化によって、大学によって差があるのが現状です。(参考:文部科学省「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」)
一方、私立大学の場合は、2021年度現在、入学金・施設設備費・授業料の4年間の平均金額は次のとおりです。(参考:文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額(定員1名当たり)の調査結果について」)
- 文系学部:約407万9015円
- 理系学部:約551万1961円
- 医歯系学部:約1633万3322円
一般的には、私立大学の方が、国立大学よりも費用が高いです。
また、国立・私立を問わず、大学に通うとなると、授業に必要な教科書や書籍代、一人暮らしの場合は家賃・光熱費などもあり、多額な費用が必要となります。
経済的に困難な場合は奨学金を利用することもできますが、大学を卒業後に返済を行う必要があるので、金銭的に負担があること自体は変わりありません。
大卒のデメリット・注意点②ダラダラ過ごす可能性がある
大卒のメリットとして「在学中に自由な時間を活かせる」ということをご紹介しましたが、逆に、自由な時間がある分、ダラダラ過ごす可能性があります。
また、自由な時間がなくても、授業などをついついサボってしまうことも珍しくありません。
大学進学時点では、学力や知的好奇心があったとしても、ダラダラ過ごしているうちに、次第に大学にも行かなくなったり留年したりして、自分でもどうしたらいいのかわからなくなることもあります。
ダラダラ過ごしたり留年したりすることが「絶対にダメ」とは言いません。長い人生、そういう時期もあるでしょう。
ただ、「不本意にそうなること」はできれば避けたい、というのも事実ではないでしょうか。
特に一人暮らしの場合は、自由な時間が逆効果とならないよう、自分を律する必要があります。
これは、「大卒の」というよりは「大学進学の」デメリット・注意点かもしれません。みんなに必ず生じるデメリット・注意点というわけではありませんが、留意しておきましょう。
高卒のメリットとデメリット・注意点
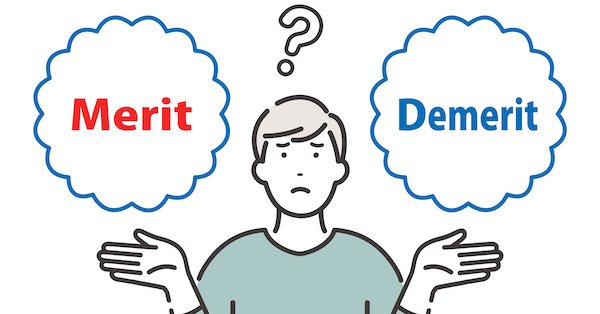
高卒の場合、メリットとデメリット・注意点はどのようなものがあるでしょうか?
高卒のメリット①大学の学費が必要ない
高卒の場合、大学に行かないので、学費を払う必要がありません。
さらに、高卒直後に就職した場合は毎月お給料がもらえるので、同じ年齢で大学に通っている人よりも金銭的に恵まれている場合もあります。
高卒のデメリット・注意点①学歴コンプレックスを抱くことがある
高卒のデメリット・注意点として、「学歴コンプレックスを抱くことがある」という点があります。
「必ず抱く」というわけではありませんが、「可能性としてはある」ということです。
高卒ですぐに就職した人は、大卒の人より4年早く社会人として働き始めます。
早く仕事を覚え、戦力として活躍しているのにもかかわらず、後から入ってきた大卒の人が先に出世したり、お給料が大卒の人より低かったりするのであれば、落胆することもあるでしょう。
職場以外でも、学歴コンプレックスを感じることはあります。
私の知人の話ですが、同じ高校の同窓会に出席した際、ほとんどの人が大卒で、高卒だと話についていけず、寂しい思いをしたそうです。
その他に、結婚をする際の条件として大卒を挙げる人も、珍しいとは言えないでしょう。
人の価値は学歴だけではありませんし、そもそも「高卒の人は、大卒の人よりも劣っている」というものではありません。
とはいえ、何かしらのきっかけでコンプレックスを抱くことがあるのです。
しかし、仮に仕事で学歴コンプレックスを感じるのであれば、学歴に関係なく出世のチャンスがある会社に転職し、再スタートを切ることもできます。
既存の会社にとらわれず、自分で起業すれば、学歴は関係なくなります。
何かの技術を身につけていれば、フリーランスとして活躍することもできます。
また、改めて大学に進学することも可能です。
学歴コンプレックスの解消法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
高卒で就ける仕事の具体例
「大企業には大卒でないと入りにくい」「大卒の方が求人数が多い」のは事実です。
しかし、高卒であってもさまざまな職業の選択肢があります。
たとえば、以下のような仕事であれば、高卒向けの求人も見つけられます。
- プログラマー
- 営業
- 建設作業員
- 配送員
- 飲食店スタッフ
- アパレルスタッフ
- 介護職
また、資格や経験が必要にはなりますが、高卒であっても以下のような職種を目指していくことができます。
- 保育士
- 医療事務
- ITエンジニア
- 建築士
- 公認会計士
以上のように、高卒であってもさまざまな職業の選択肢があります。
あなたが興味ある職業によっては、むしろ高卒で働くほうが早く現場に出れる場合もあるでしょう。
自分が興味ある分野、職業についてしっかり考え「大卒がいいか、高卒でも大丈夫か」を検討していきましょう。
大卒と高卒で、人間性や考え方に違いが出る?

結論からいうと、高卒か大卒かによって人間性の上下は決まりません。
物事の考え方については、相対的に「高卒の人は実践的な考え方の人が多い」「大卒の人は理論的な人が多い」と言われることもあります。しかしそれも、かなり大きな個人差があります。
なので、大卒か高卒かで、見ている世界が違うということにはなりません。
実際に社会に出て仕事をし始めるとわかりますが、相手が高卒か大卒かという違いは、一目ではわからないものです。
大卒、高卒という括りは人間性とは関係ないので、他人に「高卒だから(大卒だから)〜だ」といったようなことを言われても気にする必要はありません。
人間性は「何を大切にしているか」「相手のことをどれだけ思いやれているか」といったことで決まってきます。
あなたが、良い人間性を持ちたいと思うのであれば、高卒・大卒ということは気にせず「自分にとって何が大切か」「相手に対する思いやりの気持ちを持てているか」といったことを考えて、行動してみましょう。
まとめ〜あなたが自分自身で納得できる進路を考えてみましょう〜

大卒と高卒では、それぞれメリットとデメリット・注意点があります。また、一口に大卒、高卒と言っても、個別の状況は全く異なります。
大前提として、人の価値は学歴で決まるものではありません。
高卒であれ大卒であれ、さまざまな経験を積んだり、楽しく生きていくことは十分に可能です。
とはいえ、「高校卒業後の進路をどうするか」というのは、できれば「自分に合った進路」を選びたいところですよね。
いずれにしても、あなた一人で悩みを抱えないでください。家族、友人、先輩、先生など、詳しい人や仲のよい人にも相談してから決断するようにしましょう。
その上で、あなたが自分自身で納得できる進路を考えてみましょう。その進路には大卒資格がいるかもしれないし、高卒で問題ないかもしれません。
このコラムが、あなたの高校卒業後の進路を考える参考になれば幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える人のための個別指導塾です。
相談は無料です。相談や授業では、「高校卒業後の進路をどうするか」といったお悩みについて、一緒に考えていくことができます。
キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください。
Q&A よくある質問