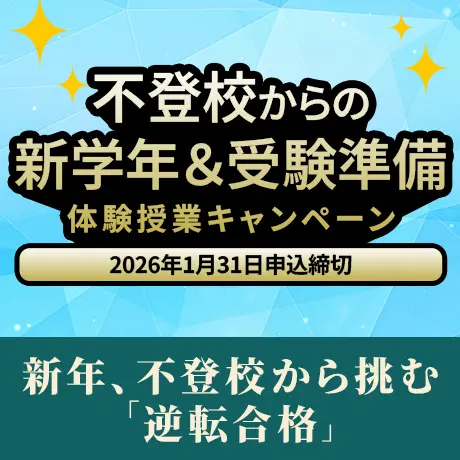学習塾には行かないほうがいい? 行ったほうがいい人の特徴を解説
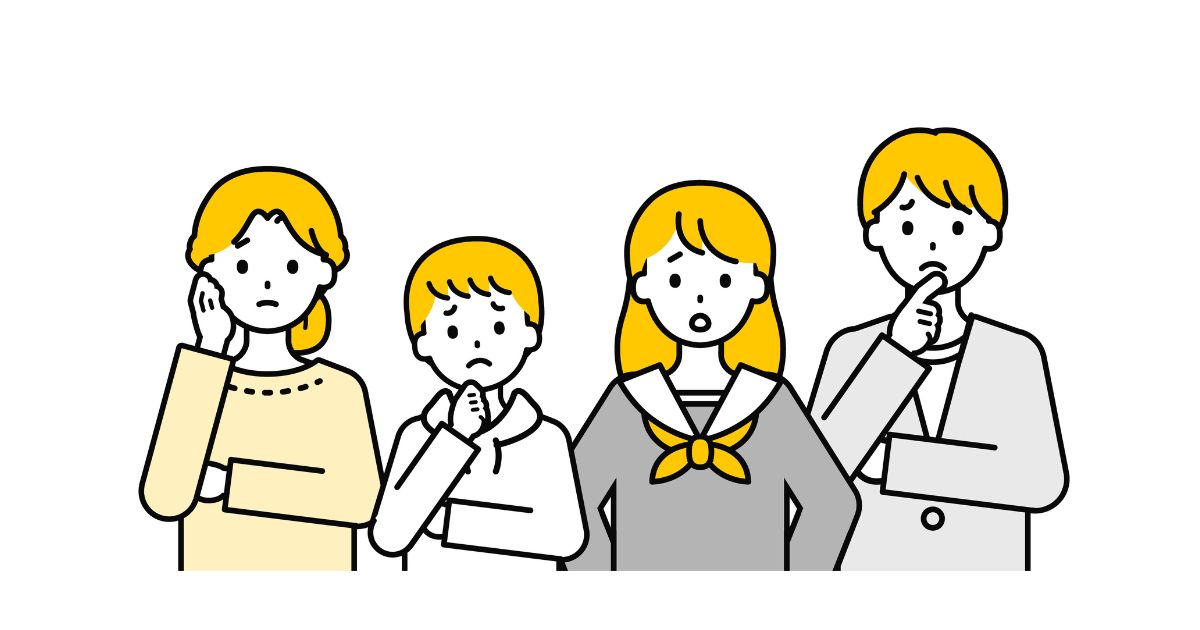
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
子どもの塾通いを検討している人のなかには、学習塾には行かないほうがいいという意見を見聞きし、迷っている人もいるのではないでしょうか。
このコラムでは、よくある学習塾に行かないほうがいい理由について解説します。
あわせて、学習塾に行ったほうがいい人の特徴や、通塾するメリットも紹介します。
子どもの塾通いを考えている親御さんや学生さんにとって参考になる内容です。
私たちキズキ共育塾は、塾に行くかどうか迷っている人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
学習塾に行かないほうがいいかどうかは人・塾によります

学習塾に行かないほうがいいかどうかは、人や塾によって異なります。
学校の授業や自学自習だけで満足のいく成績が取れている場合は、学習塾に通う必要はないかもしれません。
一方で、学習塾に通うことで自由な時間が減ったり、疲れやストレスが増えたりするケースもあります。そうした場合は、行かないほうがいいと感じるのも自然なことです。
また、本人の学力が高くて塾のレベルが合わない場合、期待していたように学力が伸びず、学習塾に行く意味がないと判断されることもあるでしょう。
ただし、反対に塾に行ったことで学力が伸びた、勉強が楽しくなったと感じている人もたくさんいます。
キズキ共育塾に通っている生徒さんの中にも、「通ってよかった」と実感している人が多数います。
このように、学習塾が合うかどうかは人それぞれであり、学習塾によっても異なります。
よくある「塾に行かないほうがいい」と言われる理由5選
この章では、よくある「塾に行かないほうがいい」と言われる主な理由について解説します。
理由①成績が伸びない

成績が思うように上がらないと、学習塾に行っても意味がない、時間の無駄と感じる人もいます。
成績が伸びない理由としては、以下のような点が考えられます。
- 授業のスタイルが合っていない
- レベルや指導方針が子どもと合っていない
- 目標を決めずに、なんとなく通い続けている
このような理由から学習塾に行かないほうがいいと感じるのは無理のないことかもしれません。
理由②授業料が高い
授業料に対して満足できる効果を感じられないという意見もあります。
特に、学校で十分な補習授業を受けられる場合は、学習塾に通う必要はないと判断されることもあります。
また、自力で学習を進められる子どもにとっては、参考書や問題集の購入だけで十分という見方もあるでしょう。
ただし、授業料をどう捉えるかは、家庭の経済状況や学習塾の指導内容によって異なります。
理由③人間関係が疲れる

集団授業を行う学習塾では、対人関係にストレスを感じることもあります。
- 同じクラス・コースに性格の合わない人がいる
- 競争意識から関係が気まずくなる
- 他の子どもとの関係でトラブルが起きる
一方で、新しい友達ができて刺激になることもありますし、完全個別指導など、マンツーマン形式の学習塾では、人間関係のストレスを最小限に抑えられます。
理由④独学のほうが好き
自分のペースで勉強したい、ひとりで集中したいと考える人にとっては、学習塾はかえって負担になる場合もあります。
この理由は、前述の人間関係のストレスとも関連しています。
とはいえ学習塾に通うことで新しい解法を知る機会が得られたり、勉強以外の悩みを相談できたりすることもあります。
独学が好きな人にとっても、学習塾や講師との相性次第ではプラスの効果が期待できるでしょう。
理由⑤学習塾の方針が合わない

学習塾は、目的や方針によって内容が大きく異なります。
- 学力アップや受験合格を重視する学習塾
- 子どもの理解度に合わせて丁寧に指導する学習塾
- 勉強を楽しむスタイルを重視する学習塾
- 学習障害などのある子どもを支援する学習塾
塾の方針と子どもの希望がすれ違っていると、勉強に対する意欲そのものが下がってしまうこともあります。
例えば、マイペースに学びたい子どもに対して、保護者が難関校向けのコースを勧めるケースでは、結果的に塾通い自体がストレスになってしまうことがあります。
このような場合は、学習塾に行かないほうがいいと判断するのも自然な流れと言えるでしょう。
勉強嫌いになる背景については、以下のコラムでも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害や不登校状態の人は学習塾に行かないほうがいい?
発達障害のある子どもや、不登校状態にある子どもの場合、学習塾に行かないほうがいいのでは、と迷う人もいるかもしれません。
結論から言えば、発達障害や不登校状態にある子どもでも、学習塾に通うことには多くのメリットがあります。
発達障害のある子どもが通塾するメリット
- 学校とは異なる授業形式で学べる
- 障害特性に合った学習法を教えてもらえる
- 障害を補えるツールや環境を取り入れながら勉強できる
不登校状態にある子どもが通塾するメリット
- 自分のペースで学べる環境がある
- 学校復帰のきっかけになる可能性がある
- 安心して過ごせるコミュニケーションの場が得られる
- 学習塾によっては学校の出席扱いになる場合もある
- 受験や進学の準備を無理なく進められる
これらのメリットを十分活かすためには、発達障害や不登校状態のある子どもの指導に対応した学習塾に限られます。
発達障害や不登校状態にある子どもへの理解と対応力がある学習塾を選ぶことが大切です。
なお、こうした特性のある子どもに向いてる学習塾の選び方については、次の章で詳しく解説します。
学習塾に行ったほうがいい人の4つの特徴
この章では、学習塾に行ったほうがいい人の特徴を解説します。
ただし、以下の特徴に当てはまるからといって、必ずしも塾通いが必要というわけではありません。あくまでも、学習塾を検討する際の参考としてご覧ください。
特徴①学校の授業に不満がある

学校の授業が合わないと感じている場合は、学習塾に通うことで勉強しやすくなる可能性があります。
- 授業のペースが早い、または遅い
- 授業の形式が合わない
- 教師との相性が合わず、理解しにくい
こうした状況で学習塾に通うと、自分に合ったスタイルで学べるようになり、勉強に前向きになれることがあります。
実際に、学習塾に通い始めたことで勉強って面白いと思えるようになった子どももいます。
特徴②モチベーションの維持が苦手
勉強のモチベーションを保つのが苦手な人にとっても、学習塾は効果的です。
- 宿題を後回しにしがち部活動や趣味が優先で、勉強の優先度が低い
- テスト直前でも学習計画を立てようとしない
学習塾に通うことで、定期的に勉強の時間を確保できるようになり、学習塾の講師や仲間から刺激を受けて意識が向きやすくなります。
特に個別指導を行っている学習塾では、学習計画の立案やモチベーションの管理もサポートしてもらえるのが強みです。
私たちキズキ共育塾も、完全個別指導の学習塾として、お子さんの学習とメンタルの両面を丁寧にサポートしています。勉強の進め方でお悩みの人は、ぜひお気軽にご相談ください。
特徴③参考書を読んでも理解できない
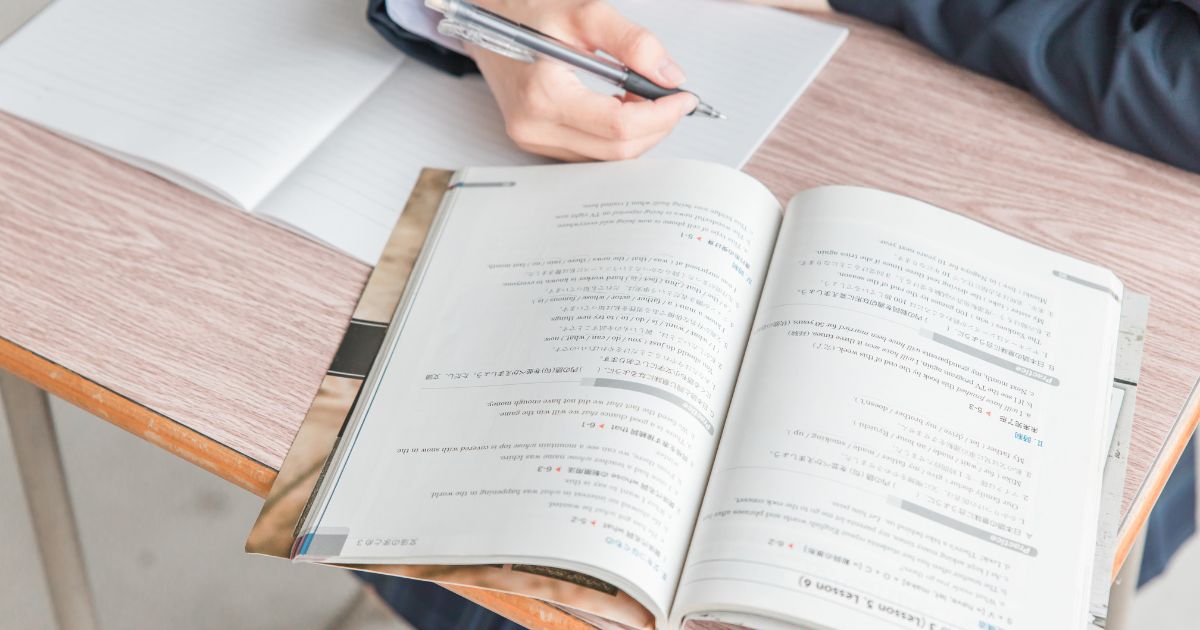
自分で参考書や問題集を使って学ぶことが難しい場合も、学習塾が大きな助けになります。
- 基本が分からず、読み進められない
- 読んで覚えるより聞いて学ぶほうが得意
- 誰かと話しながら学んだほうが集中できる
こうした傾向がある場合は、学習塾のように対話形式で学べる環境が向いています。
基本から丁寧に教えてくれる学習塾や、生徒の興味を引き出す説明が得意な講師のいる学習塾を選ぶと、学習のつまずきが解消されやすくなります。
なお、子どもが勉強に苦手意識を持つ理由と対処法については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご覧ください。
特徴④志望校に学力が追いついていない
志望校への合格を目指しているものの、現時点の学力が足りていない場合は、学習塾を活用することで効率的に実力を伸ばせます。
- 限られた時間の中でスピードアップしたい
- 模試で思うような判定が出ない
- 志望校特有の出題傾向に対応できない
受験対策に強い学習塾では、実践的なテクニックや学力を伸ばすノウハウを学べるため、短期間での得点力アップも期待できます。
レベル別のコースが用意されている塾を選べば、無理のないステップで学力を底上げできるでしょう。
学習塾に通う4つのメリット
この章では、学習塾に通うことで得られる主なメリットについて解説します。
塾通いを検討している人は、これから解説するメリットを最大限に活かせる学習塾を探してみるとよいでしょう。学習塾を選ぶ際のポイントは、こちらの章で詳しく解説します。
メリット①わからないことを気軽に質問できる

勉強していてわからないことが出てきたとき、すぐに質問できる相手がいるのは大きな安心材料です。
疑問をその場で解消できれば、理解が深まるだけでなく、不安を感じずに勉強を進められます。
特に、勉強に苦手意識がある子どもの場合、どこがわからないのか自分で説明できないという状態でつまずいていることも少なくありません。
学習塾では、講師が対話を通じて疑問を丁寧に言語化しながら整理してくれるため、子どもは安心して学習に向き合えるようになります。
メリット②学習計画を立てる手伝いをしてくれる
勉強の経験が浅い子どもは、自分に必要な学習内容を把握できておらず、学習計画を立てるのが苦手な傾向があります。
学習塾では、講師が子どもの理解度や目標に応じて、無理のない学習計画を一緒に考えてくれます。
特に、指導経験が豊富な講師であれば、どこでつまずきやすいのか、どこを重点的に取り組むと効果的かといったポイントを見極めた上で、効率的なスケジュールを提案してくれるでしょう。
メリット③同じ学習塾の仲間から刺激を得られる

学習塾は、学校以外の同年代と出会える貴重な場所でもあります。
通っている学校とは違う価値観を持つ仲間と接することで、考え方の幅が広がったり、良い刺激を受けたりすることが期待できます。
勉強だけでなく、人間関係やコミュニケーションの面でも成長できる可能性があるのは、学習塾ならではのメリットです。
環境が異なる人との交流が、視野を広げるきっかけになることもあるでしょう。
メリット④自分に合う勉強法を知れる
学習塾によっては、画一的な指導ではなく、子どもに合わせた個別対応が可能なところもあります。
オーダーメイドのカリキュラムや勉強法の提案を受けることで、自分にとってどんなやり方が合っているかを見つけやすくなるでしょう。
また、学習障害などの特性がある子どもにも対応できる教材やツールを活用し、無理なく学べる方法を提案してくれる塾もあります。
きちんとした実績がある学習塾であれば、過去の事例をもとに、どのようなアプローチで学習を進めると成果が出やすいかを把握しているため、より実践的な支援を受けられる可能性が高まります。
学習塾を選ぶときの6つのポイント
この章では、学習塾を選ぶときのポイントについて解説します。
前提として大切なのは、子どもの性格や困りごとをしっかりと把握し、話し合いを重ねながら意思決定をすることです。
以下のポイントを参考に、子どもとのコミュニケーションを大切にしながら、最適な学習塾を検討してみましょう。
ポイント①子どもに合う授業形式やコースがあるか

無理なく学習塾に通い続けるには、子どもに合った授業形式やコースを選ぶことが重要です。
授業形式には以下のような種類があります。
- 集団授業:講師1人に対して多数の生徒が同時に受ける授業形式
- 少人数授業:講師1人に対して数人程度の生徒が授業を受ける形式
- 個別授業:講師と生徒の1対1で行われる授業形式
- オンライン:自宅のパソコンやタブレットを通じて学習する形式
それぞれの授業形式には異なるメリットがあります。
例えば、個別授業なら生徒の特性や理解度に応じたきめ細やかな指導が受けられ、オンライン授業は対面が苦手な子どもでも安心して取り組めるでしょう。
子どもの学びやすさを最優先に、形式・コースを選んでください。
ポイント②学習塾の方針や講師との相性はどうか
学習塾の方針や講師との相性は、学習の成果だけでなく、通塾への意欲や継続にも大きく関わります。
塾によっては、高い目標設定を重視するところもあれば、マイペースな学びを尊重するところもあります。
事前に体験授業を受け、子どもがこの先生なら続けられそうと感じるかどうかを確認しましょう。実際に授業の雰囲気を体験することで、講師の教え方や塾全体の空気感もつかみやすくなります。
ポイント③相談しやすい雰囲気があるか

子どもが気負わずに通える学習塾かどうかを見極めるには、相談のしやすさが大切な指標となります。
相談のしやすさを測るときには、以下のポイントをチェックしてみてください。
- 勉強以外の相談も受けてもらえそうか
- 子どもが授業中に発言しやすい雰囲気があるか
- 振替や欠席の連絡がしやすいか
保護者にとっても相談しやすい雰囲気があるかどうか、教室の担当者や講師の対応を見て判断しましょう。
ポイント④通いやすい場所にあるか
通塾のしやすさは、見落とされがちですが非常に重要な要素です。
- 帰宅が遅くならない距離にあるか
- 公共交通機関を利用できるか
- 安全なルートで通えるか
通塾にかかる負担が大きいと、子どもの疲労や保護者の負担も増えてしまいます。
送迎の必要があるかどうかも含め、家族全体で無理なく続けられるかを考慮しましょう。
ポイント⑤授業料は高くないか

学習塾は長期間にわたって通うことが前提となるため、授業料や教材費が家計に与える影響も忘れずに確認しておきましょう。
学習塾によっては入塾金、テスト代、季節講習の追加費用などがかかることもあります。
指導内容とのバランスを見ながら、他の学習塾との比較もしておくと安心です。
ポイント⑥指導実績があるか
学習塾の信頼性を測る上で、指導実績は非常に重要です。
特に、以下のようなケースでは、明確な実績のある塾を選ぶことをオススメします。
- ①志望校が明確にある場合
- ②発達障害や不登校状態にある子どもの通塾を考えている場合
実績のある学習塾なら、受験対策のノウハウや特性に合わせた支援体制が整っている可能性が高いです。
補足:不登校状態や発達障害のある子どもの学習塾選びのポイント

不登校状態や発達障害のある子どもの塾選びには、以下の点に注目してください。
- 発達障害や不登校に理解のある講師がいる
- 同様の状態にある生徒が通っている実績がある
- 授業がオーダーメイドで組まれている
- 保護者と子供の両方が相談しやすい雰囲気がある講師との相性や教室の雰囲気が合っている
- 授業の振替・講師変更が柔軟に対応可能
- 学習障害を補助する教材やツールが整備されている
もしこれらの条件を満たしていない場合は、無理に通塾を始めず、慎重に検討したほうがよいでしょう。
発達障害や不登校状態の人に向いている学習塾の特徴については、以下のコラムでも解説しています。あわせて参考にしてみてください。
学習塾に行ってよかった人たちの体験談
この章では、キズキ共育塾の事例から、学習塾に行ってよかったと感じている人たちの体験談を紹介します。
体験談①学習障害に合わせた指導で中学校に合格

学習障害(LD:Learning Disabilities 学習障害/限局性学習症)がある2人の小学生は、いずれも「自分は勉強ができない」という漠然とした不安を抱えていました。
保護者のTさんは、2人が勉強の楽しさを実感できるよう、自尊心を傷つけずに、近い目線から寄り添ってくれる講師がいそうなキズキ共育塾を選びました。
実際に通ってみると、個々に丁寧に寄り添い、興味や関心、こだわりを理解しながら進める指導が印象的だったそうです。
担当講師は、どうすれば興味を持てるか、どうすれば面白く学べるかを常に工夫してくれていたとのこと。
その結果、2人とも勉強に前向きになり、毎回楽しそうに帰宅していたそうです。学びへの自信が育まれ、兄のほうは無事に私立中学校に合格しました。
体験談②不登校の状態から通塾を経て高校に合格
中学3年生のとき、に人間関係の悩みから不登校状態になったMさんは、やる気が出ず、何をしていいのかもわからない日々を過ごしていました。
夏休み明けに一度は学校へ戻ったものの、勉強についていけずに、再び不登校状態になりました。
そのまま中学校を卒業し、高校進学を希望する気持ちはあっても、勉強への取りかかり方がわからず、学習に対して自信が持てない状態が続いていました。
そこで以前通っていた学習塾を辞め、キズキ共育塾に入塾。通いはじめて感じたことは「いい意味で普通」、「特別扱いされない感じがよかった」とMさんは話しています。
通塾を通じて生活リズムが整い、完全個別指導によって無理なく学び直しが可能になりました。
高校の選び方についても相談に乗ってもらい、内申点にとらわれない進学校への合格を実現しました。
体験談③集団塾から個別指導塾に切り替えて志望大学に合格
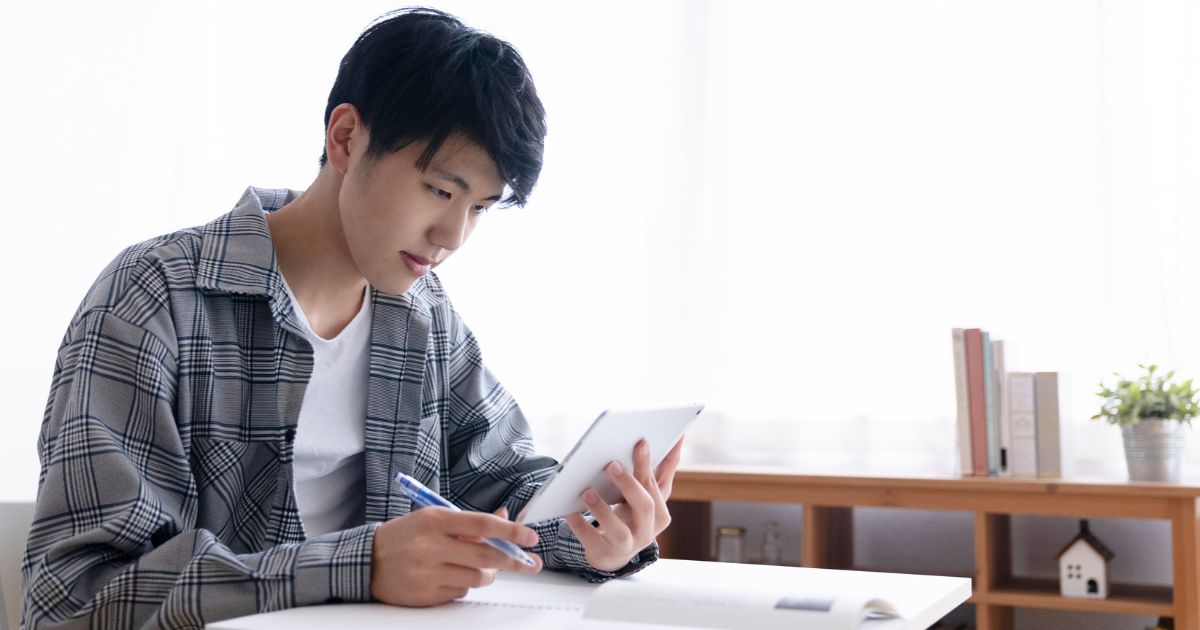
高校で部活動と勉強の両立に苦労したKさんは、退部を機に学校への足が遠のき、不登校状態になりました。
その後、不登校の学生向けの集団塾に入塾しましたが、授業のペースやクラスの雰囲気に合わず、再びひきこもり状態になってしまったそうです。
転機となったのは、キズキ共育塾との出会いでした。「ここならもう一度勉強に取り組めるかもしれない」と感じたそうです。
キズキ共育塾では、Kさんのペースや関心に配慮した指導が行われました。講師との会話や雑談も多く、勉強だけでなく、安心して通える環境が整っていたことが決め手でした。
その結果、学習への意欲を取り戻し、見事に志望大学への合格を果たしました。
まとめ:自分に合う学習塾が見つかると楽しみながら成績を伸ばせます

学習塾に行かないほうがいいという意見も少なくありません。実際、人によっては通塾が負担になることもあるでしょう。
しかし、学習塾に行くべきかどうかは、人と学習塾の相性によるものです。
このコラムで紹介したように、自分に合った学習塾に出会えたことで、学力が伸びたり、勉強への前向きな気持ちを取り戻したりする人も多くいます。
大切なのは、子どもが安心して学べる環境かどうかを見極めることです。
これまでに解説してきたポイントをもとに、お子さんにぴったりの学習塾を探してみてください。