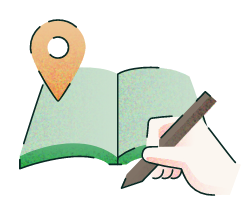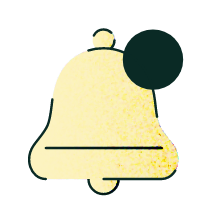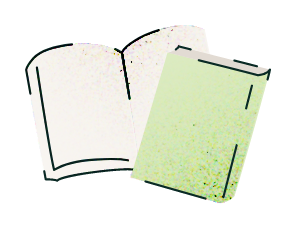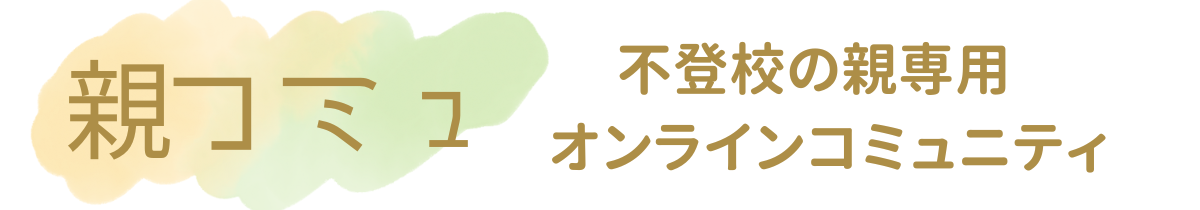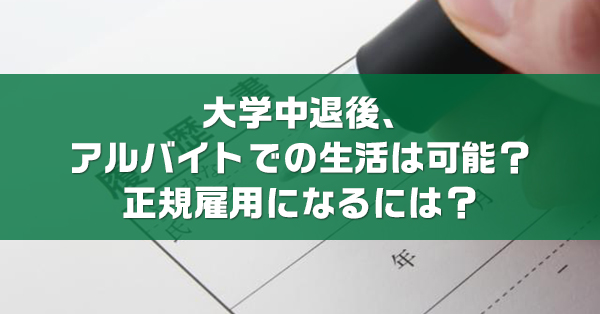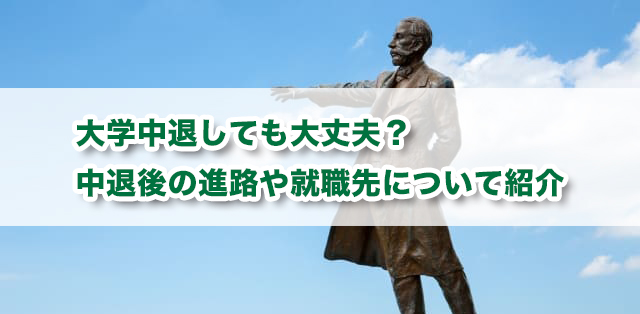大学に行く意味とは? 大学に行くメリットを解説
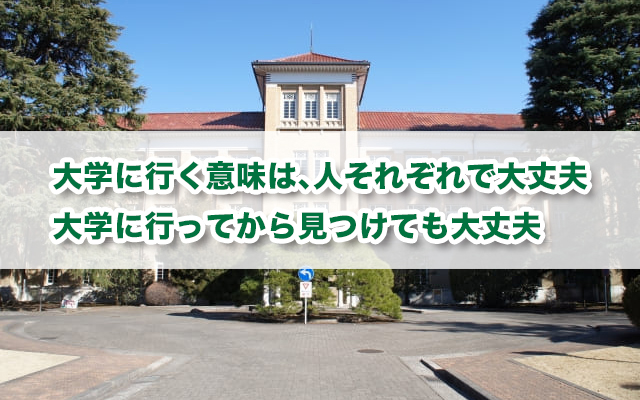
こんにちは。進路相談などもできる完全個別指導塾・キズキ共育塾の土井です。
あなたは、「大学に行く意味って何だろう?」とお悩みではありませんか?
大学に行く意味が明確になっている人もいれば、「周りが大学に行くから」「先生や親に言われたから」といった理由で、なんとなく「大学に行くことが当たり前だ」と思っている人もいるでしょう。
そして、ずっと「大学に行く意味がわからない」とお悩みの人も、ふと「何のために大学に行くのだろう」と疑問に感じて受験勉強が手につかなくなる人もいます。
私も大学受験の際、大学に行く意味や自身の将来についてすごく悩みました。
しかし、最終的に大学に進学し、結果として大学に行ってよかったと感じています。
今回は、大学に行く意味についてお悩みの人のために、「大学に行く意味」や「大学へ行くことのメリット」について、私の経験も踏まえながらお話しします。
あなたの「大学へ行く意味」についてのお悩みを解消する参考になれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、大学に行きたい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
大学に行く意味は人それぞれ〜代表的な7つの例〜
「大学に行く意味」と言うと、「こうあるべきである」という特定の意味があると考える人もいると思います。
しかし、大学に行く意味は人それぞれで構いません。
ただ、大学に行く意味について、自分の中でイメージできない人もいるでしょう。
ここでは、少しでもそのイメージがしやすいように、大学に行く意味をいくつか紹介したいと思います。
意味①専門的な学問を学ぶ
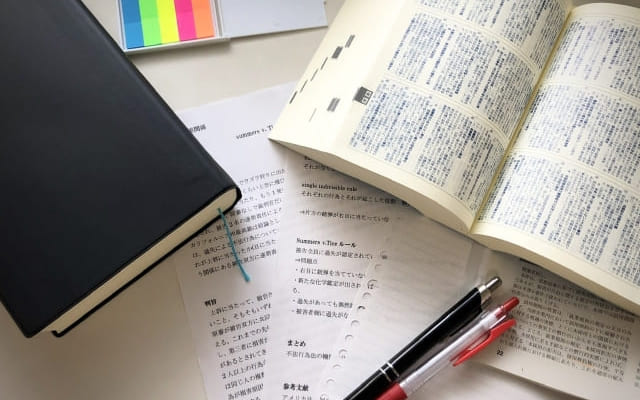
「専門的な学問を学ぶ」のは、大学に行く大きな意味のひとつです。
高校までの勉強と比べて、大学ではより専門的な学問を学ぶことができます。
大学では専門ごとに学部が分かれており、自分の興味のある学問を追求することができるのです。
例えば、文学、社会学、法学、政治学、心理学、工学、医学など様々な分野があり、その中でもさらに細分化した分野があります(「文学の中でも、シェイクスピア」など)。
大学よりもさらに専門的に学びたい人は、大学卒業後に大学院に進学する選択肢もあります。
意味②就職の幅を広げる
就職の幅を広げることも、大学に行く意味のひとつです。
大学を卒業する(大卒の資格を得る)ことで、就職の幅が広がります。
まず、工学を学んだ人がメーカーでエンジニアになるなど、大学で学ぶ内容が就職先の業務内容と関連する場合があります。
そして、文学を学んだ人間がメーカーの営業に就職するなど、学んだ内容と就職先が関連しない場合でも、「大卒」であることが応募要件になっていることは珍しくありません。
少し古いですが、2013年に首都圏の大学生を対象に実施したアンケート結果でも、大学進学の理由は「就職のため」であるという回答が50%と一番多くありました。(出典: ReseNom「大学に入学した理由、最多は「就職のため」)
意味③将来的に専門的な職業に就く

前項とも関連しますが、卒業後に専門的な職業に就くことを、大学に行く意味と考える人もいます。
例えば医師や薬剤師などに代表される国家資格のいくつかは、大学で専門的な内容を学ぶことで受験資格を得られます。
高校生時点ですでにそうした目標があるのなら、「将来」と直接つながります。
意味④やりたいことを見つける
大学受験時点で「やりたいこと」がない場合は、「やりたいことを見つけるため」というのも、大学に行く意味となります。
大学では、高校までに比べると、出会う人や得られる経験の幅も広がります。
大学生活の中では、大学での授業はもちろん、サークル活動、アルバイト、ボランティア、インターンなど、大学生だからこそ経験できることがたくさんあります。
そうした活動・経験などを通じて、「やりたいこと」を見つけることができるのです。
「やりたいこと」は、「就職先」や「取得資格」といった直近の未来の話かもしれません。また、「自分はこう生きたい(こう生きたくない)」といった大きな話・抽象的な話の場合もあります。
なお、余談ですが、「積極的にやりたいこと」がないからといって、変に心配になる必要はありません。
やりたいことがなくても、楽しく過ごすことは可能です。
意味⑤交友関係や人脈を広げる

「交友関係や人脈を広げる」というのも、大学に行く意味となるでしょう。
大学には、全国各地からさまざまなバックグラウンドが持った人が集まります。
大学に行くことで、高校までとは違う交友関係や人脈ができるのです。
「交友関係を築く!」と大げさに考えなくても構いません。少人数授業のクラスメイト、サークル仲間、バイト仲間、恋愛相手、新しくできた友達の友達、留学生、自分が留学した先の人たちなど、交友関係の元はたくさんあります。
広がった交友関係や人脈は、単純に「楽しい交流」にもなるでしょう。また、交流を通じて「新たな知見」を得られたり、「自分のこれから」を考えるきっかけにもなったりします。
意味⑥生活環境を変える
「生活環境を変える」ことも、大学に行く意味です。
大学進学は、実家を出て一人暮らしを始める、これまでとは違う場所・街などに通うようになるなど、生活環境を変えるきっかけになるのです。
一人暮らしを始める場合は、食事の準備・片付け、洗濯、掃除など、自分のことは全て自分で行うようになります。
自分で全て行うことは大変な側面もありますが、生活力がついたり、自分で自分の生活をコントロールできたりする面白さもあります。
そうした「新たな生活環境」で得られる知識・経験・能力も多くあります。
身近な例では「家事を回せるようになる」「季節ごとの野菜の値段を知る」「地域ごとの気候や風習を知る」などといったこともあるでしょう。
より大きな話では「日本の経済状況と自分の身の回りがどう結びついているのかを実感を持って考えられる」ようになったりすることもあります。
「それまでの環境にいた自分」から、一歩ずつ成長することができるのです。
意味⑦視野を広げる

やや抽象的ではありますが、大学に行くことは、視野を広げるきっかけとなります。
大学で学問を学ぶことやさまざまな人との出会いや経験の積み重ねなどで、視野が広がることは珍しくありません。
例えば私の場合、大学入学前まではビジネスの世界には興味がありませんでした。
ですが、入学後に経営学やマーケティングの授業を受けることで、ビジネスの世界に興味を持つようになりました。
また、大学入学のために上京した私は、いわゆる「地元志向」が強く、大学卒業後は地元に帰るものだと思っていました。
しかし、大学のOBから話を聞くうちに、東京での生活や就職に興味が湧き、大学卒業後も東京に残り、就職することになりました。
どちらも、大学に行ってなければ触れることのなかった世界・価値観でした(もちろん、「マーケティングに興味がないこと」や「地元志向」が悪いという意味ではありません)。
大学に行くことで得られる5つのメリット
ここまでは、大学に行く意味の例を紹介してきました。
あなたにとって大学に行く意味として、ピンとくるものはあったでしょうか。
まだピンと来てない場合は、もしかすると大学に進学するメリットを知ることで、大学に行く意味を見出すこともできるかもしれません。
そこで、ここからは大学に進学するメリットを具体的に紹介します。
ご紹介した「大学に行く意味」と重複する内容もありますが、「意味」と「メリット」を互いに言い換えることで見えてくるものもありますよ。
メリット①学ぶのに最適な環境が用意されている

様々な学問の専門家から指導してもらえることは、大学に行く大きなメリットです。
大学では、教授をはじめとした、各学問の専門家がたくさんいます。
私自身が大学を卒業してからより一層感じることですが、特定の分野の専門家がこんなに近くにいて気軽に質問できる環境は、社会人になって以降なかなかありません。
特に、ゼミや研究室では、少人数で直接指導やアドバイスを得ることができます。
専門家と密に接する機会は、大学以外ではほとんどないと言えるかもしれません。
また、大学は学習環境としても優れています。
「大学で学ぶ内容は、本やオンラインで独学できる」と考える人もいるでしょう。しかし、1人で学習することは、環境を整えたりすることも含め、簡単ではありません。
大学の授業に取り組み、同じように学ぶ学生から刺激を受けることで、あなたのモチベーションにもつながります。
また、大学の図書館には専門的な書籍が大量にあることも、学びたい人にとって素晴らしい環境であると言えるでしょう。
メリット②求人数が高卒より多い
前章でもご紹介しましたが、大学に行くことで就職の幅が広がり、高卒に比べて求人数が増えるというメリットもあります。
特定の学部や大学院を卒業しなければ就くことのできない職業もあります。また、企業に就職する場合でも大卒を応募条件にしている企業もあります。
同じ業界や企業に就職するにしても、一般的に大卒の方が選べる職種は広い場合が多いです。
求人サイトなどを見てみると、応募資格が「大卒(以上)」となっている仕事は珍しくありません。
一方で、「高卒(以上)」が条件の仕事には、大卒でも応募できます(一部例外あり)。
特に今の時点で将来的にやりたい仕事がない(わからない)場合は、大学に進学して就職の幅を広げるというのも選択肢のひとつでしょう。
メリット③年収が上がる可能性がある
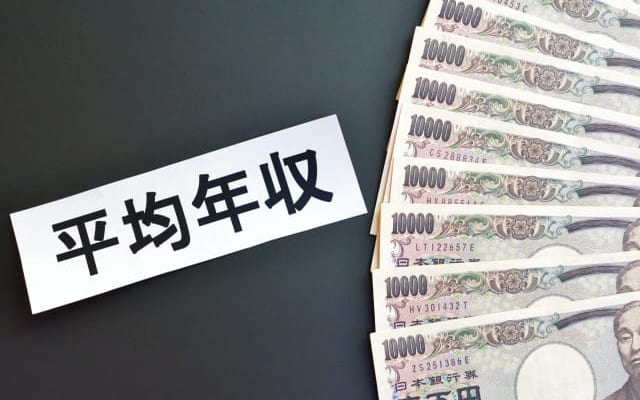
「将来的に年収が上がる可能性があること」も、大学に行くメリットのひとつです。
2022年現在、学歴別の年間平均賃金は、次のようになっています。
- 大学院卒、男性:478.4千円
- 大学院卒、女性:404.3千円
- 大学卒、男性:392.1千円
- 大学卒、女性:294.0千円
- 高専・短大卒、男性:343.8千円
- 高専・短大卒、女性:269.3千円
- 専門学校卒、男性:316.0千円
- 専門学校卒、女性:269.4千円
- 高校卒、男性:297.5千円
- 高校卒、女性:222.9千円
男女どちらも、平均では大学・大学院卒が一番賃金が高い、ということです。(出典:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」)
また、生涯賃金(※)の平均も、次のように大卒の方が高いです。(※学校卒業後フルタイムの正社員を続けた場合の60歳までの生涯賃金(退職金を含めない))
- 大学・大学院卒、男性:2億6千万円
- 大学・大学院卒、女性:2億1千万円
- 高専・短大卒、男性:2億1千万円
- 高専・短大卒、女性:1億7千万円
- 高校卒、男性:2億1千万円
- 高校卒、女性:1億5千万円
- 中学卒、男性:1億9千万円
- 中学卒、女性:1億5千万円
もちろんこれは「可能性」の話です。収入は、学歴を問わず職場や働き方によって人それぞれです。
ただ、紹介したデータに基づくと、一般論としては、大学に進学することで年収が上がる場合が多い、ということです。
メリット④多様な人たちと出会える
多様な人たちと出会えるのも、大学に行くメリットのひとつです。
大学では、さまざまな地域からさまざまなバックグラウンドを持った人たちが集まります。
出身地や年齢なども多様で、高校までとは一味違った出会いの機会となるでしょう。
特に大学では、サークル、ゼミ、研究室など、「職場」とは異なる環境で同期、先輩、後輩たちとの仲を深める機会が多くあるのです。
もちろん、高校卒業後に就職した場合でも、「職場」では高校までの知人とは違う人たちと出会う機会はありますが、それは大学卒業後に就職したときでも同じです。
また、高卒での就職の場合だと、同じ地域出身の人が多かったり、バックグラウンドや志向も比較的自分に近かったりすることが多いと思います。
大学では、全国各地からたくさんの学生が集まることやさまざまな学部があることもあり、「より多様な出会い」があるのです。
さらに学生だけでなく、大学の教授のように、普段の生活では会う機会が少ない人に出会い、コミュニケーションを通じて刺激を得られるといったように、滅多にない経験ができます。
メリット⑤まとまった自由な時間ができる

まとまった自由な時間ができるのも、大学に行くメリットでしょう。
大学生は夏休みや春休みが約2か月ずつあり、自分の好きなように時間を使うことができます(学校・学部や経済状況にもよりますが)。
自由な時間は、大学に行かなくても多少はつくることができるかもしれません。
しかし、高校卒業後の進路にアルバイトや就職などの「働くこと」を選ぶと、大学ほどまとまった自由な時間をつくることは、非常に難しくなります。
「大学生という立場」であれば、一般的に自由に時間を過ごしても許される空気感があり、やりたいことに集中して時間を使うことができるのです。
「大学時代はモラトリアムの期間だ」と言われることがあるように、自由な時間を謳歌できるのは大学生の特権とも言えるでしょう。(繰り返しますが、大学・学部によっては課題などが忙しい場合もありますし、経済状況によってはアルバイトなどで自由時間が少ない可能性はあります)
大学に行く場合に気をつけること
続いて、大学に行く場合に気をつけることを3つご紹介します。
ここまでにお伝えした、大学に行く意味やメリットとあわせて、大学に進学するかどうかを検討する際のヒントにしてください。
①まとまった費用が必要になる

気をつけることの1つ目は、まとまった費用が必要になることです。
大学に進学する場合は、入学金や学費などのお金が必要になります。どのくらいの費用がかかるかについては、進学を希望する大学によって異なるので、気になる大学があれば調べてみてください。
また、大学進学を機に実家を出て一人暮らしをする場合は、家賃や光熱費、生活費などのお金がかかることも考えられます。
さらに、大学受験のために塾や予備校に通ったり、家庭教師を利用したりする場合は、それらの費用も必要になるでしょう。
費用面については、自分だけでは判断できないことが多いかと思います。保護者の方とよく相談するようにしましょう。
また、奨学金を利用するという選択肢もあります(大学卒業後にお金を返す必要はありますが、中には返済不要な奨学金もあります)。
②勉強へのモチベーションを長期間維持しなければならない
2つ目は、勉強へのモチベーションを長期間維持しなければならないことです。
今、あなたが大学に進学すると決めた場合、大学受験のために勉強する必要があります。
どのくらいの勉強が必要かについては、現状の学力や志望校によって異なりますが、数か月から数年間の受験勉強に取り組むことになるでしょう。
無事大学に受かり受験勉強が終わっても、勉強は続きます。
こちらも進学する大学によって違いがありますが、一般的な大学だと4年間通う必要があります。
そして、卒業するためには、毎日の授業を受け、課題の提出し、テストを受けるなどをして、必要な単位を取得していくことになります。
勉強を楽しみ続けることができればよいのですが、なかなかうまくいかないこともあります。人にも相談しつつ、受験勉強や大学での勉強のモチベーションを保つ方法を探していきましょう。
また、「志望して入った学部だけど、やっぱり自分に合ってないな…」と思ったときには、別の学部に入り直すという方法もあります。
③「大学卒業=将来安泰」ではない

最後にお伝えするのは、「大学卒業=将来安泰」ではないということです。
大学を卒業すると、中卒や高卒の場合と比べて、正社員として就職しやすかったり、高い給与をもらえたりする可能性が高まります。
ですが、望み通りの就職や高い給与が絶対に保証されるわけではありません。
就職活動や職業生活で理想を叶えていくためには、「大学までの勉強(大卒という肩書き)とはまた別の努力・勉強が必要になる」ということです。
「人生はずっと勉強が続く」ということをポジティブに認識し、勉強を楽しめる(環境に身を置く)ことが大切なのかもしれません。
なお、「就職先が自分の価値観や理想に合っていなかった」「将来の安定・安泰が見えない」としても、そこから転職や起業などをすることはもちろん可能です。
その際には、大学で学んだことや、「大卒」という肩書きが役立つこともあるでしょう。
大学に行かない場合の選択肢
「大学に行く意味がわからない」と思っている人の中には、大学進学以外の選択肢が気になっている人が多いかもしれません
この章では、大学に行かない場合の選択肢を3つお伝えします。
これからのご自身の進路や将来を考えるうえでの、ヒントになる情報もあるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
選択肢①専門学校に進学する

1つ目の選択肢は、専門学校への進学です。以下、文部科学省の資料をもとに解説します。(参考:文部科学省「未来につながる専門学校」)
専門学校は、大学と同じ「高等教育機関」ではありますが、大学よりも実践的な職業教育を受けられる学校です。また、専門学校で学ぶ内容は、卒業後の就職先や職業に直結していることも特徴の1つになります。
具体的な専門学校の分野としては、工業や農業、医療、教育、服飾、文化などです。
興味があることに特化して学びたい人や、将来就きたい仕事が決まっている人であれば、専門学校に行く意味を見出しやすいでしょう。
ただし、先述した通り専門学校では、特定の分野に特化した職業教育を受けることになります。
そのため、単にその分野に「興味がある・好き」というだけではなく、「将来働く仕事としてどうか」ということを考えておくことが大切です。
専門学校の詳細は、下記コラムをご覧ください。主に高校中退の方に向けた記事ですが、専門学校の概要は、どなたが読んでも参考になると思います。
選択肢②留学する
2つ目の選択肢は、留学です。語学留学もありますし、大学進学もあります。
いずれも、日本では得られないような経験や学びを得られる可能性があります。
「大学に行く意味がわからない」と思っている人の中でも、特に「日本の大学」に限ってそう感じている人は、一度海外に目を向けてみるのもよいかもしれません。
海外の大学を卒業すれば、学歴は当然「大学卒業」になるため、就職の際の選択肢が広がるでしょう。
ただし、留学する場合、学費に加えて渡航費や生活費など、日本の大学に進学する以上にお金が掛かる可能性が高いです。
そのため、経済的に進学先として選べるかどうかを、親御さんと相談したり、奨学金の利用を検討したりする必要があるでしょう。
選択肢③仕事をする

仕事をはじめるのも選択肢の1つです。
「これ以上勉強する意味がわからない」「勉強したくない」と思っている人に向いている選択肢と言えるでしょう。
また、仕事と一括りに言っても、さまざまな働き方が考えられます。
- 正規雇用で就職する
- アルバイトをする
- フリーランスとして働く
- 起業する
それぞれにメリットやデメリットがあるため、高校卒業後に就職することを考えている人は、一度しっかりと調べておきましょう。
ただし、大学卒業後に就職するよりも応募できる求人が少なかったり、将来的に給与が上がりづらい可能性があったりします。そういった懸念点についても知っておくことが大切です。
また、働く場合であっても、「学校のような勉強」はなくなるかもしれませんが、「仕事のための勉強」が必要であったり、働くことを通して学ぶことがあったりします。
「仕事をすれば全く勉強する必要がない」というわけではないことを踏まえて、検討しましょう。
大学に行くことで意味を見つけられる場合もある〜私自身の経験から〜
大学に行く意味やメリットについてお話ししてきましたが、自分なりの意味を何となくでも見つけることはできたでしょうか。
ここからは、大学に行く意味を考えるヒントとして、私自身の体験談をご紹介します。
実は、私も受験生だったころには大学に行く明確な意味がわかりませんでした。
しかし、大学を卒業してからは、「大学に行ってよかった、意味はあった」と感じています。
私自身の経験を一例として、あなたが大学に行く意味を見つけるための参考になればと思います。
センター試験直前に大学に行く意味を失う。成績が落ち浪人に

現役時代の受験直前までの私には、「理系の研究者になりたい」という目標があり、そのために大学に行くと決めていました。
しかし、センター試験を残り1か月に控えたある日、突然「自分は本当に研究者になりたいのか?」と疑問を感じるようになったのです。
研究者になるためには、一般的には、大学と大学院の博士課程まで、最短でも合計9年間は学ぶ必要があります。
また、9年間学んでも研究者になれるとは限りません。なれたとしても将来が安泰とは限りません。
そういった条件の中で、「自分は本当にその学問を学び続けることができるのだろうか」「仕事として続けられる程の情熱があるだろうか」という迷いが生じたのです。
「大学には、行く」と当たり前のように思っていましたが、この迷いをきっかけに、大学に行く意味がわからなくなりました。
「自分はこのまま大学受験をしてよいのか」「大学に進学してよいのか」と、すごく悩み続けました。
悩む時間が増えるにつれて、勉強も少しずつ手につかなくなり、成績は急激に落ちました。
その結果、センター試験は大失敗、二次試験でも不合格となり、浪人することになりました。
大学に行く意味や目標を知るために、大学に行くことに
実は、大学に落ちたことについては、内心ほっとしていました。
「大学に行く意味もわからないまま進学する」ということにならず、浪人生活の中で大学に行く意味についてじっくり考える時間ができたからです。
「時間的に余裕がある中でしっかり考えて結論を出そう」と思いました。
さて、浪人を始めるまでの私は、進学先としては「理系の学部」しか選択肢にありませんでした。
ですが、文系・理系に関係なく、いろんな学部を検討することにしました。
「どんな大学・学部があり、各卒業後の進路がどうなっていて、どれが自分に向いているのか」について、調査を始めたのです。
しかし、調査を長く続けても、よくわかりませんでした。
いろんな分野の学問やその先につながる職業を調べましたが、当時の私にはどれも具体的にイメージできず、はっきりとした結論が出なかったのです。
そして私は、次のような考えに至りました。
「自分の少ない経験では、大学に行く意味も、将来どうしたいかも明確にはわからない」
「だからこそ、大学に行く意味やこれからの目標を見つけるために、大学に行ってみよう」
この考えに基づき、大学に行き始めた後に自分の進みたい道を見つける・選べるように、文系の内容も理系の内容も学ぶことができる学部を選び、受験することにしました。
大学に進学したことで「やりたいこと」などが見つかった

一年の浪人を経て、晴れて大学生になりました。
大学生になってからは、大学の授業はもちろん、サークル、バイト、インターン、短期留学など、これまでにはできなかったさまざまな経験をしました。
そんな経験をする中で自分の視野も広がり、だんだん自分のやりたいことが見えてきました。
結果として、「教育に関わる仕事がしたい」ということがわかり、大学卒業後は教育業界に進みました。
大学に進学したことで、「多様な経験」「視野の広がり」「自分のやりたいこと」「将来の道」などを得ることができた、ということです。
前章までにご紹介した大学に行く意味やメリットも、私自身、大学に入学する前はなかなかイメージできませんでした。
しかし、大学に進学し卒業した今となっては、たくさんの意味やメリットがあったと感じています。
「大学に行く前の段階」で大学に行く意味やメリットを感じられなくても、それは当然のことなのかもしれません。
大学に少しでも興味があるのなら、実際に進学してみることで見えてくる世界もたくさんあると思います。
キズキ共育塾の講師たちが考える、「大学に行く意味と、その理由」
この章では、「大学に行く意味と、その理由」について、お悩みがある人たちのための個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちからの考えやアドバイスを紹介します。
参考として、ぜひご覧ください。(これまでの内容もキズキ共育塾の知見に基づくものであるため、一部重複する部分もあります。また、講師名は仮名の場合もあります)
また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、「実際のあなた」のための、より具体的なアドバイスが可能です。ぜひご相談ください。
近藤翔平講師の考える、「大学に行く意味」
学業以外の活動や思考もできる
大学生活では、学業だけでなく、さまざまな活動に参加したり、将来について考える時間をじっくり取ったりすることができます。自分は大学卒業以来教育業界で働いていますが、きっかけは大学スタートと同時に始めた塾講師のアルバイトでした。
もちろん、中学や高校を出てすぐに働くという選択肢もあります。ただ、興味のあることや好きなことは、大学生活を通じて、中高時代以上に見つけることができます。自分も高校時代は教育業界で働くことなど全く考えていませんでした。大学生であればアルバイトの求人も幅広くありますし、サークルやゼミを通じてたくさんの人や団体とつながることができます。学業と学業以外の両方から、「いろんなこと」をしたり考えたりできる、ということです。
自分と向き合って成長できる
大学では、「専門的な学問を学ぶこと」と、「友達や先生とつながること」でさまざまな経験ができます。それに伴い、「自分と向き合って成長できること」が魅力です。
「友達」については、大学ではいろんな年代や出身地の学生がいます。彼らからたくさんの情報を吸収できるのも魅力です。
「学問」と「友達」の両方については、理系の私は、「仲間で難しい実験を協力して終わらせてから食事に行くこと」が何よりの楽しみであり、達成感を覚えました。大学へ行ってよかったなと感じています。
このように、大学では仲間と協力し合い、共有し合っていくことで、絆を形成することができます。これは大学卒業後に働く上でもとても大切なことです。大学入学をきっかけに、いろんな経験をしてみてはいかがでしょうか。
金城龍介講師の考える、「大学に行く意味」
生徒さんと関わる中で、大学に行く意味を毎日のように考えるようになりました。そして、私が考える大学に行く意味は3つあります。
①フラットな人付き合いができる
大学に行く意味の一つ目は、大学生活が自由にあふれていて、その中でフラットに人付き合いができることです。
社会に出ると、そんな機会はあまりありません。まさに大学でしか味わえない雰囲気です。そうした付き合いは、のちに続くこともありますし、その中での経験がのちに活きることもあります。
②視野が広がる
二つ目は、多様な人と会えるので視野が広がるということです。
大学には、学生、いろいろなジャンルの教授、海外からの留学生など、さまざまな人がいます。社会に出ても、このように多様性に富んでいる場所は多くはありません。私は、「人間は人間から刺激を一番もらう」と考えております。さまざまな人に出会える大学という環境は、人の視野を広げます。
③問題解決能力を高められる
②とも関連して、また大学に行く前の「受験勉強」の段階から、大学では問題解決能力を高めることができます。
問題解決能力とは、「問題を解決するために、広い視野から考えて最適な方法を考えてそれを一つ一つ実行できる能力」だと思います。社会に出て仕事をしていても、問題解決能力が常に求められます。視野については前述のとおりです。そして、受験勉強は、志望校に合格するという課題(問題)に挑む過程です。問題解決能力を養うためにいい手段と言えるでしょう。
私にとって大学に行く意味は、2つあります。
①「教員免許取得」
将来数学の教師になりたいと思っていて、そのためには大学の存在が不可欠です。そして、教師を志す仲間とともに4年間勉強できることは、大学特有の魅力的な環境です。②「私のやりたいことを自由にできる」
高校生まではやることに制限があったり、両親の許可が必要だったりすると思います。ですが、大学生は、よくも悪くも自分の責任で選択できることが大きく増えます。これは大学生ならではのよさだと思います。つまり、大学で勉強するのもよし、アルバイトに力を注ぐのもよし、留学に行くのもよし、もちろん何か新しいことを見つけて大学を辞めてもよし、などです。自分の人生を自分で決められる時間ということです。①自分の興味のある分野を、好きなだけ勉強できる
大学の面白いところは、自分の興味のある分野を、好きなだけ勉強できることです(あまり好きではない必修科目もありますが)。興味を持って授業や課題に取り組んだら、最大限に授業を楽しめると思います。
また、大学について、1つの授業を100人近くの学生が受けているイメージを持っている人もいるでしょう。大学や学部によっては、そのイメージは正解です。ですが、大人数の授業でも、よいレポートを書いたり、積極的に授業に参加したりすると、先生は必ず気づきます。そのときはまるで少人数授業のように、先生との距離を近く感じることができ、一層楽しく学べると思います。
大学の先生は、それぞれ自分の好きなことを研究してきて、仕事にしている専門家の方々です。気軽にたくさん質問をすると、とても喜んで話してくれます。
②課外活動も楽しい
授業以外の課外活動にも参加すると、すてきな経験になると思います。
大学で始める活動もあれば、中高の頃からの活動を続けることもあるでしょう。同じ活動を他の人といっしょにできることは、本当に楽しいです。別の学部や学年の学生と仲よくなったりして、交友の幅が広がってきっと良い思い出がたくさんできると思います。
部活やサークル活動に集中したいときは、授業数を減らしたり、週3日休みにしたりなど、理系でもある程度自分の好きなように予定を組むことができます。
N.T講師の考える、「大学に行く意味」
大学に行く意味について、私なりの答えを3つ書かせていただこうと思います。
①将来の幅が広がる
大学卒業の資格を得ると、就職できる企業や就ける仕事の幅が広がります。そのため、「将来に迷っていて、具体的な進路がまだ決まっていない」という人は、大学に行くことで将来の選択肢を広げることができます。
②学問を追究できる
大学という場所は、各分野に精通した教授や充実した設備などを通じて、学問に打ち込める環境が整っています。そのため、好きな学問についてとことん学び、向き合うことができます。
③自分の将来について考え行動する余裕ができる
大学生には多くの自由時間があります。そのため、「自分が何に向いているのか、将来何をしたいのか」などを考えて、いろいろ行動して、さまざまな経験を積むことができます。
O.S講師の考える、「大学に行く意味」
行かないよりも行く方がコスパがいいと思った
私自身が大学に行った理由は、恥ずかしながら「不安を低減したいから」というものが大きかったと思います。
「臨床心理士の資格取得のため、大学院を卒業する必要がある」という理由もありました。ですが、それがなくても大学に行ったと思いますし、資格は結局取りませんでした。
サッカーでも歌でも、何か自分に圧倒的な才能があれば、勉強なんてしないでそれに全力で打ち込んだかもしれません。けれども、そこまで胸を張れる一芸はありませんでした。そこで、「勉強をせず大学を卒業しないで過ごす人生での苦労」と、「大学受験のために勉強する苦労」を天秤にかけました。そして、大学受験の方がコスパがいいと思ったんです。
楽をすること、結論を先延ばしにすること、向上心がないことなどは、ともすると批判されがちです。ですが、いまの平均寿命などを考えると、「少しでも凪(な)いでる人生」を目指して大学に行くのも悪くはないのではないかなと思います。
M.Y講師の、「大学に行く意味」のアドバイス
私自身も、大学に行く意味については以前からときどき考え、そして迷っていました。もちろん、こういった疑問には絶対の答えはありません。ですが、いろいろな失敗を経た上で、「大学で何を学ぶのか」という疑問を中心に、現時点で自分の思うところをお伝えしたいと思います。
まずは、たとえば医学部や看護学部などの資格を要する職業のような専門性が高い大学や学部に行く場合を考えてみます。
その場合は、大学で学ぶ内容からしても明確な目的を持って行くことになります。後になって向き不向きを感じる懸念はあるかもしれません。しかし、こういった学部を検討するなら、基本的には「大学に行く意味とは」といった疑問は解消される可能性が高いです。ですので、自分に合う分野が見つかれば、それに関連する大学を検討するのも一つの手かもしれません。
ただ、大学の進学先を迷う多くの人にとっては、このような専門に特化した学部を目指すケースは少ないのではないかと思います。
事実、多くの文系の生徒さんに当てはまりますが、むしろ、仕事と必ずしも直結しなさそうな学問を学ぶ場合が大半だと思います。そして、現に大半の人にとって、いざ大学を終えてみたら、仕事と大学の勉強内容が直接関係なくてもあまり問題ないのだと思います。
多様な学問を選択し学べる学部(たとえば教養学部・リベラルアーツ)を選択するのであれば、大学での学問を将来に直結させなければならないというわけではないので、そこまで難しく考えなくてもよいのかもしれません。
ただし、それらを踏まえた上で、個人的に大事だと思うことがいくつかあります。それは次の2つです。
①その分野に何となくでも興味があること、あるいは嫌いではないこと
そうでないと大学での勉強を苦痛に感じたり、有意義でなくなったりするかもしれません。
②「学問に意味や意義を感じるか、あるいは好きかどうかは、究極的には情報に触れたり、体験してみないとわからない」ということ
私たちは、一切わからないことを本当の意味で好きになることはできません。だから、実際に大学に飛び込んでみるまでわからないということはどうしても残るでしょう。
ただ、全くわからないかと言うと、決してそういうことはないと思います。ネットや本などに、その大学で求められる勉強や適性など、多くの人の意見が載っています。それらを調べることで、果たして自分に向いているのか推測できます。また、大学に入る前に、自らその分野について本などで学習することもできます。人間、何かに触れさえすれば、よいとか微妙とか合わないとか、何かを感じるものです。 それらの情報や経験の解像度が高ければ高いほど、大学に入った後の「こんなつもりじゃなかった」というギャップも小さくなります。
「大学は誰かが全て教えてくれる場」とは限りません。「自分から学びたいものを学びに行く(一応)研究機関」です。なので、その練習としても、好きになるかもしれないものを試しに調べて・触れて・経験してみる。その段階で、大学で意欲的に勉強できる自分に合った学問が見つかれば、大学に行く意味についての疑問も自然と解消されるのではないでしょうか?
最近は、「偏差値の高い大学に入ればゴール」ということではなくなりました。むしろ、大学名以上に、「その大学でどう過ごし何を身に付けたか」の方に比重が移って来ています。そういう意味でも、自分からいろいろと調べたりする時間は、トータルで見ると、とても価値のある時間だと思います。
キズキ共育塾の講師が、想定していた「大学に行く意味」を実現できた体験談
この章では、個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちが、「大学入学前に想定していた『大学に行く意味』が実現できた体験談」を紹介します。参考として、ぜひご覧ください。(講師名は仮名の場合もあります)
O.S講師の体験談
①興味のある分野の情報を集めやすかった
自分の興味が入学前から固まっていれば、大学に行くことで、関連した情報をより集めやすい環境に身を置くことができます。自分は「心理学」を専攻し、入学するまで知らなかった心理学関連の職種を実際に多く知りました(家庭裁判所調査官など)。また、興味が固まっていなくても、高校ではなかなか手に入らない情報(大卒、院卒前提の求人情報やインターンの情報)も入手がしやすいと思います。
②自分のキャパシティを増やすことができた
大学は、高校までと生活環境が変わり、よくも悪くも自由度が高まり、自分で背負う責任も大きくなります。ただ、これは遅かれ早かれ人生の中でそう言うタイミングがあります。納税関係など、社会人よりはやることが少ない時期に、段階的に自分のできることのキャパシティを増やしていけるのはいいことだと思います。自分はそれぞれの家事にどれだけ時間をとられるか、どれくらい家事を省略しても生きていけるか、などを経験できたのはよかったと思います。
キズキ共育塾の講師が、想定していなかった「大学に行く意味」を知った体験談
この章では、個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちが、「大学入学前に想定していなかった『大学に行く意味』を、大学に行くことで知った体験談」を紹介します。参考として、ぜひご覧ください。(講師名は仮名の場合もあります)
近藤翔平講師の体験談
読解力やコミュニケーション力が身についた
大学に入学すると、レポート作成やゼミでのプレゼンテーションの準備などで、論文や本を読む機会が必然的に増えました。
高校時代は読解が国語・英語ともに苦手で苦労しましたが、大学生になって論文を読む習慣がついたことはプラスでした。読解力だけではなく、レポートにまとめる要約力も身につきました。
さらに、プレゼンテーションでは話の構成を意識することで、コミュニケーション能力の向上にもつながりました。大学には図書館があり自由にいろいろな本を読むことができ、ゼミという発表の場もあるため、社会人に必要な知力をつける上で非常に有意義な時間を過ごせました。
村下莉未講師の体験談
自己理解を深められた
大学に通ってみて、「自己理解を深めること」も大学に行く意味だと感じました。
大学は、中学校や高校よりも自由度が高く、さまざまなことにチャレンジできる環境があります。その中で、どの授業やコースを選択するか、どのようなサークルやアルバイトをやるか、サークル内でどのような役割を担うかなど意思決定を重ねて過ごしました。
そして、これらの判断をするためには、自分の関心や適性、癖、キャパシティを把握する必要があります。さまざまな機会の中で自己理解が深まり、その自己理解に基づいて機会を取り…ということを繰り返す中で、「自分との付き合い方」を学ぶことができました。
有木彩華講師の体験談
人生の選択肢が広がり、柔軟な考え方ができるようになった
大学に行くことで、高校までの固定観念を覆されました。人生の選択肢が広がり、柔軟な考え方ができるようになったことは、大きな利点でした。
まず、大学は非常に自由で選択肢がたくさんあります。授業の選択、バイトやサークル、休日の過ごし方まで自分で決める必要があります。初めは戸惑いましたが、授業の配分やバイト選びなど、(失敗も繰り返しながら)自分で責任を持って選んでいくことを学びました。
また、大学にはさまざまな経歴や夢を持った人がいます。ですので、たとえ「自分の考えっておかしい?」と感じたとしても、それに共感してくれる人や、むしろもっと奇抜な考え方の人がいました。いい意味で、「自分では普通で、このままでいいんだ!」と思えるようになりました。
それに付随して、高校時代までには興味のなかったロックバンドに興味を持ってツアーで日本中を旅したり、演劇サークルの裏方を手伝ったり、ラジオDJをしたりしました。以前は、想像もつかなかったことを始めました。新しい世界に飛び込むことで、毎日が楽しくなるのを感じました。
そして、「憧れの職種」に関連する勉強をする中で、また別のことに興味を持つこともあります。向いてなかったと気づいてしまうこともあります。しかし、それは悪いことだけでなく、自分自身の新たな一面に気づくきっかけにもなりました。
私はいま、高校時代では考えなかった人生を歩んでいます。視野が広がっただけでなく、さまざまな出会いを通じて、自分の新たな一面に出会えたことが、大学に行ってよかったと思うことだったように思います。
O.S講師の体験談
多様な交友関係を築けた
大学には想像していたよりも多種多様な人がいると感じました。
ただ、実際に多種多様だったのか、高校に比べて友人と関わる場面が授業以外にも多いために、いろいろな側面を知ったことでそう感じたのかは不明です。
友人が多いことが、「絶対にいいこと」かどうかはわかりません。ですが、多様な交友関係はメンタルヘルス上のリスクを低減してくれると思います。大学の入学オリエンテーションで、心理学の教授が「『精神的に自立している』とは多くの依存先を保有している状態である」という話をしていました。依存先が局所的に集中していると、そこが潰れたときに逃げ道がなくなります。
「逃げ道」となりえるような、多様な交友関係を築く場としての大学の意義は、実際に入学してみて気づいたものでした。
まとめ〜実際に大学に進学してみることでわかることもたくさんあります〜

大学に行くかどうかの決断は、簡単なことではありません。
学費や生活費もかかりますし、地元から離れる人もいるでしょう。
何よりも「大学に行く意味」がわからなければ、決断もできず、勉強にも身が入らないということはよくわかります。
大きな決断だからこそ、「しっかりと意味を考えたい」「自分の中で納得する意味がほしい」と考えるのは、とてもよいことだと思います。
しかし、事前に明確にわかる意味だけでなく、実際に大学に進学してみることでわかることもたくさんあります。
「大学に行く意味とは、○○でなければならない」ということに縛られず、少しでも大学に行くことに興味を感じ、行ってみたいと思う気持ちがあれば、それだけでも十分ではないでしょうか。
今回の記事が、あなたの「大学に行く意味」を探すヒントになったなら幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える人のための個別指導塾です。
無料相談や授業では、「高校卒業後の進路をどうするか」といったお悩みについて、一緒に考えていくことができます。
キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください。
/Q&Aよくある質問