不登校中のゲーム依存を防ぐ 禁止以外の上手な付き合い方を解説

こんにちは、不登校のお子さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートするキズキ共育塾です。
不登校中のお子さんがゲームばかりしていることについて、お悩みではありませんか?
- 不登校中、ゲームしかしてないけど大丈夫…?
- もしかしたらゲーム依存症なのかも?
- ゲーム三昧だから取り上げて禁止するしかない?
ですが、ゲーム自体は「悪いもの」ではありません。とはいえ、生活に支障が出るほどゲームに依存している場合は、何らかの対処が必要です。
大切なのは、「ゲームとうまく付き合うこと」です。
このコラムでは、子どもが不登校中にゲームとうまく付き合う方法、親御さんへの注意点などを解説します。
また、発達障害やゲーム依存の子どもの治療にあたっている、児童精神科医・関正樹医師へのインタビューや、実際に不登校だった時期にゲームに夢中になっていたキズキ講師による経験談もお伝えします。
このコラムが、不登校のお子さんとゲームの関係に悩む、あなたのお役に立ちましたら幸いです。
目次
不登校とゲーム依存~医師からのアドバイス~

年間約7,000人(2022年の延人数)の発達障害やゲーム依存の子どもの治療にあたっている、岐阜県大湫(おおくて)病院の児童精神科医・関正樹医師に、「不登校とゲーム依存の関係性」について伺いました。
①ゲーム依存と発達障害の関係
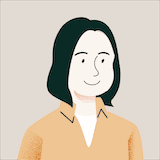
![]()
関係①ADHDの衝動性(特性)によるもの
ADHDには、多動・衝動性、不注意といった特性があります。
また、即時報酬といって、すぐに得られる報酬を好む傾向が知られています。反対に、遅延報酬と言って、遅くやってくる報酬は敬遠しやすいと言われています
それらの特性が、ゲームが持つ要素と結びつきやすいのです。
格闘ゲームやFPSやTPSなどのシューティングゲームは短時間で結果が得られやすいため、ADHDの即時報酬を好む傾向と相性がよいと考えられます。
逆に、ロールプレイングゲーム(RPG)など、コツコツと成果を積み上げる必要があるものは、クリアする前に途中で飽きることもあります。
関係②ASDの自閉的な特性によるもの
ASDのお子さんもゲームとの関係性はあるものと考えられますが、直接的な関係性ではないかもしれません。
ASDのお子さんは感情のコントロールが苦手なため、人間関係をうまく築けず、不登校に至ることも少なくありません。
不登校になり自宅にいる時間が増えると、嫌なことを考える時間も増えます。そのような嫌な気持ちを振り払うようにゲームに傾倒していくこともあります。
このように、ゲームに傾倒する原因やきっかけは、発達障害の特性によっても異なると言えます。
②最近のゲームの傾向
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査によると、2013年から2020年にかけてオンラインゲーム市場規模は約1.7倍に増えており、市場が年々拡大しています。(参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「オンラインゲームの動向整理 2022年3月」 )
中でも、スマートフォンでの市場の伸びが著しく、全体の8割以上がスマートフォンでの利用でした。(参考:「ポストコロナ時代のオンラインゲーム市場はどうなる?」)
そして今は、昔に比べて多種多様なゲームの種類も増えています。
マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると、プレイゲームの種類にも変化がみられます。(参考:クロスマーケティング『ゲームに関する調査(2023年)コンシューマーゲームプレイヒストリー編』2023年7月)
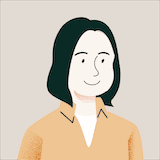
![]()
スマホでのゲームが発達してきてからは、課金をしすぎるなどのお金のコントロールの問題も出てきていますが、ガチャなどのゲームシステムはギャンブルとの共通点もあると言われています。
また、インターネットの発達とともにゲーム上で人との関わりが増えたことによって「ゲームをやめるにするタイミングが難しい」などの問題も出てきています。
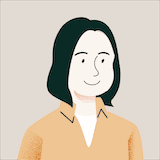
![]()
『ゲームをスムーズにやめられた方がいいことがある!』と思えば、言われなくても自然にやゲームをめらえるからです。
ゲームを辞めるタイミングに付随して、『楽しいことやいいこと』を話し合いながら見つけていくことがポイントです。
③ゲーム依存症の治療
関医師によると、治療には2つの道筋があるとされています。
その道筋は、何が原因・きっかけでゲーム依存になっているかで変わります。
![]()
ゲーム依存の背景には、不登校やADHDなどの発達障害が認められることも多くありますので、それに応じた支援が必要になってきます。
簡単に説明すると、次のような治療です。
治療法①不登校が背景にある場合
カウンセリングなどを通じて、不登校の支援をしていきます。
本人に対しては、本人の苦しみなどに共感しながら、居場所の担保や、居場所の広がりを、親御さんに対しては、対立しない親子のコミュニケーションを考えながら、家庭内でお子さんの居場所を作るよう支援していきます。
治療法②ADHDなどの発達障害が背景にある場合
親御さんに対してADHDの心理教育やぺアントトレーニングを行うとともにADHDの子どもが過ごしやすい環境調整を行っていきます。それでもうまく行きにくい場合には薬物療法も検討されます。
④ゲームと上手く付き合う方法
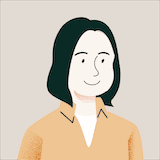
![]()
けれども、ゲームにはまったとしても、どのように回復していくかが大切です。
ゲームのオフ会など、お子さんが好きなこと・興味があることをきっかけに外出するきっかけになることがあります。
オフ会で出会った人から、新しい影響を受けることも少なくありません。そのような人との出会いが、社会参加につながっていくことも多いです。
将来のことが心配な気持ちはとてもよくわかりますが、あまり先のことばかりを考えても、嫌になると思います。
先への不安は考えれば考えるほど大きくなります。ですので、いったん横に置きながら今できることに目を向けていく必要があります。
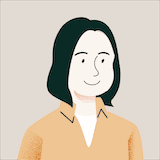
![]()
ですが、家庭内でのケンカが増えて、お子さんが引きこもりがちにならないよう、対立しないコミュニケーションを築くことが大切です。
まずは、お子さんを肯定することが大切になります。そして、お子さんが興味を持っていることに対して興味を持ち、近づいてみましょう。
子どもにとって一番の居場所は家庭です。子どもは、家庭という居場所があることで外の世界へとチャレンジしていけます。
⑤ネットと現実の考え方
お子さんとのコミュニケーションを築くにあたり、ゲーム(ネット)と現実に対する考え方は大切です。
両者をどのように考えたらよいのか、関医師に具体的な考え方を聞きました。
ゲーム(ネット)の中には、現実の学校などで会う以上に、さまざまな世代の人間がいます。
例えば、通信制高校に通っている人などに出会い、そういう人に励まされたりすることもあります(もちろんいさかいもあります)。ですので、「ネットと現実(リアル)は同一」と考えてほしいと思います。
ゲームやネットで発言している(交流している)のは、現実(=リアル)の人間です。「現実の人との関わりの方がよい」という考えは古いかもしれません。
お子さんに対して、「ネットの人間関係よりも、現実の人間関係の方が価値は高い」などといった否定的な発言をすれば、家族との会話にも耳を傾けたくなくなるでしょう。
不登校になると、学校に行っていない負い目から、子どもは「何者にもなれない」と思いがちです。
ですが、ゲームを通して人と交流することで、「人とゲームをして楽しかった」などの感情が芽生えます。そうした社会性が、ゲーム(インターネット)のよいところです。
ゲームの中では、学校とは異なり、「不登校のAくん」ではなくなります。「ただのAくん」になれることが、お子さんにとって自由で居心地のよい場所になり得るのです。
このようなお子さんの世界を理解し、親子で会話ができる関係を築いていくことが大切になります。
いずれ、お子さん自身も同じ生活の繰り返しに、だんだん退屈になっていくかもしれません。そんなとき、ちゃんと話を聞ける関係性でいられるかが、鍵となります。
⑥関医師からのメッセージ
ここからは、ゲームに依存しがちなお子さんを持つ親御さんに向けた、関医師からのメッセージをご紹介します。
ゲームにかかわらず、お子さんの好きなものは大切にしてほしいと思っています。
ただし、ゲームだけに一点集中するのではなく、ほかの余暇活動も一緒にできるとよいでしょう。ゲーム以外の楽しいことを見つけていくことが大切です。
お子さんが、「ゲームの中の何に惹かれてやっているのか」を知ることで、ヒントがあるかもしれません。また、親御さんも一緒にやってみるなど、お子さんのやっていることに興味・関心を寄せることが大事です。
親御さんは、お子さんに対して「ゲームをやめてほしい」と思うケースが多いのですが、そればかりに焦点があたっているように感じるからです。
そんなときには、次のようなことを考えてほしいと思います。
- お子さんとどんな生活がしたいのか
- お子さんに勉強をしてほしいのか
- お子さんともっと会話をしたいのか
- お子さんと一緒に買い物がしたいのか
お子さんとどんな関係でいたい・なりたいのかを、ぜひ一度立ち止まって考えてみてほしいと思います。
それによって今できるコミュニケーションは違ってくるからです。
ゲームが不登校の「原因」とは限らない

この章では、不登校だった時期にゲームに夢中になっていたことがあるキズキ講師の経験を交えて、不登校とゲームの関係について解説します。
ゲームを取り上げるより「根本的な解決」が必要
不登校のお子さんがゲーム三昧な様子を見ている親御さんは、「不登校の『原因』はゲームにあるのでは?」と考えることもあると思います。
「不登校の原因がゲームである」ケースは、確かにあるかもしれません。
しかし、先ほど関医師も指摘していたとおり、諸々の調査やキズキ共育塾にご相談いただくケースを踏まえると、それはかなり少数派のように思われます。
発達障害やゲーム依存の治療相談に携わる精神科医の八木眞佐彦先生は、自身の著書の中で、子どもにとってゲームは「学校や家庭での孤立感、対人関係のストレスなどを解消するもの」としています。(参考:花田照久・八木眞佐彦『ゲーム依存からわが子を守る本』)
つまり、八木先生の言葉を借りるなら、ゲームがその子にとっての心の拠りどころ、「生きていくための心の杖になっている」場合があるのです。
さらに、その著書の中では、ゲームを取り上げたり禁止したりすることは、根本的な解決には結び付かず、それよりも「ゲームに打ち込む要因となった環境を改善する必要がある」とされています。
実際に、私が不登校だった間、惰性でゲームをやり続けていた時期がありました。そのときに私の根底にあったのは、他にすることがない、拠りどころがない現状や環境への不満でした。
きっかけは「いじめ・人間関係の悩み」である場合も
いじめや人間関係の悩みなどがきっかけで不登校になった子もいると思います。
そうした子の場合は、不登校で生じた孤独な時間を埋めるものがないから、オンラインゲームなどでネット上の人との交流を図ったり、時間を潰したりしているケースもあります。
「ゲームが原因で不登校になった」のではなく、「不登校ですることがない、またはその不安を解消するためにゲームをしているだけ」の可能性があるのです。
ただし、ゲームと関係なく不登校になった場合でも、不登校によってゲームとの距離感・バランスが崩れる「ゲーム依存」は、防ぐ必要があります。
ゲーム依存になると、学校や勉強だけでなく、日常生活にも支障が出る可能性が高いからです。
ゲーム依存に関する社会の動き
ゲーム依存は、2019年5月にWHOが「ゲーム障害」を定めたこともあり、社会問題としても広く認知されつつあります。
日本でも、香川県が「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」を定めたのは有名な話です(賛否両論ありますが)。
ゲームが不登校の直接の原因だとしても、またはそうでなかったとしても、いずれにせよ「ゲーム依存」を回避することが大切だということを、ぜひ心に留めておきましょう。
不登校の子どもがゲームをする5つの理由
この章では、不登校の子どもがゲームをする理由を具体的に解説します。
ひとつ念頭に置いていただきたいのが、これから挙げる理由は「ゲームだけに限らない」ことです。
不登校の子の中には、ゲームではなく、漫画を夢中になって読んだり、アニメやYouTubeなどを観たりする子もいます。
ゲームには、もちろんゲームだけの特徴があります。ですが、ある種の娯楽や当面の現実逃避という点では、その他のメディアなどと同じです。
そのため、これから解説する理由は、「不登校の子が娯楽に夢中になる(なっているように見える)理由」と捉えていただけると、より理解が深まります。
また、これから紹介する理由は、実際に「ゲームが原因の不登校」に共通する点もあります。「原因がゲームかどうか」に関わらずご覧ください。
理由①ゲームの他にやることがないから

1つ目の理由は、ゲームの他にやることがないからです。
先述したように、これは不登校だった当時の私も感じていたことです。
不登校になるまでは朝から夕方まで学校で授業を受けていたため、不登校になってからは時間が間延びして感じられました。
そうした暇を持て余しているときに、自宅で手軽に楽しめるゲームのような娯楽があると、その間延びした時間を埋めるために、際限なく続けることがあります。
「他にやることがない」という感情は、不登校の子であれば多かれ少なかれ感じているはずです。
理由②ゲームをしていると現実を忘れられるから

2つ目の理由は、現実を忘れられるからです。
不登校や引きこもりの子どもは、自分の現状を振り返ったり自覚したりすることが苦痛になることもあります。
そうしたときに、ゲームの世界に没頭することで、現実逃避できるのです。
また、学校での嫌な体験やトラウマを抱えている不登校の子には、ゲームで現実を忘れることが気持ちの回復につながる場合もあります。
理由③ゲームが単純に楽しいから

3つ目の理由は、単純に楽しいからです。
昨今のゲームは、プレイヤーをゲームの世界に引き込む仕掛けがたくさん盛り込まれています。映像技術を駆使して演出を派手にしたり、他人とのコミュニケーションを楽しめるシステムを取り入れたりなど。
ほかにも、新しいイベントや期間限定のフェアを次々に開催して、プレーヤーを飽きさせないようにしているのです。
そのため、「単純に楽しいから」ゲームにのめり込む不登校の子も少なくありません。
理由④ゲームが居場所になるから

4つ目の理由は、居場所になるからです。
特にオンラインゲームでは、プレイヤー同士が会話できるチャット機能があったり、一緒に協力してプレイしたりするものが多いです。
気に入った名前を付けて、現実世界の友達と同じようにやり取りができます。
そのため、学校の人間関係に問題があったり、対人不安を抱えていたりする子どもにとって、ゲームが「居場所」になるケースがあるのです。
不登校の子の中には、こうした理由から「ゲームをしていると落ちつく」と感じる子もいるようです。
理由⑤ゲームをすると達成感を得られるから

5つ目の理由は、達成感があるからです。
ゲームによっては、「クエスト」と呼ばれる依頼やタスクをこなすことで、操作しているキャラクターが成長していくものがあります。
先述したように、協力してプレイをする場合には、そうした成長がチームの仲間を助けることに直結するため、自信を高めることにもつながるのです。
このようなゲーム内での成長と結びつく「達成感」も、不登校の子がゲームに入れ込む理由の一つと言えます。
不登校の子どもがゲームとうまく付き合う方法5選
この章では、不登校の子どもがゲームとうまく付き合う方法を解説します。
大切なのは、これから解説する方法を「強制する」のではなく、子どもが自らやろうとする「自主性を促す」ことです。
徐々に習慣づけていき、お子さんが自然に実行できるまで、根気強く付き合うことを意識しましょう。
方法①区切りをつけてやりきる

1つ目の方法は、区切りをつけてやりきることです。
不登校の子に頭ごなしに「ゲームをしてはいけない」と禁止したり取り上げたりしても、反発を招くなど逆効果になる場合があります。
それよりも「何時から何時までの間は思いきりやっていい」と割り切って、限定付きでゲームを肯定することがオススメです。
子どものゲームへの欲求を満たすことで、自然とゲーム離れが進みやすくなります。
また、先述したように、タスク単位で進むゲームであれば、それを片付けて達成感を得たタイミングで区切ることも効果的です。
まずは、時間やタスクなどの「区切りをつけてやりきる」方法を取りいれてみましょう。
方法②一日のスケジュールを立てる

2つ目の方法は、一日のスケジュールを立てることです。
楽しいからゲームをする子も、惰性でやり続けている子も、根底に「予定がない」感覚があります。
まずは日課を作ったり、行動予定表を考えたりしてみましょう。
買い物や家事など、あまり負担に感じない範囲の軽いお願いごとをするのも有効です。
また、スケジュールにはゲームの時間も盛り込むことも大切です。
ゲームの時間を決めるきっかけにするためにも、「一日のスケジュール」を立ててみてください。
方法③生活の中で目標を持つ

3つ目の方法は、生活の中で目標を持つことです。
不登校や引きこもりの期間は、「生活に張り合いを持てない」子どもも多いです。
結果として、長時間ゲームを続けることで、時間を潰すことがあります。
そのため、子どもが生活の中で「目標を持つこと」自体が前進につながるのです。
前の項目で挙げた「スケジュール」を守るなど、最初は簡単なことで構いません。その日の目標を親子で一緒に定めてみましょう。
なお、最初のうちから目標をいくつも作ると、達成することが難しくなります。まずは一つだけ簡単な目標から始めて、継続することを意識しましょう。
方法④ゲーム以外に興味が持てることを探す

4つ目の方法は、ゲーム以外に興味が持てることを探すことです。
ゲームしかしてない状態であれば「依存」かもしれません。ですが、ゲーム以外にも好きなことを見つけて時間を分散させているのであれば、それは「趣味のひとつ」です。
特に不登校の場合は、長時間ゲームだけをしていることで、結果的に引きこもりになるケースもあります。
こうした場合は、屋外で楽しめる趣味を探すことがオススメです。
外に連れ出すことが難しい場合は、一緒に映画を観るなど、家族の時間を作るのもよいかもしれません。
無理に外出しなくとも、家庭でできる趣味はゲーム以外にもたくさんあります。
ぜひ、ゲーム以外に興味が持てることがないかを、ぜひ考えてみましょう。
方法⑤外に居場所を見つける

5つ目の方法は、外に居場所を見つけることです。
先述したように、ゲームの中に居場所を求めている不登校の子は、学校以外に居場所を見つけることで、ゲームと距離を取れる場合があります。
ぜひ、お子さんの居場所を親子で一緒に探してみましょう。
例えば、不登校のお子さんの居場所として、フリースクールが挙げられます。
フリースクールとは、不登校など、何らかの事情で学校に通えない子どものための教育施設です。
学校によっては、そうしたフリースクールやサポート校への出席を「学校への出席」とカウントできる場合があります。
まずは、在籍している学校やご検討中のフリースクールなどに確認してみてください。
また、学習塾もお子さんの居場所として考えられます。
学習塾によっては、不登校の子を指導した実績を多く持つところもあります。
このような塾では、不登校を実際に経験した講師の先生がいることもあるので、不登校の悩みを相談しやすいと思います(私たちキズキ共育塾でも、不登校に関する無料相談を受け付けています)。
いきなり勉強することが難しければ、簡単な習いごとから始めることもよいでしょう。
ゲームに居場所を求めている子には、他に居場所になりそうなところを提案してみてください。
動画では、このコラムの内容に補足して、実際にゲーム依存で高校を不登校だったときの生活・気持ち、ゲーム依存から抜け出した方法などをお伝えしています。
ご興味がありましたらぜひご覧ください。
ゲーム好きの不登校の子どもを持つ親の注意点
この章では、ゲーム好きの不登校の子を持つ親御さん向けに注意点を5つ解説します。
不登校の子に接する上で一番大切なのは、「見守る姿勢を保つこと」です。
親御さんにとっては一見無意味に思えたり怠けて見えたりする場合であっても、不登校の子には心の調子を取り戻すために必要な期間であることが多いです。
そうした時期に親御さんから過敏に反応されると、心が休まりません。逆に、「不登校から次の一歩を踏み出すこと」にお子さんが戸惑いを感じることがあります。
ただし、「見守る姿勢を保つ」だけではなく、(見守る姿勢を保つためにも)親御さん自身も心の余裕を持つことが必要です。
親御さんも意識的に、気持ちを切り替えるための息抜きやリフレッシュをしてください。
注意点①無理にゲームを取り上げない

1点目の注意点は、無理にゲームを取り上げないことです。
お子さんからゲームを取り上げ感情を刺激すると、親子の信頼関係が損なわれる可能性があります。
また、ゲームが居場所になっていた子にとっては、急に居場所を失うことになるため、ストレスが増す恐れもあります。
無理にゲームを取り上げることは、不登校の解決にはつながりません。
不登校の子がゲームから離れ、次の一歩を踏み出すためには、取り上げる以外の他の手段を探すことが大切です。
注意点②感情的に叱らない

2点目の注意点は、感情的に叱らないことです。
ゲームしかしてないお子さんの様子を見ると、イライラするのも仕方ないかもしれません。
ですが、先述したように、ゲームによる現実逃避はお子さんが心の調子を取りもどすための行動である可能があります。
親御さんが感情的に叱ることでお子さんが萎縮して、よりゲームにのめり込んだりストレスが大きくなったりする可能性があるのです。
お子さんがゲームに依存しないか心配になるお気持ちはとてもよくわかりますが、感情的に叱ることなく長い目でお子さんを見守りましょう。
注意点③ゲームの肯定的な面を考える

3点目の注意点は、ゲームの肯定的な面を考えることです。
ゲームは否定的な面ばかりが取り上げられがちですが、肯定的な面もあります。
- オンラインゲームでコミュニケーション不足を補う
- チャット機能のあるゲームで人との距離感や付き合い方を学ぶ
- パズルゲームで思考力や記憶力を鍛える
また、近年ではゲームが「eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)」として競技化されたり、各地で大会が催されたりするなど、肯定的に捉える動きが高まっています。
そのため、引きこもりや不登校の子どもであっても、ゲーム好きが高じて大会を観戦に行ったり、趣味の友達を作ったりすることに積極的になるケースもあるようです。
ゲームには否定的な面だけでなく、肯定的な面もありますので「ゲーム好きを活かせないか」と視点を変えてみてください。
注意点④課金や犯罪に気をつける

4点目の注意点は、課金や犯罪に気をつけることです。
最近では、「子どもがスマホゲームに没頭するあまり、多額の費用をつぎ込んだ」という話を聞くこともあります。
お小遣いや自分で稼いだお金で楽しむ分には問題ないのでしょう。ですが、詐欺に巻き込まれたり気づかずに犯罪に加担していたりするケースもあります。
自宅に請求の連絡があったりしない限り、親御さんが気付くのは難しいかもしれません。ただし、お子さんがやたらにお金を必要としていないかなど、日頃の振る舞いや言動に注意しましょう。
注意点⑤ゲーム依存症かどうか医師の判断を仰ぐ
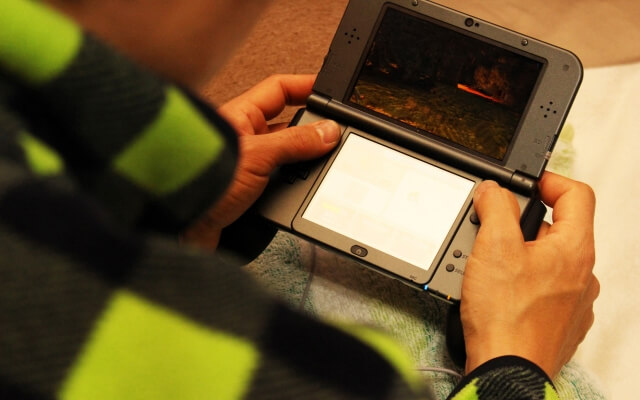
5つ目の注意点は、ゲーム依存症かどうか医師の判断を仰ぐことです。
先述したWHOの「ゲーム障害」のように、生活に支障を来たす程度の「ゲーム依存」になっている場合には、親御さんの力だけでは断ち切れない可能性があります。
激昂したお子さんが暴力を振るうといった事件も、ニュースなどで耳にします。
ゲーム依存症が疑われる場合は、ひとまず医師に判断を仰ぎましょう。
まとめ~不登校中はゲームと上手に付き合いましょう~

繰り返しにはなりますが、ゲームは必ずしも不登校の原因とは限りません。
また、ゲーム自体は決して悪いものではないのです。
大切なのは、ゲームとの上手な付き合い方です。
不登校中は時間も余っているため、ゲーム依存に陥りやすい状況です。ですが、日頃の心掛けと親御さんの注意、そして医師や「不登校のサポート団体」などとの相談などで、依存を防いだり解消したりすることはできます。
不登校の間の生活を充実させて、次の一歩を踏み出しましょう。
このコラムが、不登校でゲームに三昧になっている子どもを持つ親御さんの助けになれば幸いです。
Q&A よくある質問









