落ち込みやすいあなたへ 落ち込みやすい原因と改善法を解説
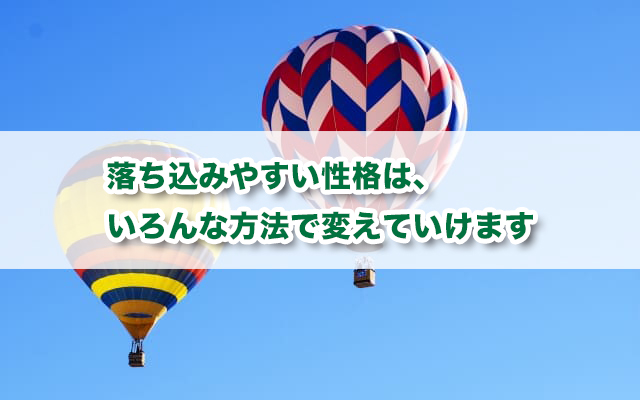
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、自分が落ち込みやすいことに悩んでいませんか?
- 「どうしてこんなことで落ち込んでしまうのだろう…?」
- 「もっと強いメンタルがほしい」
筆者も、とても落ち込みやすい性格だったので、お気持ちがよくわかります。
落ち込みやすい性格は、ものの見方を変えてみたり、ちょっとした行動を積み重ねたりすることで改善できます。
例えば、「自己肯定感を持つ(ための行動をする)」「隣の芝生は青く見えることを知る」などです。
今回は、落ち込みやすい原因と対処法、落ち込みやすい性格の改善方法を、詳しく解説していきます。
私たちキズキ共育塾は、落ち込みやすい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
落ち込みやすい10の原因と対処法
落ち込みやすい自分の性格を責めたり、メンタルの強い人をうらやましく思ったりしていませんか?
- 「どうしてこんなに落ち込みやすいんだろう…」
- 「あの人みたいにポジティブで明るい性格になりたい」
この章では、落ち込みやすい原因と、原因に対応するカンタンな対処法をお伝えします。
原因①劣等感がある

劣等感がある人は、落ち込みやすくなります。
思考の根底に「自分は劣っている」という意識があるからです。そして、何か嫌なことが起きると「自分の責任だ」「自分が劣っているからだ」と考えるのです。
劣等感の克服の仕方は、以下のコラムをご覧ください。
原因②比較しすぎる癖がある
人と自分を比べすぎる人も、落ち込みやすいです。
「隣の芝生は青く見える」と、よく言いますよね。
自分と他者を比較する癖がある人は、「他者のよいところ」と「自分のできていないところ」が目につきやすくなります。
そして、自分はダメだと落ち込むことに繋がるのです。
自分と他人を比較すること自体は、悪いことではありません。
ですが、「比較しすぎている」ときは、別のことを考えたり体を動かしたりして、その思考から離れるように意識してみください。
原因③物事を客観視できない

物事を客観視できない人も、落ち込みやすいでしょう。
例えば、友達が不機嫌な態度だったとき、「私が何か言ったから怒ったのかな」と落ち込むことはないでしょうか?
「友達が不機嫌」なのは「自分が原因」と即座に考えるのは、物事を客観的に見れていないことのあらわれです。
友達には何か嫌なことがあって、たまたまあなたと会ったときにも不機嫌だったのかもしれません。
筆者が見てきた限りでは、「あなたが原因」と「あなた以外が原因」では、むしろ後者が圧倒的に多いと言えます。
このように、状況を客観視できないと、何事も「自分のせいだ」「私が劣っているからだ」と考えて落ち込みやすいくなるのです。
「何かの出来事」を自分と関連づけて考える前に、それ以外の可能性を考えてみましょう。
原因④周りの目や協調性を気にしすぎる
周囲の目を必要以上に気にしたり、協調性を大切にしたりする人も落ち込みやすい傾向があります。
人間関係は、常にスムーズにいくとは限りません。
誰かに腹の立つこともあれば、つい不機嫌な態度を取ったり、嫌なことを言ったりすることもあります。
その一つひとつを必要以上に気にしていると、落ち込む頻度が増えるのです。
みんなと仲よく過ごしたい気持ちは保ちつつ、一方で、人間関係で過剰に気を使って疲れないよう、必要以上に人の目を気にしないように意識してみてください。
原因⑤自分への理想が高い

自分への理想が高い人も、落ち込みやすいです。
「理想の自分」にこだわりすぎると、何かあるたびに「まだ理想に達していない自分」が気になります。
理想に向かって向上しようとすることは素晴らしいです。ですが、「今の自分」のいいところ、できているところにも適度に目を向けることが大切です。
原因⑥完璧主義・ゼロか100か思考
理想が高い人とも関連しますが、完璧主義の人も落ち込みやすいです。
完璧主義の人は、「理想どおりにできた(100点)」か「理想どおりにできなかった(0点)」と、極端な考えになりがちです。
そして、完璧に理想どおり(100点)にできないと、やる気を失って落ち込み、自分を責めるのです。
「何かが完璧にできること(100点)」は、「完璧にできない体験(30点や60点の体験)」を積み重ねてこそ、できるようになります。
30点や60点の自分でもOKと思えるように、心掛けてみましょう。
完璧主義の克服方法は、以下のコラムをご覧ください。
原因⑦心に傷がある

いつも同じことで落ち込む人や、一つの失敗のことで繰り返し落ち込む人は、心に傷を抱えているのかもしれません。
たとえば、「仲よくなった友達と最終的にはいつも不仲になり絶交して落ち込む人」について考えてみましょう。
こういう人は、「人を信用するのが怖い」「親しい人に敵意を感じる」といった心の傷を抱えている可能性があるのです。
心の傷がある場合は、カウンセリングなどを受けることを一度検討してみてください。
原因⑧環境が合っていない
「優秀な生徒ばかりの進学校に入学した」「競争心の激しい人の多い職場で働いている」など、今置かれている環境が落ち込みやすさの原因になる場合もあります。
そのような環境では、日頃は自他を比較しない性格であっても、単純な事実として「周りと比べてできない自分」を意識する機会が多くなるのです。
可能であれば、一度今の環境から離れることを検討してみてください。
いきなり「学校や仕事を変える」のではなく、休暇を取る、旅行に行くなど、まずは少しだけ今の環境から離れて自分を見つめ直すことがオススメです。
その後、今の環境が本当に向いていないと思ったら、本格的な変更を考えてみてください。
原因⑨褒め言葉をネガティブにとらえる
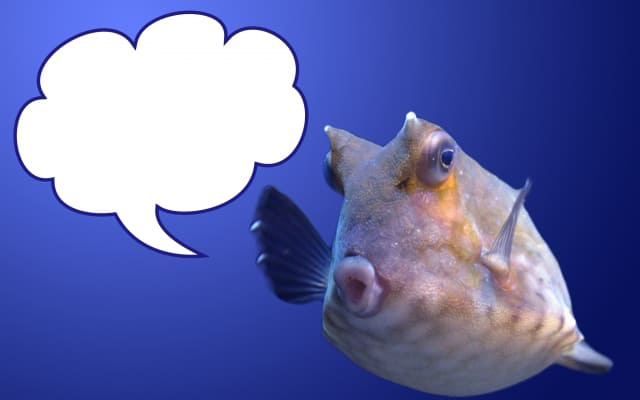
言われた言葉をネガティブにとらえる人も、落ち込みやすいです。
たとえば、「まじめな人ですね」という言葉は、基本的には褒め言葉です。
あなたがそう言われたなら、それはあなたの誠実な人柄を褒められているのでしょう。
ですが、「面白味のない人だ」という皮肉の意味で使われる場合が考えらるかもしれません。
しかし、どんな場合でも褒め言葉を「皮肉だ」と受け止めて落ち込むのは、あなたの物事のとらえ方が間違っており、そのために落ち込んでいる可能性があるのです(これを、「認知の歪み」と言います)。
「おとなしい」「マイペース」なども同様です。
褒め言葉を言われたら、基本的には素直に受け止めるようにしましょう。
原因⑩発達障害が関係する
発達障害という言葉を聞いたことはありますか?
ここでは詳細な説明は省きますが、発達障害とは「脳の機能の障害のこと」です。
発達障害の症状には、「一つのことに集中して取り組めない」「忘れ物が多い」「漢字が覚えられない」などがあります。
見た目でわかる障害ではありません。ですので、自分も周りもなかなか気づかないことも多いのです。
その結果、「周りと同じように行動したい、結果を出したいけど、できない」という経験が積み重なり、落ち込みやすくなります。
発達障害があると大変なことはありますが、それをフォローする方法もたくさんあります。
気になる人は、医療機関に行って診断と対応方法を聞いてみてください。
発達障害の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください(親御さん向けの記事ですが、ご本人が読んでも参考になります)。
落ち込みやすい性格の改善法13選
この章では、「落ち込みやすい性格をどうにかしたい!」と思っているあなたに、ここからは落ち込みやすさの改善法を13個お伝えします。
これまでにお伝えした「原因と関連する対応」を深掘りした改善法もありますが、直接的に原因と関連しなくてもある程度は役立ちます。ですので、あなたの状況や性格に合わせて取り入れてみてください。
方法①自己肯定感を持つ

「自己肯定感」は、とても大切です。
「自己肯定感」を持つだけで、落ち込みやすかったり悩んだりすることが大幅になくなり、あなたの人生は大きく変わります。
今この瞬間から、「私はすばらしい」と思うことは難しいかもしれません。ですが、毎日の生活の中でコツコツと「自己肯定感」を育てていくことはできるのです。
「自己肯定感」を持つためにできることとして、以下が挙げられます。
- 自分を責めることをやめる
- 他人を責めたり見下したりするのをやめる
- 今までの人生を全肯定する
そして、自分や他人を責める気持ちや後悔が襲ってきたら、「あ、私は自分をいじめている」と意識してその思考を断ち切りましょう。
毎日コツコツと続けていけば、少しずつ「自己肯定感」は育ちます。
自己肯定感そのものや、自己肯定感を持つ方法は、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
方法②反省して改善策を見つける
落ち込んだときは、つらいと落ち込むばかりではなく、「何がいけなかったのだろう」と反省することも大切です。
例えば、「テストの成績が悪かった…」と落ち込むだけでは、次回も同じことを繰り返す可能性があります。
そうではなく、反省して「テストの成績が悪かったのは、勉強を始めるのが遅かったからだ」と気づければ、「次回はもっと計画的に勉強しよう」と対処法を考えられます。
すると、次のテストでは対策ができて、落ち込むことが減っていくでしょう。
他に、友達に悪口を言われて落ち込んでいるの場合は、反省することで「『言い返せる自分』になる必要性」に気づくかもしれません。
反省するのための方法として、「落ち込んだときに、ノートを使って自分の気持ちを整理する」ことがオススメです。
「自分の感情が何に落ち込んでいるのだろう?」「本当の問題はどこにある?」
自分の部屋やカフェ、図書館で1人になって、こういったことを考えながら、ノートをどんどん埋めていきましょう。
ノートに感情を吐き出し反省することで、「何がいけなかったのか」「どうすればいいのか」が見えてくるはずです。
また逆に、気持ちを整理するうちに「そんなに落ち込むことじゃなかったな」と気づけることもあるかもしれません。
方法③周りは立派に見えていても錯覚だと知る
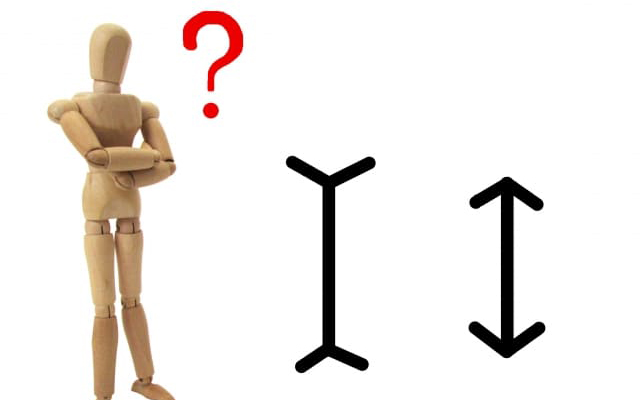
自分と周りの人とを比較しすぎて落ち込みやすい人は、「(特に比較するときには)他人は、実際以上によく見える」ことを覚えておくようにしましょう。
先述した通り、「隣の芝生は青く見える」ものです。
反対に、他者を見下して優越感に浸る人も、他人と比較して落ち込む人と同じだと考えられます。
自分に自信がなくて隣の芝生が青く見えるのが怖いから、先に他人を見下すことで自分を守っているのです。
また、他人があなたに見せているのは「よく見える部分」「盛った部分」だけであることも、よくあります。
家族や親友など親しい人の中にも、「いい部分」しか見せない人はたくさんいます。
いつもうまくいっているように見える人は、「盛って見せる」のが上手い人であることも少なくありません。
勉強のできるあの子も、出世していく同期も、実際はあなたと同じように、欠点や劣等感に悩んでいるかもしれないのです。
「あの人はすごいかもしれないけど、完璧ではないはず。そして、自分もよくやっている」と思うことで、落ち込みやすい性格は次第に変わっていきます。
あなたも充分にがんばっていますし、周りから見ればあなたの芝生だって青く見えていますよ。
方法④状況を客観視する
落ち込んだときは、自分の状況を客観的に見ることを意識しましょう。
そうすると、以下のような現実が見え、対応方法がわかってきます。
- 落ち込んでいたけど、よく考えると落ち込む必要はないのかも
- これは落ち込んで当然の失敗。でも原因が分かったから次からは気をつけよう
- もっと事実を確認しないと、なんとも言えない
状況を客観視するためには、反省と同じく、ノートに書いて振り返ってみることがオススメです。
自分の部屋や図書館やカフェで、好きな飲み物を飲みながら、落ち込んだ出来事の経緯、自分の感情、そこに隠れている本当の問題、私はどうしたいかなどを、思いつくままにどんどん書き出してみましょう。
例えば、簡単な例として、以下のようなことが考えられます。
状況
- 朝、友達のAくんに挨拶したけれど無視された
そのときの気持ち
- Aくんは自分のことを嫌いになったから挨拶を返さなかったんだと思い、とても落ち込んだ
客観的な事実や可能性
- 挨拶を返さなかったのは事実だけど、僕を嫌いかどうかは確認できていない
- 僕の挨拶に気づかなかったのかもしれないし、体調が悪くて他の人にも挨拶を返していないのかもしれないし、別の可能性もある
- 明日、様子をしっかり確認しよう
- 実際に嫌われているとしても、自分には原因が思い当たらない。誤解があるのかもしれないし、僕が気づかずに失礼なことを言ったのかもしれないから、これもできれば確認したい
このように、事実や可能性などを書き出すことで、次の一手が見つかりやすくなります。
こうした思考や手法を習慣づけると、落ち込みやすい性格は変わっていくはずです。
方法⑤自分の認知傾向を知り変える

例えば、「まじめですね」と言われたときに、「面白味のない人間だと言われた」と落ち込む人は、物事のとらえ方が間違っているかもしれません。
そんな状態のことを、「認知の歪み(認知が歪んでいる、認知に歪みがある)」と言います。
認知の歪みの多くは、自分が気にしていること(コンプレックス)に深く関わりがあります。
他の例として、太っていることを気にしている人が、「たくさん食べてね」と言われたときに落ち込むことがあります。
これは、相手は「(おいしいから)たくさん食べてね」と言っただけなのに、その人は「私が太っていて大食いに見えるからそう言ったんだ」と一方的に解釈して落ち込むのです。
認知の歪みを感じたときも、ノートに状況や自分の気持ちを書き出してみてください。
- 相手は直接的に何と言ったのか?
- 自分はその言葉を聞いてなぜ落ち込んだのか?
- その解釈は正しいのか?
事実や感情などを書き出すと、自分の認知の傾向がわかり、徐々に歪みを改善できるでしょう/span>。
方法⑥自分の力でどうにもならないことは気にしない
人生で遭遇する出来事などは、以下の2つに分けられます。
- 自分の力でできる(変えられる)こと
- 自分の力ではどうにもならないこと
例えば、受験勉強では「合格のために勉強すること」は、「ある程度は、自分の力でできること」です。
では、「ある程度の勉強」をすれば、必ず合格するのでしょうか。
以下のように、自分の力ではどうしようもないことが関係して、不合格になったり進学できなくなったりすることもありますよね。
- 「ある程度」以上の、志望大学のための対策が受けられる塾が近所になかった
- 家庭の事情でアルバイトを行う必要があり、受験勉強に集中できなかった
- 同じ大学を受験する人たちが、去年までよりもたまたまレベルが高かった
- 受験直前に、相手の不注意で交通事故にあって利き腕を骨折した
また、友人関係や恋愛の例では、「相手の気持ち」を「ある程度」までであれば、あなたの言動で変えられることもあるかもしれません。ですが、それ以上に仲を深められるかどうかは、相手次第なのです。
あなたが「仲よくなりたい」と思っても、相手も同じようにそう思うかどうかはわかりません。
望んだような結果が得られなくても、「自分の力ではどうにもならないこと」を気にしないことが、落ち込まなくなるコツです。
とはいえ、全く落ち込まないのは難しいでしょう。
ですが、以下のように、少しずつ考えや行動を変えていくことで、落ち込みやすい性格は変わっていきます。
- 自分にはどうしようもないことで悩んでも仕方ない
- できることを増やして、ちょっとでも可能性を広げよう
- この目的・希望は叶わなかったけど、それに代わるものはないかな
方法⑦人との交流を増やす

人間関係の幅が狭いと、どうしても視野が狭くなりやすいです。
筆者の教えている生徒さんにも、「普段、親としか話をしない」「特定の友達としか関わらない」ために、狭い考えにとらわれて悩んでいる人がいらっしゃいます。
人との交流(人間関係)を広げると、多様な価値観に触れたり、あなたを尊重する人と出会ったりできるため、落ち込みやすい性格は変わることがあるのです。
落ち込みやすい人は、意識的に交流する人を増やしてみてください。
たとえば、以下のような例があります
- 職場や学校以外の人(新しくアルバイト・習い事・ボランティアなどを始めると出会えます)
- 学校や塾や習い事の先生
- カウンセラー
- (実家を出て家族と疎遠なら)日頃、連絡を取らない実家の家族
- SNSなどで知り合った人
あなたの周りにも、「この人とならちょっと話ができそうだな」と思える人や、「ここに行ったらいろんな人と交流できそうだな」という場所がありませんか?
心当たりがあれば、積極的に行動してみましょう。(ただし、アルバイト・習い事・ボランティアなどの場では、労働や慈善活動など、その「本来の目的」にも興味を持ち、実行することが大切です)
心当たりがない場合は、以上の例のようなものをインターネットで探してみてください。
また、人づき合い以外でも、本を読むと新しい考えに触れられます。
特に人間関係を描写した小説、心理・哲学を扱った本、自己啓発本などからは、落ち込みやすさ解決のヒントが得られることがあるはずです。
方法⑧安心できる場所・人間関係をつくる
「落ち込みやすい環境にいるけれど、転校(転職)はすぐにできない」ときには、安心できる場所(人間関係)を一つ作ってみましょう。
前項「人との交流を増やす」はどちらかというと「広く浅く」で、こちらは「深く狭く」というイメージです。
家族、恋人、親しい友人など、あなたのことを大切にしてくれる人と一緒にいる時間を、意識的に作るのです。ペットもあなたを受け入れて入れる大切な仲間の一人です。
身近には安心できる人がいない人も、大丈夫です。
まずは、家族や親戚が候補になります。
実家を離れているなら(そして家族仲が悪くないなら)、実家の親兄弟に連絡してみてください。
実家にいても、「別に仲が悪いわけじゃないけど、あまり話していない…」と思うなら、試しに話してみてはどうでしょうか。
家族仲があまりよくなかったり、今現在親しい友達や恋人がいなかったりするようなら、新しい居場所(人間関係)を作ってみましょう。
前項「人との交流を増やす」であげた候補を参考に、まずは「広く浅く」人付き合いを増やし、その中から特に安心できる居場所(人間関係)の候補が見つかれば、「狭く深く」関わってみてください。
方法⑨闘う(やめてほしいとはっきり言う、周りに相談するなど)

いじめやパワハラがあるために落ち込みやすい、と言って環境を変えることも(すぐには)できない、など場合には、闘うことも必要です。
いじめ、パワハラ、マウンティングなどをする人は、「言いやすい人」に八つ当たりをして自分の不満を解消しているのです。
何かを言われて「落ち込む」のではなく、「闘う勇気」を持ちましょう。
「闘う」と言っても、「暴力的にやり返す」わけではありません。
具体的には、「言い返す」「やめてほしいとはっきり言う」「(環境は変えられないとしても、少しでも)距離を置く」などの方法です(「距離を置く」のも、立派な「闘い」ですよ)。
しかし、これは今現在落ち込みやすいことに悩んでいるあなたにとって、また相手がどんな人かによっては、難しいかもしれません。
そんなときは、声に出して言い返すのではなく、心の中で言い返しましょう。
心の中で「パワハラをしたら許さない」と毅然と構えているだけでも、不思議と状況は変わることがあるのです。
筆者も、以前の職場にパワハラをする上司がいたことがあります。
嫌がらせを受けるたびに、心の中で言い返して毅然としていると、上司は嫌がらせをしなくなりました。
あなたが「言いやすい人」でなくなれば、相手の態度も変わるのです。
そして、もう一つ有効な手段が、「第三者に訴える(頼りになる人を巻き込んで闘う)です。
学校ならば友人・先輩・先生などに、会社なら同僚・上司・人事・労働組合などに相談してみましょう。
具体的に解決法が見つかることもありますし、相談するだけでも気が晴れたり、「自分には味方がいる」と思えることで気を強く保てたりすることもあります。
このとき注意すべき点は、相談した人が結果としてあてにならなくても、そこで落ち込まずに別の相談相手を探すことです。
あなたの味方になってくれる人は、きっといます(もし「その環境」にいなくても、前項までに紹介した「新たな居場所」にはきっといます)
方法⑩環境を変える
自分を落ち込ませる原因が多い環境にいる場合は、環境を変えてみましょう。
たとえば、以下のような環境にいるときに、転校や転職・異動を検討してみてください。
- 優秀な人ばかりがいる学校や職場に入った
- いじめや嫌がらせをする人がいる
- 一緒にいて嫌な気持ちになる人が近くにいる
転校は、あなただけで決めるのではなく、保護者の方との相談も必要です。
転職は、転職エージェントや転職支援サービスを利用することで、スムーズに進みやすくなるでしょう。
異動は、信用できる上司や人事に相談してみてください(会社全体が「そういう環境」である場合は、あえて相談しない選択も考えられます)。
なお、思い付きで「転職する!」と決断するのではなく、少し休息期間を作り、冷静に状況を考えてから行動することがオススメです。
なぜなら、転校や転職は、簡単ではないからです。
ちょっと休んでみて、気力や体力が回復したら、前項で紹介した「闘う」の内容も試してみてください。
また、職場や学校の他に、「家族が優秀で、落ち込みがち」「家族が自分をよく責めるので、落ち込みやすい」なども考えられます。
あなたが大人なら、適当な理由をつけて実家を出たり連絡回数を減らしたりすることも一つの対応策になるかもしれません。
あなたが子どもだったり、大人であっても距離を置けない理由があったりするようでしたら、学校の先生、スクールカウンセラー、お住まいの自治体の相談窓口などに悩みを相談することをオススメします。
また、環境の中にはリアルの環境ではなく、「見ると落ち込む原因となる、SNS、テレビ、インターネット」なども含みます。
落ち込みを誘発するネット環境から距離を置くのも一つの方法です。
方法⑪人生には「嫌なことも起きる」し「いいことも起きる」と思う

どんなにいい大学に合格しても、理想の恋人と付き合っても、大金持ちになっても、「嫌なこと」は確実に起こります。
むしろ、「とてもいいこと」はその後の人生の「とても悪いこと」を繋がっていることが少なくありません。
例えば、「大金持ちになった結果、生活が変わり、それまでの大切な友達が離れていった」という話は、その典型です。
しかし逆に、今は嫌なことが起こって落ち込んでいるけれど、それがいいことに転ずる日も来るのです。
例えば、「第一志望の大学に不合格だったけれど、進学した第二志望の大学で生涯の親友ができた」ということがあるかもしれません。
「どうやったら『嫌なこと』を『いいこと』に繋げられるだろう」と考えるようにしてみてください。そうすると、落ち込んだときにも回復しやすくなり、落ち込みやすさも軽減されていくでしょう。
方法⑫歴史に学ぶ
落ち込んでどうしようもない場合の対処法です。
歴史上、多くの人々が戦火や飢えに苦しめられてきました。
人類史上、50年以上戦争が起こっていない時代は、とても珍しいそうです。
私たちは、その「稀有な時代」である現代日本に生きています。
あなたの具体的な状況はわかりませんが、少なくとも、今インターネットを使えていると思います。
インターネットを使えるのであれば、より優先度の高い衣・食・住も、生命に危険がないレベルには満たされているのではないでしょうか。
あなたが今、何かで落ち込んでいたとしても、「生命に危険がなく、インターネットを見ている」状況自体が、歴史上の大多数の人類と比べたら幸福なのだと考えられるのです。
そして、そう考えると自分の悩みがちっぽけであり、自分にはまだできることをあると気づき、落ち込みやすさが軽減され、解決策が見えてくるかもしれません。
かつて筆者は、失恋してとても落ち込んだことありました。
そんなとき、偶然、ホロコーストを生き延びた人の手記を読む機会があったのです。
すると、「私と同じような年齢の女性が、人を好きになることも許されずに人生を奪われている事実が歴史上ごまんとあり、現在もそんな状況にいる人はいる。そんな人の苦境と比べたら、失恋して落ち込んでいる場合ではない」と心境が変化しました。
なお、念のために言っておきますが、「不幸な時代の人間を見下して安心しよう」「積極的に人と自分を比べてみよう」などの意味ではありません。
また、「生命に危険がないなら現状に満足しよう」という意味でもありません。
あくまで「歴史に学ぶ」「これからの生活を充実させる」という謙虚かつ前向きな姿勢がいることが、落ち込みやすさの改善につながるのです。
加えて、「歴史上の人と比べたって、今自分が落ち込んでいる(落ち込みやすい、苦しい)ことは解決しない」と思う人はもちろんいるでしょう。
そういう方は、この方法は無理に試さず、別の方法を実施してみてください。
方法⑬専門家に相談する

落ち込みやすい性格を変えるために、専門家に相談する方法もあります。
特に、「落ち込みやすさ」や「落ち込んでいる時期」によって日常生活や勉強などに支障が出る場合や、発達障害の関連を疑っている場合は、迷わず相談しましょう。
相談先として挙げられる専門家・支援機関には、以下のようなものがあります。
- 学校や職場の相談室(学校ならスクールカウンセラーや保険医、職場なら産業医など)
- 心療内科・精神科
- 自治体の相談機関
専門家によるカウンセリングを受けることで、落ち込みやすい性格を変えたり、落ち込みやすい原因がわかったりすることもあります。「リフレーミング」など認知の歪みを改善する療法を受けられることもあります。
「性格のことで相談するなんて恥ずかしい…」と思わず、積極的に専門家に相談してみてください。
まとめ〜落ち込みやすい性格は改善できます〜

落ち込みやすい原因10個と、その改善方法13個を解説してきました。
落ち込みやすい性格は改善できます。
ご紹介した方法の中で、自分の原因に対応しそうなものや、できそうだなものを、少しずつ試してみてください。
あなたの「落ち込みやすい性格」が軽減され、楽しく過ごせるようになることを祈っています。
さて、私たちキズキ共育塾はお悩みを抱える人のための学習塾です。
穏やかな講師と一対一でお悩みを解消しながら、学習をすすめていきます。
ご相談は無料です。学校、勉強、不登校、ひきこもり、受験などに関連して落ち込んでいる人は、ぜひ一度ご相談に来てください。保護者様だけのご相談も歓迎です。
あなたに最適な「落ち込みやすい」への対応法を、一緒に考えていけると思います。
Q&A よくある質問
落ち込みやすい原因を教えてください。
以下が考えられます。
- 劣等感がある
- 比較しすぎる癖がある
- 物事を客観視できない
- 周りの目や協調性を気にしすぎる
- 自分への理想が高い
- 完璧主義・ゼロか100か思考
- 心に傷がある
- 環境が合っていない
- 褒め言葉をネガティブにとらえる
- 発達障害が関係する
詳細については、こちらで解説しています。
落ち込みやすい性格の改善法はありますか?
以下が考えられます。
- 自己肯定感を持つ
- 反省して改善策を見つける
- 周りは立派に見えていても錯覚だと知る
- 状況を客観視する
- 自分の認知傾向を知り変える
- 自分の力でどうにもならないことは気にしない
- 人との交流を増やす
- 安心できる場所・人間関係をつくる
- 闘う(やめてほしいとはっきり言う、周りに相談するなど)
- 環境を変える
- 人生には「嫌なことも起きる」し「いいことも起きる」と思う
- 歴史に学ぶ
- 専門家に相談する
詳細については、こちらで解説しています。















