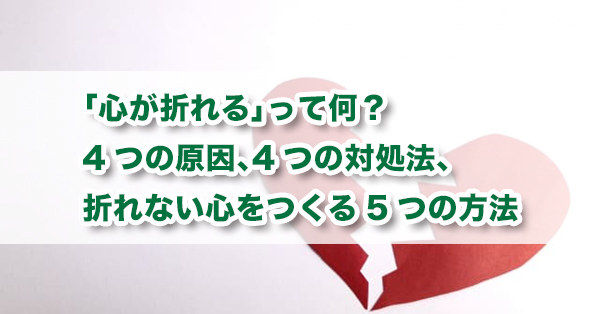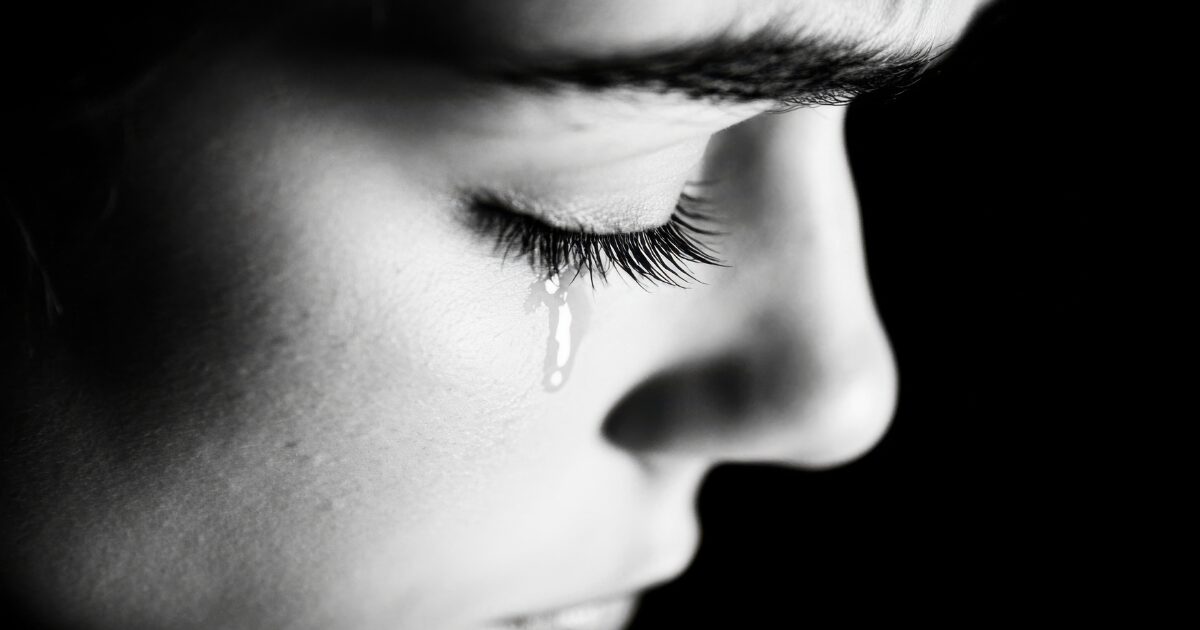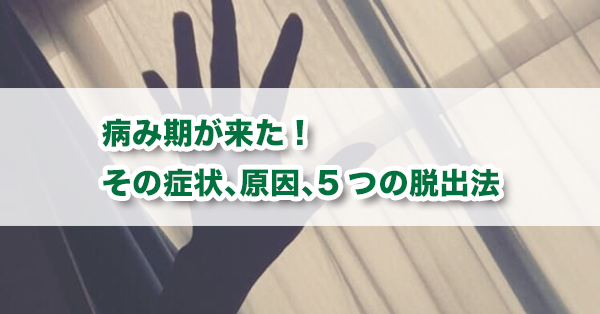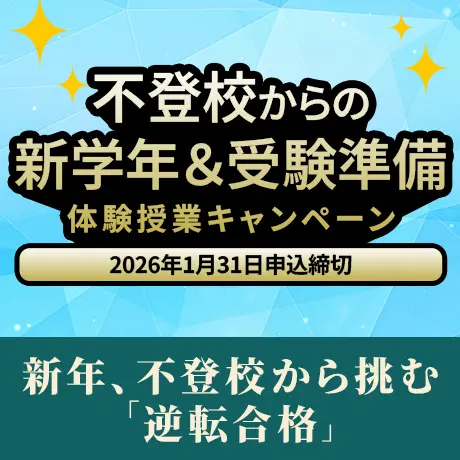生きてる意味がわからないあなたへ 生きてる意味を見つける方法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、「自分の生きてる意味って何だろう」と思っているのではありませんか?
- 生きてる意味がわからなくて漠然と不安を抱えている
- 生きてる意味がわからないから自分の存在意義もわからない
このコラムでは、生きてる意味、生きてる意味がわからなくなる場面、生きてる意味を見つける方法について解説します。また、生きてる意味がわからない状態を克服した事例を紹介します。
基本的に学生向けの内容ですが、いま働いている人にも参考になるはずです。
今生きてる意味がわからない人はもちろん、今後のために知っておきたい人もぜひ最後までご覧ください。
私たちキズキ共育塾は、生きてる意味を見つけたい人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
生きてる意味とは?

生きてる意味には「これ」という正解はありません。人それぞれで違うものです。
生きてる意味が人と違うのは悪いことではありません。生きてる意味自体、どんなものでもよく、これがいい、これが悪いというものはないのです。
テストや部活などで結果が出ないとき、「自分の生きてる意味は何だろう」と悩むことがあるでしょう。
また、生活自体に不満はなくても、ふとしたときに自分の生きてる意味がわからなくなり、漠然とした不安を抱えるタイミングがあるかもしれません。
そんなときこそ、「生きてる意味は、どんなものでもいい」と思い出してください。
もちろん、生きる目標があれば、人生が楽しくなったり活力が出てきたりする場合もあります。自分の生きてる意味を探そうとする思いは、とてもよいことだと思います。しかし、その思いを持ちつつも、あまり意気込みすぎないことが大切です。
生きてる意味がわからなくなる6つの場面
この章では、生きてる意味がわからなくなる場面を6つ、解説します。
- 場面①人間関係の疲れや孤独を感じた
- 場面②忙しさや自己喪失感を覚えた
- 場面③挫折や絶望を味わった
- 場面④大切な人や大切な物を失った
- 場面⑤強い後悔や自責の念を覚えた
- 場面⑥漠然とした不安を感じた
- 補足:うつ病などの病気・障害の可能性もある
場面①人間関係の疲れや孤独を感じた

人間関係の疲れや孤独を感じたとき、が1つ目です。学校生活で人間関係がこじれてつらい思いをすると、「こんな思いをしてまで生きる意味があるのか」と考える瞬間があるかもしれません。
「自分は必要とされていない」「自分を理解してもらえない」と感じて、自分の存在価値を見失う瞬間もあるでしょう。
人との関わりは人生の中で欠かせません。そのため、人間関係の問題で生きてる意味がわからなくなることはよくあります。
場面②忙しさや自己喪失感を覚えた
2つ目は、忙しさや自己喪失感を覚えたときです。勉強などで忙しくなり、自分のやりたいことをやれないでいると、何のために生きているのかふとわからなくなる瞬間があります。
また、周りについていくのに必死だったり、周りに合わせてばかりいたりすると、本当の自分がわからなくなり、自己喪失感を覚えて生きてる意味がわからなくなる瞬間もあるでしょう。
場面③挫折や絶望を味わった
3つ目は、挫折や絶望を味わったときです。学生生活の中では、以下のように挫折や絶望を味わう瞬間は多々あります。
- テストで結果が出なかった
- 部活でレギュラーになれなかった
- 最後の大会に怪我で出られなかった
- 受験に失敗した
自分の中で大きな出来事であるほど生きてる意味がわからなくなり、「こんな人生なら放り出したい」と思う瞬間もあるでしょう。
場面④大切な人や大切な物を失った
大切な人や大切な物を失ったとき、が4つ目です。家族、ペット、恋人、友人など、自分の中で大きな存在を失うと、心の中にぽっかり穴があいたような感覚になります。
「あの人がいない世界でどうやって生きていけばいいんだろう」と考えるようになり、生きてる意味を見つけようとするのです。
場面⑤強い後悔や自責の念を覚えた

5つ目は、強い後悔や自責の念を覚えたときです。家族や友人にひどいことを言った、いじめられている現場を目撃したが助けられなかったなど、後になって振り返るとあのときこうしておけばよかったと後悔することもあるでしょう。
そのようなときに自分の存在意義を考え、生きてる意味を見つけようとする場合があります。
場面⑥漠然とした不安を感じた
6つ目は、漠然とした不安を感じたときです。これという出来事はなくても、なんとなくこのままでいいのか不安に感じる瞬間があります。
毎日同じ時間に起きて学校へ行き、授業を受けて帰る…そんな繰り返しになんとなく不安を抱き、何かしなければならないのではないかと思っている人もいるかもしれません。
誰しも、漠然とした不安を抱える可能性があると言えるでしょう。
補足:うつ病などの病気・障害の可能性もある
生きてる意味を深く考えすぎてひどく落ち込む状態が続く場合は、うつ病などの病気・障害の可能性があります。(学生年齢でも、うつ病、適応障害、双極性障害などを発症することはあります)
病気・障害の場合は、なるべく早く対処することが大切です。この可能性が気になる方は、病院を受診しましょう。
生きてる意味を見つける方法7選
この章では、生きてる意味を見つける方法を7つ、解説します。
- 方法①ポジティブな言動を心がける
- 方法②好きなことややりたいことを優先する
- 方法③SNSから距離を置く
- 方法④他人のために行動してみる
- 方法⑤環境を変えてみる
- 方法⑥ゆっくりする時間を作る
- 方法⑦誰かに相談してみる
方法①ポジティブな言動を心がける

1つ目は、ポジティブな言動を心がけることです。(参考:結川雅『生きる意味を知らずに大人になったあなたへ』)
後ろ向きな考えがつい先行する人は、まず前向きに発言することから始めるといいでしょう。
すると、意識もポジティブになっていき、生きてる意味を前向きに考えられるようになるきっかけになっていきます。
方法②好きなことややりたいことを優先する
好きなことややりたいことを優先すること、が2つ目です。
人生は限りあるため、やることを取捨選択する必要があります。生きてる意味を見つけるには、自分の好きなことややりたいことを優先して満足感を得てみましょう。(参考:オリバー・バークマン・著、橋璃子・訳『限りある時間の使い方』)
そこで初めて、自分が本当に望んでいることが見つかるかもしれません。
方法③SNSから距離を置く
3つ目は、SNSから距離を置くことです。
心理学の巨匠であるアドラーは、「すべての悩みは対人関係だ」と言っています。(参考:岸見一郎・古賀史健『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』)
SNSでは他人の生活が細かくわかるため、対人関係について、「この人とこの人は仲がよかったんだ(…でも、そこに自分はいない)」「友人たちが一緒に遊んでいる(…けど、自分は誘われていない)」など、悩む機会が多くなりやすいのです。
SNSから距離を置くことで、他人との関係ではなく、自分自身に目を向けられるようになるでしょう。
自分は何をしたいのか、心から望んでいることが何なのかわかれば、生きてる意味を見つけられるかもしれません。
現代には欠かせないSNSですが、思い切って通知をオフにしたりアプリをアンインストールしたりして距離を置いてみることをオススメします。
もう一つお伝えすると、SNSでの発信内容は、「人に見せるために、盛(も)っていること」も珍しくありません。画像や動画から見える「楽しさ」は、本当ではない可能性もあります。
方法④他人のために行動してみる

4つ目は、他人のために行動してみることです。他人のために尽くすことが生きてる意味になる人もいるのです。
ただ、初めからそれが分かる人は多くないはずです。他人のために一度行動してみると、自分は他人に尽くすのが好きかどうかを判断できるでしょう。
自分でもわからない生きてる意味を探るためにも、一度他人のために行動してみましょう。
方法⑤環境を変えてみる
5つ目は、環境を変えてみることです。特に、代わり映えしない毎日に生きてる意味を感じられない場合は有効です。
例えば、次のような方法があります。
- 勉強する場所を変えてみる
- 話したことがない人と話してみる
- 降りたことのない駅で降りてみる
普段と違うことをすると、いつもの生活では見えてこなかった発見や楽しみが見つかる可能性があります。
方法⑥ゆっくりする時間を作る
6つ目は、ゆっくりする時間を作ることです。
ゆっくりして何もしない時間を作ると、自分に向き合うことができて、新たな発想が浮かんでくることがあります。
部屋でぼーっとするのもいいですし、家の周り、公園、河川敷、国道沿いや線路沿いなどを散歩したりしてみるのもいいでしょう。
方法⑦誰かに相談してみる
7つ目は、誰かに相談してみることです。一人では自分のなかにある考えしか出てきません。しかし他の人に相談すると新たな視点の意見が出てくるかもしれません。
漠然とした不安を抱えている場合は、話を聞いてもらうだけで心が少し落ち着くこともあります。
以下のコラムでは、ケース別の相談先をまとめています。ぜひご覧ください。
生きてる意味がわからなくても大丈夫

生きてる意味がは、今すぐにわからなくても大丈夫です。周りの大人に聞いても、生きてる意味をしっかり答えられる人は多くないでしょう。
今生きてる意味がわからなくても、いずれ見つかるかもしれません。ですから、急いで見つけようとしなくていいのです。
また、一度見つけても生活していくなかで変わる可能性もあります。「見つけなきゃいけない」と思うより、「見つかったらいいな」くらいの心持ちでいるのがいいでしょう。
生きてる意味がわからない状態を克服した2つの事例

この章では、生きてる意味がわからない状態を克服した事例を紹介します。
事例①生きてる意味を見失いかけたが大学に進学したいという思いに気づけた
Aさんは中高一貫校で授業についていけず、なんとか高校は卒業したものの引きこもりになりました。勉強しても結果が出ず、何のために努力してきたのか、何のために生きているのかわからなくなり、死にたいと毎日思い続けていたのです。
20歳を過ぎたころ、友人たちは楽しそうに大学生活を送っており、Aさんも大学に進学したいという思いが出てきました。
そんなときにAさんはキズキ共育塾を見つけました。自分に合っているとなんとなくは思ったものの、数カ月放っておいた後、勇気を出して無料相談に申込したのです。
そこで自分が勉強できることに気付き、自信を持てるようになったと言います。最終的にAさんは1日8〜11時間ほど勉強できるまでに成長し、慶應義塾大学の経済学部の合格を手にしました。
一度は生きてる意味を見失いかけましたが、ゆっくりする時間があったことで自分のやりたいことを見つけられたいい例です。
事例②高校に行く意味がわからなかったが大学進学で漠然とした不安がなくなった
Bさんは高2の夏、ふと自分が高校に行っている理由がわからなくなって不登校になりました。学校生活自体には問題なかったようですが、考える時間が欲しくなったようです。
しかし、1日中そのことについて考えているわけではないので、他の時間はゲームをしたり漫画を読んだりして過ごしていました。結局、高校へ再び通うことはなく、11月ころに中退しました。
ただ、Bさんは大学には行きたいとなんとなく思っていて、中退時点で高卒認定試験の受験を考えていました。そして今の生活にも嫌気がさした12月ごろ、キズキ共育塾に通い始めたのです。
そこで学ぶことは面白いと気付き、18歳になる年度の夏に高認を取得しました。勉強はそのまま続け、第一志望だった立教大学の文学部に合格しました。
キズキ共育塾に通う前は、将来はどうなるのか、これからどうしたらいいのかという不安を抱えていたというBさん。キズキ共育塾に通ってからは視野が広がり、なんとかなるかなというマインドに変わっていったそうです。
大学に合格したことでなんとなく安心したBさんは、当時の漠然とした不安は所属先がなかったことだったと振り返ります。漠然とした不安を乗り越えられたいい例です。
まとめ~生きてる意味がわからなくても、あせる必要はありません~

生きてる意味に正解はなく、人それぞれの理由があります。
そして、大人になっても自分の生きてる意味を見つけられていない人(けれど、充実して生活している人)もいます。
今生きてる意味がわからなくても焦る必要はないのです。
とはいえ、生きてる意味を見つけようとする行為は、自分の人生を豊かにする上でとてもいいことです。自分に向き合う時間を持ち、ゆっくりと生きてる意味を見つけていきましょう。