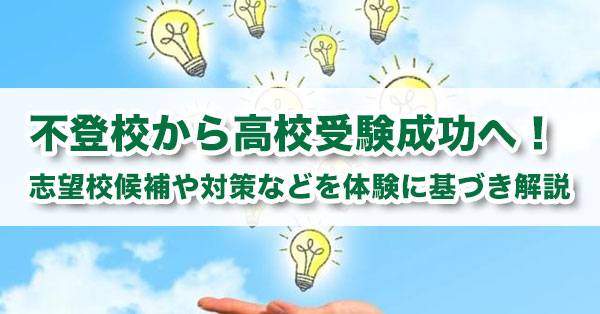不登校の女子中学生に親ができること7選|学校に行かない原因も解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムを読んでいるあなたは今、「娘が不登校になったのはなぜ?」「どのように接したらいいかわからない」と、疑問や悩みを抱えているのではないでしょうか?
小学校までは学校に通っていたお子さんが中学校で不登校状態になれば、親としても心配になりますよね。「まさかウチの子が」と、困惑する親御さんも多いと思います。
このコラムでは、女子中学生が学校に行かなくなる主な理由と、不登校状態になりやすい生徒さんのタイプ、子どもが不登校になったときの親の接し方について解説します。
お子さんに歩み寄り、一緒に前を向いていくきっかけになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、不登校のお子さんのための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
女子中学生の不登校で悩んでいるのは、あなただけではありません

今あなたは、お子さんが不登校状態になり、誰に相談していいのかわからず思いつめているかもしれません。
しかし、ひとりで悩みや不安を抱える必要はありません。実際に、中学生は不登校状態になりやすい時期です。
令和6年度(2024年度)の文部科学省の調査によると、全国の中学校で不登校状態にある生徒さんの数は、21万6,266人。
小学校の13万7,704人と比較すると、約1.6倍多いことがわかります。(参考:文部科学省初等中等教育局児童生徒課「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)
つまり、中学生になってから学校に行けなくなったというケースは、決して珍しいことではありません。
中学生は思春期を迎え、心と体に変化が起きやすく、また学業のプレッシャーも感じやすい時期です。
大切なことは、焦らずに今の状況を受け止めることです。
周囲の人のアドバイスや手助けを求めながら、お子さんが安心できる環境を整えていきましょう。
女子中学生の不登校に多い原因

もしかしたら、あなたは今、お子さんに不登校の理由を聞けず、悩んでいるかもしれません。
中学生が不登校になる背景には、学校での出来事、家庭環境、そして本人の心の状態など、さまざまな要因が関係しています。
この章では、文部科学省の調査結果をふまえながら、女子中学生が不登校状態になる理由について解説します。(参考:文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)
ただし、後でもお伝えしますが、「不登校の原因」を本人に問い詰めないようにしましょう。また、何が原因であっても、お子さん本人と、親であるご自身を責めないようにしましょう。
原因①友人関係・人間関係
女子中学生が不登校状態になる理由のひとつが、友人関係・人間関係です。
全国の不登校状態にある中学生について、学校が把握している事実に、次のようなものがあります。
- いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった:14.1%
- 教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった:2.3%
- いじめの被害の情報や相談があった:1.1%
特に女子中学生は、友人グループの中での立ち位置や関係性を強く意識する傾向があります。そのため、「友だちに合わせなければいけない」と感じ、自分の本音を後回しにすることがあります。
そうした我慢の状態が続くと、強いストレスや誰にも本音を打ち明けられない孤独感が増すことがあります。結果として、学校に行くのに抵抗を感じるのです。
原因②学習への不安
中学校に入学してから、学習への悩みとプレッシャーが増えて学校に行けなくなる場合もあります。
全国の不登校状態にある中学生について、学校が把握している事実に、次のようなものがあります。
- 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた:15.7%
中学校に入ると勉強の難易度が上がり、授業についていけなくなったり、同級生に遅れをとっているように感じたりする場合があります。
高校受験が近づくにつれ、受験勉強や自分の将来にプレッシャーを感じることも増えるでしょう。
頑張って勉強したのに結果が出ず、自信をなくしているお子さんもいます。
こうしたプレッシャーが続くと自己肯定感が下がり、自信が持てなくなったり自分の将来に希望が持てなくなったりします。結果として、学校に行く意欲が下がる場合があるのです。
原因③家庭環境
家庭内の状況が原因で、お子さんが不登校になる場合があります。
全国の不登校状態にある中学生について、学校が把握している事実に、次のようなものがあります。
- 親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった:9.9%
- 家庭生活の変化に関する情報や相談があった:6.6%
例えば、親御さんが学業に強いプレッシャーをかけることで、お子さんが学習や学校に対して抵抗感を持つことがあります。また、家庭内に不和があると、子どもは不安や孤立感を抱えやすくなります。
中学生にとって、家庭は日常生活の大部分を占めます。安心できない環境が続くと、学校に行く意欲や人間関係にも影響が出る場合があるでしょう。
ただし、心当たりがあっても自分を責める必要はありません。完ぺきな親はいませんし、乗り越えたい課題や悩みは誰にでもあるからです。
不登校状態になったときは、家庭や親子関係を見直す機会と捉えてみてください。そして、今できることから取り組んでみましょう。
原因④心の内側
女子中学生の不登校状態の原因は、必ずしも人間関係や家庭環境といった外的要因だけとは言えません。
全国の不登校状態にある中学生について、学校が把握している事実に、次のようなものがあります。
- 学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった:30.1%
- 不安・抑うつの相談があった:24.4%
- 生活リズムの不調に関する相談があった:24.3%
- あそび、非行に関する情報や相談があった:3.8%
こうした数字からわかるように、不登校の原因の多くは心の内側にも存在します。ただし、これはもちろん「本人が悪い」というものではありません。
やる気が出ない、不安がある、生活リズムが乱れている、あそびや非行に走っている、そして学校に行けなくなる…。
その裏にある理由を責めるのではなく、理解しようとするまなざしが、子どもにとっていちばんの支えになります。
原因⑤自分でもわからない
自分でも理由はわからないけれど、学校に行けなくなったと感じている女子中学生もいます。
全国の不登校状態にある中学生について、学校が把握している事実に、次のようなものがあります。
- 該当なし(=不登校と関連するような事実の把握がない):4.9%
なぜ自分が登校に抵抗を感じているのかわからないお子さんもいます。
また、前の項で挙げたやる気や不安が関連する不登校にも、なぜ気力が湧かないのか自覚がない場合が多くあります。
お子さんが不登校になると、つい理由を聞き出したくなるかもしれません。しかし、自分でも理由がわからないときは、親からの問いかけ自体が強いストレスになります。
理由を答えないとき、お子さんは「教えたくない」「隠したい」と思っているとは限りません。ただ、心を整理する時間が必要なのです。
不登校になる女子中学生の7つのタイプ
不登校の原因や背景は、一人ひとり違います。しかしそれぞれ違って見える不登校の状態像には、多くの共通点も存在します。
キズキ家学では、特定非営利活動法人教育研究所の監修のもと、これまでの支援の経験と先行研究から不登校の状態像を、以下の7つのタイプに分類しています。
タイプ |
特徴 |
①母子分離不安型 |
・母親から離れると強い不安が起こる ・母親にスキンシップを求める ・母親の近くだと友人と楽しく遊べる |
②情緒混乱型 |
・気分の落ち込みや混乱が多い |
③混乱型 |
・落ち込むこともあるが好きなことはできる |
④無気力型 |
・何事にも無気力 |
⑤人間関係型 |
・人間関係をきっかけに登校できなくなる |
⑥ストレスによる |
・主観的なこだわりがある |
⑦発達障害・学習障害を |
・発達障害や学習障害との関連性がある |
ただし、「各特徴に該当すれば、必ず不登校になる」というわけではありません(母子分離不安など、中学生にはあまり当てはまらないものもあります)。
あくまでも、参考情報としてご覧ください。
各タイプの詳しい特徴は、「不登校7つのタイプ」で解説しています。お子さんと接するときの留意点や学校との連携方法も解説したリンクも掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
不登校の女子中学生に対する親の接し方

不登校のお子さんを目の前にして、何とかしてあげたいけれど、何をすればいいかわからず悩む親御さんは多いでしょう。
接し方によっては、反発されたり、かえって親子の溝が深まったりすることもあり、不安になりますよね。
この章では、不登校状態にある女子中学生に対するオススメの接し方を、5つ紹介します。
接し方①不登校の原因を無理に追及しない
お子さんが不登校状態になったときは、学校に行かない理由や原因を無理に追及しないようにしましょう。
なぜなら、不登校の原因は、お子さん自身にも明確に言葉にできないケースが多いからです。
また、親に心配をかけたくないという思いから伝えることをためらう場合もあります。
それでも原因を無理に聞き出そうとすると、それはお子さんの課題を解決するためではなく、親御さん本人の不安を解消するための行動になります。
まずは、お子さんが自分の気持ちと向き合う余裕を持てるように見守りましょう。
「言いたくなったら教えてね」と優しく伝え、いつでも聞く耳を持っているという姿勢を見せてください。
接し方②お子さんの話を否定せずに聞く
お子さんが悩みや不安を打ち明けてくれたときは、その気持ちを否定せずに聞くことを意識しましょう。
例えば、お子さんが「私は嫌われていると思う」と話したとき、「そんなことないよ」「ネガティブに考えないで」と、すぐに励ましたくなるかもしれません。
しかし、その悩みや不安の背景には、お子さんなりの理由や原因が必ず存在します。
「そんなことはない」と否定的に伝えると、「自分の感情が間違っている」「誰にも理解してもらえない」と感じ、孤独感を深めるかもしれません。
その結果、余計に心を閉ざすこともあります。
自分の考えを伝えるのではなく、「何があったの?」「どうしてそう思うの?」と、気持ちの背景を聞くことを意識しましょう。お子さんが自分の気持ちや考えを整理するきっかけにもなります。
もし、すぐに何も答えられなかったり、黙ったりした場合は、考える時間が必要なだけです。
急かさずに静かに返事を待つか、「また話したくなったら聞くよ」と伝えましょう。
接し方③親は親の生活を充実させる
お子さんが不登校状態にあるときは、親御さんご自身の生活を大切にすることも忘れないでください。
自分だけが楽しんでいるようで罪悪感を覚える方もいるかもしれません。
しかし、親御さんが自分の人生を充実させることは、結果的にお子さんを支える力につながります。
親御さんが仕事や人付き合いを後回しにしてお子さんに付きっきりになると、親子そろって社会から孤立しやすくなります。
相談できる相手がいないと、押し込めた不安や焦りをお子さんにぶつけてしまうこともあるでしょう。
そうなると、お子さんも息苦しさや罪悪感を感じ、ますます心を閉ざしてしまうことがあります。
一方で、親御さんが自分の時間を楽しみ、困ったときには周囲に助けを求められる状態であれば、自然と笑顔が増えます。
その笑顔や落ち着いた雰囲気が、お子さんの安心感につながるのです。
また、「大人になったらあんなふうに生きたい」「外の世界も悪くないかも」と、お子さんが前向きな気持ちを持てることもあります。
自分の生活を楽しむことは、お子さんとの関係を穏やかにし、よいロールモデルとなる大切な一歩なのです。
接し方④専門家に相談する
お子さんが不登校状態にあるときは、専門家の力を借りることが解決への大切な一歩となります。
ひとりで解決しようとすると、親御さんご自身が孤立感や不安感を抱え、心身ともに疲れてしまう場合があります。
一方で専門家に相談すると、適切なアドバイスが得られます。
また、不登校状態にある原因や今のお子さんの気持ちを整理してもらうと、次に取るべき行動が見えてくることもあるでしょう。
フリースクールや学習塾といった学校以外の学びの場など、将来を前向きに進んでいくための選択肢を教えてくれることもあります。
ひとりで悩まず、以下のような相談先を頼ってみてください。
- 児童相談所、児童相談センター
- 引きこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
- 心療内科
- フリースクール
- 学校のスクールカウンセラー
- 不登校向けの学習塾・家庭教師
接し方⑤学習の遅れをサポートする
お子さんが不登校状態になったら、学習の遅れをサポートする機会を設けましょう。
欠席が続くと、お子さん自身も学習の遅れに対して焦りや引け目を感じるケースが少なくありません。
学校に行かずに、学習する習慣を身につけておくことは可能です。
まずはお子さんの心身の回復を優先し、余裕ができたらまた勉強をしてみないかお子さんに相談してみてください。
学習する時間を作ることで、将来への不安が和らぎ心にゆとりが生まれます。また、自信をつけるきっかけにもなるでしょう。
家にいながら学習したい場合は、以下のような方法があります。
- 通信教育(オンライン教材)
- 問題集・参考書
- 家庭教師
外出する機会を増やしたい方は、以下のような環境を活用してみてください。
- 学習塾
- フリースクール
中でも、不登校に理解のある家庭教師や学習塾を利用してみてください。
例えば、私たちキズキ共育塾では、不登校やひきこもりを経験した生徒を多くサポートしてきました。
一人ひとりの学習状況や将来の目標に合わせてカリキュラムを設計するだけでなく、心の相談にも丁寧に対応しています。
こうした環境なら、お子さんの不安や心配ごとを和らげながら、安心して一歩ずつ前に進むことができるでしょう。
不登校の女子中学生のその後の進路

お子さんが不登校状態になると、今後の進路を不安に感じる親御さんも多いでしょう。
少し古いデータではありますが、文部科学省が平成18年度に行った調査によると、不登校状態にあった中学生のうち、卒業後に高校に進学した割合は約85%。大半が進学していることがわかります。(参考:文部科学省「「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(概要版)」)
この調査が行われた当時から見て、不登校に関するサポートは充実し続けています。「不登校になったら、将来が絶望的だ」などと思わないようにしましょう。
とはいえ、「高校に入学できたとしても、また学校に行けなくなったらどうしよう」「うまく馴染めるだろうか」という心配もあると思います。
基本的には、「中学校での不登校」と「高校に通えるかどうか」は、全く別の話ですので、過度な心配は不要です(これは、「高校不登校や高校中退」と「大学に通えるかどうか」についても同じことが言えます)。
校風、通学環境、卒業後の進路など、お子さんに合いそうな高校を見つけることで、高校生活を楽しく過ごせる確率は上がります。
高校受験時には、以下の点に留意して対策をしておくことが大切です。
- 内申点(調査書)
- 欠席日数
- 学力
内申点とは、調査書に記載される教科の成績を点数化したもので、特に公立高校で重視されます。
欠席日数も合否審査の基準となる高校があり、多いと不合格になる可能性があります。
学力が伸び悩んでいると学力試験で不合格になる場合があります。
なお、不登校の経験がある生徒に理解のある高校としては、次のようなものがあります。
- 私立の全日制高校(内申点の審査をしない受験方式)
- 通信制高校
- 定時制高校
- 東京都のチャレンジスクールのように、地域独自の特色ある高校
なお、不登校からの高校受験については、それに詳しい学習塾や家庭教師の利用もあわせて検討してみましょう。
志望校の選び方、対策方法などを、「実際のお子さんの状況」に合わせて考えていくことができます。
志望校の選び方や、各留意点に関する解決策は、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ:女子中学生のお子さんが不登校になったときは、ひとりで悩まないでください
女子中学生のお子さんが不登校状態にあるとき、親御さん自身も不安や焦りでいっぱいになることがありますよね。
ひとりで抱え込まず、専門家を頼ってみてください。
自治体の相談窓口や、キズキ共育塾のように不登校状態にある生徒を支援する学習塾など、頼れる場所はたくさんあります。
また、今お子さんが不登校の状態にあっても、将来が閉ざされるわけではありません。実際に、高校に進学し、自分らしい道を歩んでいるお子さんは大勢います。
専門的な知識や経験のある人に相談することで、現状を客観的に整理し、次に取るべき方向が見えてくるはずです。
まずは、親御さんが心にゆとりを持ち、お子さんが安心できる環境を整えていきましょう。そのうえで、少しずつ将来への道筋を一緒に考えてみてくださいね。