不登校の後悔に関する調査結果 不登校の体験談や相談先を紹介
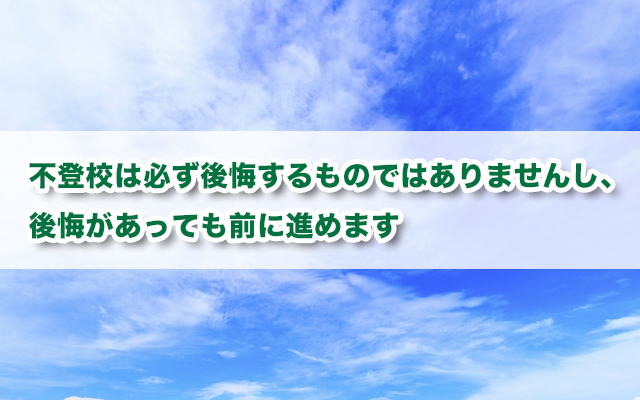
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、「この子が成長したとき、不登校だったことを後悔しないだろうか…」など、お子さんの不登校について悩んでいませんか?
また、これからの人生で不登校の経験を悪い形で引きずることを心配しているかもしれません。
このコラムでは、実際に中学校で不登校を経験した人の体験談に基づいて、不登校の後悔に関する調査結果について解説します。
なお、このコラムは、不登校状態にあるお子さんを持つ親御さん向けですが、現在不登校のご本人にも役に立つ内容だと思います。
このコラムを読み、不登校で後悔しがちな内容をあらかじめ知ることで、不登校でも後悔しない選択をするための助けとなるはずです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
不登校は、子どもが「答え」にたどり着ける期間になります
このコラムで紹介する、「不登校に関する後悔の有無」の割合は、非常に意外なはずです。
先に言いますと、不登校の経験を「よい」とも「悪い」とも言いきっている人は少ない(どちらも過半数に至らない)のです。このデータは、私も含めていろんな人が精査しました。
共通して言えるのは、「不登校の経験者は、その期間に『価値』や『気づき』を得ている」ということです。不登校の期間は無駄ではなく、子どもが「納得のできる答えにたどり着ける期間」と言えるのではないでしょうか。
親御さんには、不登校の専門家や支援団体とも話しながら、そのためのサポートをしていただければと思います。
私たちキズキ共育塾は、不登校にお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校の後悔に関する調査結果
あなたは、不登校の子どもの現在や将来について、以下のように心配・悲観しているかもしれません。
- 人生で一度しかない学生時代を不登校で過ごすなんて、後悔するんじゃないか
- 関連する情報を収集したくても、実際に不登校だった人に「後悔してる?」なんて気軽に聞けない
- 聞けたとしても「あなたのお子さん」に当てはまる話かどうかはわからない
- そもそも、周りに不登校だった人がいない
以上の心配・悲観に関して、文部科学省による不登校生徒に関する追跡調査が参考になるかと思います。
- 「かつて不登校だった子が何年かを経て、現在どのような状況なのか」を調査・分析
- 「平成18年度に中学校第3学年に在籍し学校基本調査において不登校として計上された者(調査概要より抜粋)」を対象
- 平成23年度に行われた調査内容をもとにして、平成26年度に『「不登校に関する実態調査」~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~』(以下、報告書)として公表された
この章では、文部科学省の調査結果に基づき、不登校の後悔に関する調査結果について解説します。
①不登校に対する後悔の有無
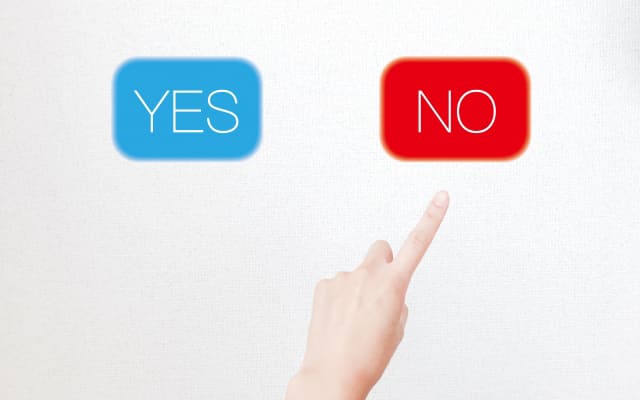
報告書には、不登校状態にある人に対する後悔の有無として、以下のような設問があります。
「今、考えると、小中学生の頃、不登校で学校に行かなかったことをどう思いますか。次の1~4の中からいちばん近いものをひとつ選んで○をつけてください。」
この設問の回答結果は以下のとおりです(有効回答数1604)。
- 行けばよかった 606件(37.8%)
- しかたがなかった 494件(30.8%)
- 行かなくてよかった 183件(11.4%)
- 何とも思わない 273件(17.0%)
- 未回答・無効回答 48件(3.0%)
この回答結果から、以下のことが読み取れます。
- 「行けばよかった」と後悔の念を抱いている人が最も多く、37.8%
- 「行かなくてよかった」という肯定的な回答は最も少なく、11.4%
つまり、不登校に対して後悔している人は、肯定的な人に比べて3倍以上いると言えます。
ただし以上は、以下のようなグループ分けで考えることもできます。
- 「行けばよかった」は「後悔がある」で、37.8%
- 「しかたがなかった」は「中立的」で、30.8%
- 「行かなくてよかった」「何とも思わない」は、「後悔がない」で、28.4%
こうすると、不登校について「中立的」「後悔がない」人の割合が、「後悔がある」人たちよりもかなり多いことがわかります。
②不登校に対する後悔の内容
以下に、報告書内で触れられている不登校に対する後悔の内容を紹介します。
「なぜ、不登校を後悔しているのか」を、報告書の内容から分類・要約しています。
当該項目は、「不登校により失ったものがある」と回答した人数を100とし、失ったものの具体的内容の内訳をパーセンテージで示しています。
また、併せて私たちキズキ共育塾の生徒さんの声もご紹介します。
(a)学力、勉強(14.6%)
- 一般知識が欠如していると感じる
- 進みたい学校に進学できなかった
- 不登校による勉強不足で、高校、専門学校、大学でも学力差や勉強についていけない感覚がある
(b)友人関係(6.9%)
- 不登校当時に友人との時間が持てなかった
- 学生時代の友人が少なく、周囲がうらやましい
- 留年や浪人で、同級生が年下になった
- 学校でもっと友人をつくればよかった
(c)進路(10.9%)
- 進学や就職に悪影響を感じた
- 不登校でなければもっといい進学先や就職先に行けた
- 「今の自分の力ではこんな仕事しかできない」と自己否定的になった
(d)思い出(6.3%)
- 学校の楽しい思い出ができなかった
- 今の友人と、中学時代の思い出を語り合えない
- 成人式で、周りの参加者と思い出を共有できなかった
キズキ共育塾の生徒さんたちからは、以下のような声もあります(一部です)。
- 中学で不登校になって、そのまま学校の友達と会わなくなった。そのモヤモヤを5年も引きずっている
- 学校行事に参加する、友だちと買い食いする、ちょっと誰かとケンカするなど、学生時代にしか体験できないことができなかった
- 不登校であることに劣等感を持って、面白そうな場所や活動にどんどん行けなくなった
- 高校を不登校から中退したことで最終学歴が中卒になった。進学や就職で不利になったため、今学び直している
- 些細なことで先生とケンカをして高校を不登校になったけれど、もっとよく考えてから行動すればよかった
③「不登校を後悔していない」という意見

報告書には、不登校を肯定的にとらえている人の意見も掲載されています。
こちらも、報告書の内容およびキズキ共育塾の生徒の声を、分類・要約して記載します。
当該項目は、「不登校により得たものがある」と回答した人数を100とし、得たものの具体的内容の内訳をパーセンテージで示しています。
(a)休んだおかげで今の自分がある(18.9%)
- 苦しんでいた時間があったから今の自分がいる
- 不登校のつらさを乗り越えて自信がついた
(b)成長した、視野が広がった(13.2%)
- 自分のことや周りのことが見つめ直せて成長できた
- 肯定的な休息だった
- 学校のメリット・デメリットが俯瞰的に見れた
(c)出会いがあった、学校に巡りあった(16.0%)
- 不登校の間に、新しい友達やカウンセラーなど、自分を支えてくれる存在と出会えた
- 不登校の自分を見捨てないでいてくれる友人や先生の大切さを実感した
(d)人とは違う経験をした(11.3%)
- 学校では得られない経験を積んだ
- ほかの人とは違う見方ができるようになった
(e)その他
- 同じ経験をしている人の気持ちが理解できる
- 自分で決めたことなので後悔はしていない
- 無理して学校に行っていたら取り返しがつかなかったかもしれない
- 学校に行っていても今よりいい状況になるかわからない
- 友だちもいるし仕事もしているので後悔はない
キズキ共育塾の生徒さんからは、以下のような声があります(一部です)。
- 登校し続けていたら精神的な不調が悪化したかもしれず、それを防げてよかった
- 他人と違う道を進むことに抵抗がなくなった
- 不登校をきっかけに、将来のことを真剣に考えるようになった
- 不登校のときに身につけた知識や雑学が、思わぬところで役に立った
補足:不登校期間中の過ごし方が大切です
不登校の後悔について、補足します。
不登校期間は、学校に行かない分、自分で何かをする時間が多く取れます。
不登校期間中に継続して何かをやっておくと、継続できた事実そのものや、それが具体的に役立つ機会によって、「不登校の期間があってよかった」と思える可能性は高まります。
ただし、心身の調子を整っていないときに無理は禁物です。心身の調子を整えることが一番です。
嫌なことを無理やりするのではなく、楽しみながら自分の自信につながることのほうがよいでしょう。例えば、以下のようなことはいかがでしょうか。
- 読書
- 動画編集
- イラスト
- プログラミング
また、もしかしたら楽しんではできないかもしれませんが、勉強はもちろん一般論として役に立ちます。
不登校の次の一歩は「今の学校への登校再開」とは限らない

ご紹介してきたように、不登校にまつわる後悔については、しているかいないかも含めて、その思いや内容はさまざまです。
現実として、後悔している人はそれなりにいる、学力や進路とに苦労が生じる場合があることは否めません。
とはいえ、後悔があること自体は絶対的に悪いことでもありません。学力や進路を後からカバーすることも可能です。
その上で、「できれば子どもには後悔や苦労をしてほしくない」と思うのが親心でしょう。
では、あなたのお子さんが不登校について後悔をしない、または、後悔はあっても前向きに生きていくためには、どうすればよいのでしょうか。
そのためには、主には以下の観点があります。
- 在籍している学校への登校を再開する
- 別の学校へ転校する
- 学校以外の居場所を見つける
不登校の次の一歩として、在籍している学校への登校再開を考える親御さんは多いのですが、それだけとは限りません。
新しい学校も、学校以外の居場所も、次の一歩になり得ます。
今の学校で、不登校のためにできなかったことや、それに伴う後悔を、全く同じ形で取り戻すことはできないでしょう。
ですが、新しい学校や学校以外の場所で同じような経験や全く別の経験をすることはできますし、それらが後悔を小さくしていくこともできます。
学校以外の居場所とは、以下ような場所です。(後で改めて紹介します)。
- 学習塾・予備校
- フリースクール
- アルバイト先
学校以外の居場所のメリットは、以下のようなことが挙げられます。
- 勉強やコミュニケーションを直接的に学ぶこともできる
- 登校再開や転校に向けて自尊心やエネルギーを回復させられる
報告書からは、不登校を後悔するかどうかは、不登校の時間をどのように過ごすかに左右されやすいといった傾向が読み取れます。
ぜひ、在籍している学校に限らず、お子さんのための次の一歩を探してみてください。
ただし、親御さんだけで探す必要はありません。
次章で紹介するように、お子さんのことや親御さん自身のことを相談できるところはたくさんあります。
相談先を積極的に頼ることで、どのルートを選んだ方がいいかもわかるでしょう。
そうすれば、お子さんも親御さんも、きっと今の状況は変わっていきます。
特に親御さんにとっては、「あのとき、子どもにこうすればよかった(こうしなければよかった)」という後悔を減らすことにもつながります。
子どもの不登校に関する相談先

この章では、お子さんの不登校について、また親であるご自身のお悩みについて、相談先を紹介します。
まずは、お子さんの在籍している学校、担任、学年主任、保健医、スクールカウンセラーなどへのご相談をオススメします。
親ではわからない、学校での様子を知ることで、次の一歩が見つかるかもしれません。
学校以外には、以下のように、自治体が運営している相談窓口があります。
- 児童相談所、児童相談センター
- 教育センター
- ひきこもり地域支援センター(不登校に加え、引きこもりの兆候・状態もある場合)
- 発達障害支援センター(発達障害が関係しそうな場合)
公的な窓口の詳細は、お住まいの自治体の公式サイトから確認できます。
名称や機能はお住まいの自治体によって異なることもありますので、窓口がわからない場合は、総合窓口にメールや電話で確認してみましょう。
さらに、公的な機関以外にも、以下のような相談先があります。
- 病院(児童精神科など)
- 不登校に詳しい学習塾・予備校
- フリースクール
そのほか、相談機能はなくても、お子さんが楽しく過ごすことで次の一歩に進めるようになるところもあります。
例としては、以下のようなものがあります。
- 習い事教室
- 趣味のサークル
- (高校生年齢であれば)アルバイト
このように、お子さんの不登校について相談できる場所、お子さんが次の一歩に進むための場所はたくさんあります。
こうした場所を適切に頼る・利用することで、不登校に関連して将来的に後悔が生じる可能性を減らすこともできるでしょう。
相談先によっては、学校以外の居場所として、学校に代わり、学力や社会性を身につけたり、楽しく過ごせたり、将来のためのする場所となる可能性もあります。
不登校のお子さんの言葉に耳を傾けましょう

「データも、不登校経験者の声も、相談機関のこともわかった。それでもわが子のことは客観的には見られない。どうしても心配だ」と思う親御さんもいらっしゃるでしょう。
不安や心配のあまり、お子さんの生活などについて、ついつい厳しく口を出したくなるかもしれません。
しかし、不登校の子どもは、自分の言葉に耳を傾けてくれる存在を求めています。
望んで不登校になる子は多くありません。
お子さんには、不登校になる、不登校にならざるをえなかった理由があるはずです。
厳しいことを言いたくなる気持ちはよくわかりますが、子どもの気持ちを第一に考えましょう。
相談機関のアドバイスにも従いつつ、親が自分の意見を言うのは、子どもから相談などを通じて求められたときにとどめておきましょう。
親御さん自身のストレスケアも大切です

ここまで不登校に対する後悔に関して、子どもを中心に解説してきました。
ただ、親であるあなたも、子どもと同じくらい、あるいはそれ以上に心に負担を抱えているかもしれません。
自分のことではないぶん、余計に歯がゆかったりじれったかったりしますよね。
前章でお伝えしたように、厳しいことを言わないようにすると、余計に心配が増すこともあるでしょう。
親御さん自身も、その不安をケアしていく必要があります。
そのために大切なのは、以下の2つです。
- 常に子どものそばにいるのではなく、子どもの世話はしつつ、自分自身の人生を生きること
- 子どもが不登校かどうかに限らず、どんな親子関係においても、子どもと適度な距離感を保つこと
特に不登校の子どもは、常に親がそばにいると、「いつも親に心配をかけて、自分に時間を割いてもらって申しわけない」といった罪悪感を抱く可能性があります。
子どもに対しては、必要な世話はもちろん行いつつ、少し距離を置いて、自分の時間を持つように心がけましょう。
子どもにとっても、そうした生活は、以上のような罪悪感が発生せず、安心して過ごせるようになります。
また、子どもは、楽しそうな時間を過ごす親を見ることで、自分の将来に対して希望を持つこともできます。
どこまでが必要な世話かは、前章の相談先にも話をしつつ、子どもと同じように、あなた自身のケアを心がけましょう。
この章では、不登校のお子さんがいる親御さんのストレスケアの方法について解説します。
ストレスケア①同じ悩みを抱える人に相談する
一人だけ・夫婦だけ・親子だけで悩んでいると、どうしても行き詰まることが多くなります。
他者からの視点によるアドバイスをもらうことで、状況を打開できる場合があります。
そんなときは、以下のような行動を起こしてみましょう。
(1)友人や親戚など、同じような悩みを抱える人に相談する
具体的な解決策に繋がらなくても、気持ちを話すだけでもすっきりしたり、共感をもらえて安心したりできて、ストレスの解消につながります。
(2)不登校の親の会に参加する
不登校の子どもを持つ親が情報交換や交流を行える、不登校の親の会は全国にたくさんあります。気になるようならインターネットで調べてみましょう。
ストレスケア②一人の時間・夫婦の時間を持つ
子どもから離れて、自分一人の時間や夫婦の時間を持つことも有効です。
そうした時間を有意義に過ごすことで、ストレスが緩和されます。
有意義に過ごすとは、必ずしも何かをしなければならないということではありません。
日常の悩みから一時的に避難できる、リラックスできる環境に身を置くことが大切です。
そのためには、以下のような自分や夫婦に合ったリラックス法を見つけましょう。
- アロマ
- マッサージ
- 入浴
- カフェで過ごす
- 映画館に行く
- 睡眠をとる
特に睡眠が足りていないと、ストレスがたまりやすくなるので注意です。
ストレスケア③専門機関を利用する
繰り返しとなりますが、専門機関を利用することをオススメします。
親は、不登校の専門家ではありません。
もっと言うと、子育ての専門家でもありません。
不登校や子育てなどについての専門的な知識や経験を持つ専門機関を利用することで、お子さんのみならず、親御さんのストレスケアにも役立ちます。
専門機関はさまざまなケースを通じて知識やノウハウを蓄積しているため、類似ケースから解決策を見出してくれることも多いです。
不登校の後悔に関するキズキ共育塾講師の体験談
私たちキズキ共育塾の講師には、挫折経験がある人もたくさんいます。
不登校経験についても例外ではありません。
筆者自身も、中学1年生から3年生までの間、不登校でした。
この章では、そんな私自身やほかの講師の、不登校と後悔にまつわる体験談を紹介します。
体験談①全く後悔していない

私自身は、結論から申し上げると、不登校だったことに全く後悔はありません。
理由は2つあります。
1つ目の理由は、中学不登校から進学した高校で、今でもつき合いのあるかけがえのない友人たちと出会えたからです。
私は、高校受験・進学にあたり、私が中学で不登校だったことを知る人がいないであろう、地元から少し離れた学校を選びました。
不登校でなかったなら、家から遠いその高校は選ばず、違う高校に進学していたと思います。
それでも楽しい生活を送れたかもしれませんが、少なくとも、今の友人たちとは出会えなかったでしょう。
そして、2つ目の理由は、今に通ずる価値観を得られたからです。
もし不登校になっていなければ、おそらくこうして不登校の子を支援する仕事に就くことはなかったでしょう。
また、自分自身が不登校というマイノリティを体験したことは、社会的にマイノリティな立場の人や弱い立場の人の不安や苦しみを理解する上での助けとなっています。
ただし、後悔はしていないものの、特に高校では、以下のような中学不登校の悪影響を感じることはありました。
- 中学内容の基礎学力が完全に身についていなかったため、高校で学ぶ単元の一部において、基礎があるほかのクラスメイトとの間にハンデキャップを感じた
- 不登校時の生活習慣がなかなか改まらず、平均的な生徒と比べて欠席日数も多かった
とは言え、その悪影響は深刻なものではなかったようで、学力も出席日数も、中学に比べるとよくなっていたことは確かです。
結果としてその後の私は、高校を卒業し、大学に進学・卒業でき、就職することもできています。
このように、あなたのお子さんも、今現在で学校や不登校にまつわる悪影響や後悔をすでに持っていたとしても、これから楽しい時間や充実した時間を過ごすことで、それらを次第に小さくしていくこともできます。
大切なのは、過去や今の不登校にこだわりすぎず、これからの人間関係や勉強環境を大切にしていくことだと思います。
体験談②後悔もあるが、いいこともあった

私以外の体験談として、佐藤講師(仮名)も、中学で不登校を経験しています。
以下、佐藤講師の一人称で、不登校と後悔についてお伝えします。
私が不登校で後悔したのは、給食、授業、運動会、文化祭、合唱祭、修学旅行、卒業遠足、卒業式などのイベントを経験できなかったことでした。
ただ、不登校だった当時には、そのことに気づいていませんでした。
なぜなら、経験していないために、それらが楽しいかどうかもわからなかったからです。
そんな私は、その後高校と大学を卒業し、一時期は都立の学校で教師として働いていました。
そして、教師として以上のようなイベントを経験したとき、教師という立場であっても、それらを楽しんでいる自分に気づいたんです。
そのとき私は、学校に行けなかったことをどこかで後悔していたんだなとあらためて感じました。
しかし、不登校でよかったこともあります。
それは、不登校を経験したからこそ出会えた人がたくさんいることです。
不登校でぽっかり穴があいたような気持ちだった私の心を、出会った人たちが少しずつ埋めてくれたように思えます。
世の中には優しい人たちがいる、自分のことを思ってくれる人たちがいる…。
学校に通っていたら、こうしたことはあまり意識せずに過ごしていたかもしれません。
よい出会いがあったこと、そしてそれに気づけたことが、不登校をしてよかったと思う理由です。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ~必ず不登校を後悔するとは限りません~

、不登校に伴って後悔や困難が発生する可能性は否定できません。ですが、必ず発生するとも限りません。
また、発生したとしても、その後の別の経験で、それらを小さくしていけます。
あなたとお子さんの人生が、これから、より充実していくことを祈っています。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える人のための個別指導塾です。
生徒さんには、不登校状態にある人や、過去に不登校を経験している人も少なくありません。
キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になる人は、お気軽にお問い合わせください。
あなたのお子さんのための、これからの話ができると思います。
Q&A よくある質問
親ができる自分自身のストレスケアはありますか?









