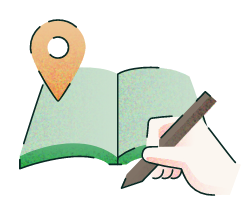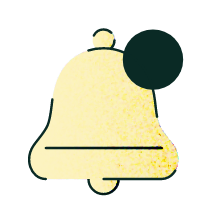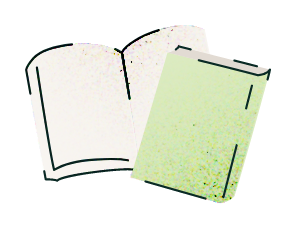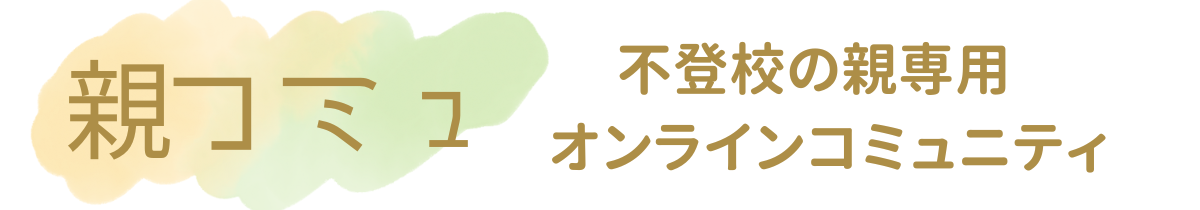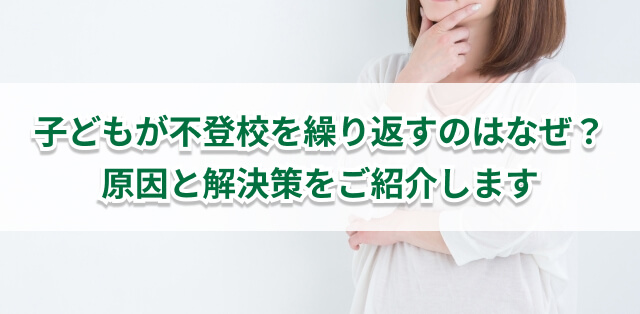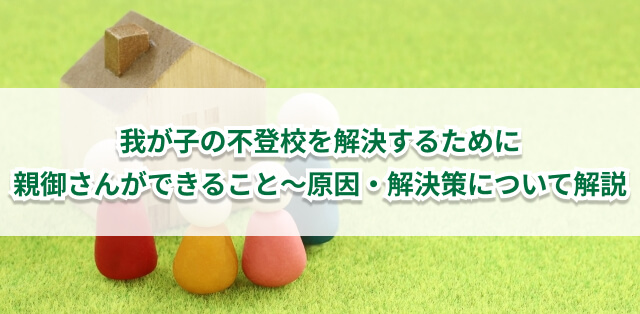夏休み明けの不登校になるのはなぜ? 気をつけたいポイントを解説
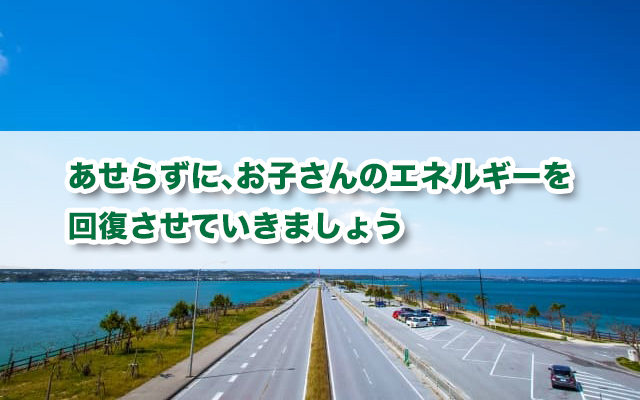
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
お子さんが1学期は元気に学校に通っていたのに、夏休み明けに突然行けなくなり、「なぜ…?どうすればいいの…?」とお悩みではありませんか?
夏休みやゴールデンウィークなどの長期休み明けは、不登校になりやすい時期と言われています。
親御さんとしては、「休み前までは普通に通っていたのになぜ…?」と戸惑うこともあるでしょう。
実は、私自身も中学1年生の夏休み明けに学校に行けなくなり、不登校になりました。
このコラムでは、キズキ共育塾の知見や、筆者の私自身の経験に基づき、夏休み明けに不登校が増える理由や予防・対策、対応のポイントについて解説します。
お悩みを抱えるお子さんと、そして親であるあなたの次の一歩に役立てば幸いです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
子どもによって、不登校が必要な時期があります
夏休み明けは、不登校になる人がもっとも多い時期の一つです。前提として、不登校になるのは、親の育て方が悪かったり、子どもがなまけていたりするためではありません。文部科学省も、「不登校にはどの子どももなりうる。『問題行動』と見てはならない」と訴えています。
子どもによって、不登校が必要な時期があるのです。不安にさせるつもりはありませんが、無理に登校させる・させようとすると、過剰適応(環境に合わせるために、度を超えて自分を変えている状態)になり、自傷行為やOD(オーバードーズ:薬の大量摂取)に発展する危険性もあります。
「学校に戻す」よりも、お子さんが「学校を離れても大丈夫と思える安心できる環境をそろえる」ことを意識していただければと思います。そして、親御さんとお子さんをサポートする不登校の支援団体はたくさんあります。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にあるの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
夏休み明けに不登校になる6つの理由
夏休み明けの不登校のよくある原因や例を6つご紹介します。
お子さんに当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
ただ、子どもが不登校になる理由はさまざまです。
このコラムでは、特に夏休みに関係する理由をご紹介しますが、それ以外が原因である可能性もご留意ください。
理由①息切れ・エネルギー切れ

夏休み明けに不登校になる理由の1つは、息切れ・エネルギー切れです。
学校では、授業・部活・生徒会・その他行事などで、がんばる場面や緊張する場面がよくあります。
1学期中はそういう場面になんとか対応できていたものの、夏休みに入るくらいのときに息切れ・エネルギー切れになるのです。
その後、再び気力などが充実しないことで、がんばりが必要な学校へ通う気力がわかなくなります。
休み前まではすごく一生懸命がんばっていたのに、休みに入ると急に無気力になり何もできなくなったお子さんは、息切れ・エネルギー切れの可能性があるでしょう。
理由②学校での負担の自覚
2つ目の理由は、夏休みをきっかけに学校での負担を自覚することです。
学校があるうちは本人も気づかなかった負担に、夏休みで学校を離れて過ごすことで気づくことがあります。
例えば、夏休みに部活や勉強から離れることで、それらの負担の大きさに気づくなど、距離を置くことでその苦しさに初めて気づくのです。
特定の大きな負担だけではなく、一つひとつは小さな負担の積み重ねである場合もあります。
前項との違いは、1学期中は、がんばり・緊張・苦しみなどを、自分でも気づいていなかった点でしょう。
理由③生活リズムの乱れ
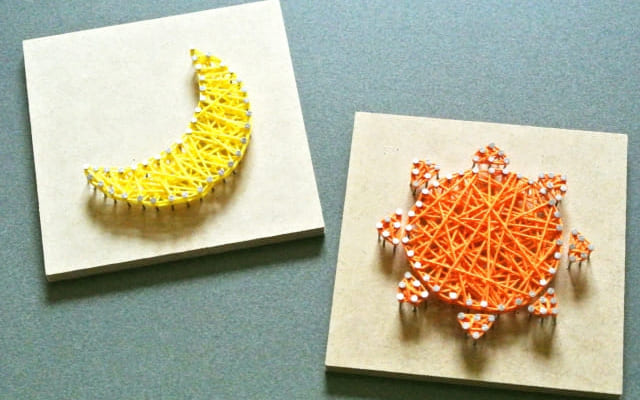
3点目は、生活リズムの乱れです。
夏休み中は学校に合わせた生活の制約がなくなるため、生活リズムが乱れやすくなります。
朝起きなければいけない理由や予定がなければ、ついつい夜更かしをして夜型の生活になりがちです。
たまに夜更かしするだけで、数日後にはいつもの生活リズムに戻せるのならば問題ないでしょう。
ですが、夏休み中に夜型の生活が続くと、いざ学校が始まったときに簡単には朝型のリズムに戻せません。
朝が起きられず学校に行けなかったり、無理やり朝起きても体調が優れなかったりすることで、学校に行きづらくなるのです。
理由④宿題や課題ができていない
夏休みの宿題や課題ができていないことも、学校に行きにくい原因となります。
宿題というやるべきことをやっていない状態であるため、「先生から叱られたり友達からからかわれたりするかも…」という気持ちが生まれ、学校に行きにくくなるのです。
また、宿題ができていないことで、勉強や学力への自信を持てなくなることもあるかもしれません。
ほかにも、夏休み明けに実施されるテストの勉強ができていないケースもあるでしょう。
このコラムをご覧になっているのが「夏休み後に不登校にならないか不安」という段階で、かつ子どもに仲のよい友達がいるようであれば、子どもに「宿題やテスト勉強のことを、友達と話してみたら?」と提案してみることが不登校の予防・対策になることもあります。
理由⑤2学期からの学校生活が憂鬱

これから先の学校生活を心配するあまり、学校に行けなくなることもあります。
夏休み明けの2学期は、一般的に他の学期よりも長く、また行事なども多い時期です(地域や学校にもよりますが)。
勉強や部活も、1学期よりも難しくなったり本格化したりすることもあるでしょう。
1学期の時点では「まだ先だ」と思っていても、夏休みを挟んで2学期が近づくことで、「嫌な行事が近づいてきた」「勉強がもっと難しくなったらついていけない」「部活の練習がもっと大変になる」などと心理的な負担が先回りして、学校に行きにくくなるのです。
理由⑥夏休み明けの人間関係が不安
夏休み中に人間関係がリセットされるような気がしたり、「同級生との関係が、自分の知らないところで1学期と変わっているかも」と不安になったりすることで、不登校になることもあります。
夏休み中は、仲のよい友達以外と会う機会は限られます。
学校の人間関係を気にしなくてよい気楽な日々…と言えるかもしれませんが、交流がなければ不安が生じるのです。
例えば、「クラスメイトたちは、夏休み中も部活仲間と過ごしていたり、学習塾で親交が続いていたりする。部活や学習塾に入っていない自分だけ、周りとの距離が開いたのではないか。そんな自分が登校しても、きっと仲よくできない…」などといった不安です。
特に、お子さんが1学期中から人間関係に不安がある場合は、ならなおさらでしょう。
このコラムをご覧になっているのが夏休み後に不登校にならないか不安という段階で、かつ子どもに仲のよい友達がいるようであれば、夏休み中の子どもと友達の交流を後押ししてみることが不登校の予防・対策になることもあります。
夏休み明けの不登校の対応で気をつけたい5つのポイント
夏休み明けに不登校になる理由をお伝えしましたが、そんなお子さんにどう対応すればよいかわからない親御さんも多いと思います。
この章では、夏休み明けの不登校への対応について解説します。
ただ、これからお話する対応は夏休み明けの不登校に限った話ではありません。
基本的な対応は、夏休み明けの不登校でも、別のタイミングの不登校でも変わりません。
また、必ずしも学校に行かせるための対応ではなく、学校への復帰も含め、お子さんにとってよりよい生活、よりよい将来のための対応として、参考にしてみてください。
ポイント①無理に学校に行かせない

まず悩まれるのが、学校へ行くよう促すかべきかだと思いますが、無理には行かせないことがとても重要です。
1週間、2週間と休みが続き、不安に感じる親御さんのお気持ちは、とても良くわかります。
「無理にでも学校に行かせれば、そのまま行けるようになるのでは?」と思われることもあるかもしれません。
しかし、基本的にはお子さんが「休みたい」「行きたくない(行けない)」と言っていたり、態度からそう読み取れたりする場合は、無理に学校に行かせないようにしましょう。
本人が望まないタイミングで無理やり学校に行かせても、よい結果が出ることは少なく、むしろ余計に行きにくくなるなど、逆効果になることが多いです。
ポイント②エネルギーが回復するまで休ませる
休むことは容認したとしても、「じゃあいつまで休ませればよいの?」と次の疑問が湧いてくるかと思います。
しかし焦らず、お子さんのエネルギーが回復を待つことが大切です(お子さんのエネルギーを回復させていきましょう)。
休みが続くと焦る気持ちが募っていくと思いますが、お子さんのエネルギーが回復するまでゆっくり休ませてください。
原因が何であれ、一度不登校になったお子さんは、多くの場合エネルギーが不足しており、学校や勉強にすぐに立ち向かうのは難しい状態なのです。
学校に行くこと以外にも、家の手伝いや家での勉強も同じです。
まずは何かに挑戦するためのエネルギーを回復させることを優先させてください。
エネルギーを回復させるためには、まず学校や勉強などの本人にとって負担になることを取り除くことが大切です。
学校を休んでいても気がかりなことがあると、心も体も休まりません。
何も考えずゆっくりさせる、少し余裕があれば好きなことをさせるなど、できるだけエネルギーの回復に集中できるような環境を整えましょう。
私の場合は、夏休み明けに不登校になってから、長い間、学校に毎日欠席連絡をしていました。
明日も行けなさそうだと自分の中でわかっていても、翌朝にまた連絡しなければいけないという状況はプレッシャーでした。
前日の夜に「明日は行けるだろうか」、「明日も欠席連絡しないといけないのか…」と毎日憂鬱になり、その結果あまり眠れなかったこともありました。
こういう状況では、エネルギーの回復に時間がかかります。
できるだけ不安のない状況で、お子さんをゆっくりさせてあげましょう。
ポイント③焦らずできことから取り組む

心身ともにゆっくり休みがとれると、少しずつエネルギーが回復し、それに伴い気力も出てきて、活動的になってきます。
そして、お子さん自身が学校へ行ってみようと思ったり、勉強を再開してみよう思ったりするのです。
この段階を示すサインの例には、直接的には「そろそろ勉強しようかな(学校に行ってみようかな)」と言ったり、間接的には「暇だな…」と言ったりする、などがあります。
しかし、親御さんも本人も焦りすぎないことが大切です。
本人が望むのであれば、さまざまなことに挑戦することは問題ありません。
その上で、「焦らずに、できるところから」という心構えが重要になります。
なぜなら、いきなり「生活を全て元に戻す!」と意気込んでも、思った以上に疲れたり、思うようにいかなかったりすることがあるからです。
親御さんを不安にさせるつもりはありませんが、そういった状況になるとお子さんは「やっぱり自分はダメだ…」と思い、再び気力を失う可能性もあります。
例えば、いきなり学校に行くではなく、まずは学校に行くのと同じ時間に起きてみる、休日に学校まで登校してみるなど、少しずつできるところから始めてみましょう。
学校や学校に関することに気持ちが向かないのであれば、まずはお子さんの好きなことから始めるのもオススメです。
不登校の子どもは学校に行けない自分に自信を失っていることが少なくありません。
ですが、好きなことをきっかけに自信を少しずつ回復して、以前のように活動できるようになることもあるのです。
ポイント④学校復帰は本人の意思を優先する
いろんなことが少しずつできるようになってきたら、やはり気になるのが今在籍している学校への復帰でしょう。
お子さんがだんだん元気で活動的になってくると、「次は学校」と思う親御さんも多いと思います。
しかし、今所属している学校への復帰も、本人の意思を優先しましょう。
本人の意に沿わず登校を再開させた場合は、気力・体力・諸々の不安などの関係で、再び不登校になる可能性があります。
さらに、自分の意思で登校を再開しても、再び不登校になることもあるのです。
これは、親御さんを心配させるためにお伝えするのではなく、「再び不登校になることは珍しいことではないので、そうなっても思い詰めないでほしい」という思いからお伝えしています。
不登校の繰り返しについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
その上で、お子さんが「今所属している学校に、もう一回通ってみたいな」などと言ったときには、前項までと同様、焦らないことが大切です。
最初から「毎日、全ての授業を受ける」ことを目標とせずに、例えば「まずは午後だけ行く」「保健室登校から始める」「つらいときには遅刻・早退もOKと考える」といったことをお子さんに伝えておきましょう。
ポイント⑤「今在籍している学校への復帰」以外も検討する

では、お子さんが「(気力・体力はあるけれど)今所属している学校には、もう行きたくない」という意思を示したらどうするべきでしょうか。
まずは、今所属している学校には行かなくていいけれど、現在と将来のために、どこかで勉強や社会性を身につけた方がよいし、身につける場所はあると理解していただければ幸いです。
そして、「今所属している学校は嫌だけれど、学校自体には行きたい」場合には、転校が選択肢になるでしょう。
不登校からの転校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
学校自体に行きたくない場合にも、勉強する方法や社会性を身につける方法はあります。
例えば、学習塾やフリースクール、習い事教室などの選択肢が考えられるでしょう。
学校より手間がかかるかもしれませんが、学校に行かないと将来がなくなるわけではないということは、安心につながるのではないでしょうか。
お子さんに伝えたうえで、今所属している学校への復帰にこだわらず、お子さんの希望やお子さんに合ったやり方を一緒に探してみてください。
親御さん自身とお子さんのための3つのスタンス
これまでお伝えした対応は、主にはお子さんに向けたものです。
この章では、親御さんご自身のため、ひいてはお子さんのためとなるスタンスについて解説します。
スタンス①不登校の原因にこだわりすぎない

最初の方で少し触れましたが、(夏休み明けに)学校に行けなくなった原因を追究しても、不登校の解決にはつながらないことがあります。
逆に、不登校になった原因は解決しないままでも、次の一歩に進めることは少なくないのです。
例えば、夏休みで、部活の練習内容がキツいと自覚したことが原因で、夏休み明けに不登校になったとします。
この場合、原因の直接的な解決とは、部活の練習内容が変わるでしょう。
ですが、仮に部活の練習内容が変わっても、不登校期間によって部活のメンバーと気まずくなった、不登校中に生活リズムが乱れたなどの理由によって、不登校が続くことがあります。
そして、そもそも生徒一人の都合で部活の練習内容が変わることは、現実的にはあまり考えられません。
しかし、「部活の練習内容」が変わらなくても、「自分のできる範囲で練習すること」を顧問に認めてもらう、部活を辞める、転校するなどで、次の一歩に進める可能性があります。
不登校の原因を追究・解決したいお気持ちはわかりますが、原因の追究・解決は次の一歩に進むために絶対に必要なことではないのです。
「なぜ不登校になったのか」よりも、現状の把握と今後の対策に着目してみましょう。
ただし、以下のように、原因を無視してはいけないケースがあります。
- うつ病、統合失調症など精神的な疾患(精神疾患から無気力になる、生活リズムが崩れることで不登校になることもあります)
- 発達障害(学業や人間関係に困難を抱えやすい発達障害は、一見普通に見えて、ある部分の能力は高いケースもあるので、親が気づかないことも多いのです)
- 夫婦の問題、経済的問題など、子どもに悪影響を与える家庭内の問題
- いじめ
- 虐待
このような場合は、未来に向けての対策を考えると同時に、原因への対応につとめることも必要です(とは言えこれも、対応は直接的な解決とは限りません)」。
特に精神疾患や発達障害の可能性があるときは、すぐに精神科や心療内科を受診しましょう。
その他の問題も、その分野の専門家の力を借りることが大切です。
スタンス②専門家・第三者を頼る
不登校解決のためには、親子が社会や学校から孤立し、家庭の中にひきこもることは避けた方がよいでしょう。
不安にさせるつもりはありませんが、そうなると不登校の長期化を招き、長期の引きこもりにつながる可能性があるのです。
逆を言うと、第三者の援助があると、お子さんも親御さんも、次の一歩に進みやすくなります。
第三者とは、不登校に詳しい人や、不登校支援を行う団体などの専門家のことです。
学校に在籍しているのであれば、担任や学年主任、スクールカウンセラーなどに相談してみてください。
以下のような、お住まいの自治体の相談窓口に相談する方法もあります。
名称などは自治体によって違っていることもありますので、お住まいの自治体のウェブサイトや代表電話で確認してみましょう。
- 児童相談所、児童相談センター
- 引きこもり地域支援センター
- 発達障害支援センター
- 教育センター(高校相当年齢)
民間にも、不登校の支援団体として、全国の「不登校の親の会」や、私たちキズキ共育塾などがあります。
親だけ、または子どもだけで相談できる場所もありますので、「まずは自分だけで(子どもだけで)」と思う場合は、そういうところを探してみてください。
また、最近はインターネットや電話で不登校の相談を受け付けているところも多いので、家の近くに相談機関がなくても頼ることができます。
相談先については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
専門家には守秘義務があるので、相談に行ったからといってそれが周囲に知られることはないので、ご安心ください。
ご本人だけ、親子だけ、ご家族だけで悩まずに、必ず専門家の助けを借りましょう。
スタンス③親は親で生活を楽しむ

親は親で、自分の生活を充実させましょう。
「子どもが不登校なのに、私だけが仕事に行ったり、趣味のサークルを楽しんだりしていいのだろうか?」などと思われるかもしれませんが、親は親で自分の人生を楽しむことが、不登校の解決に繋がります。
そうはいっても、子どもが苦しんでいるときに、自分だけ楽しめないと思う親御さんもいらっしゃるでしょう。
ですが、親が自分の生活を充実させることで、以下のような効果が得られるのです。
(1)親子が社会から孤立することを防ぐ
親が生活を楽しむことで、視野も適切に広くなり、社会からの孤立を防げます。
先述のとおり、親子とも外との繋がりがなくなり、家庭ごと地域から(世間・社会から)孤立する、ケースがあります。
親が働きに出ている場合でも、子どものことで心にずっと不安を抱えていると、社会との心理的な距離が開いていくのです。
地域や社会から孤立すると、家族・家庭という密閉した空間の中で、親の心・視点は子どもに向かう一方で、親子の不安はますます増幅します。
親の過度な不安や心配が子どもの心を圧迫していく…といった悪循環にも陥りかねません。
ぜひ、積極的に社会と関わることを意識してみましょう。
(2)親が大人のロールモデルになる
親が充実した生活を送ることで、大人のロールモデルを子どもに与えられるのです。
充実している親の姿を見ることで、子どもが「今は不登校で苦しいけど、大人になったらこんなふうに生活したい」と思えるようになることがあります。
子どもに「外の世界は楽しいよ」「大人になるっていいものだよ」と示すことが、不登校の次の一歩につながる可能性があるのです。
夏休み明けに不登校になった私が登校を再開するまで
夏休み明けに不登校が多くなるということをお伝えしましたが、最初にお伝えしたとおり、実は私もその1人です。
中学1年生の夏休み明けに学校に行けなくなり、結果的に中3の一学期まで、約1年半の間不登校でした。
私が夏休みに不登校になった理由や次の一歩に進んだ経緯をお伝えします。
①1学期に溜まっていた心身の疲れ

夏休み明けに行けなくなった原因を今になって考えると、1学期に溜まっていた心身の疲れだったように思います。
小学生の頃から体が弱く休みが多かった私は、中学に入りそんな自分を克服したいと思っていました。
そんな気持ちから、いつも気を張り、勉強に部活とがんばっていました。
がんばった結果が出たのか、中1の一学期は学校の休みも少なく、勉強や部活もよい結果が出るなど充実感のある日々でした。
②夏休みの部活で疲れがピークに
そして夏休みを迎えます。
夏休み中も、部活は毎日のようにありました。
炎天下の中、何時間も部活を行うことは、体力的に苦しく感じることも多かったです。
「今日は部活を休みたい」と思うこともありました。
ですが、「休んだら試合に出してもらえなくなるかも」「周りもがんばっているのに自分だけ休むわけにはいかない」などの思いがあり、休めませんでした。
体力的にも精神的にもつらさを感じながらも、お盆休みまではなんとかがんばって部活に行けていました。
しかし、あと10日程で夏休みが終わるタイミングで、私は突然部活に行けなくなりました。
疲労がピークに達して、部活へのがんばろうと思う気持ちが持てなくなったのです。
③部活を休んだことから学校も休みがちに
部活の時間になると気持ちが憂鬱になり、部活を休む日々が続きました。
初めは、1〜2日休めば部活にまた行けるようになると思っていました。
しかし、数日休んでも体はキツく、部活に行く気持ちにはなれませんでした。
そして、部活に行けないまま夏休みが明けました。
少しずつ体力は回復してきており、学校には行こうと思っていたのですが、「部活はずっと休んでいるのに、学校に行ったらどう思われるのだろう?」と心配になり、学校も行きにくくなっていました。
そして、休みが続くと学校に行くハードルもどんどん高くなっていき、気づくと不登校になっていました。
結果として、私は中1の夏休み明けから1年半の不登校生活を送りました。
そんな私は、中3になると、それまでのことがなかったことのように学校に行けるようになりました。
不登校を脱したきっかけと心の変化をお話しします。
④ボーッと過ごすうちに心身のエネルギーが回復

学校を休み始めてからしばらくは、何もする気になりませんでした。
何かをがんばることができなかったのです。ボーッとテレビを見たり、ベッドに横になったりして一日の大半を過ごしました。
そんな日々をしばらく過ごしていると、少しずつですがエネルギーが回復してきたようで、何かやってみようかなと思えるようになってきました。
学校に行くことはハードルが高かったので、家にいながら本を読んだり、少しだけ机に向かって勉強したりするようになりました。
⑤回復しても自信の喪失から登校を再開できない
少しずつやる気も回復していき、できることも増えてきました。
ですが、学校には行ける気がしませんでした。
自信を失っていたのだと思います。
学校に行けないことにより、私は自信が全くなくなっていたのです。
「学校に行けない=中学生として最低限のことができていない」と思っていたので、自分が恥ずかしい存在のように思っていました。
そんな恥ずかしい自分は学校に行っても認められず、つらい思いをするだけだと勝手に思い込んでいたのです。
体調的には学校に行けるような状態だったとは思うのですが、自信のなさが学校への恐怖や不安を生んでいました。
学校に行けないことが、自信の全てを奪っていたように感じます。
⑥親も最初はどうしたらいいのかわからなかった
私の不登校は、親も初めてのことで不安や戸惑いがあり、どう対応すればよいかわからなかったと思います。
親には「学校に行かせないといけない」という気持ちが強く、それが学校に行けていない自分を間接的に否定することにもつながっていました。
今の私には、「親は、私のためを思って、学校に行かせたがっていた」と理解できます。
ですが当時の私は、「学校が全てではない」「学校に行けなくても人の価値は変わらない」といった言葉を欲していました。
それだけで、ずいぶん気持ちも楽になったと思います。
学校に行けないなら勉強をがんばろうと思い、テストでいい成績(テストの日だけ登校していました)をとっても、学校に行けないために、親からはなかなか褒められることがありませんでした。
しかし一方で、親が私に協力してくれることも、もちろんありました。
⑦親の協力のもと趣味を通じて自信を回復
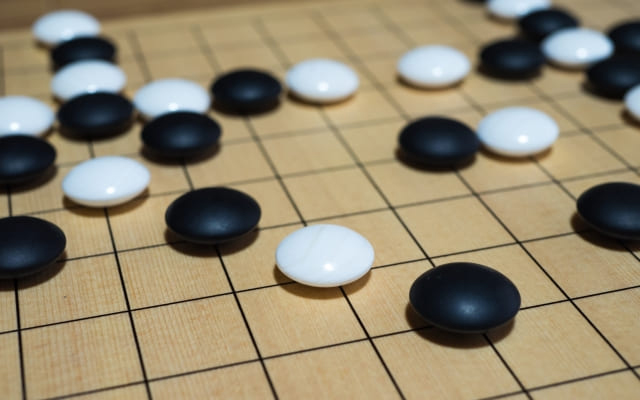
失った自信を回復したきっかけは、自分の好きなことでした。
趣味である囲碁をきっかけに出会った同級生や大人の人たちとの関係の中で、自信が徐々に回復したのです。
勉強では、いくらがんばっても学校に行かないと認められませんでした。
ですが、趣味の世界では、学校に行っている・行っていないに関わらず、努力や成果を認めてもらえたのです。
もっと言うと、同好の士であるというだけでも、認めてもらえました。
親は、子供が学校に行かずに囲碁をすることに対して、心配や不安もあったでしょう。
ですが、私が囲碁を続けられるようにサポートしてくれました。
好きなことを続けることを認めてくれて、サポートし続けてくれたことは、今でもとても感謝しています。
囲碁を通じて、自分自身を認めてもらえる場に出会ったことで、少しずつ自信が回復していきました。
⑧担任が代わったことをきっかけに登校を再開
不登校になってから一年程で、少しずつ自信も回復していき、体調も回復していきました。
学校に行っていないという事実はありましたが、心身は以前のような状態に戻っていました。
そんな状態の中、中3になりました。
中3になると、担任の先生が他の学校からきた新しい先生に変わりました。
新しい先生に変わったことで、私はなんとなく「その先生の前では新しい自分でいれるのではないか」と思うことができ、学校にもう一度挑戦してみようと思えました。
そして、中3の初日から登校し、たまに休む日はあったものの中1の一学期のように学校に通えるようになりました。
心身の調子を整えつつ、親のサポートの元で好きなことを通じて自信を回復し、自分の中で「いまなら行ける!」と思うきっかけがあったことが、不登校の次の一歩に進めた大きな要因だったように思います。
私の体験談が、あなたと、あなたのお子さんのお役に立ったなら幸いです。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
まとめ〜夏休み明けに限らず不登校は心身のSOSです〜

夏休み明けは、1学期での無理や我慢が心身の不調として出やすいタイミングです。
つまり、夏休み明けの不登校は、子どもからのSOSとも言えます。
まずはエネルギーの回復を優先させ、しっかり心身の体調を整えてから、これからのことを考えるようにしましょう。
また、お子さんの様子が心配な場合は、今回お伝えした夏休み明けの不登校の予防・対策になる方法を実践してみてください。
さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方々のための個別指導塾です。
生徒さんの中には、夏休み明けに不登校になった方も大勢いらっしゃいます。
無料相談も承っており、ご相談いただければ、あなたのお子さんのための具体的なお話ができると思います。
キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください(ご相談は無料です。また、親御さんだけ・お子さんだけでのご相談も承っています)。
Q&A よくある質問