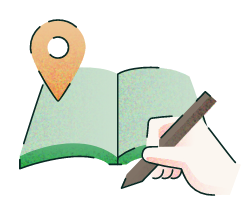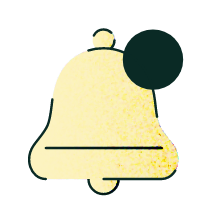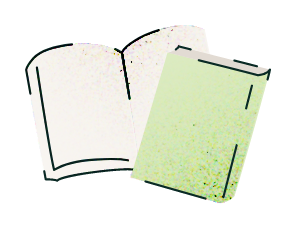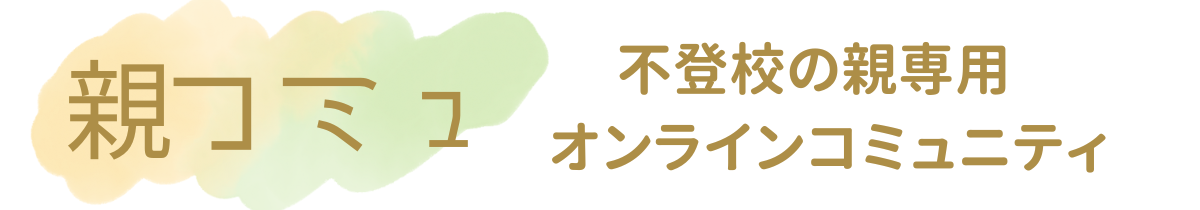子どもが不登校になったら親は仕事を辞めるべき? 体験談から解説
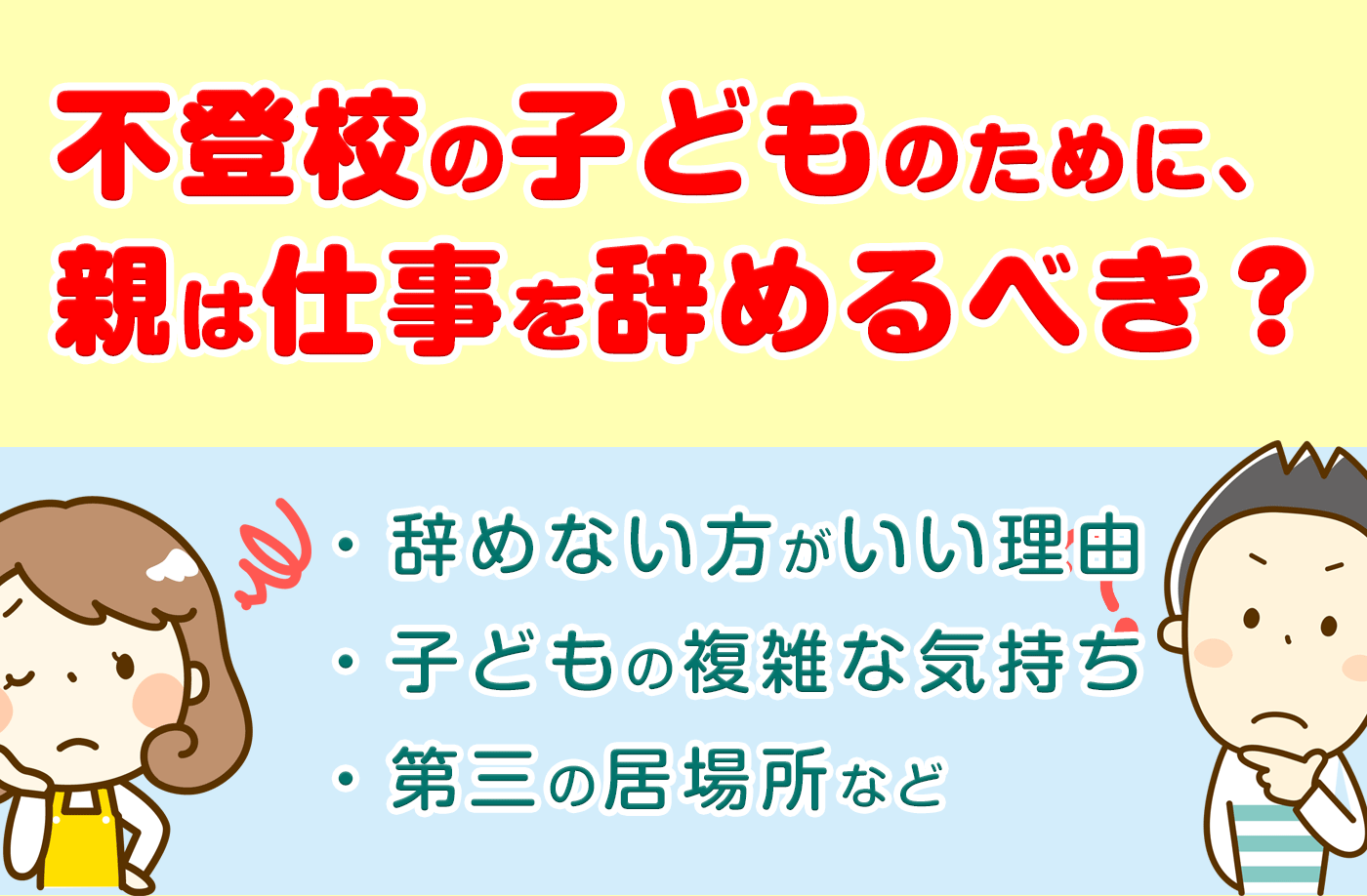
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
不登校状態にあるお子さんがいるあなたは、子どものために仕事を辞めるかどうか悩んでいませんか?
不登校状態にあるお子さんがいるで、仕事をしている親には、以下のようなお悩みがつきものです。
- 子どもは、不登校状態になる前も不登校状態になった今も、苦しんでいる…
- 自分が仕事を辞めて世話をした方がいいんだろうか…
このコラムでは、不登校状態にあるお子さんがいる親御さんに向けて、不登校状態にあるお子さんの親が仕事を辞めるべきではない理由や家庭・学校以外の第三の居場所の重要性について解説します。
私自身、中学3年生の秋から春にかけて不登校状態だった不登校当事者です。
このコラムを読むことで、不登校状態にある子どもがいる親と仕事をする個人という両方の立場を持つあなたの気持ちが少しでも軽くなり、次の一歩が見つかれば幸いです。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
体験談をたくさん読むと、解決策が見えてきます
このコラムは、かゆいところに手が届くコラムです。
不登校状態にあるお子さんがいる親御さんは、誰しも一度は子どものために仕事を辞めるかどうかを考えるものです。そのお悩みを解決するためには、このコラムをはじめ、たくさんの体験談を読んでいただくといいかなと思います。
読んだ体験談の内容があなたのお子さんに似ているかどうかは、あまり関係ありません。ただ、読んでいくうちに、お子さんの気持ちが見えてくる瞬間があるのです。
そして、お子さんの気持ちが見えてくると、実際のあなたがどうするべきか、答えも見えてくるはずです。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
不登校状態にある子どもの親は仕事を辞めるべき?続けてもいい?
お子さんが不登校になり、お子さんを思って「仕事を辞めようか」と考える親は多いです。
親が仕事を辞めようかと考える大きな理由は、お子さんが心配だからというお子さんへの愛だと思います。
では、親が仕事を辞めることで子どもは幸せになるのでしょうか?
この問いに対して、全ての家庭に当てはまる答えはありません。
というのも、収入・支出、仕事の内容、お子さんの状況などの諸条件は、それぞれの家庭によって異なるからです。
ですが、できる限り、親は仕事を辞めるべきではないというのが私の考えです。
不登校経験者の体験談「お母さん、私のために無理しないで」

私は中学3年生の秋に不登校状態になりました。
不登校の直接のきっかけとなったのは、部活動のチームメイトのきつい言葉です。その言葉を思い出して、涙が止まらない日もありました。
また、高校進学を考えていた私は、不登校状態からの高校受験のプレッシャーに押しつぶされそうになっていました。
そんな日々、母は仕事を早退し、私の好きなご飯をつくってくれたり、「勉強疲れてない?彩の好きなお菓子を買ってきたよ」と声をかけたりしてくれました。
母は、当時のことを振り返って、「彩が受験のプレッシャーで苦しんでいたから、少しでもそばにいて励ましたかった。」と言ってます。
私はそんな母の対応が嬉しかったのですが、一方で、以下のように、母が無理をしている様子も見てとれました。
- 仕事の早退について職場の同僚に電話で謝っている様子
- 「私が仕事をしてなかったらもっと彩の相談に乗れて、彩は不登校状態になるまで悩まなかったんじゃないか…」と親戚に悩みを打ち明ける姿
そんな母を見て、「自分が不登校状態になったせいで、母は仕事を辞めるのかもしれない。」と不安や罪悪感でいっぱいになりました。
そのほかにも、当時の気持ちを、昨日のことのように覚えています。
当時の気持ち
- お母さんが、自分のことを思ってくれて嬉しい
- お母さんに、自分のために仕事を早退させて申し訳ない
- お母さんはお母さんらしくいてほしい。無理しないでほしい
- でも、ひとりで家にいるのは寂しい…
つまり、母への思いには、感謝と同時に、罪悪感や自分でも、母にどうしてほしいのかわからない気持ちなどが入り混じっていたのです。
子どもが不登校状態でも親が仕事を辞めるべきではない理由

不登校状態にある私たちは、親に対して、以下のような複雑な気持ちを持っています。
不登校状態にある子どもの気持ち
- 親が働いていると寂しいこともある反面、自分のために仕事に支障があると申し訳ない
そのため、親が仕事を辞めると、親に対する申し訳なさは増していきます。
もちろん、家に親がいると、寂しさはなくなります。
ですが、やがて以下のような気持ちになることもよくあるのです。
親が仕事を辞めた後の子どもの気持ち
- いつもいるからうっとうしくなってきた…。あまり話したくないな…
- 仕事を辞めるなんて、よっぽど自分は信用されていないんだな…
そして、不登校状態にあるお子さんが思う親に対する申し訳なさの一つには、家計のこともあります。
お子さんには、以下の思いこみによって、悩みが深くなることがあるのです。
親が仕事を辞めた後の家計への思い
- 自分のために親が仕事を辞めた
- 自分のために収入が減ったんだから、自分は高校や大学に進学しない方がいいな
- でも、進学以外で『次』に何ができるのかわからない…
- ますます悩みが深くなる…
不安にさせるつもりは決してありませんが、こういう状況になっては、お子さんはなかなか次の一歩に進めません。また、親も苦しくなるでしょう。
これが、お子さんのために仕事を辞めるべきではないという理由です。
お子さんへの愛はわかります。
親がお子さんに寄り添うことは重要です。
ですが、仕事を辞めてつきっきりになることはオススメしません。
ポイント
先述のとおり、お子さんは親に対して複雑な気持ちを持っていて、自分でもうまく表現できません。まずは、自分の気持ちをうまく表現できないお子さんの声をじっくり聞いてください。
その上で、お子さんがそばにいてほしいと願うときは、いきなり退職ではなく、以下のような手段が取れないか、職場に相談することをオススメします。
- 柔軟な遅刻・早退
- 時短勤務
- 時間の都合がつきやすい部署への異動
- (一部を)在宅勤務化
お子さんの複雑な気持ちの理解が難しければ、カウンセラーへの相談や相談機関の利用も考えてみてください。 私たちキズキ共育塾も無料相談を受け付けています。
家・学校以外の第三の居場所を利用しましょう
お子さんが不登校になった場合は、家でも学校でもない、第三の居場所を利用しましょう。
お子さんとしても家で一人っきりではさみしいはずです。そして、不登校の次に向けた準備も必要です。
最近では、フリースクールや適応指導教室などが増えてきました。
そこでは、お子さんと一緒にご飯を食べる人や、一緒に趣味の話をする人や、勉強を教える人がいます。
ポイント
フリースクールのような、家でも学校でもない第三の居場所をうまく利用できれば、お子さんは孤独を感じることはありません。
また、「今日は楽しかったな」「そろそろ次のことを考えようかな」と前向きな気持ちを持てるようになります。親としても、家を空けている時間の心配が減ります。
送迎が難しかったり、近くにそういう場所がなかったり、行ってみた団体がお子さんに合わなかったりしたときは、オンラインで話ができるサービスもあります。
子どもの不登校と、親である自分の仕事についての体験談
この章では、我が子の不登校と、自分の仕事について、学校が苦手な人たちのための個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちの、親の立場からの体験談を紹介します。お子さんへの接し方の参考として、ぜひご覧ください。(講師名は仮名の場合もあります)
また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、ほかの事例も紹介可能です。ぜひご相談ください。
加藤殿音講師の体験談
子どもは、小学校の入学式に行けなかったときから、学校には行っていません。最初の担任の先生とおりが合わず、不登校状態になりました。学年の変わり目で担任が変わるときを機に、がんばって保健室登校をしていた時期もありましたが、連休を境にして行けなくなりました。いまではもう学校に行っていない状況です。
親として何ができるのか、子どもになるべく付き添い、話をしてました。解決できないか、学校に行ける方法はないかと手を尽くしましたが、次第に反抗も加わるようになり、状況は悪くなる一方でした。
そんなときに、偶然、勤務先でリモートワークが始まりました。リモートワークのため、インフラを整えようと、タブレットとPCを購入しました。仕事以外に子どもと楽しめる使い方がないかと考え、私は絵が好きだったこともあり、タブレットのお絵かきソフトで絵を描くことをし始めたんです。
私自身、子どもの不登校という状況に追い詰められていたんだと思います。逃げるような気持ちはなかったのですが、私自身が楽しめることを見つけ、そちらに流れてしまったんです。
子どもは、初めはあまり興味を示しませんでした。ですが、私がネットを通じてイラストを販売し始めたあたりから、すごく興味を持ち始めたんです。そして、隣に来て一緒に絵を描くようになりました。
最近では、学校のプリントもやるようになってきました。無理矢理やらせようとしても嫌がってやらなかったのに、何も言わなくなったいま、なぜ自分でやるようになったのか、私にはわかりません。でも、そんな我が子を見ていて、何故かすごく愛おしく、自慢に思えてくるんです。いま思えば、私自身に余裕がなかったんだと思います。義務のように子どもと向き合い、言うことを無理矢理聞かせようとしていたのかと、反省しています。
まとめ〜子どもの不登校で仕事を辞めることはオススメできません~

不登校状態にあるお子さんのために、「仕事を辞めて面倒を見た方がいいのだろうか」とお思いでしょう。
しかし、実際に仕事を辞めると、お子さんは嬉しい反面、以下のような感情を覚えることがよくあります。
- 自分のせいで仕事を辞めさせて申し訳ないという罪悪感
- 自分を信じてもらえてないんじゃないかという不信感
- 家計に対する過剰な気遣い
仕事を辞めてつきっきりで面倒を見ると「いつも顔を合わせるとうっとうしいな」と思うようになることもあります。
そうなると家族仲がギスギスし、お子さんも親も苦しい状況が続きます。
そのため、仕事を辞めることはオススメしません。
まずは落ち着いてお子さんの声を聞きつつ、仕事を辞めずにお子さんをケアする方法を探してみませんか?
お子さんがどう思っているのかわからなかったり、お子さんに対して何ができるか悩んでいたりする場合は、相談機関等を利用しましょう。
相談することで、それぞれのご家族・お子さんに応じてより具体的なアドバイスがもらえると思います。
このコラムが、不登校に悩むお子さんと親の、次の一歩につながったなら幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾でも無料相談を行っており、親だけのご相談も可能です。
キズキ共育塾では、不登校経験を乗り越えた講師やスタッフも大勢働いています。
私たちとの出会いを通して、何かお子さんの気持ちに気づくきっかけになればと思います。
少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。
/Q&Aよくある質問