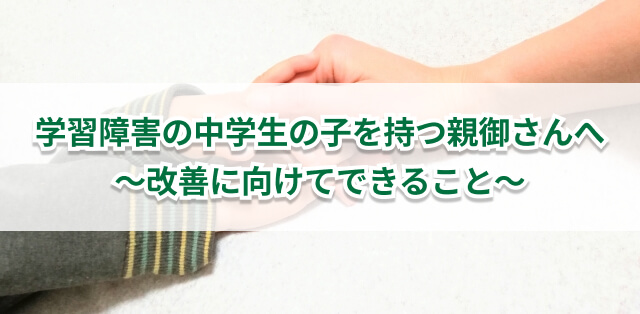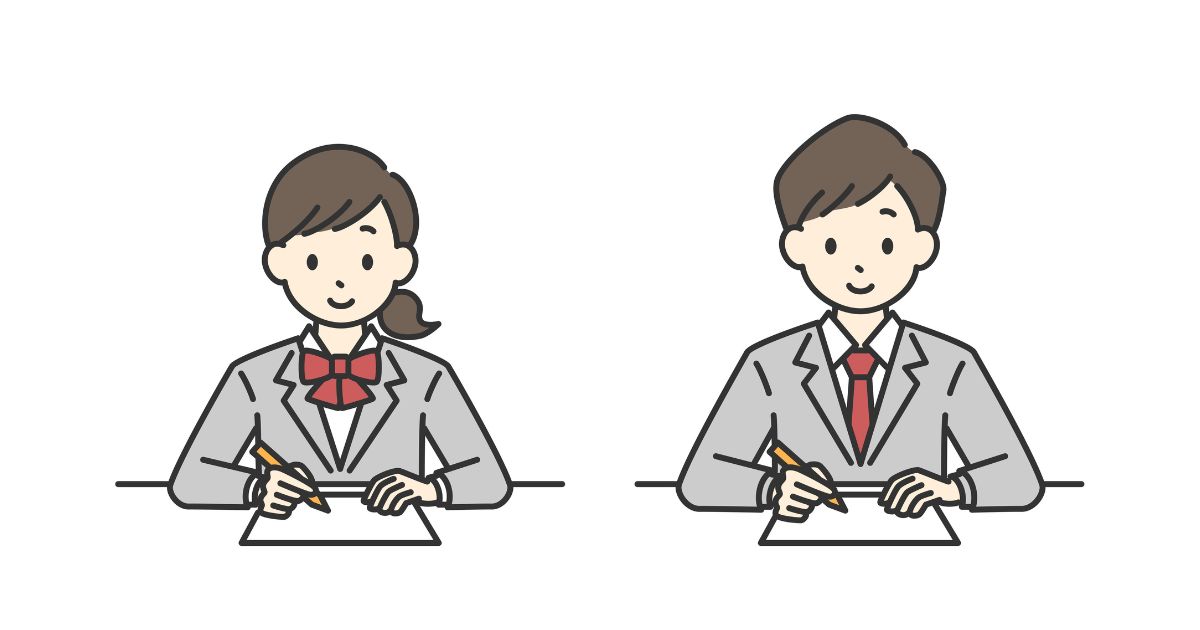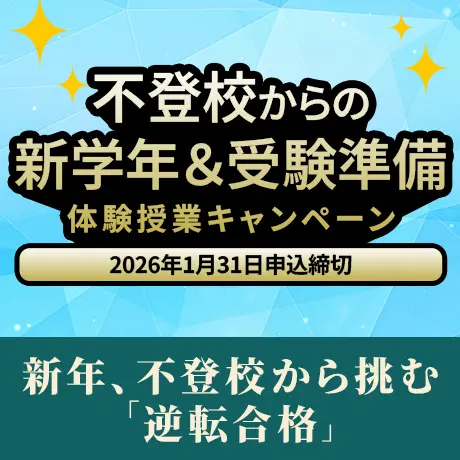LD/SLDと不登校の関連性 きっかけや親ができる対応を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、LD/SLDのある中学生のことで、以下のような疑問や不安を抱えていませんか?
- LD/SLDのある人が不登校になるきっかけは?
- 親ができることはある?
このように悩む人は、少なくありません。このコラムでは、LD/SLDと不登校の関連性やきっかけ、親ができる対応、将来の選択肢などについて解説します。あわせて、よくある質問にも回答します。
LD/SLDのある人や親御さんはもちろん、今後のために知っておきたい人もぜひ最後までお読みください。
私たちキズキ共育塾は、LD/SLDのある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
LD/SLDと不登校の関連性

LD/SLDのあるお子さんは、そうでない子どもたちと比べて物事の理解が遅れることなどが原因となり、不登校になるケースがあります。
調査によると、調査対象の教師のうち約20.6%が、児童が不登校になる背景にはLD/SLDを含む発達障害の診断・疑いがあると回答しています。(参考:公益社団法人 子どもの発達科学研究所・浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター「文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究 報告書」)
また、福島大学の調査では、福島県の県北・県中地域の公立の小・中・高校の不登校児童生徒のうち発達障害が疑われたのは、小学生で約16.1%、中学生で約7.9%、高校生で約13.3%でした。(参考:福島大学「発達障害が疑われる不登校児童生徒の実態― 福島県における調査から―」)
このことから、LD/SLDと不登校には一定の関連性があると考えられます。
LD/SLDのある人が不登校になる3つのきっかけ
この章では、LD/SLDのある人が不登校になるきっかけについて解説します。
きっかけ①周囲の人から誤解されたりからかわれたりする
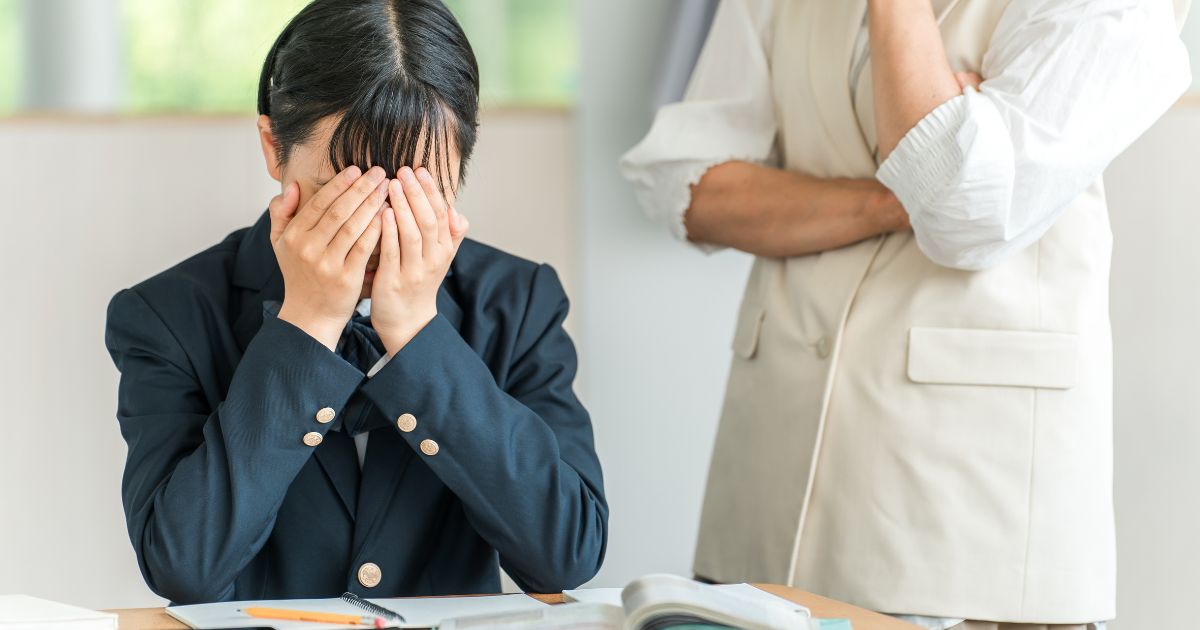
1つ目のきっかけは、周囲の人から誤解されたりからかわれたりすることです。
LD/SLDのある人は、読み書きといった学習面で困難が生じるため、周囲の人から注目を集める場合があります。
問題を解けないことを笑われたり、周囲の人に自分の意見がうまく伝わらなかったりすることがあるのです。
この様にからかわれるのが嫌で、不登校になるケースがあります。
きっかけ②周囲の人と比べて自信をなくす
2つ目のきっかけは、周囲の人と比べて自信をなくすことです。
LD/SLDのある人は、学習のペースが周囲の人と異なる場合があるため、「自分だけ勉強ができない」と自信をなくすケースがあります。
その差が一向に埋まらないと、さらに自信をなくして不登校につながるのです。
きっかけ③努力が報われない経験をする
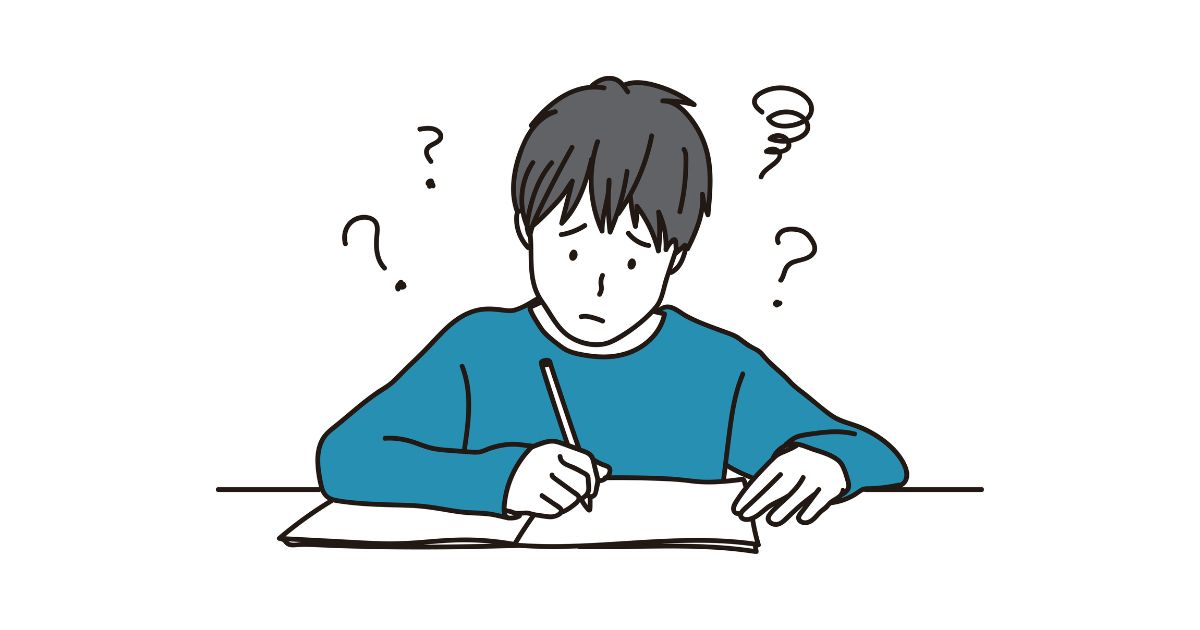
3つ目のきっかけは、努力が報われない経験をすることです。
例えば、本人はすらすらと計算ができるようになりたいのに、どれだけ頑張っても実際にはできないという経験です。
LD/SLDが原因であり、努力が足りないわけではないのですが、どれだけやってもできない自分に自信をなくして不登校につながるケースがあります。
不登校になったLD/SLDのある子どもに親ができる対応15選
この章では、不登校になったLD/SLDのある子どもに親ができる対応について解説します。
前提:専門家や支援機関に相談する

前提として、お子さんの不登校やLD/SLDについて、親だけで対策を行う必要はありません。専門家や支援機関に相談するようにしましょう。
不登校やLD/SLDに対する社会の理解は、少しずつとはいえ、確かに広まってきています。
以下のような支援機関では、不登校やLD/SLDについての相談ができたり、サポートを受けられたりします。
- 病院
- 自治体の子育て・発達障害に関する相談窓口
- 発達障害や不登校の親子を支援するボランティア
- 発達障害や不登校の親の会
- 発達障害や不登校の子どもを支援する学習塾 など
このような支援機関に相談すれば、専門的な知見に基づいたアドバイスやサポートをもらえます。そのため、お子さんの次の一歩につながりやすくなるのです。また、親御さん自身のお悩みや不安を相談できる場合もあります。
最初は相談することに抵抗があるかもしれませんが、お子さんはもちろん親御さん自身のためにも、積極的に支援機関を活用してみてください。
対応①休ませる
1つ目は、お子さんを休ませることです。
不登校状態にあるお子さんは、学校に行かなくなるまでに、大変な状況に身を置いていたり、精神的に追い込まれていたりすることが多く、心身ともに疲れ切っています。
そのため、親御さんからは「学校を休んでもいいよ」「家でゆっくり休んでね」と声をかけてあげてください。
また、声をかける以外にも、以下のようなサポートができます。
- 好きなことをさせる
- 睡眠をたっぷりとらせる
- 栄養のある食事を用意する
親御さんの中には、「休ませると、本格的な不登校になったり、ひきこもりになったりするのでは…?」と不安に思われる方もいるかもしれません。
ですが、しっかりと休息をとり、エネルギーを回復できれば、「そろそろ何かしたい」と、お子さん自らが次の一歩を踏み出し始める場合もあります。
焦る気持ちはあるかもしれませんが、お子さんが回復するためには休む時間が必要です。
対応②お子さんの話に耳を傾ける

お子さんの話にしっかり耳を傾けることも、親御さんができる対応の1つです。
親が自分の話をしっかりと受け止めてくれたという実感は、お子さんの安心感に繋がり、次の一歩に踏み出しやすくなります。
また、親御さんの方も、お子さんの状況や気持ちを把握できるため、これからのことを考える際のヒントを得られるかもしれません。もし、不登校になったきっかけが分かれば、対策が見えやすくなるでしょう。
対応③無理に話を聞き出そうとしない
お子さんの話を聞くことは大切ですが、お子さんが自ら話をしてくれるのを待つことも重要です。
無理に話をさせようとしたり、「何があったの?」「どうして学校に行かないの?」などと問い詰めたりすると、お子さんを精神的に追い詰めることになります。
不登校のきっかけを、自分でもよくわかっていないケースもあります。お子さんと話したいことはたくさんあるかもしれませんが、まずはお子さんが自分から話してくれるまで待つようにしましょう。(参考:文部科学省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」)
お子さんが話してくれるときがきたら、以下のことを意識して話を聞くようにしてみてください。
- 話したくない様子であれば「話さなくてもいいよ」と伝える
- 子どもが話し始めたら、批判や否定をせずに最後まで話を聞く
親御さんがこういった姿勢で話を聞いていると、お子さんは安心感を得られ、自分が思っていることや考えていることを話しやすくなるでしょう。
対応④家を居心地のよい場所にする

家を居心地のよい場所にすることも、とても大切です。
これまでにお伝えした対応にもつながりますが、不登校状態にあるお子さんには、エネルギーを回復するための時間と安心できる場所が必要です。
家がお子さんにとって居心地がよく、安心できる場所であれば、次の一歩に進むためのエネルギーが溜まりやすくなるでしょう。
居心地がよい場所とは、具体的には以下のような場所のことです。
- 自分の気持ちを素直に言える場所
- 人間関係に気を使わなくていい場所
親御さんの中には、「居心地がよすぎると家から出なくなり、不登校が長期化するのでは?」と不安な方もいるかもしれません。
ですが、学校が安心できる居場所ではないというお子さんには、それに代わる居場所が必要です。
エネルギーが回復すれば「何かしたい」「勉強でもしようかな」という前向きな気持ちや発言が出てくるはずです。
親御さんとして、焦る気持ちは当然です。ですが、お子さんの中に前向きな気持ちが生まれてくるまで、辛抱強く見守りましょう。
対応⑤学校と連絡を取る
学校と連絡を取ることも、大切な対応です。
具体的には、以下のようなことを聞いたり、相談したりしてみてください。
- 学校での様子
- 休んでいる間のテストや提出物、宿題
- 保健室登校など学校で受けられる不登校支援
- 内申点や進路指導
こういったことを学校と話しておくと、お子さんのこれからについて考えやすくなります。
また、お子さんが「学校に復帰したい」と言いだした時も、スムーズに対応することができるでしょう。
ただし、学校から支援を受けるかどうか、学校に復帰する方向で話を進めるかどうかなどについては、お子さんの意思を確認することが大切です。
親御さんや学校の先生の判断だけで話を進めると、お子さんを精神的に追い詰めることになり、信頼関係も築きづらくなります。必ず、お子さんに確認するようにしましょう。
対応⑥学校復帰以外の選択肢を考える

お子さんがこれまで通っていた学校に再び通うことを望まない場合は、それ以外の選択肢を考えましょう。
親御さんの中には、以下のように悩んでいる方がいるかもしれません。
- 子どもが学校に行けないなんて、恥ずかしい
- 普通のルートから外れたら今後が大変だ
- 学校に行かないと、将来がない
ですが、そのようなことはないのです。
今在籍している学校に行かなくても、進学や就職をすることは、十分に可能です。また、近年は、不登校状態の理解が進みつつあり、不登校状態にある子どもの居場所となる場も増えてきています。
もちろん、学校に通わないことによるデメリットはあります。ですが、そのデメリットを軽減したり回避したりする方法はあるのです。
これまで通っていた学校に再び通うことにこだわりすぎず、お子さんに合った選択肢を探してみてください。
具体的な選択肢については、こちらで解説します。
対応⑦LD/SLDについて学び、子どもの特性を知る
専門家や支援機関に相談したり、関連本を読んだりして、LD/SLDの特性などについて学びましょう。
LD/SLDの特性が不登校と関連する場合は、その特性に対する適切なサポートが必要ということです。
これは、現在の不登校に対してだけでなく、将来的に大学に進学したり社会に出たりしたときにも有効です。
親子でお子さんの特性を理解することで、現在への対応や将来のことなどについて、お子さんにあった方法を考えられるようになります。
対応⑧ペアレント・トレーニングや療育などを受ける

ペアレント・トレーニングなど、親子で、または親だけ・子どもだけで受けられる、LD/SLDのある人を支援するプログラムがあります。
ペアレント・トレーニングでは、子どもの行動を理解し、親はどんな対応をするのが望ましいかを、グループワークや個別指導で学ぶことができます。
自治体や病院、大学、親の会などが数日間の講座として行うことが多いようです。
そのほかにも、TEACCH、感覚統合法、応用行動分析、放課後デイサービスなどの療育を行っている自治体や支援機関もあります。自治体が主催する場合、多くは無料開催の傾向にあります。
ペアレント・トレーニングも含めて、近隣の施設でどのような療育を受けることができるのか、お住まいの自治体の福祉課を担当する部署・窓口や児童課を担当する部署・窓口、子育て支援センター、発達障害支援センターなどに問い合わせてみてください。
対応⑨親の会に参加する
同じような悩みをお抱えの親御さんが集まる親の会などで、情報交換をすることも大変有効です。
最近では、LD/SLDのある子どもを育てた親や不登校状態にあった子どもを育てた親が、いま育てている親に寄り添い、アドバイスをするペアレント・メンターという活動も盛んに行われています。
子育てに唯一の正解はありません。
家族会や親の会でいろいろな意見を聞き、「この子に合う育児が我が家の育児なんだ」「いろんな子育てがあっていいんだ」と前向きな気持ちを取り戻す親御さんもいます。
お子さんのことで悩む親同士で話し合うことで、具体的な解決策が見つかることもあれば、話したり気持ちを共有するだけで楽になることもあるでしょう。
親の会は全国にあります。「LD/SLD 親の会 ○○市」「不登校 親の会 ○○県」などとインターネット検索を行うと、複数見つかると思います。
近隣の親の会で知っている人に合うのを避けたい場合は、隣県の親の会に参加することも可能です。
一人で悩まず、親の会や家族会に参加してみましょう。中にはオンラインで参加できる親の会もあります。ぜひ、参加をご検討ください。
対応⑩勉強が気になるなら、LD/SLDに理解のある学習塾などを利用する

学校に行かなくなると、勉強についていけなくなることが心配かもしれません。
そのような場合は、LD/SLDの特性への理解と指導実績のある学習塾などを利用しましょう。私たちキズキ共育塾もその一つです。
そうした学習塾では、一般的なLD/SLDの特性に対応した授業を行うことはもちろん、お子さん一人ひとりに合わせて柔軟な対応を行っていることも珍しくありません。
「LD/SLD 塾」「不登校 塾」などとインターネット検索をすると、いくつか候補が見つかると思います。気になるところがあれば、ぜひ見学に行ってみてください。
対応⑪一緒に予習をする
お子さんが勉強をする際に、一緒に予習をするのも有効です。
お子さんにアドバイスができるということもありますが、 算数問題を解いていく過程などを見ることで、具体的にどのようなLD/SLDがあるのかを細かく把握できるメリットがあります。
また、ネットワークや支援機関からのアドバイスで、親御さん自身が見知った学習方法を教えるよい機会にもなります。
リビングのテーブルで一緒に勉強するなど、ちょっとした工夫を取り入れて、一緒に予習をする習慣をつけるとよいでしょう。
ですが、お仕事などの事情で、お子さんと一緒に予習する時間を確保することが難しいという方もいるかと思います。
お子さんと予習する時間を取ることが難しい人は、支援機関などへ相談すると、親御さんの状況に合わせた代替案を一緒に考えてくれるはずです。キズキ共育塾もそのひとつです。ぜひご相談ください。
親御さんがお仕事やご家庭の事情などでご多忙なことは、決して珍しいことではありません。
お子さんのために時間を確保できないことを、負い目を感じる必要はありません。積極的に、状況に合わせた適切なサポートを得るようにしましょう。
対応⑫タブレットなどの電子機器を取り入れる

お子さんのLD/SLDの特性によっては、タブレットなどの電子機器を活用することで劇的に効果が上がる場合があります。
例えば、読字障害がある場合には、タブレットやスマートフォンの読み上げ機能を用いることで、教科書の内容を追いやすくなります。
また、オンライン図書などは、画面上の読むべき箇所がハイライトされていたりして、読みやすくなる工夫がされています。
まずは、どのような工夫があれば学習環境が整うかを、お子さんと話してみましょう。それを満たせる電子機器があれば、取り入れてみてください。
お子さんの特性によっては、学校でもタブレットなどの電子機器を使用できるとよいかもしれません。その際は、先生や協力機関の支援員に、電子機器の使用を相談してみてください。
対応⑬愛情のメッセージを絶やさない
「私はあなたが可愛くて、好きで、誰よりも愛している!」というメッセージを、お子さんに送り続けることを忘れないようにしましょう。
学校の授業でつまずいていたり、自分の期待に沿わない成績をとっていたりすると、お子さんは自信をなくします。
お子さんに自信を持たせ、自己の存在感、生きがいなどを育てていくためには、親御さんから愛情を注がれているという自覚を持てることが重要です。
そうすることで、親子の信頼関係を築き、保っていくことができます。
親子の信頼関係は、勉強以外にも、今後生きていく上での土台となっていくことでしょう。
対応⑭細かいことはあまり注意しない

お子さんの不得意な部分について、細かいことまで言いすぎないようにしましょう。
不得意な部分の改善に注目すると、あれもこれもと気になって、いつも注意をしているような状況に陥りがちです。
これが続くと、お子さんは自信をなくし、家族にはストレスがたまります。
改善のポイントは一つに絞り、そのポイントに関係ないことについてはあまり注意しないことがコツです。そのポイントが改善したら次のポイントについて対応していく、といったように、順序立てて行っていきましょう。
不登校になったLD/SLDなどの発達障害のある子どもの将来の選択肢5選
不登校になったLD/SLDなどの発達障害のある子どもの将来の選択肢は、以下のとおりです。
- 学校復帰する
- 学校以外の場所で勉強する
- 転校する
- 高卒認定試験を受けて進学する
- 就職する
発達障害のある子どもが不登校になる原因や親ができる対応、発達障害と不登校の関連性について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
LD/SLDのあるお子さんが受けられる支援3例

LD/SLDのあるお子さんが受けられる支援は、以下のとおりです。
- 特別支援教育
- 発達障害者支援センター
- 民間の学習支援機関
LD/SLDの特徴がある子どもとの接し方や親御さんができる対応、進路を考える際の注意点について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
発達障害とは?
発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? – 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
同じ診断名でも、人によって様々な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人に、他の発達障害が併存している可能性もあります。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害とは?生まれつき? ADHD、ASD、LD/SLDを解説」
LD/SLDとは?

LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)
LD/SLDは症状別に、以下の3つの種類に分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
LD/SLDのある人は、全ての学習行為に困難が生じるというわけではありません。
いずれか1つの学習行為、または複数の学習行為に困難が生じている人もいます。読むことと書くことが不得意、計算することのみが不得意などのように、人によってそれぞれです。
また、いずれの学習行為においても、人によって得意なこと、不得意なことは違います。
例えば、読字障害のある人のなかでも、音読はできてもその内容を理解することが難しいという人もいれば、スムーズな音読が不得意な人もいます。
このように、LD/SLDのある人は、学習する事柄が総合的に不得意というわけではなく、ごく一部の事柄に困難が生じるという点が大きな特徴です。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)とは? 特性や診断基準を解説」
学習障害による二次障害とは?
二次障害とは、主障害に起因して起こる副次的な障害のことです。ここで取り上げている発達障害の二次障害とは、発達障害や発達障害グレーゾーンの傾向・特性に伴って発生する精神障害やひきこもりなどの二次的な困難や問題のことを指します。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』、小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ』)
発達障害のあるお子さんは、障害に伴って日常生活に困難を抱えているため、いじめや仲間外れなどを経験する場合もあります。
そのような経験から、自信を失ったり、心に傷を負ったりすることで、二次障害を併発する可能性があるのです。
そのため、ご家族や学校の先生が、いち早く変化に気づいてサポートすることが大切です。
具体的には、行動面と情緒面で以下のような様態があらわれます。(参考:竹田契一『LD(学習障害)のある子を理解して育てる本』)
行動面
- 引きこもり
- 不登校
- 家出
- 暴言や暴力
- 素行不良
情緒面
- うつ病
- 社会不安障害
- パニック障害
二次障害と聞くと、不安に思われるかもしれません。ですが、お子さんが落ち込んだとき、または落ち込みそうなときに、きちんとケアできれば問題はありませんので、ご安心ください。
また、二次障害に繋がる元々の障害は、LD/SLDだけでなく、ASDなどの発達障害である場合もあります。正確な診断については、必ず専門医にかかるようにしましょう。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害の二次障害とは? 抱える悩みや予防策、対処法を解説」
LD/SLDによる不登校に関するよくある質問
この章では、LD/SLDによる不登校に関するよくある質問について回答します。
質問①LD/SLDのある小学生の特徴は?

LD/SLDのある小学生の特徴は、以下のとおりです。
小学生前の幼児期(1歳〜小学校入学)
- 言葉や文字を覚えるのが遅い
- 折り紙が折れない、ボタンがとめられないなど手先が不器用
- 身体の使い方がぎこちない
小学生時期(6歳〜12歳)
- 文字が読めない
- 文章を読むのがぎこちない
- 憶測で文章を読む
- 行を飛ばして読む
- 鏡文字を書く
- 板書が苦手
- 文字が行やマス目からはみ出す
- 数が正確に数えられない
- 時計が読めない
- 計算が苦手
- 筆算の数字がずれる
質問②LD/SLDのある中学生の進路はどう考えればいい?
LD/SLDのある中学生の進路を考える際の注意点は、以下の2つです。
- 学習障害に関連する素行などが、内申点に響いていないか
- 志望校の、学習障害に対する支援体制
学習障害の特徴があるお子さんとの接し方や親御さんができる対応、将来の展望について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
質問③共働きでLD/SLDのある子どもが不登校になったらどうすればいい?

共働きだと時間を取るのが大変だと思いますが、まずはお子さんと話す機会を作ってみましょう。思わぬ原因があるかもしれません。
とはいえ、家庭だけで抱え込む必要はありません。不登校について相談できるところはたくさんあるので、頼ってみてください。相談先には、以下のようなところがあります。
- 担任・学校のスクールカウンセラー
- 心療内科・小児科
- 市区町村の子育て相談窓口
- 児童相談所・発達障害者支援センター
- 不登校や発達障害の子どもの支援実績がある塾・家庭教師・フリースクールなど(私たちキズキ共育塾もその一つです)
- 不登校・発達障害のお子さんの親御さんが集まる「親の会」
発達障害や生活上の困難、不登校の次の一歩について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ~LD/SLDなどの発達障害による不登校は、専門機関に相談しましょう~

LD/SLDは不登校のきっかけになることがありますが、決して否定的に捉える必要はありません。
お子さんの話を聞いたり家を居心地のいい場所にしたりなど、親御さんができることはたくさんあります。
相談できる場所もたくさんありますので、ぜひ相談してみてください。このコラムが、お子さんにとって最適な選択をするための助けとなれば幸いです。
Q&A よくある質問
LD/SLDのある人が不登校になるきっかけを教えてください。
不登校になったLD/SLDのある子どもに親ができる対応を教えてください。
以下が考えられます。
- 休ませる
- お子さんの話に耳を傾ける
- 無理に話を聞き出そうとしない
- 家を居心地のよい場所にする
- 学校と連絡を取る
- 学校復帰以外の選択肢を考える
- LD/SLDについて学び、子どもの特性を知る
- ペアレント・トレーニングや療育などを受ける
- 親の会に参加する
- 勉強が気になるなら、LD/SLDに理解のある学習塾などを利用する
- 一緒に予習をする
- タブレットなどの電子機器を取り入れる
- 愛情のメッセージを絶やさない
- 細かいことはあまり注意しない
詳細については、こちらで解説しています。