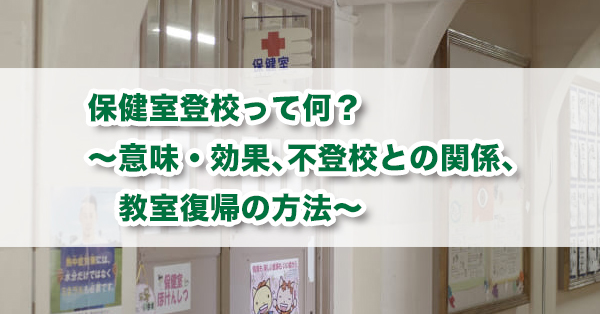別室登校とは? 教室復帰を目指すときに親ができる対応を解説
私たちキズキ共育塾は、学校が苦手な人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
別室登校とは?
別室登校とは、教室(在籍しているクラス)の代わりに相談室や保健室などの学校内の別室に登校することです。
別室登校について調査研究をおこなっている京都府総合教育センタ-では、以下のように定義しています。(参考:京都府総合教育センター「別室登校研究」)
不登校傾向の児童生徒が学校に登校している間、定められた通常の教育活動から離れて、常時もしくは特定の時間帯に相談室や保健室などの校内の別室(や他の場所)で、個別もしくは小集団で活動している状態
(参考:京都府総合教育センター「別室登校研究」)
以上を踏まえて、この章では、別室登校の目的や登校中の過ごし方について解説します。
別室登校の目的

別室登校というと、不登校状態にある人のための措置という印象が強いかもしれません。しかし実際は、さまざまな目的で利用されます。
- 不登校の「予防」
- 子どもを孤立から防ぐ
- 不登校からの教室復帰に向けた慣らし登校
学校を休みがちで不登校になりそうな人や、教室に居場所がないという人も対象です。
つまり、別室登校の目的の中心にあるのは、教室での学習が難しい人に別の学びの場を提供し、学校への登校を維持することだと言えるでしょう。
それを前提として、教室復帰の足がかりにするという目的も持っている、というイメージです。
ちなみに、京都府教育委員会が別室登校中の小学生111人、中学生340人を対象におこなった調査では、小学校で約49.1%、中学校で約26.8%が完全に教室登校に戻ったり教室登校が増えたりしたという結果が出ています。(参考:京都府総合教育センター「「別室登校」児童生徒の教室復帰に効果的な関わり-児童生徒と保護者の声から-」)
別室登校中の過ごし方
別室登校をしている人は、決まった時間に登下校をしなくてはいけないわけではありません。体調や気持ち、目標など、本人の希望が尊重されます。
別室登校中の過ごし方も定められていないことがほとんどです。一般的には、次のような活動をすることが多いです。
- ドリルや教科書を使った勉強
- タブレットなどを利用した学習
- 先生やカウンセラーとの会話
休憩時間には別室登校をしている他の生徒と話したり、読書をしたりすることもあります。先生やカウンセラーとの面談は、一般的にどの学校でも行われます。
保健室登校・放課後登校との違い

別室登校に似た登校スタイルとして、保健室登校と放課後登校があります。
- 保健室登校:教室の代わりに保健室に登校すること
- 放課後登校:同級生が下校した時間帯に教室に登校すること
保健室登校は別室登校の一種であり、放課後登校は基本的には登下校の時間だけをずらす、という違いがあります。
また、放課後登校は保健室登校(別室登校)に比べて学校にいる時間が短くなりがちです。簡単な面談をしたり、家でやってきた課題の質問に答えてもらうなどのサポートは受けられます。
小学校・中学校・高校での扱いの違い
学校にもよりますが、小学校・中学校・高校では、別室登校の扱いに違いがあると言われています。
まず、小学校と中学校は、(教室に通わない)別室登校だけでも、一般的には進級・卒業できます。
しかし高校では、別室登校だけで進級・卒業できるとは限りません。
実際に京都府総合教育センターの調査研究では、高校は別室登校をしていても欠席・欠課扱いになりうることが難点として挙げられています。(参考:京都府総合教育センター「別室登校V」)
別室登校を出席とみなすかどうかは、各高校が判断します。出席扱いになる高校もあります。
逆に、中学校でも私立のように独自のルールがある場合は、別室登校だと進級・卒業に関わる場合があります。別室登校の扱いがどうなっているのかは、必ず学校に確認を取るようにしましょう。
別室登校の4つのメリット
不登校状態にある人や教室に居場所がない人が別室登校をすることには、多くのメリットがあります。
この章では、別室登校をするメリットを解説します。
メリット①出席扱いになる

別室登校は、公立の小中学校では、基本的に出席としてカウントされます。
そのため、教室に行きたくても行けない人や、どうしても行く気になれない人でも、別室登校をすることで(高校や私立の小中学校の)進級・卒業に必要な条件を満たせる可能性があります。
ただし、学校によって差があることも事実ですので、必ず学校に確認しましょう。
メリット②学習を継続できる
不登校の間は授業が受けられないので、自然と勉強をしなくなりやすいです。
別室登校をしていれば勉強の習慣を保てるため、学習を継続できます。課題を進めるなかで分からないところがあれば、先生に直接質問することもできるでしょう。
分からないときに質問できる相手がいることで、安心して勉強を続けられるという心理的なメリットもあります。
メリット③学校と接点を保てる

別室登校を続けていれば、教室に入らなくても学校と接点を保つことができます。そのため、完全な不登校やひきこもりの状態になることを予防できます。
他にも別室登校をしている生徒がいれば、その生徒と交流を図ることで、よい影響を得られるかもしれません。給食の時間にクラスメイトが来て一緒に食べようと誘ってくれたという事例もあります。(参考:京都府教育委員会「別室登校研究Ⅱ」)
また、学校と接点を保つことは、親御さんにもメリットがあります。
先生の方針によっては、生徒が不登校になると、学校との接点が親との定期的な連絡のみになることがあります。すると、相談をしたり、支援を依頼しづらくなったりするかもしれません。
別室登校をしていれば、先生も生徒の様子をある程度は把握しているため、比較的コミュニケーションが取りやすくなります。
メリット④生活リズムの維持に役立つ
不登校になると生活が不規則になりがちです。別室登校をしていると外出する習慣ができるため、生活リズムの維持に役立ちます。
自宅以外の居場所や通う場所を持つというのは、生活習慣を整えるために大切なことです。
別室登校は勉強面だけでなく、生活面でも意義が大きいということをぜひ覚えておいてください。
別室登校の4つのデメリット・注意点
見方によっては、別室登校にもデメリット・注意点があります。
この章では、別室登校のデメリット・注意点について解説します。
注意点①丁寧な支援が受けづらい場合がある

別室登校をしている生徒がいても、先生には、授業の準備やテストの採点などの仕事がさまざまあります。
授業時間でなかったとしても、別室登校中の生徒の支援に多くの時間を割くことはできないのです。
また、別室登校の指導は集団授業と違い、抱えている事情や進度が生徒ごとに異なります。そのため、どうしても一人ひとりに対応できるわけではないという面があります。
丁寧な支援を受けたい場合は、別室登校とは別に、完全個別指導の学習塾の利用なども検討してみるとよいでしょう。
注意点②学習内容に遅れが生じやすい
別室登校をする頻度は、週に数回、数時間など、通常の登校よりも少ないのが一般的です。
そのため、週に5日フルで授業を受けている生徒に比べると、学習内容に遅れが生じやすいと言われています。
ただし、自宅や塾でたくさん勉強している人や、授業よりも自習の方がはかどるという人は、別室登校をしていても進度が遅れないかもしれません。
注意点③負い目を感じやすい

人によっては、別室登校に負い目を感じることもあるようです。
クラスメイトが教室で授業を受けている時間に登校することや、自分だけが人目につかない部屋で勉強していることに罪悪感を持つ場合があります。
特に、他に別室登校をしている仲間がいない人ほど、引け目をおぼえやすいかもしれません。
言うまでもなく別室登校は悪いことではないのですが、なかには気にする人もいるということには配慮する必要があります。
補足:教室復帰を希望する場合、復帰が難しくなる可能性がある
別室登校が不登校の予防に役立つことは確かです。一方で教室復帰を希望している場合、「別室登校のままでもいい」と思うことで、復帰が難しくなる可能性があるという問題点も指摘されています。
たとえば、こちらで解説したとおり、小学生の約49.1%、中学生の約26.8%が完全に教室登校に戻ったり教室登校が増えたりしたという調査結果が出ています。
なお、これは、あくまで教室復帰を希望する場合の注意点です。別室登校によって心理的な安全性が保てる場合、そこを拠点にし続けることもひとつの選択肢です。お子さんにあった選択をしましょう。
別室登校から教室復帰を目指すときに親ができる4つの対応
別室登校を経て教室復帰をするまでには、段階を踏むことが大切です。
この章では、親御さんに向けて、別室登校から教室復帰を目指すときに親ができる対応を紹介します。(参考:福島大学総合教育研究センター「効果的な「別室登校」支援のあり方について : 福島県における実態調査からの考察」)
前提として、この章でお伝えする内容は、「お子さんが教室復帰を目指している場合の話」です。そうでないお子さんには、無理に教室復帰を促さないようにしましょう。
対応①無理をさせずに見守る

別室登校では、登校に不安を感じている子どもが学校内に安心できる場所を確保することが優先されます。
そのため、別室登校だからといって無理に登校を促して、居心地が悪い思いをさせるようなことがあってはなりません。
無理はさせずに、見守る態度を保ちましょう。
別室登校に慣れてペースができてきて初めて、「そろそろ教室に顔を出してみようかな?」という気持ちになれるものです。まずは本人のペースを尊重しましょう。
対応②先生とこまめに相談する
保護者が学校側と密に情報を共有し、相談することも大切です。別室登校中に相談できる相手としては、担任の先生、別室担当者、カウンセラーなどがいます。
相談内容はお子さんの状況によって変わります。
安定して別室登校ができるようになったら、クラスの状況や授業の進み具合などを共有しながら、教室復帰の時期を検討するとよいでしょう。
反対にうまく定着していないようであれば、別室登校のどのような点で居心地が悪くなっているのか考える必要があります。
家での様子と別室登校中の様子についてしっかりと情報交換をしながら、最適な解決策を探しましょう。
対応③段階的に人に慣れさせていく

別室登校は教室復帰に向けた慣らし登校の一環ではあるものの、その後いきなり人の多い教室で授業を受けるのはハードルが高いでしょう。
そのため、段階的に人に慣れさせていくことも大切です。
- クラスメイトに給食や学食に誘ってもらう
- 教材などを教室に運ぶ手伝いをしてもらう
- 参加しやすい学校行事への参加をうながす
- ペアでの活動がない授業から出席を提案する
選択授業などの比較的少人数の授業に出られるようになってから、本人の意思も確認したうえで、少しずつ通常の授業参加に切り替えていくのが一般的です。
対応④教室復帰後も見守り・相談を継続する
教室復帰に成功しても、人によっては再び不登校になったり、別室登校に戻りたくなったりすることがあります。
そのため、復帰後も見守る姿勢が重要です。親御さんは担任の先生と小まめに情報共有をし、折に触れて相談することを忘れないようにしましょう。
また、教室復帰をした子どもが相談しやすい雰囲気を作ることも大切です。
ただし、過剰に心配して悩みを引き出そうとするのは逆効果なので、あくまでも子どもから話しやすい環境を作るということを意識してください。
補足:教室復帰以外の選択肢もあります
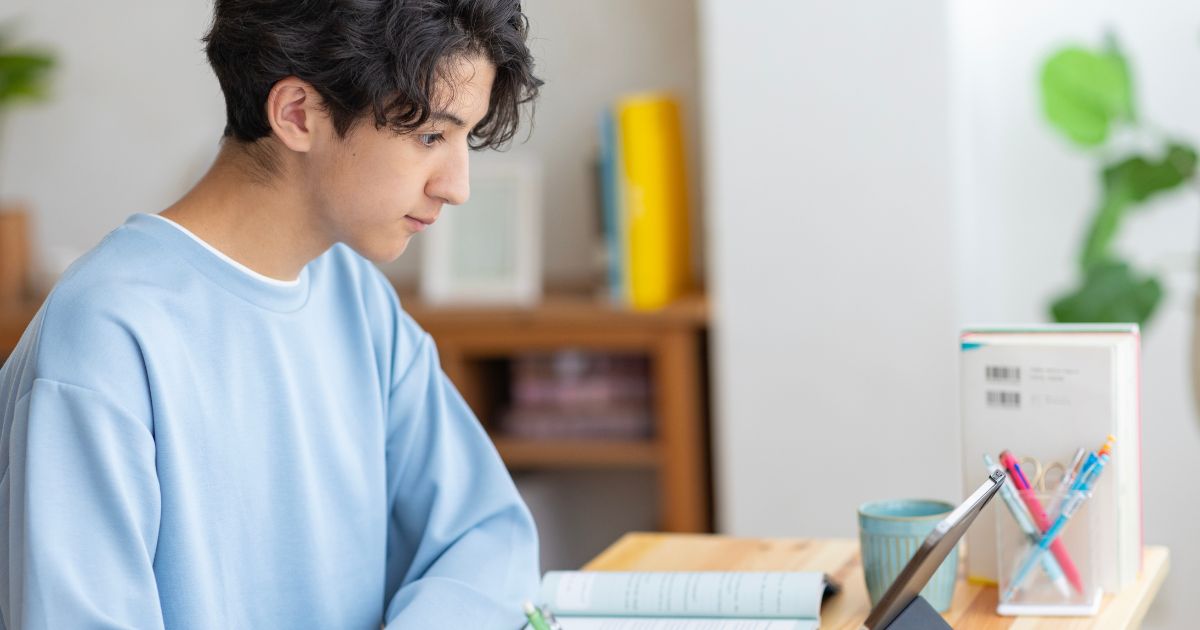
忘れてはならないのは、教室復帰以外の選択肢もあるということです。
別室登校の目的のひとつは教室復帰ですが、教室復帰にこだわるために次の一歩を踏みだせないこともあります。
特に、子どもが教室復帰を望んでいなかったり転校を望んでいたりする場合に、親だけが教室復帰を望んでいると、学校や支援者も含めて、「次の一歩」への足並みがそろいません。
学校というシステムにこだわらなくても、勉強を続ける方法はたくさんあります。
- 学習塾
- 家庭教師
- 動画授業
- 通信教材
以上のような学習支援サービスを利用して学校を卒業した・高校や大学に進学したという人は大勢います。
私たちキズキ共育塾も、学校に行きたくない子どもに完全個別指導で勉強を教えています。
精神面・生活面のサポートもできますので、お気軽にご相談ください。
別室登校に関するよくある3つの質問
この章では、別室登校に関するよくある質問について回答します。
Q1.別室登校をした場合、内申点はどうなりますか?
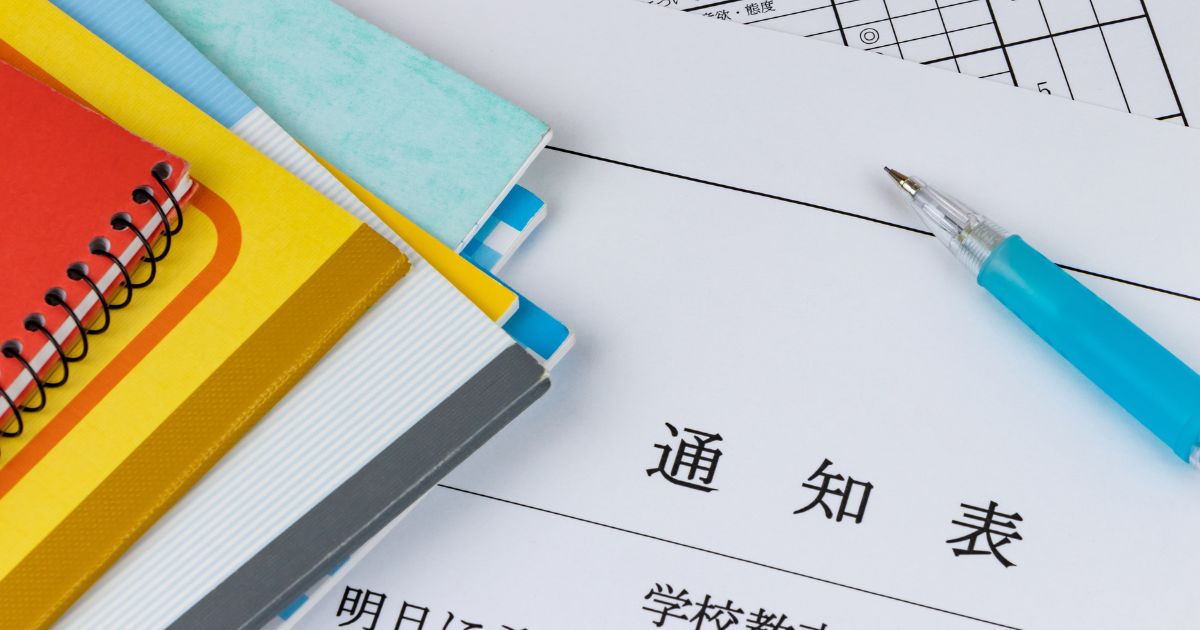
別室登校が内申点に関わるのは、出席日数として認められるかどうかという点です。
一般論として、義務教育である小学校・中学校では、別室登校も出席日数にカウントされます。成績面で対応できれば、内申点への影響は大きくないかもしれません。
ただし、「必ずカウントされる」とは限らず、別室登校の取り扱いは、学校によって異なります。
試験を受けていなかったり、1日のうち少しの時間しか登校していないと全日の出席扱いではなく遅刻・早退扱いになったりする場合は、内申点が低くなる可能性もあります。
また、全日の出席扱いになっても、内申書に別室登校をしていた旨が記載されることもあります。
このように、別室登校をした場合の内申点の扱いは一概には言えません。詳しくは通っている学校の先生に必ず確認を取ってください。
Q2.別室登校をしていても高校受験は可能でしょうか?
可能です。
別室登校が内申点などに影響した場合でも、内申点にかかわらず受験できる高校はたくさんあります。ご安心ください。
Q3.別室登校経験者の体験談や実際に感じた効果を知りたいです。

別室登校の体験談としては、「先生に教えてもらえたり、プリントを使ったりして、勉強できてよかった」「学級の友達と会えてよかった」という声が多いです。
参考までに、京都府総合教育センターの調査で寄せられた別室登校経験者と保護者の声を引用します。
小学生
・「休み時間のたびに友だちが遊びにきてくれたことや給食を一緒に食べることができてうれしかった。」
・「先生と一緒に勉強できたことや、先生に自分の気持ちが話せたことがよかった。」
中学生
・「勉強をしながら、いろんな先生と雑談ができた。」
・「他の別室の子た ちと友だちになり、よく話すことができてよかった。」
保護者
・「別室での一年間は、子どもにとって大きな力になりました。子どもに寄り添い、子どものペースを大切にしながら少しずつ進んでいくことができ、先生方への感謝は言葉では言い尽くせません。」
・「子どもの今の状態を見ながら段階を踏んで過ごしやすい場所を作ることが必要だと感じました。学校に行くことは大切です。だだからこそ、別室は学校での居場所となり、親も子どもも安心できました。」
(引用:京都府総合教育センター「別室登校研究Ⅱ」)
まとめ~別室登校、お子さんと話をして、学校とも相談しながら検討しましょう~

別室登校は、不登校の人や学校を休みがちな人が次の一歩を踏みだすために効果的な手段です。
学習を継続できたり生活リズムを維持するのに役立ったりと、さまざまなメリットがあります。親御さんにとっても、学校との接点を保てるというメリットがあるでしょう。
「学校には行きたい。でも教室に通えない」というお子さんには、一つの選択肢になると思います。
別室登校を検討している人は、まずは担任の先生に相談してみてください。いきなり学校の先生に話すのは緊張するという場合は、学習塾の先生などに話を聞くのもオススメです。
私たちキズキ共育塾でも、不登校に悩んでいる人の相談を受け付けています。
まずはお気軽に、ご相談ください。