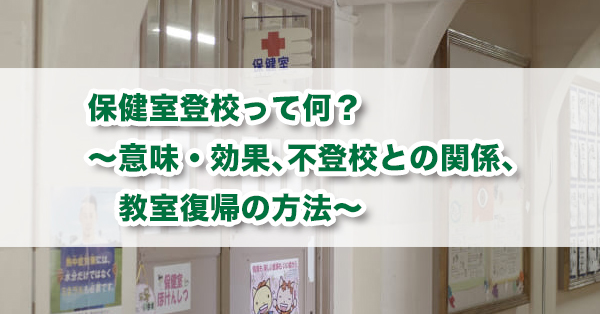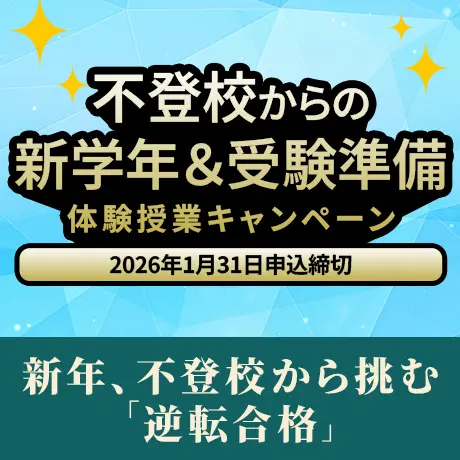学校をズル休みするのは悪いこと? 親への伝え方を解説
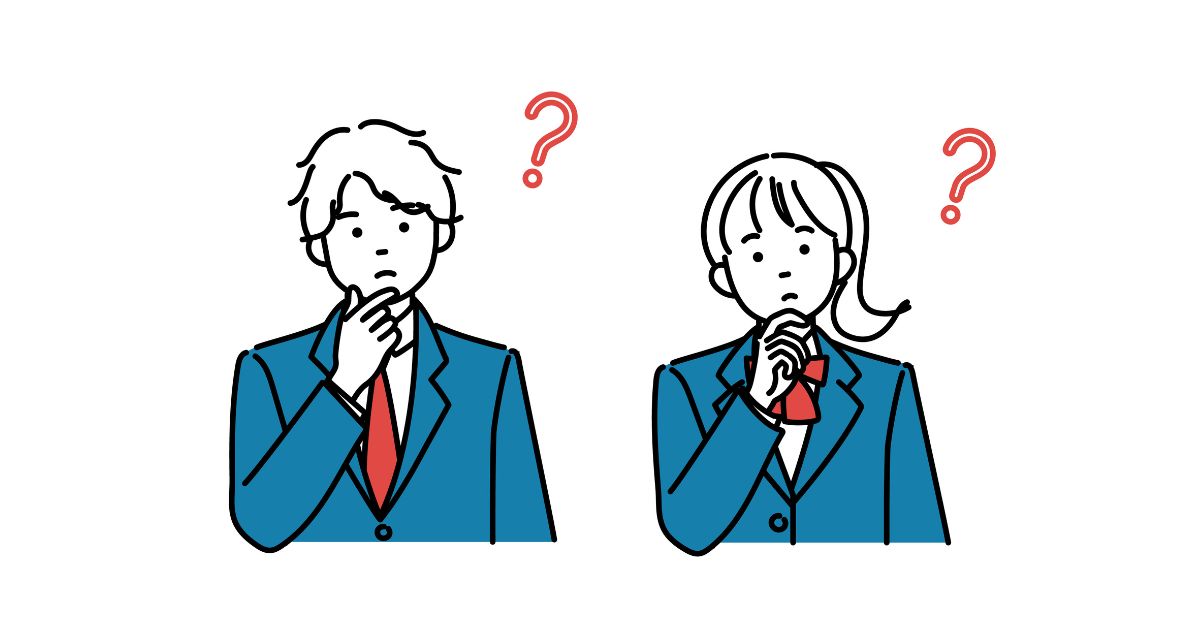
こんにちは。生徒さんの気持ちに寄り添う完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
- 理由はうまく説明できないけど学校を休みたい…でも怒られるかも
- なんとなく行きたくないけど、理由もないし言いづらい
そんなふうに悩んでいませんか?
学校を休むことに罪悪感を抱いたり、「ズルしているだけなのかも…」と自分を責めたりする中高生は少なくありません。
でも、本当に大切なのは「どうして休みたいのか?」という気持ちに向き合うことです。
このコラムでは、具体的な理由なく学校をズル休みしたくなる主な理由、親への伝え方の工夫、休んだときの過ごし方や心の持ち方などについて解説します。
「ズル休み=悪いこと」と決めつけず、自分の気持ちと向き合うヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
私たちキズキ共育塾は、学校を休みたい気持ちのある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
学校を休むことは悪いことではない

学校を休むことは、決して悪いことではありません。むしろ、心や体が疲れているときにしっかり休むことは、自分を守るための大切な行動です。
人は誰でも日々の生活の中でストレスや疲れを感じるもので、中学生や高校生であっても同じです。
学校が「面倒だ」「だるいな」と感じたり「今日は行きたくない…」と思ったりするのは、決して特別なことではありません。
ズル休みはよくないと言われることもありますが、ズル休みしたくなるほどつらい気持ちを抱えているなら、それはわがままではなく、何らかの理由があるはずです。
そうした自分の気持ちに向き合い、必要に応じて休むことはむしろ前向きな選択です。
今は、学習塾やフリースクール、オンライン学習、地域の居場所など、学校以外にも学びやつながりの方法はたくさんあります。
文部科学省も、以下のように明言しています。
不登校は、取り巻く環境によっては、どの子どもにも起こりうるもの。不登校は決して問題行動ではありません
(参考:文部科学省「フリースクール・不登校に対する取組」)
大切なのは、ズルで終わらせず、自分の気持ちに向き合ってみることです。
自分の気持ちや状態を丁寧に見つめて「今日は休もう」と思ったら、素直にその気持ちを受け入れてみましょう。
学校をズル休みしたいと思う6つの理由
この章では、学校をズル休みしたいと思う理由について解説します。
理由①身体・心の不調

1つ目の理由は、身体・心の不調です。
体調が優れなかったり、気分が落ち込んでいたりすると「今日は学校を休みたい」と感じやすくなります。(参考:文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」)
- 小学生:約27.0%
- 中学生:約33.0%
身体の不調は、子どもたちにとって登校をためらう大きな要因となっています。
心身のコンディションが整っていないときは、無理をせず一度立ち止まって休むことも大切です。
理由②人間関係のストレス
2つ目の理由は、人間関係のストレスです。
先生や友達との関係に悩みがあると、学校に行くことが精神的に大きな負担になります。(参考:文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」)
友達のこと
- 小学生:約25.0%
- 中学生:約26.0%
人間関係の悩みは、小学生・中学生を問わず、多くの子どもが抱えている大きな要因の一つです。日常的に顔を合わせる相手との関係がうまくいかないと、学校が行きたくない場所になることもあります。
理由③生活リズムの乱れ

3つ目の理由は、生活リズムの乱れです。
夜更かしや朝起きられない日が続くと、登校のハードルがどんどん高くなります。(参考:文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」)
- 小学生:約26.0%
- 中学生:約26.0%
全体の4人に1人以上が、生活リズムの乱れを理由に登校をためらっていることがわかります。
特に夜更かしや昼夜逆転が習慣化すると、朝起きること自体がつらくなり、学校をズル休みしたくなるケースも少なくありません。
理由④学業への不安
4つ目の理由は、学業への不安です。
「勉強がわからない」「授業についていけない」などの不安が積み重なると、登校をためらう場合があります。(参考:文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」)
- 小学生:約31.0%
- 中学生:約42.0%
学業への不安は、登校をためらう大きな要因のひとつです。
苦手意識や置いていかれる感覚が強まるほど、学校に対するストレスも増加します。
理由⑤インターネット・SNSによる影響

5つ目の理由は、インターネットやSNSの影響です。
ゲームや動画、SNSなどに夢中になりすぎて夜更かしをしてしまい、翌朝起きられなくなり学校を休みたくなる場合もあるでしょう。(参考:文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」)
- 小学生:約18.1%
- 中学生:約17.3%
インターネットの使い方次第では生活リズムを大きく崩し、登校に支障をきたすこともあります。
また、SNS上の人間関係やトラブルが、精神的な負担となるケースも少なくありません。インターネットやSNSは便利で楽しい側面がある一方、使い方や時間の管理が難しいため、学校を休みたくなる一因になる可能性もあります。
理由⑥特に理由はないが気が進まない
6つ目の理由は、特に明確な理由はないけど、なんとなく学校に行きたくないというものです。(参考:文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」)
- 小学生:約25.5%
- 中学生:約22.9%
小学生の約4人に1人、中学生の約5人に1人が「理由ははっきりしないけれど、学校に行きたくなかった」と感じていることになります。
本人も気づかないうちに正体の見えない不安や疲れが積み重なっている場合もあります。
自分でも理由をうまく説明できない感情こそ、丁寧に向き合う必要があるでしょう。
学校をズル休みしたいと思ったときに親に伝える際のポイント3点
この章では、学校をズル休みしたいと思ったときに親に伝える際のポイントについて解説します。
ポイント①休みたい理由を正直に伝える

学校を休みたいときは、できるだけ正直に理由を伝えることが大切です。
仮病などの嘘をついて休もうとすると、後から親に伝わったときに、気まずい思いをする可能性があります。
例えば「クラスのことで悩んでいる」「少し気分が落ち込んでいる」など、自分の中にあるモヤモヤをそのまま伝えるだけでも構いません。
理由がはっきりしない場合やうまく言葉にできないときもあるでしょう。そんなときは「なんか調子が悪い」「ちょっと疲れてるだけ」などの伝え方でも大丈夫です。
大切なのは、感情的にならず落ち着いて自分の気持ちを伝える姿勢です。
すべてを完璧に伝えようとせず、可能な範囲で自分の気持ちに正直になってみましょう。
ポイント②前日に伝える
学校を休みたいときは、前日のうちに伝えるのも効果的です。
当日の朝に突然伝えると「ただの気まぐれかな?」と思われる可能性があります。
前日の夜に「明日は学校を休みたい」と話しておけば、落ち着いて相談でき、気持ちも伝わりやすくなるでしょう。
例えば、夕食中などリラックスした時間に「ちょっと明日は行く気になれなくて…」と話せば、親も受け止めやすくなるでしょう。
前もって相談すると、信頼感が生まれ話もスムーズに進みやすくなります。
ポイント③何をするつもりかも一緒に伝える

学校を休みたいときは、その日どう過ごすかまで伝えると親の安心につながります。
ただ「休みたい」とだけ伝えると、親は「何もせずダラダラするのでは?」と不安になる場合があります。
やりたくないことをやると伝えるのは気が重いかもしれませんが、まずは休むことへの理解を得るのが重要です。
例えば、「勉強の遅れを取り戻したい」「掃除をして気分をリセットしたい」など、普段はやらないことに取り組む意志を見せると真剣さも伝わるでしょう。
やることややりたいことを伝えると、休みたい気持ちへの理解を得やすなります。く
学校を休んだときの過ごし方3選
この章では、学校を休んだときの過ごし方について解説します。
前提:休んだ自分を責めない
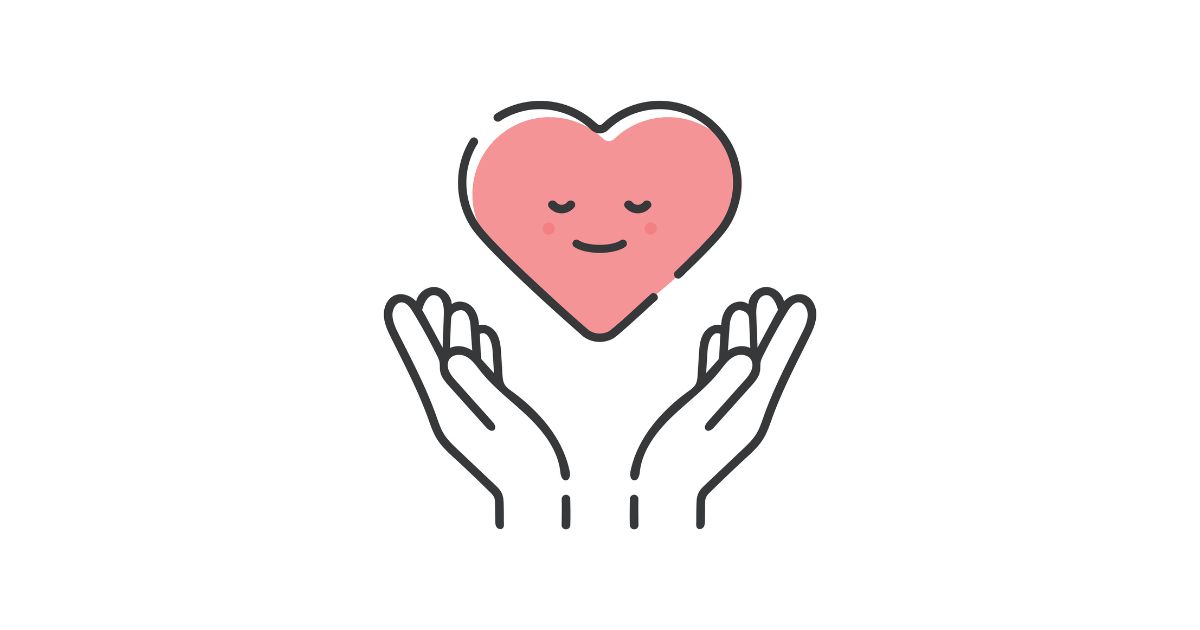
学校を休むと、自分を責めることがあるかもしれません。
例えば、「どんなことがあっても学校には行かなきゃ」などの思いが強すぎると、かえって心も身体も疲れ切るでしょう。ちょっとでもそれを守れなかったときに、「自分はダメだ」と感じて、罪悪感が生まれることもあるかもしれません。
「今日はうまくいかない日もある」「調子がいい日も、悪い日もある」「たまには休んでも大丈夫」と、少し肩の力を抜いて考えてみましょう。
無理をせず、自然体で過ごすことが、長く勉強や登校を続けるコツです。
罪悪感を感じたときは、「○○すべき」「○○してはいけない」という考えから、「こんな日もあるよね」と受け入れる思考に切り替えてみてください。
過ごし方①ゆっくり休む
学校を休んだ日は、まずは心と身体をしっかり休めましょう。
無理に何かをしようとせず、ゆったりとした時間を過ごすと、気持ちの疲れや身体のだるさが少しずつ和らいでいきます。
例えば、ぐっすり寝たり、ぼーっとする時間を作ってみてもいいでしょう。何もしない時間が、逆に気持ちを軽くしてくれることもあります。
疲れがたまっているときは、しっかり充電するのも立派な過ごし方です。
過ごし方②好きなことをして過ごす

学校を休んだ日は、自分が楽しいと感じることに時間を使ってみましょう。
心が疲れているときこそ、自分が楽しいと感じることに集中すると気持ちを前向きに整えるきっかけになります。
例えば、気になっていた本を読んだり、趣味にじっくり取り組んだりするなど、落ち着くと思えるものを選ぶのがポイントです。無理に有意義に過ごそうとせず、楽しいと感じる時間を意識的に作ってみましょう。
好きなことをする時間は、心を整えるひとつの方法です。リラックスしながら、自分の感情に素直に向き合ってみましょう。
過ごし方③できる範囲で勉強する
学校を休んだ日でも、ほんの少しだけでも勉強に取り組んでおくと安心です。
例えば、10分だけ教科書を読んだり、簡単な問題を1ページ解いてみたり、「ちょっとだけやる」くらいの気持ちで大丈夫です。
休んだ1日を完全にオフにするよりも、少しでも机に向かう時間を作ると「明日からまた頑張ろう」という気持ちになりやすくなります。
少しでもやれたことがあると、それだけで気持ちが前向きになります。
ズル休みが続きそうなときにチェックしたい2つのこと
この章では、ズル休みが続きそうなときにチェックしておきたいことを解説します。
チェック①「また休みたい」と思う頻度が増えた

「もう1日だけ休みたいかも」と思う日が増えてきたら、少し立ち止まって自分の気持ちを見つめ直してみましょう。
たった1日のズル休みのつもりでも、今日も明日もと繰り返すと、気づかないうちに学校に行くハードルが高くなる場合があります。
特に、休んだことに少しでも「ホッとした」「楽だった」と感じた場合、その安心感から連続して休みたくなる傾向が出やすくなります。
「また休みたい」が習慣になる前に、その気持ちの背景を振り返ってみるといいでしょう。
チェック②学校を休みたい理由がうまく説明できない
ズル休みが続く背景には、はっきりとした理由がないまま、気づかないうちに学校に行くことへの抵抗感が大きくなっているケースがあります。
こうした状態は「不登校予備期」とも呼ばれ、一見普通に登校できているように見えても、心の中では少しずつ負担が蓄積している段階です。(参考:一般社団法人 不登校支援センター「不登校の6段階」)
例えば、以下のような状況が挙げられます。
- 登校前に気分が重くなる
- 部活や習い事を休みたがる
- 宿題をしなくなる
- 家で学校や友達へのネガティブな言葉が増える
明確な問題行動が見えにくいため、この段階は見過ごされやすいのが特徴です。
予備期が進むと、頭痛・腹痛・吐き気・不眠・起きられないなど、心因性の身体症状が表れる場合もあります。
理由が説明できないけど行けないという状態は、甘えやわがままではなく、目に見えにくい不調のサインであることを、まずは自分自身や周囲が理解するのが重要です。(参考:一般社団法人 不登校支援センター「不登校の6段階」)
学校を休みたがる子どもに親ができる3つの対応
この章では、学校を休みたがる子どもに親ができる対応について解説します。
対応①体調やメンタル不調のサインを見逃さない

子どもが「学校に行きたくない」と言い出したとき、心や身体が発している小さなサインに早めに気づくことが大切です。
登校できていたとしても、少しずつ疲れやストレスがたまり「そろそろ限界かも…」という前兆が行動に表れる場合があります。
前兆としてよく見られる行動の変化は、以下のとおりです。
- 登校前に「行きたくない」と渋る様子が見られる
- 頭痛や腹痛など、体の不調を繰り返し訴える
- 習い事や部活を頻繁に休むようになる
- 宿題や家庭学習を避ける・まったく手をつけない
- 学校や先生、友達に対する否定的な発言が増える
こうした変化は、子ども自身も理由をうまく説明できない場合が多く、親から見ても「なんとなく様子がおかしい」と感じる程度かもしれません。
無理に理由を問い詰めず、今のままでも大丈夫と安心させる対応が、子どもが自分自身を受け入れるきっかけになります。(参考:特定非営利活動法人schoot「子どもの登校で悩んだら開くリーフレット」)
対応②その都度休ませる
子どもが「学校を休みたい」と伝えてきたときは、まず気持ちを受け止めて、一度しっかりと休ませることが大切です。
この段階は、不登校の前兆期と呼ばれる時期で、子どもがときどき学校を休み始めるような状態です。一見すると、気まぐれや怠けに見えるかもしれませんが、実は心身のエネルギーが減っているサインの場合もあります。
無理に登校を促すよりも、その都度しっかり休むことで、子ども自身が心と身体を整える時間を持てるようになります。
「今日は休みたい」と伝えられたときは、子どもの中で何かがサインとして表れている証拠です。その声に静かに寄り添い、安心できる時間を与えてあげましょう。(参考:特定非営利活動法人schoot「子どもの登校で悩んだら開くリーフレット」)
対応③「頑張って行かせる」が逆効果になる場合もあると理解しておく
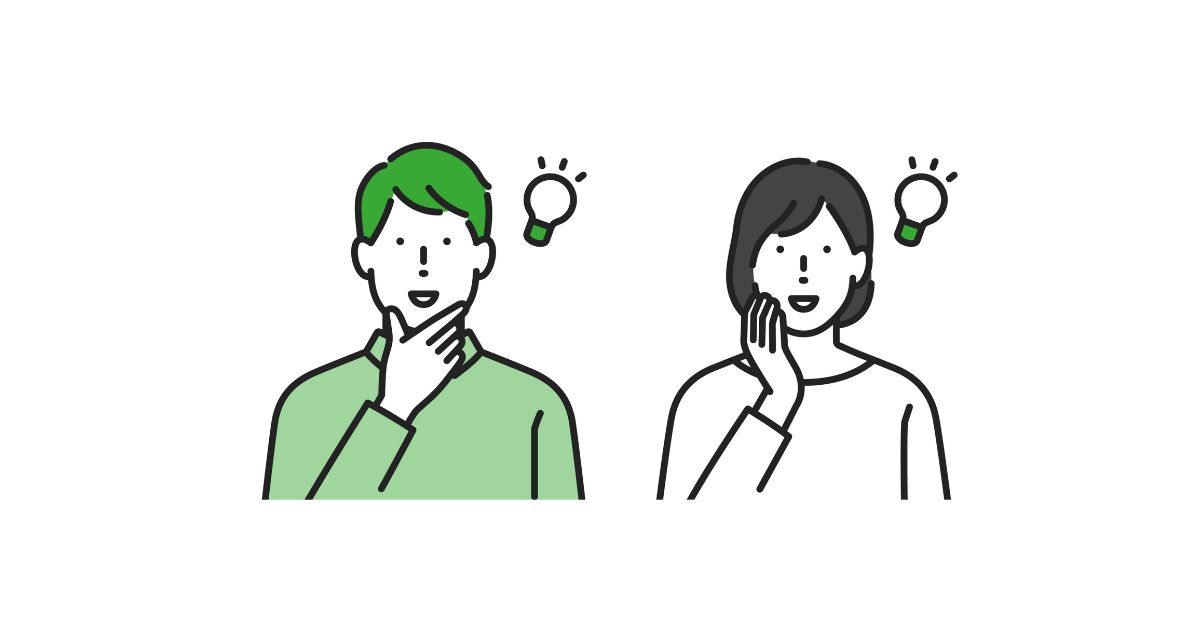
子どもを励まそうとして「とにかく学校へ行こう」と促すのは、かえって逆効果になる場合もあります。
学校に行けなくなり始めた初期の段階では、子どもは心身のエネルギーがかなり落ちている状態です。登校するのがプレッシャーとなり、無理に行かせようとするとかえって状態が悪化する可能性があります。
この時期に最優先すべきは、体力と気力を回復させるための休養期間をしっかり確保することです。
例えば「しばらくは学校のことを気にしなくて大丈夫だよ」と本人に伝えると、安心して過ごせる環境が整います。
登校再開を急ぐよりも、まずは子どもが安心できる場所があると感じられるのが、回復のスタートになるでしょう。(参考:特定非営利活動法人schoot「子どもの登校で悩んだら開くリーフレット」)
子どもの休みが長引きそうなときに親ができる3つの対応
この章では、子どもの休みが長引きそうなときに親ができる対応について解説します。
対応①平日もなるべく起床・就寝時間を一定に保つ
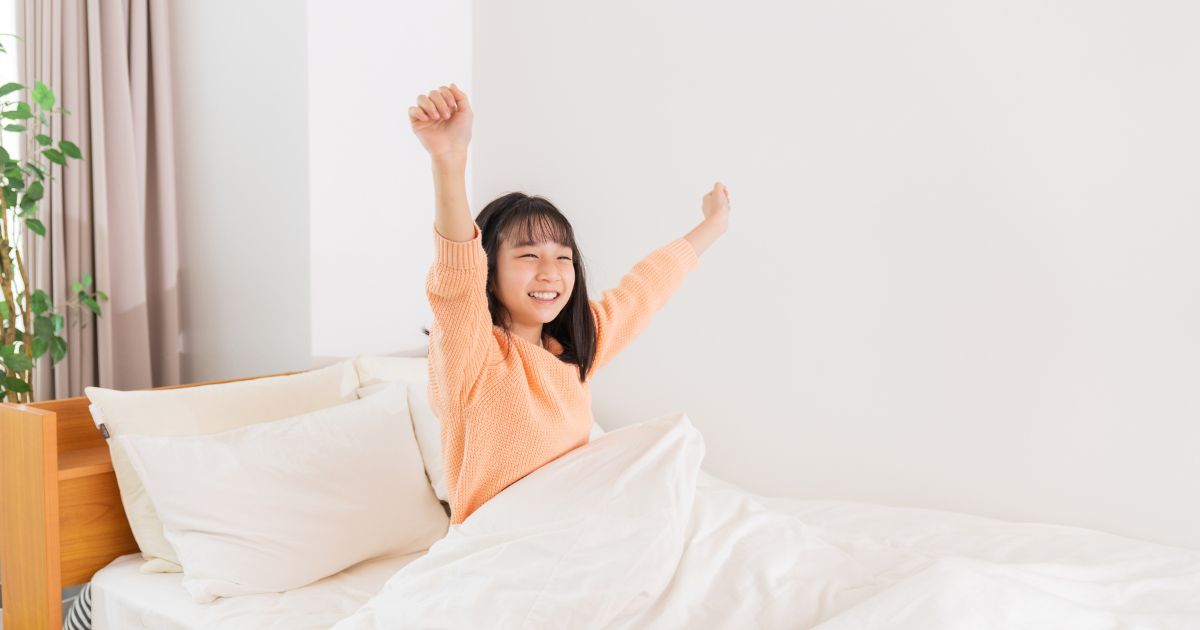
子どもの休みが長引きそうなときには、生活リズムの維持が重要です。
学校がない日でもできるだけ同じ時間に寝起きする習慣を続けることで、心身の安定につながるためです。
文部科学省の調査によると「平日と休日の起床・就寝時間に差があると、体内時計が乱れ、翌週に時差ぼけのような状態になる」と指摘されています。(参考:文部科学省「中高生を中心とした子供の生活習慣が心身へ与える影響等に関する検討委員会(第4回)」)
集中力や記憶力の低下だけでなく、不調や不登校につながるおそれもあるとされています。
子どもが「休みたい」と言うときでも、朝の起床や夜の就寝はなるべくいつもどおりの時間にしておくと、体内リズムの乱れを防ぎ、次の登校へのハードルを下げることができます。
対応②子どもの気持ちを受け止め、話しやすい環境を整える
子どもの気持ちを理解しようとする姿勢は、休みが長引く時期にとても大切です。
特に以下のような接し方が、子どもにとって安心感につながります。
接し方①日常会話や雑談を意識して取り入れる
趣味の話やテレビ、ゲーム、何気ない話題での会話が「今のままの自分を受け入れてもらっている」と感じさせます。
将来や勉強の話に無理に結びつけるのは避けましょう。
接し方②何かしてくれたときは「ありがとう」と感謝する
家事を手伝ってくれた時など、感謝を伝えることで「自分の存在が家族に必要とされている」と実感できます。
接し方③普段通りに接する
「特別扱いされず、自然に声をかけてもらえたことがうれしかった」という不登校経験者の声もあります。
接し方④子どもの話は途中で遮らず、最後まで聞く
内容に矛盾があっても否定せず「そう思っているんだね」と気持ちを受け止めましょう。
親への不満やつらい気持ちも、まずは耳を傾けて受け入れるのが大切です。
接し方⑤本人の過ごし方を尊重する
好きなことをして過ごす時間は、自分を取り戻すために必要な時間です。
関わり方を通して、少しずつ自分自身の状態に向き合っていけるようになるでしょう。(参考:特定非営利活動法人schoot「子どもの登校で悩んだら開くリーフレット」)
対応③学校や支援機関と連携し、親だけで抱え込まない

子どもが長く学校を休みそうなとき、親だけで対応を続けるのはとても大変です。学校や専門機関に早めに相談することで、心の負担が軽くなります。
以下は、主な相談先とその役割です。
相談先①スクールカウンセラー(SC)
子ども本人だけでなく、保護者の不安や悩みにも対応できる心の専門家です。
利用したい場合は、話しやすい先生に「相談してみたい」と伝えるとスムーズです。
相談先②スクールソーシャルワーカー(SSW)
家庭の状況や子どもの生活全体に配慮し、地域の施設・支援サービスとつなぐ役割を担います。
学校・保護者・地域との橋渡し役として幅広く支援に関わります。
相談先③教育相談員
スクールソーシャルワーカー(SSW)スクールソーシャルワーカー(SSW)と連携しながら、学校に行きづらくなっている子どもの把握や家庭訪問、相談支援などを行います。
利用希望の際は、担任や学校の窓口へ伝えるといいでしょう。
相談先④養護教諭(保健室の先生)
子どもが保健室を頻繁に利用している場合、保護者とのちょっとした会話の中から、必要な支援につなげてくれる場合があります。
お迎えの際など、気になることを気軽に相談するのもひとつの方法です。
「誰に何を相談すればいいのか分からない」と感じたときこそ、まずは話しやすい先生に声をかけてみてください。
親が相談する姿勢を見せるのは、子どもにとっても大きな安心材料になるでしょう。(参考:特定非営利活動法人schoot「子どもの登校で悩んだら開くリーフレット」)
学校をズル休みしたい気持ちに関するよくある質問2選
この章では、学校をズル休みしたい気持ちに関するよくある質問について紹介します。
Q1.学校に行かないと将来困りますか?

必ずしも学校に行かない=将来が閉ざされるというわけではありません。
文部科学省の調査によると、不登校経験者の進学率や中退率などは、年々改善しています。
不登校経験者の進路状況は、以下のとおりです。
高校進学率
- 1993年:約65.3%
- 2018年:約85.1%
高校中退率
- 1993年:約37.9%
- 2018年:約14.0%
大学・短大・高専への進学率
- 1993年:約8.5%
- 2018年:約22.8%
専門学校・各種学校への進学率
- 1993年:約8.0%
- 2018年:約14.9%
過去と比べて不登校を経験した生徒の進路の幅は、社会や教育現場の変化があります。学校に行かなかったからこそ、自分のペースで進路を考え直し、自分に合った道を見つけられる場合もあるでしょう。
焦らず、自分のペースで進んでいけば、未来の可能性は十分に広がっていきます。
Q2.保健室登校・別室登校ってどんな人が使いますか?
教室に入るのがつらい子どもが、安心して過ごせる場所として利用します。
人間関係や環境のストレスで教室に居づらいと感じている子どもが「それでも学校には来たい」と思ったときの選択肢として使われるのが保健室や別室です。
保健室登校・別室登校利用するのは以下のような場合が挙げられます。
- 教室の人間関係に悩みがある
- 多人数の空間が不安
- 登校はできても教室に入るのが難しい
また、保健室登校のメリットは以下のとおりです。
- 養護教諭が常駐していて、一人きりにならずに安心できる
- 体調不良の生徒も出入りするため、自分だけが特別ではないと思いやすい
- 滞在に時間制限があることで、次のステップへの意識も生まれる
無理に教室に戻すのではなく、段階的に学校にいることに慣れていくサポートとして役立つ方法です。(参考:青木真理「別室登校について 効果的な保健室登校指導についての一考察」)
まとめ〜ズル休みは「甘え」ではない。大切なのは気持ちに向き合うこと〜

ズル休みと聞くとネガティブな印象を抱きがちですが、休みたくなるほどの気持ちには、必ず何かしらの理由が隠れています。
まずは「休むこと自体は悪いことではない」と受け止めるのが重要です。
むしろ、その気持ちに気づき、向き合うことこそが、自分を大切にするという前向きな行動です。
ズル休みは、サボりではなく、サインです。サインに気づいたら、自分の心と丁寧に向き合ってみましょう。
Q&A よくある質問