不登校の子どもに親がかけるべき言葉は正論?同情? 体験談を紹介

不登校のお子さんのための完全個別指導塾・キズキ共育塾の講師、青柳翔太と申します。
不登校の生徒さんは、「親との距離感」に悩んでいることが少なくありません。
このコラムでは、不登校の生徒さんを多数見てきた個性的な塾の視点から、「不登校の子どもへの親としての接し方」についてお伝えします。
共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの
アドバイス
不登校のお子さんを持つ親御さんなら、「子どもにどう対応すればいいんだろうか」と誰もが悩むはずです。
本コラムでも指摘しているとおり、親の思いを一方的にぶつけると、子どもは傷つきます。たとえ親御さんの言っていることが正論であってもです。
子どもの視点に合わせた、寄り添った対応が大切です。
私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
私の母も、私の兄の不登校で悩んでいました
前置きが少し長くなるのですが、私には4歳年上の兄がいます。
兄は高校時代に不登校となり、その後10年以上社会に出ていません。
私は中学生のころから、兄のことで悩む母の姿を見て育ちました。
母は、次のように、兄のことで長年自分を責めながら生きてきました。
- なぜわが子のことをわかってやれなかったのだろう
- 私は本当にバカ親だ
そして、ストレスによる慢性的な自律神経失調症になりました。
そんな家庭環境で育った私は、子どもやきょうだいが不登校になると、本人だけでなく家族全体が疲弊するということを、身をもって学びました。
私の母のような人の苦労を軽減できればと思い記事を執筆しました。
お子さんの不登校に悩むあなたの悩みを、少しでも軽減できれば幸いです。
不登校の我が子に、親はどう接すればいいのか?
さて、本題に入ります。
不登校になったお子さんに対して、親としてはどのように接すればいいのでしょうか?
親として、次のような「正論」の説教をしなければならないのでしょうか?
- 現実を見ろ
- 将来どうするつもりだ?
- みんながんばっているんだ
または「正論」を控えて、次のようにお子さんの境遇をいたわり、同情の念を向けるのがいいのでしょうか?
- つらくない?
- 無理してない?
- 大丈夫?
正論は無意味なことが多い
不登校(のお子さん)について、「甘えだ!」「このまま放置してはますます自立できなくなる!」と思った親御さんは、お子さんのことをつい正論で叱ることもあると思います。
しかし親からの正論を聞いて、お子さんは心を改め学校に通い出すでしょうか?
残念ながら、私の見てきた限り、そうはならないことが多いです。
むしろお子さんをさらなる引きこもりにおちいらせる可能性があります。
生徒さんの事例から、どういうことかお伝えします。
朝起きられなくて学校に行きづらくなったAさん
キズキ共育塾のある生徒さん(以下、Aさん)は朝起きるのが苦手な、現在不登校の高校1年生。
Aさんの所属する中高一貫校は、規律に厳しい学校です。
朝起きられず、遅刻を繰り返していたAさんは、生活指導を度々受けていました。
しかしどうしても朝起きられず、遅刻が治らないAさんは学校にいづらくなり、高校1年生の2学期から不登校になりました。
窮屈(きゅうくつ)な学校を逃れ不登校に。しかし窮屈は家にまで

学校での教師のお説教を逃れたAさんを待ち受けていたのは、親(この場合は母親)からの“正論”攻めでした。
- 遅刻してでも学校に行くしかないじゃない
- いじめられているわけでもないのに不登校なんて…そんなの甘えよ
そうした正論を受けて、Aさんは、「自分が悪いと思っているから言い返せない。でもどうしようもない」と思い詰め、母親からの接触をさけるようになりました。
母親と顔を合わせないように、夜活動して昼まで寝る、昼夜逆転の生活になったのです。
こうしてAさんは不登校になる前よりも朝に起きられなくなり、学校(や社会)への復帰はより一層難しくなりました。
この時点では不可能と言っていいでしょう。
しかしAさんも、自分の状況を肯定的に思ってはいませんでした。
「このままでは高校中退になる。その後のことを真剣に考えないと、将来が不安だ」と考えたAさんは、(高校中退と高卒認定の取得も視野に入れた上で)大学受験を決意。キズキ共育塾に入塾しました。
母親も、不登校については相変わらず正論で考えているものの、Aさんが将来を前向きに考えたことには理解を示し、入塾に賛成してくれました。
家で落ち着いて勉強できないため、成績が伸びない
Aさんは、いわゆる「地頭(じあたま)がよい」タイプでしたし、中学受験を経験していたこともあって勉強にも慣れていました。
担当となった私は、成績はすぐに伸びるだろうと思いました。
しかしAさんは授業で同じ間違いを繰り返し、実力がつきません。
宿題を全くやってこないため、知識が定着しないのです。
そこで私は、なぜ宿題をやってこないのか、家ではどのように過ごしているのかを訊きました。
Aさんは、次のように答えました。
「家にいると、親が不登校について正論をうるさく言ってくるんです。それ以外のときもいつもピリピリしてるし。だから起きている時間は家にはいなくて、一日中外をさまよっています。勉強できる場所も探してはいるんですけどまだ見つけられなくて…」
つまりAさんは、家の中では落ち着いて勉強できないようになっていたのです。
Aさんは、その後キズキ共育塾で自習するようになり、勉強場所という問題は「いったん」解決となりました。
しかし「根本的な」解決には、親子関係の修復が必要でしょう。
正論に意味がない理由
Aさんの事例を見て、どう思われたでしょうか?
親から正論をぶつけられると、冷静に受け止めることができない、自分のことを責める、家庭に居場所がないと感じるお子さんもいるということです。
そのようなお子さんは、正論を言われると、親と距離を置こうとします。
また親の目を過剰に気にしだすと、イキイキと活動できなくなります。
そうした状態では、(受験勉強に限らず)将来のために生産的なことをしようとしても、計画は頓挫しがちです。
性格や状況、それまでの親子関係などから、不登校について「親からの正論の説教」が効果的な場合もあるでしょう。
しかし、(あくまで私の見聞きした範囲ですが、)そのケースは少ないです。
親御さんには、正論を言う前にいったん思いとどまってほしいと思います。
では同情すればいいのか
以上は、不登校のお子さんに正論をぶつけることの弊害でした。
では逆に、不登校のお子さんに対して、親は同情すればいいのでしょうか?腫れ物に触れるように接するのがいいのでしょうか?
残念ながら、こちらの振る舞いもお子さんの活力を奪っている可能性があります。
勉強についていけなくて不登校になったB君
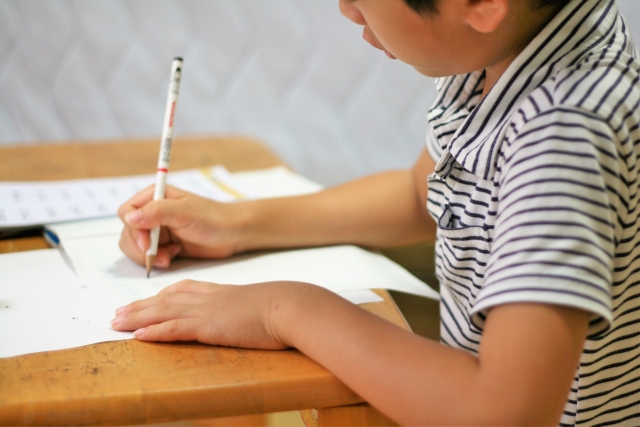
大学受験を目指すキズキ共育塾のある生徒さん(以下、B君)には、中学不登校の経験があります。
B君が不登校になった経緯、そして不登校になってからの生活については、以下のとおりです。
父親の厳しい方針のもと、中学受験に合格。しかし…
B君の父親は勉強に対して厳しい方で、B君を小学生のころから某有名塾に通わせて、算数と英語を勉強させました。
B君は、算数は好きになって積極的に学び、成績が伸びました。
ですが、英語については勉強する意義を見出だせず、身が入りませんでした。
そのため英語では父親を満足させる点数を取れず、よく怒られていたそうです。
そんな生活を振り返ったB君は、次のように言っています。
「意義を見出せない勉強をガシガシさせられることに違和感を覚えていました。趣味に費やす時間もなかったので」。
そしてB君は、父親の意向で中学受験をしました。
受験勉強を始めた時期は周りの人よりも遅かったのですが、何とか合格しました。
しかし中学でB君を待っていたのは、進行の早い授業と課題の山。
この時期のことについては、B君は、次のように言っています。
「周りは普通についていっているのに、僕は全然ついていけなくて、それがものすごい劣等感でした」。
結局B君は、その劣等感をきっかけとして中学1年の2学期から不登校になりました。
父親はB君のことを理解せず、B君について失望したそぶりを見せるようになったそうです。
母親は同情してくれたが、次第に煩わしくなり…

一方、B君の母親は、夫(つまりB君の父親)の厳しい教育方針にあまり共感していませんでした。
そのためB君が不登校になってからも、B君を叱らずに心配し、いたわりました。
父親に失望されたB君にとって、そんな母親の存在はありがたいものでした。
しかし不登校で家にずっといるうちに、B君は母親が自分に向ける視線が気になるようになりました。
さげすむような視線は決して向けない代わりに、傷つけないように気を遣っている同情的になりすぎているのが伝わったそうです。
B君は、次のように言います。
「自分と話すとき、母がオロオロしているのを見て申しわけなくなりました」
「自分のせいで家族の雰囲気が暗くなった気がしたのも、申しわけなかったです」
また、不登校になってから数か月が経過しても学校に復帰できないB君はカウンセリングに通い、カウンセラーから「今は好きなことをやった方がいい。」と言われました。
母親もその意見に同意し、B君は小さいころに習っていたピアノを再び弾き始めました。
しかし長続きしませんでした。
それは、母親の過剰な同情・心配が原因でした。
「僕が楽しくやっているときでさえ、母は心配して声をかけてくるんです」
「だんだん母と話すのにも疲れてきたのですが、気を遣ってくれているのがわかるから強く退けられないんですよね。」
その後は気晴らしもできなくなり、一日中家にこもりっきりで特に何もしない無気力な日々が続いたそうです。
不登校の「次」(=大学進学とそのための受験勉強)へ気持ちを切り替え具体的に行動するためには、それから数年間が必要となりました。
なぜ同情もダメなのか
B君の母親の心遣いは、B君にどう影響したでしょうか?
B君は母親の態度を察知し、疲弊しています。同情する側(親)は相手の心に寄り添っているつもりでも、される側(お子さん)は「かわいそうな奴だと決めつけられている」ように感じ、自尊心を傷つけられるのです。
それが原因で、親子間には不信感が漂い始めます。
このようなプロセスによって、お子さんに同情しすぎて接すると、正論をぶつけたときと同じように、親子ともども疲弊してしまうことがあるのです。
参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。
このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。
このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。
公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら
- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら
- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)
私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。
「安心できる家庭」が重要。そのためには、親御さんが「自身の生活」を大切にすること

いかがだったでしょうか?不登校のお子さんに正論を言うのも同情を向けるのも、親子関係を悪くする可能性を秘めています。
その結果、不登校のお子さんにとって家庭は居心地の悪い場所になり、前向きに努力しようと決意することが難しくなります。
このような事態を避けるためには、お子さんを萎縮させず、お子さんが家庭で安心感を抱けることができるように心がけるのがいいと思います。
では親御さんは、何をすればいいのでしょうか?
それは「自分自身の生活を大切にすること」とお考えください。
お子さんが不登校だからと言って、そのことばかりを過剰に気にする必要はありません。
親御さんは親御さんで、旅行に行ったり、買い物をしたり、趣味の活動を行ったりなど、日常を楽しんでよいのです。
お子さんが不登校になった際、お子さん本人にとって重要なことは、心を休めることです。
家族がピリピリしていると、心を休めるどころではなくなります。
逆に、家族が楽しそうにしていれば、お子さんの心も気楽になり、活力が沸いてくることが多いのです。
そのため、親であるあなた自身がストレスをため込むことのないよう、日々の生活に楽しみを見出してほしいのです。
それが、ひいてはお子さんのためにつながります。
いつかお子さんが不登校からの「次」に進もうと思ったとき、お子さんだけでは何をすればいいのかわからないかもしれません。
そのときこそ、親の力が必要になるのです。
そのときに親が追い詰められていたり親子関係が悪かったりすると、お子さんは親を頼らなければ達成できないような選択肢を切り捨ててしまうかもしれません。
そうならないよう、親は親で楽しく過ごし、親子関係を適切な距離感に保ってほしいと思います。
私の母もかつてそう過ごしていたら、その後が違っていたのかなと、振り返って思います。
ただ、「お子さんのこと」は、親だけ(家庭だけ)で対応する必要はありません。不登校に詳しい専門家や相談先を、ぜひ積極的に利用してください。
私たちキズキ共育塾はその1つであると思います。
保護者さまだけでのご相談もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
/Q&Aよくある質問









