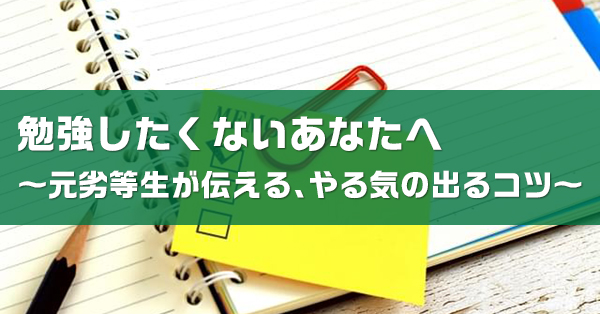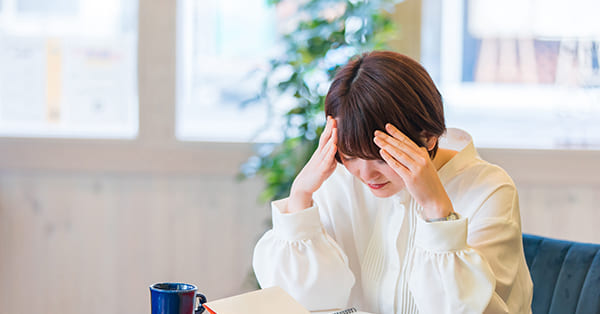宿題がめんどくさいと言う子どもへの対処法 NG対応を解説
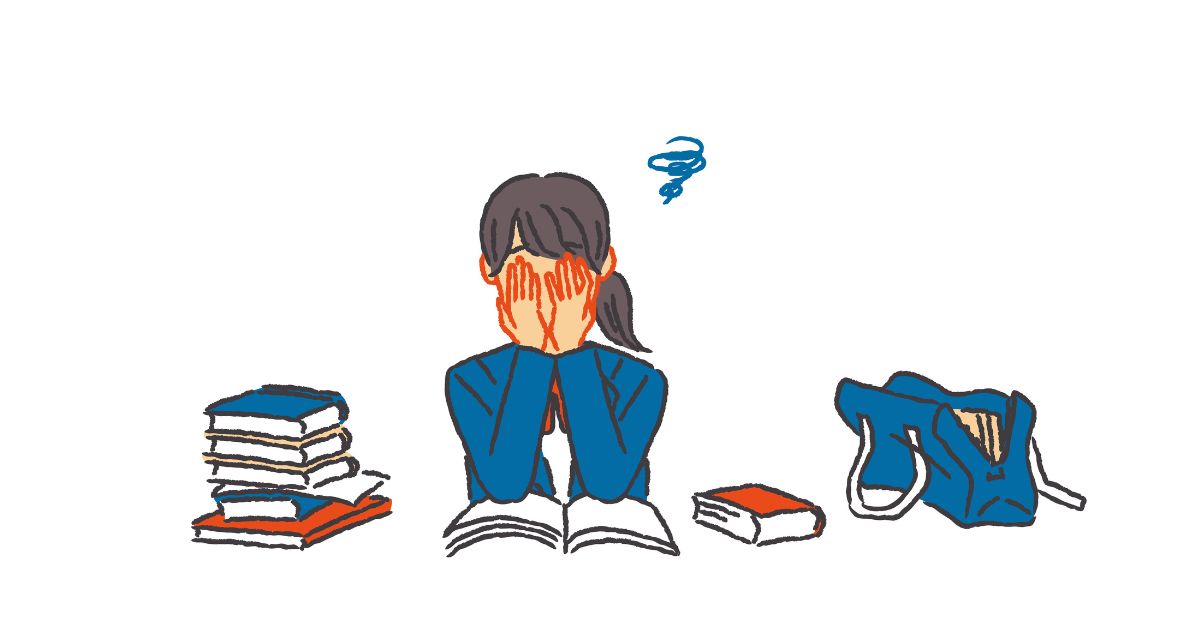
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートするキズキ共育塾です。
宿題をめんどくさいと感じる子どもは珍しくありません。しかし、そのように思う理由の背景には学習環境の問題などが潜んでいることもあります。
このコラムでは、宿題をめんどくさいと感じる理由や効果的な対処法について解説します。
宿題を先延ばしにしがちな子どもをサポートしたい親御さんは、ぜひ参考にしてください。
私たちキズキ共育塾は、宿題をめんどくさいと感じやすい子どものいる人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
宿題をめんどくさいと思う7つの理由
宿題をめんどくさいと思う理由は、お子さんによってさまざまです。
この章では、子どもが宿題をめんどくさいと思う理由について解説します。
理由①宿題の量が多すぎる
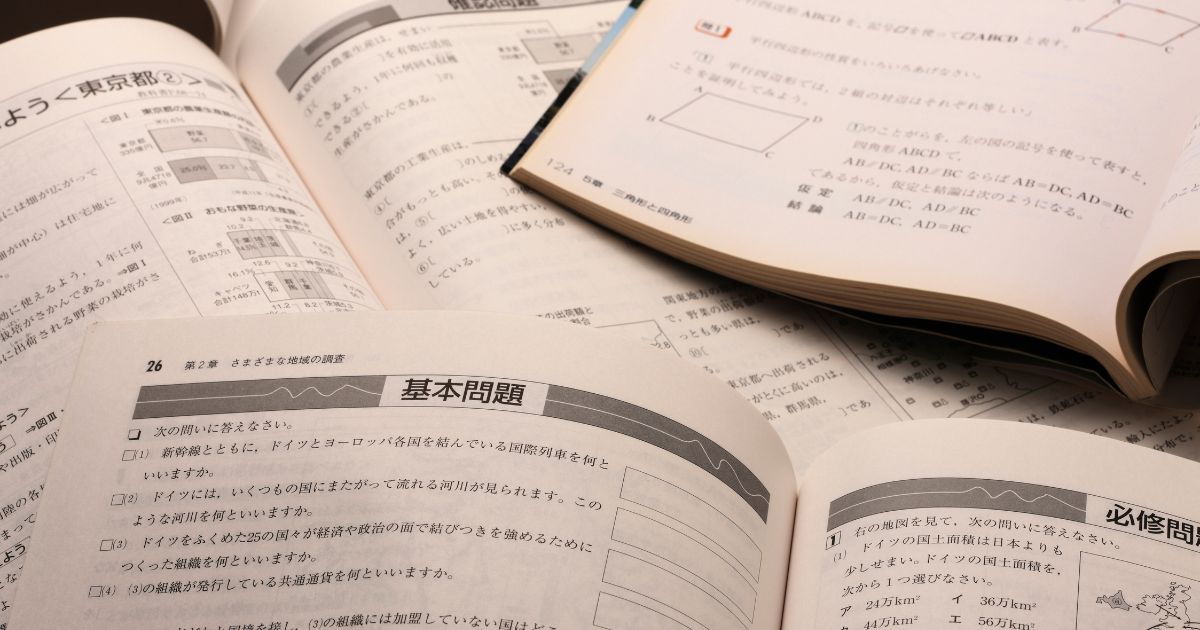
当たり前のことですが、宿題が多すぎると子どもはめんどくさいと感じがちです。
特に複数の教科で宿題を出されると、宿題を整理することから始めなくてはならず、手を付けるのが遅くなりやすいでしょう。
ただし、その宿題を多いと感じるかどうかは子どもによります。苦手な教科の宿題の場合、それほどの量でなくても、片付けるのが大変だと思う子どももいます。
理由②そもそも勉強が嫌い
勉強そのものが嫌いな子どもは、宿題もめんどくさいと感じやすいです。
子どもが勉強嫌いになる原因として、以下が考えられます。
- 教科数が増えた
- 先生が嫌い
- 勉強方法がわからない
- テストで点が取れない
- 周りと比べられる
- 勉強を強制させられる
原因はひとつとは限らず、いくつかの原因が絡みあうことで、勉強への嫌悪感になっている場合もあります。
理由③学校の授業がわからない

宿題は基本的に、学校の授業の復習・補習のために出されます。
したがって、授業を理解しきれていない状態で宿題に着手しても、と解き方がわからず、めんどくさいと感じやすくなります。
また、習った直後は理解できても、後になると記憶が薄れてわからなくなることもあります。思い出すのに時間と手間がかかるため、宿題をめんどくさいと思いやすいのです。
理由④部活動や習い事で疲れている
部活動や習い事で疲れていて宿題ができないという子どももいます。
- 部活動が忙しくて帰宅が遅い
- 部活動をやって帰るとすぐに眠くなる
- 大会やコンクールのことで頭がいっぱいだ
以上のような状況では、宿題をする気になれないのも無理はないでしょう。
体力的・時間的に宿題ができないのであれば、顧問の先生などに相談して、両立の方法を考えることも必要です。
理由⑤宿題をする意味がわからない

宿題をする意味がわからないことが、めんどくさいという感情につながっている場合もあります。
特に、勉強に意味を見出せずに悩んでいる子どもに多いです。
- 古文単語を覚えて、何の意味があるんだろう…
- サイン・コサイン・タンジェントとか言ってるけど、将来何の役に立つの?
- 英単語を50個覚えたって、覚えた直後に受験に受かるわけじゃないし…
成績が優秀な生徒の場合、宿題が簡単すぎてやる意味がないと思うこともあります。
理由⑥宿題に集中できる環境がない
集中できる環境がないせいで、宿題をめんどくさいと思う子どももいます。
- 自分の部屋や勉強机がない
- 家族やきょうだいがうるさい
- 机の上や部屋の中が散らかっている
本人が意欲を見せている場合、集中できる環境さえ用意すれば解決できる可能性が高いです。
理由⑦宿題以外にやりたいことがある

宿題よりも優先度の高いことがあるせいで、先延ばしにしている子どももいます。
- ゲーム・音楽・スポーツなどの趣味
- 恋人や親友といる時間
- 動画を見たりマンガを読んだりする楽しい時間
時間に区切りを付けずに、のめり込みがちな子どもに多い理由です。
補足:発達障害の特性が影響していることもあります
文字の読み書きや計算など、特定の作業を伴う宿題を極端に嫌がる場合は、発達障害の特性が影響している可能性があります。
発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。
発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)
ADHDであれば誤字や計算ミスが多い、LD/SLDであれば文字の読み書きに時間がかかるなど、特性が影響して宿題をめんどくさいと感じていることもあるということです。
発達障害が疑われる場合、まずは医師の診断を受ける必要があります。
発達障害と宿題の関係については、以下のコラムで解説しています。ぜひ参考にしてください。
参考記事:キズキ家学「発達障害で宿題に時間がかかるのはなぜ?理由・改善方法・相談先を紹介」
宿題がめんどくさい子どもに効果的な対処法8選
この章では、宿題がめんどくさい子どもに効果的な対処法について解説します。
対処法①早めに片付けるメリットを教える

先延ばし癖のある子どもには、宿題を早めに片付けるメリットを教えることが効果的です。
宿題は習った範囲が問題になることが多いため、授業の記憶がはっきりと残っているうちに着手すると、それほど時間をかけずに終わらせることができます。
また、夜遅くに眠気と闘いながら宿題をするのはつらいものです。一方、目が覚めているうちに宿題をすると頭が働きやすいので、それほど苦にはなりません。
つまり、宿題を早めに片付けることにはメリットがあるのです。
しかし、親御さんの中にはこうしたメリットを説明せずに、頭ごなしに「早く宿題を片付けなさい」と言う人もいるのではないでしょうか?
説明なしに命令されると、反発したくなるという子どももいます。そのため、まずは宿題を早めに片付けるメリットを教えてから諭すようにしましょう。
対処法②出されている宿題の整理を手伝う
子どもの学年が低い場合は、出されている宿題の整理を手伝うことが有効です。
特に、夏休みなどの長期休暇には、さまざまな教科の宿題が出されます。
なかには植物の観察記録など、休暇が始まったときから着手していないとまずい宿題もありますので、親が整理を手伝ってあげましょう。
それでなくても整理整頓が苦手なお子さんの場合、出されている宿題を把握できていないせいで、なんとなく宿題をたくさん出されている気がしているだけということもあります。
こうした状況を改善するだけで宿題がめんどくさいという感覚が無くなることもあるため、ぜひ試してみてください。
対処法③勉強に対する苦手意識を軽減する
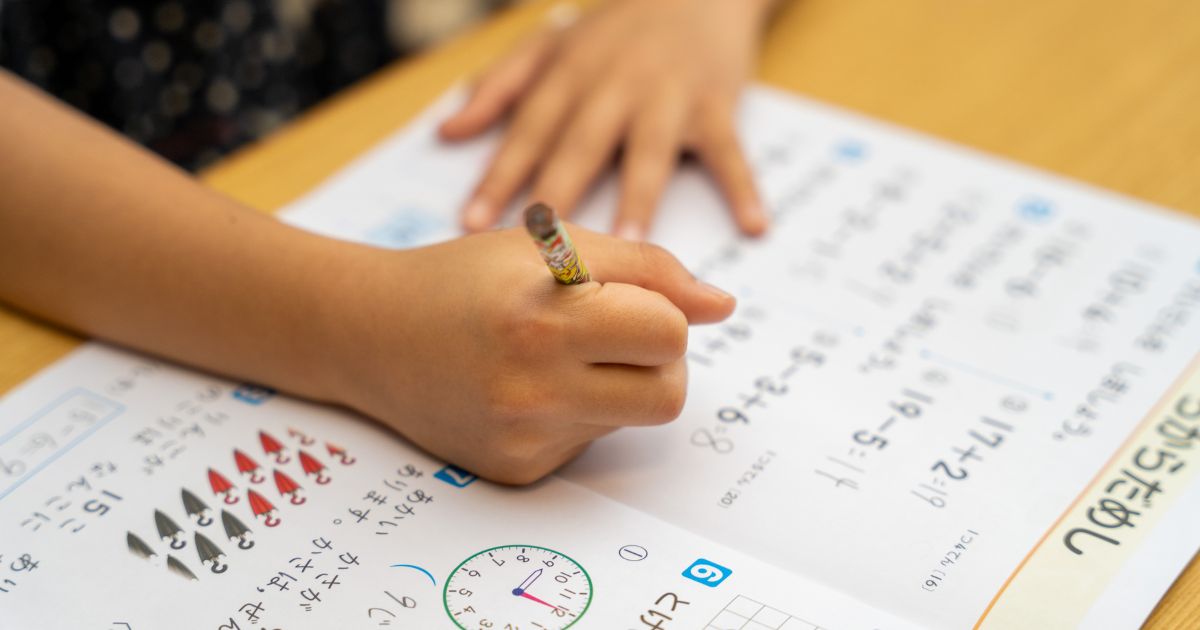
勉強が好きになるうちに、自然と宿題がめんどくさいと思わないようになることもあります。
勉強への苦手意識を軽減するには、以下のような対策が効果的です。
- 勉強が得意な友達と一緒に宿題をやる
- 得意科目を伸ばすことで勉強のコツを掴む
- 予備校の短期集中コースなどで得意な教科を増やす
わからないからめんどくさいだけで、スラスラ解けるようになったら積極的に宿題をやる子どもは多いものです。
「勉強がわかる!」という感覚を掴むための方法を探してみましょう。
対処法④気軽に勉強を見てくれる学習塾に入る
宿題へのハードルを下げるという意味では、気軽に勉強を見てくれる学習塾に通うというのも良い解決策です。
学習塾というと、学校と同じように集団授業をするイメージを持つかもしれませんが、なかには個別で宿題を見てくれたり、学校生活の相談に乗ったりと、幅広いサポートをしてくれるところもあります。
とりわけ、完全個別指導を行っている学習塾ほど、子どもに合わせた柔軟な学習支援が得られます。
私たちキズキ共育塾でも、完全個別指導をしています。興味のある人は、ぜひお気軽にご相談ください。
対処法⑤宿題をしたことを褒めるようにする

宿題をやるのは当然という態度では、子どものモチベーションを上げるのは難しいでしょう。
宿題をしたことを褒めることも忘れないようにしてみてください。
- こんなにたくさん宿題やったんだ、偉いね!
- 宿題をこんなに早くやれるなんてすごい!
- 前よりも問題解くのが早くなったね!
親が褒めてくれるから一生懸命にやろうと思える子どももいます。声掛けしだいで子どもの学習意欲が変わることもあるということを意識しましょう。
対処法⑥家族・きょうだいなどと一緒にやる
ひとりで宿題をしていると退屈しがちという子どもは、家族・きょうだいなどに見てもらうことがオススメです。
わからない問題があったときに「ここがわからない!」と口に出せるだけでも、気持ちに余裕が持てることがあります。
回答の手助けができなくても、一緒に考えてくれる相手がいるというだけで、心細さを感じずに宿題に取り組めるものです。
親が仕事や家事で忙しい場合は、同居している祖父母などに頼るのもよいでしょう。手の空いている家族がサポートしてあげてください。
対処法⑦机の上や部屋をきれいにする

机の上や部屋をきれいにすることで、宿題をする意欲が湧いてくることもあります。
特に、ゲームやマンガやタブレットなど、勉強に関係のないものが周囲にあると注意が散漫になりやすいです。
短時間でもいいので、宿題をする前に気が散るものが視界に入らないように片付けるなどして、学習環境を整えましょう。
対処法⑧お気にいりの文房具を揃える
宿題のハードルを下げるという点では、好きな文房具を身のまわりに揃えるのも効果的です。
- キャラクター付きのペン
- きれいなインクのマーカー
- おしゃれなデザインの筆箱
彩りを添えることで無味乾燥な宿題にも積極的に取り組めるようになります。子どもと外出したときに文具店に立ち寄るなどして、モチベーションの上がる物を探してみましょう。
補足:発達障害の場合は特性をカバーする道具が効果的
発達障害は脳の機能障害が原因とされています。そのため、宿題をめんどくさいと感じる理由が発達障害にある場合、本人の努力だけでは改善しづらいこともあります。
こうした発達障害の場合、特性をカバーできる道具を利用するのが有効です。
例えば、LD/SLDのある子どもなら、以下のような道具をオススメします。
リーディングルーラー(リーディングトラッカー)
色付けされた箇所を上から当てて、テキストの中の読みたい行に集中できるようにする定規
三角えんぴつ
イメージどおりに手指を動かせない書字表出障害のある子ども向けに握りやすく設計された鉛筆
ただし、どの道具が子どもに適しているかは特性によります。まずは発達障害の検査を受けて、特性を理解するところから始めましょう。
学習塾によっては、以上のような学習支援ツールを取り入れているところもあります。
そのため、子どもに発達障害の疑いがある場合、発達障害のある子どもを指導している学習塾に相談するのがオススメです。
LD/SLDのある子どもの学習塾については、以下のコラムで解説しています。ぜひ参考にしてください。
宿題がめんどくさい子どもに接するときの5つのNG対応
宿題がめんどくさい子どもへの対処法も大切ですが、それ以上に重要なのが子どもに接するときの態度です。
この章では、宿題がめんどくさい子どもに接するときのNG対応について解説します。
対応①早く宿題をやるようにと急かす

子どもが宿題をやらずにゲームをやったりしていると、「早く宿題をやりなさい!」と言いたくなる人もいるでしょう。
しかし、宿題をやるようにと急かすのは禁物です。
宿題は親に言われてからするものという認識が強まりますし、自分なりに予定を立てて片付けようとしていた子どもにとっては、自発的に行動する機会を奪われるからです。
とはいえ、宿題をやらない子どもが心配になるときもあると思います。そういうときは、以下のような比較的フラットな呼びかけがオススメです。
- 宿題はちゃんと進んでる?
- 今日は宿題をやらなくていいの?
- 何時になったら宿題を始める予定?
ただし、口うるさく何度も呼びかけることは避けましょう。
対応②子どもの人格を否定することを言う
子どもが言うことを聞かないからといって、人格を否定するようなことを言うのは厳禁です。
- 本当にだらしない子ね
- 宿題もやらないなんてありえない
- どうしてこんな簡単なこともできないの?
このようなことを言われると、学びのために課せられている宿題が嫌な気持ちを引き起こす源になり、いっそう宿題へのハードルが上がります。
宿題がめんどくさいどころか、忌避の対象になりかねません。そのため、子どもの人格と宿題を結びつけるようなことは言わないようにしましょう。
対応③子どもにイライラしている態度を示す

同様に、宿題をやらない子どもにイライラした態度を示すのもNGです。
親を怒らせないために宿題をやるようになると、勉強が息苦しいものになります。
まったく緊張感がないのも考えものかもしれませんが、恐怖で縛りつけるのも好ましくありません。
子どもが自発的に宿題へ向かうようにするためにも、態度に余裕を持って接することが大切なのです。
対応④きょうだいや他の家の子どもと比べる
あなたは無意識のうちに、自分の子どもをきょうだいや他の家の子どもと比べていませんか?
- 〇〇なら言われなくても宿題をやるのにね
- どうしてお兄ちゃんみたいに宿題をすぐやらないの?
- 〇〇くんは家に帰ったらすぐに宿題を片付けるって聞いたよ
以上のような言葉を投げかけると、子どもに劣等感を植えつける可能性があります。
自信や意欲の喪失につながりかねないため、決して言わないようにしましょう。
対応⑤宿題をやるのは当然だからと褒めない

宿題をやるのは当然というスタンスで子どもを褒めない親がいます。
しかし、子どものモチベーションを上げるためには、ときに褒めてあげることも大切です。
特に学年が低いほど、宿題をやる意義が希薄になりがちです。そんなときに親が褒めてくれるだけで、「もっと頑張ろう!」と思える子どももいます。
子どもが宿題完了の報告をしてきたときに良いリアクションを取れているかどうか、一度、振り返って考えてみましょう。
宿題がめんどくさい子どもだった筆者の体験談
子どもが宿題をめんどくさいと思う理由や対処法について解説してきましたが、何を隠そう、筆者自身が宿題が嫌いな子どもでした。
小学5年生までは日中は友達と運動をして遊びたかったですし、夜はゲームをやりたくて仕方ないという子どもでした。宿題をめんどくさいと思うのも当然だったと思います。
しかし、小学6年生になってから、きちんと宿題に取り組むようになりました。
そのきっかけになったのが、同居している祖父が宿題を見てくれるようになったことです。
17時まで遊んで帰宅したあと、19時の夕食までは祖父の隣で勉強するというのが家庭内の決まりになりました。私があまりに宿題をしないので、親が見かねたのだと思います。
私もひとりで宿題をするより温和な性格の祖父としたほうが気が楽でしたし、あまりうるさく言われなかったので、自然と慣れていきました。
また、その時間に宿題を片付ける習慣ができたことで、勉強へのハードルが下がり、成績もだんだん良くなってきたため、ますます宿題が苦ではなくなるという好循環に入りました。
このときに宿題への抵抗感を無くすことができたことで、中学生になってからも宿題をめんどくさいと思わずに済みました。
これには中学校から通いはじめた学習塾が比較的自由なところで、講師の先生が授業を早めに切り上げて宿題を見てくれたというのも大きかったと思います。
早い時期にこうした下地を作れたおかげで、高校に進学してからも、割と楽しく勉強できたと感謝しています。
宿題をめんどくさいと思わずにやれるかどうかは、子どものその後の学習に大きく影響するというのが私の持論です。
ぜひあなたも他の家族や学習塾のサポートを借りながら、お子さんの「宿題はめんどくさい」というイメージを払拭してあげてください。
まとめ~宿題がめんどくさい子どもは急かさないことが大切です~

宿題をめんどくさいと思っている子どもをどうにかしたい親御さんはたくさんいます。
しかし、だからといって子どもに宿題をやるように急かすと、意欲を失わせて、逆効果につながる可能性があります。
大切なのは、子どもを急かさずに、適切なフォローをすることです。
ぜひこれまでに解説してきた対処法を組み合わせて、お子さんに合った方法を探してください。
このコラムが、「宿題はめんどくさい」という感覚を無くす手助けになれば幸いです。
Q&A よくある質問
宿題をめんどくさいと思う理由を教えてください。
以下が考えられます。
- 宿題の量が多すぎる
- そもそも勉強が嫌い
- 学校の授業がわからない
- 部活動や習い事で疲れている
- 宿題をする意味がわからない
- 宿題に集中できる環境がない
- 宿題以外にやりたいことがある
詳細については、こちらで解説しています。
宿題がめんどくさい子どもに効果的な対処法はありますか?
以下が考えられます。
- 早めに片付けるメリットを教える
- 出されている宿題の整理を手伝う
- 勉強に対する苦手意識を軽減する
- 気軽に勉強を見てくれる学習塾に入る
- 宿題をしたことを褒めるようにする
- 家族・きょうだいなどと一緒にやる
- 机の上や部屋をきれいにする
- お気にいりの文房具を揃える
詳細については、こちらで解説しています。