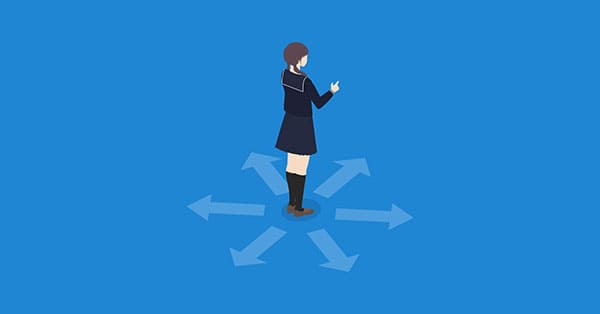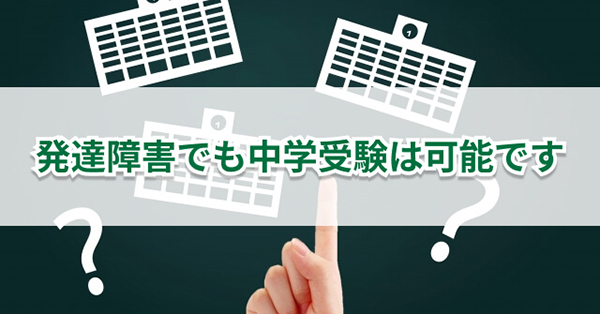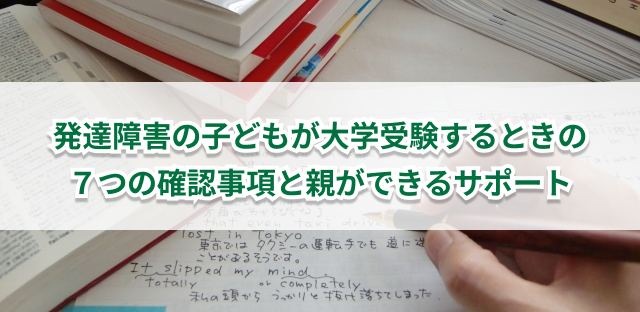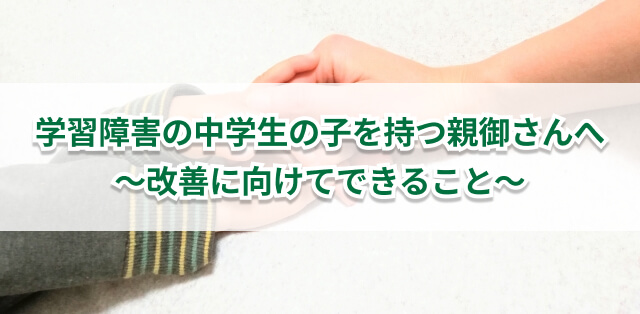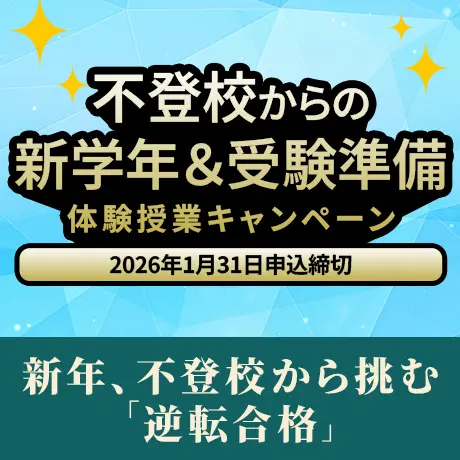学習障害(LD/SLD)の受験のポイント 受けられる配慮や親ができるサポートを解説
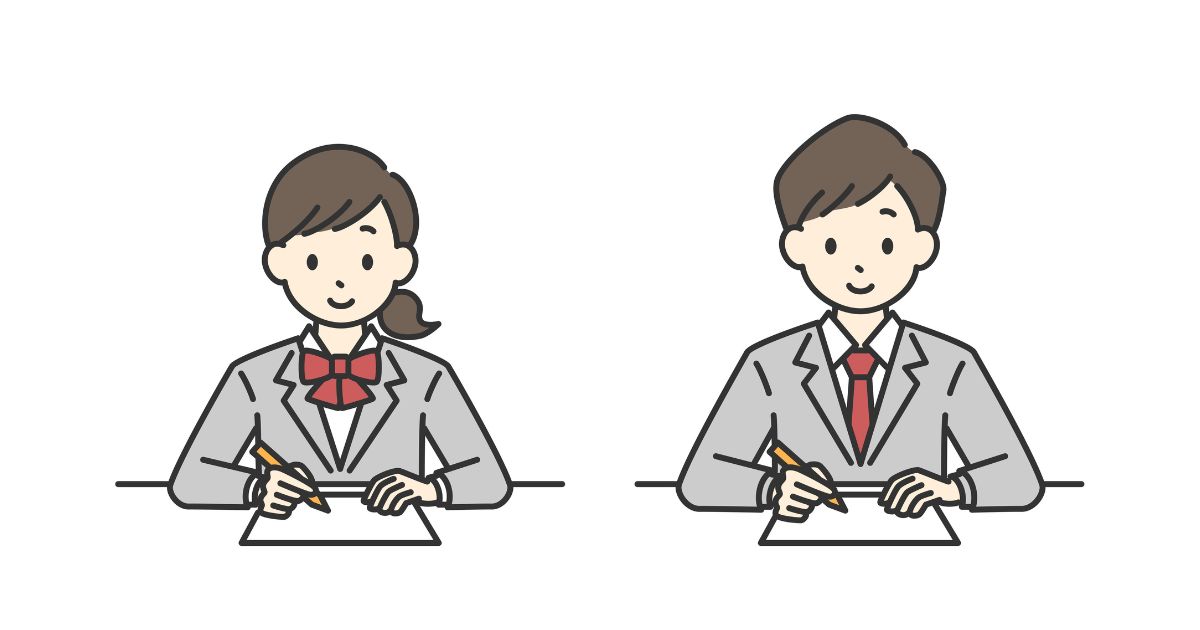
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、学習障害(LD/SLD)があるお子さんの受験について気になったことはありませんか?以下のような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
- 学習障害(LD/SLD)のある人の受験のポイントは?
- 親ができることはある?
このコラムでは、学習障害(LD/SLD)のある人が確認すべきポイント、受験時に受けられる配慮、親ができるサポートなどについて解説します。
学習障害(LD/SLD)のある人や親御さんはもちろん、今後のために知っておきたい人もぜひ最後までご覧ください。
私たちキズキ共育塾は、学習障害(LD/SLD)のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
学習障害(LD/SLD)のある人の受験にはさまざまな選択肢がある

学習障害(LD/SLD)のある人の受験には、以下のようにさまざまな選択肢があります。(参考:文部科学省「教育」、東京都教育委員会「多様なタイプの学校の紹介」)
- 小学生
- 公立中学校
- 私立中学校
- 通信制中学校
- 中高一貫教育校
- 特別支援学校
- 中学生
- 公立高校
- 私立高校
- 全日制高校
- 定時制高校
- 通信制高校
- 高等専門学校
- 高等専修学校
- 特別支援学校
- チャレンジスクール
- エンカレッジスクール
- 高校生
- 国公立大学
- 私立大学
- 短期大学
- 専門学校
「学習障害(LD/SLD)があることによって、受験できない学校」はありません。ただ、確認すべきポイントはあるので、こちらの章で見ていきましょう。
学習障害(LD/SLD)のある人が受験するときに確認すべきポイント
この章では、学習障害(LD/SLD)のある人が受験するときに確認すべきポイントについて解説します。
ポイント①中学受験
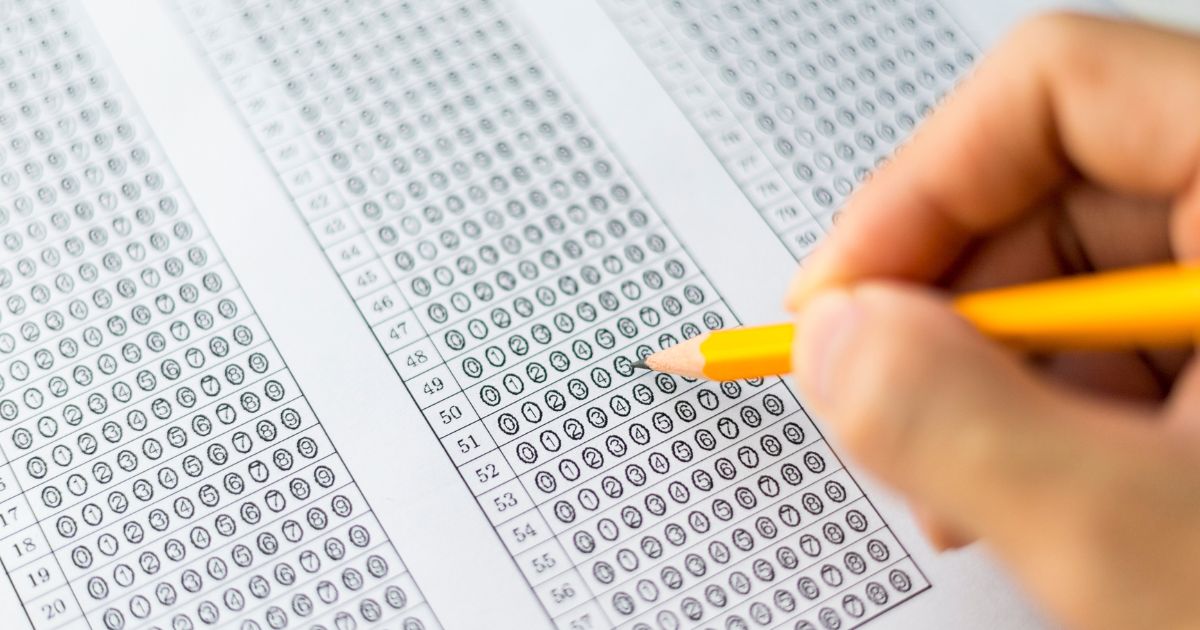
中学受験をするときに確認すべきポイントは、以下のとおりです。
- お子さんの意思が尊重されているか
- 学習障害(LD/SLD)があることを中学校に開示するか
- 入学後にどのような配慮を受けられるか
- 受験勉強が過剰な負担になっていないか
- 通学時間や手段に無理がないか
- 学校の制度や校風から考えて、卒業できそうか
- 学校の設備は適切か
まず最も大事なのは、お子さんの意志が尊重されているかです。
もしかすると、中学受験をしたくなかったり友達と離れたくなかったりするかもしれません。小学生だからと親が勝手に決めることなく、しっかりとお子さん自身の気持ちを聞きましょう。
また、学習障害(LD/SLD)のあるお子さんの場合、入学後の配慮で補助ツールを使えれば、学習に伴う負担を軽減することができるはずです。
学校の設備面でいうと、照明や黒板、ホワイトボードの色によっては集中しづらい可能性があります。
学習障害(LD/SLD)特有の悩みなので、しっかりチェックしておくのがオススメです。
それぞれの項目について、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
ポイント②高校受験
高校受験をするときに確認すべきポイントには、以下のものがあります。
- お子さん本人の意思を確認したか
- 学習障害(LD/SLD)であることを高校に開示するか
- 内申点はどのくらいか
- 進学後にどのような配慮を受けられるか
- 学校の制度や校風が合いそうか
- 高校卒業後の進路をどうするか
高校受験では、内申点が重要な項目になります。特に公立高校では、学科試験の点数に加えて内申点も重視されます。
内申点には主に定期テストの点数や提出物の取り組みが影響するため、中学生活の過ごし方によっては内申点が下がっているケースがあります。
内申点が合否に大きく影響しない高校を選択する必要がある場合もあるでしょう。
また、高校になると将来の進路を意識した学校選びが大切になってきます。例えば、高校卒業後に進学したいのか就職したいのかなどです。
はっきり決まっていなくても大丈夫ですが、考えておくとよいでしょう。以下のコラムでは、それぞれの項目について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
ポイント③大学受験

大学受験をするときに確認すべきポイントは、以下のとおりです。
- 興味・こだわりの強い分野があるか
- 学習障害(LD/SLD)があることを大学に告知するか
- 知的発達に遅れがある場合、志望校に支援体制があるか
- 進学後にどのような配慮を受けられるか
- 学校の制度や修学面の特徴から考えて、卒業できそうか
- 大学卒業後の進路をどうするか
- 自宅から通学するか、一人暮らしか
大学でも、中学校・高校と同じく配慮や支援体制は確認しておきましょう。
また、学習障害(LD/SLD)の有無は問いませんが、大学進学時は将来のことを本格的に考えて学校選択をする時期でもあります。将来のことを早めから考えていたほうが、進路や就職先を具体的にイメージしやすくなるでしょう。
さらに、考えるべきポイントとして、自宅通学か一人暮らしかもあります。一人暮らしをすると、勉強以外に身の回りの家事なども自分でする必要があります。
実際に大学へ通って生活するイメージが湧くか、事前に考えておきましょう。それぞれの項目について、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
学習障害(LD/SLD)のある人が受験時に受けられる配慮
学習障害(LD/SLD)のある人は、受験時に配慮を受けられるため、活用しましょう。
例えば、学習障害(LD/SLD)のある人は、高等学校の入学試験受験時に以下のような配慮を受けられます。 (参考:文部科学省「資料2高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への配慮の事例」)
- 別室受験
- 試験時間の延長
- 問題用紙の拡大
- 問題文の読み上げ
- 監督者による口述筆記
- 学力検査問題の漢字のルビ振り
- 面接の際、質問をわかりやすく伝え、回答を急かさない
また、学習障害(LD/SLD)のある人は、大学入学共通テスト受験時に以下のような配慮を受けられます。 (参考:独立行政法人 大学入試センター「令和7年度 受験上の配慮案内(PDF形式)」)
- 試験時間の延長(1.3倍)
- チェック解答
- 拡大文字問題冊子(14ポイント)の配付(一般問題冊子も配付)
- 拡大文字問題冊子(22ポイント)の配付(一般問題冊子も配付)
- 注意事項等の文書による伝達
- 別室の設定
- 試験室入口までの付添者の同伴
いずれも配慮を受けるには、申請書や医師の診断書が必要です。前もった準備が必要なため、余裕をもって早めに行動しておきましょう。
以下のコラムで、詳しい内容や申請方法について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
学習障害(LD/SLD)のある子どもの受験時に親ができるサポート
この章では、学習障害(LD/SLD)のある子どもの受験時に親ができるサポートについて解説します。
サポート①中学受験

中学受験を控える小学生のお子さんには、以下のようなサポートをしましょう。
- 担任の先生・スクールカウンセラーとよく相談する
- 専門機関・学習塾に協力を求める
- 親の会で情報収集や意見交換をする
- 集中しやすい環境を整える
- 適度に休ませる
- ペアレントトレーニングを受ける
- 愛情のメッセージを絶やさない
- 子どもの発達の特性を理解する
- 細かいことはあまり注意しない
共通しているのは、お子さんが勉強に集中できる環境を整えることです。
ただ、学習障害(LD/SLD)があるかどうかにかかわらず、小学生のお子さんは集中力が続かなかったり家族が自分のことを気にかけているか不安になったりします。
ですから、適度に休ませたり愛情のメッセージを送ったりするのが重要なのです。また、小学生のお子さんなら親が直接勉強を教えることもできるでしょう。
勉強を教える際の注意点や具体的なサポート方法などについて、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
サポート②高校受験
高校受験を控える中学生のお子さんには、以下のようなサポートが大切です。
- 在籍している中学校とよく相談する
- 支援機関や学習塾を利用する
- 親の会で情報収集や意見交換をする
- メンタル面のケアを心掛ける
- 学習障害について正しく学び、お子さんへ伝える
- タブレットなどの電子機器を取り入れる
- 一緒に予習をする
補助ツールを導入すると、直接的に学習の負担が減ります。勉強する環境を整えることも大事なので、検討してみてください。
また、高校受験は周りもピリピリしており、成績が伸びずイライラするケースもあります。そんなときに重要なのがメンタルケアです。
とはいえ、親御さんのメンタルが不調になるとお子さんにも伝わるため、バランスを取りながら見守りましょう。
具体的なサポート方法や接し方などについて、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
サポート③大学受験

大学受験を控える高校生のお子さんには、以下のようなサポートをしましょう。
- 担任の先生やカウンセラーに相談する
- 専門機関や学習塾に相談する
- 親の会で情報収集や意見交換をする
- メンタル面のケアを心掛ける
- 特性に合わせて勉強に集中しやすい環境を整える
大学受験の場合は内容も難しくなってくるため、直接勉強を教えられる機会は少なくなります。そのため、勉強環境の整備に注力するのがオススメです。
特に、学習塾は勉強を教えるだけでなく、進路相談にも乗ってくれます。
キズキ共育塾のように学習障害(LD/SLD)のある生徒さんが多く通っていて理解のある学習塾であれば、親身になってプロの目線から的確にアドバイスしてくれます。頼ってみましょう。
具体的なサポート方法について、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
学習障害(LD/SLD)のある人向けの勉強法〜種類別に解説〜
この章では、学習障害(LD/SLD)のある人向けの勉強法について種類別に解説します。(参考:発達障害教育推進センター「学習面でのつまずきと指導・支援」)
種類①読字障害(ディスレクシア)

読字障害(ディスレクシア、Dyslexia)とは、目で見た文字や文章を読むことに困難が生じる学習障害(LD/SLD)のことです。
読字障害(ディスレクシア)のある人には、以下のような勉強法がオススメです。
- 単語ごとに丸をつけて読む
- 補助ツールで音声を聞く
- 重要な箇所に印をつける
- 文章や段落ごとの関係を図示する
一つひとつの文字ではなく単語で認識したり、文章のつながりを理解したりする練習をすると、読みやすくなってきます。
種類②書字表出障害(ディスグラフィア)
書字表出障害(ディスグラフィア、Dysgraphia)とは、文字や文章を書くことに困難が生じる学習障害(LD/SLD)のことです。
書字表出障害(ディスグラフィア)のある人には、以下のような勉強法がオススメです。
- 文章や文字をなぞり書きする
- 文字の意味を学ぶ
- 漢字の成り立ちなどの付加的な情報を学ぶ
文字を思い出せない・書けない場合は、なぞり書きで文字の書き方を学ぶのが有効です。細かい部分を間違う場合は、文字の意味や成り立ちなどを学び、意味づけして思い出せるようにしてみましょう。
種類③算数障害(ディスカリキュリア)
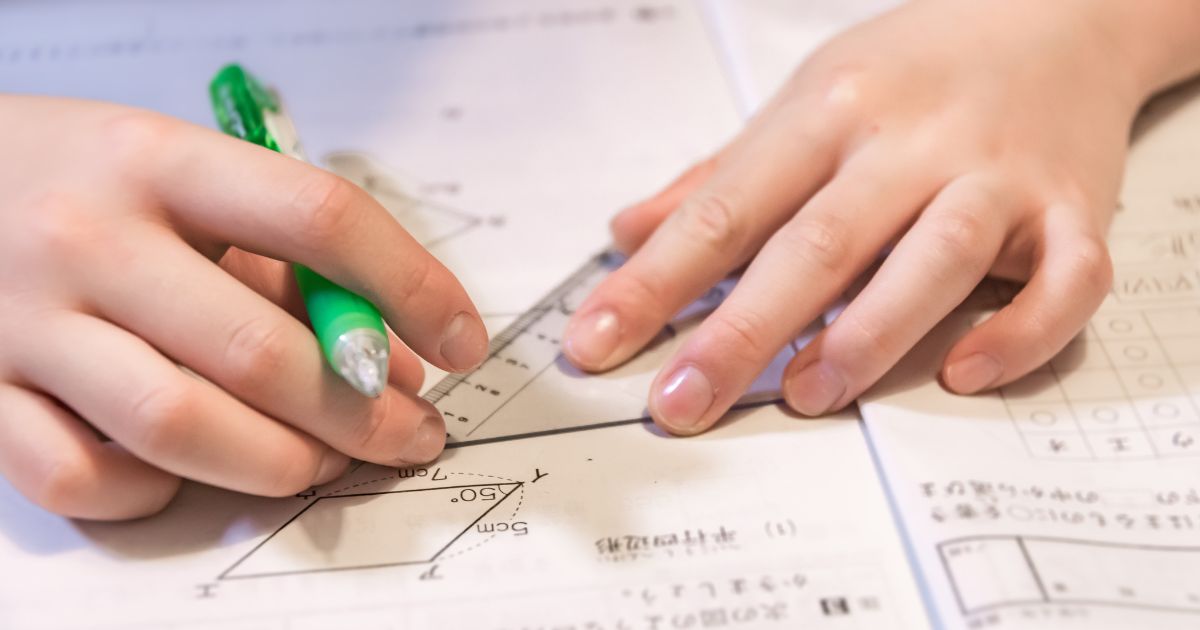
算数障害(ディスカリキュリア、Dyscalculia)とは、計算すること、または数学的な推論をすることに困難が生じる学習障害(LD/SLD)のことです。
算数障害(ディスカリキュリア)のある人には、以下のような勉強法がオススメです。
- 絵カードなどの補助ツールを活用する
- 計算の手順を図や記号で表す
- 筆算にマス目のあるノートを使う
ポイントは、頭の中で計算しようとせず、視覚を使って理解を試みることです。途中計算を省略せずに書くといいでしょう。
学習障害(LD/SLD)のある人の勉強サポートには学習塾がオススメ
学習障害(LD/SLD)がある人の中には、学校の勉強についていけない、学習が遅れているなどの悩みを抱えている人が多くいます。
学習障害(LD/SLD)のある人を実際に勉強面でサポートするなら、学習塾がオススメです。学習塾では勉強も教えてくれますし、進路相談にも乗ってくれます。
学習塾を選ぶ際は、自分のペースで進められる個別指導塾が最もオススメです。そのうえで、学習障害(LD/SLD)に理解のある学習塾ならなおいいでしょう。
キズキ共育塾では完全1対1のマンツーマン授業を採用しており、目的や性格などを考慮して授業を進めます。
また、学習障害(LD/SLD)のあるお子さんも通塾しており、不登校・中退・引きこもりなどにも理解がある学習塾です。
学習障害(LD/SLD)のある人の学習塾選びのポイントやキズキ共育塾への通塾体験談について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
学習障害(LD/SLD)とは?
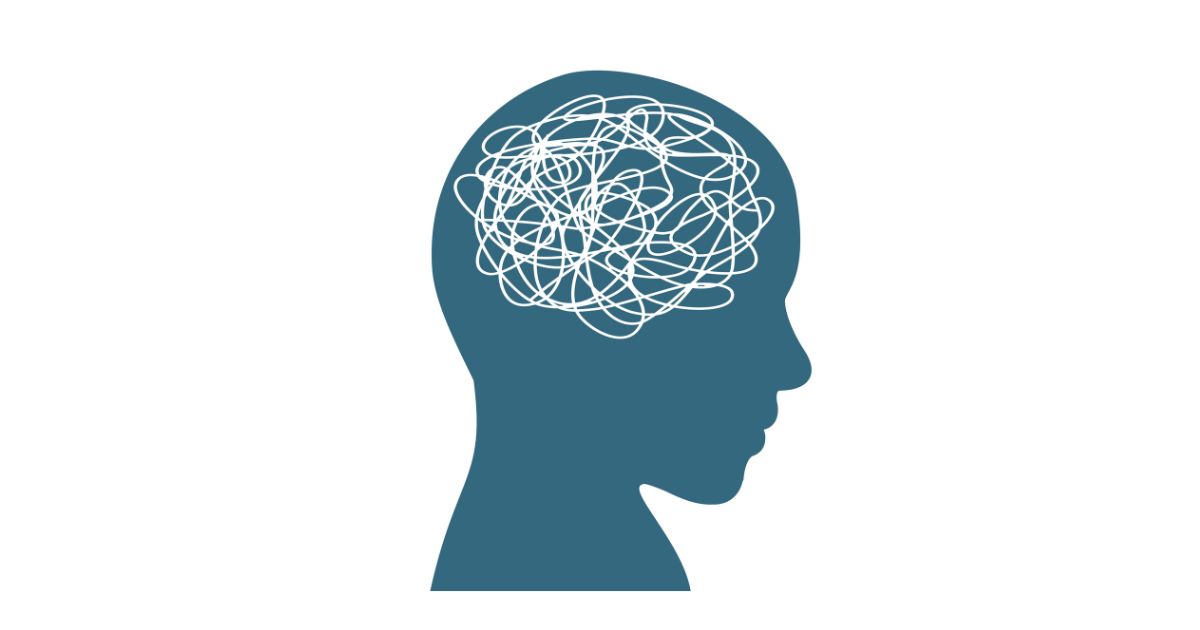
LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
LD/SLDのある人は、全ての学習行為に困難が生じるというわけではありません。
いずれかの学習行為、または複数の学習行為に困難が生じている人もいます。計算することのみが不得意、読むことと書くことが不得意などのように、人によって様々です。
また、いずれの学習行為においても、人によって得意なこと、不得意なことは異なってきます。
例えば、読字障害のある人のなかでも、音読はできてもその内容を理解することが難しいという人もいれば、スムーズな音読が不得意な人もいます。
このように、LD/SLDのある人は、学習する事柄が総合的に不得意というわけではなく、ごく一部の事柄に困難が生じるという点が大きな特徴です。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)とは? 特性や診断基準を解説」
まとめ~学習障害(LD/SLD)のある人の受験は配慮を受けられます~

学習障害(LD/SLD)があるからといって、行きたい学校への受験をあきらめることはありません。不安もあると思いますが、配慮を受けられるので安心してください。
親御さんは、お子さんが勉強に集中できる環境、夢を目指せる環境を整えてサポートしていきましょう。
ただ、助けてくれる存在はありますので、学校や学習塾などを頼ってみてください。