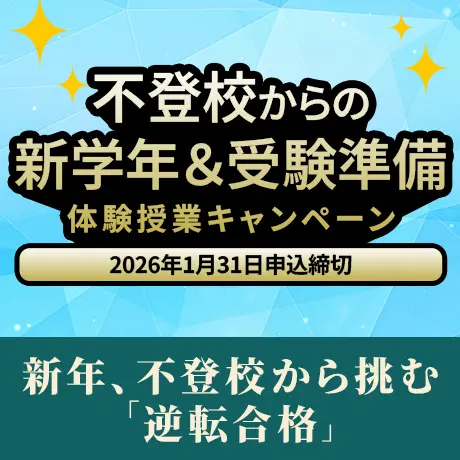勉強してると眠くなるあなたへ 予防策を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾、キズキ共育塾です。
このコラムを読んでいるあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 教科書を開くとすぐにまぶたが重くなる
- やらなきゃいけないとわかっているのに集中できない
- 勉強中に眠くならない対策を取り入れたい
このコラムでは、勉強中に眠くなる原因や勉強中に眠くならないための予防策、眠くなったときの対処法について解説します。
このコラムが、勉強中に眠くて困っている人の支えになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、勉強中の眠気に悩む人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
勉強中に眠くなるのは多くの人が経験する悩み

勉強をしている最中に強い眠気に襲われるのは、誰しもが共通して抱える悩みです。
集中しようと思っても意識がぼんやりし、気づけば机に突っ伏してしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
眠くなる原因は、単純な睡眠不足だけでなく、生活リズムの乱れや食事内容、学習環境や心理的な要因など、さまざまな要素が重なって生じます。
なぜ自分が勉強中に眠くなるのかを理解することで、適切な対策を立てられるようになるでしょう。
勉強中に眠くなる8つの原因
勉強中に眠くなったとき、場当たり的な対処をしている人もいるかもしれません。しかし、根本的な原因がわからないと、正しい解決策も立てられません。
まずは、複数ある原因をしっかりと確認しておきましょう。
この章では、勉強中に眠くなる原因について解説します。
原因①睡眠不足や睡眠の質の低下

睡眠は脳や体を回復させるために欠かせません。十分な睡眠が取れていないと、日中の集中力や判断力が大きく低下し、勉強中に強い眠気を感じやすくなります。
また、十分な時間眠っても、睡眠の質が低いと効果は半減します。例えば、寝る直前までスマホを見てブルーライトを浴びたことが原因で、夜中に何度も目が覚めると、深い眠りが妨げられます。
脳は記憶の整理を睡眠中に行うため、学習効率を高めるためにも質の良い睡眠が必要です。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」)
原因②疲労やストレスの蓄積
体の疲れや精神的なストレスが蓄積すると、自律神経のバランスが乱れ、脳が休ませようと信号を出します。これが、眠気として表れます。
例えば、部活動やアルバイトで体が疲れていたり、人間関係や勉強への不安などで精神的にストレスを抱えていたりすると、集中力が途切れて眠気につながります。
さらに慢性的な疲労が続くと、意欲や記憶力の低下にもつながります。そんなときは、無理に机に向かい続けるのではなく、休養や気分転換を取り入れることが重要です。
原因③食後の血糖値変動

食事を取ると、体内では血糖値が一時的に急上昇します。その後、血糖値を下げるためにインスリンが分泌され、今度は血糖値が急降下します。
この現象は血糖値スパイクと呼ばれ、血糖値の変動によって脳のエネルギー供給が不安定になり、眠気を感じやすくなるのです。
特に白米やパン、ラーメンなど炭水化物中心の食事を多く摂った後は眠気が顕著に出やすい傾向にあります。
食後の血糖値のゆれによる眠気を減らすには、食後すぐに勉強を始めずに、10~20分ほど軽く休憩を入れるのがオススメです。
原因④座りっぱなしによる血流の低下
長時間同じ姿勢で勉強していると、血流のめぐりが悪くなり、頭が重い・ぼんやりするといった症状に繋がります。その結果、眠気につながることもあるでしょう。
同じ姿勢が長く続くと、どうしても血のめぐりが落ちて頭が重くなりがちです。30~60分に一度は席を立って、1~2分体を動かすことを習慣にしましょう。
激しい運動をする必要はありません。デスクの周りをゆっくり一周歩いたり、肩や首を軽く回したり、つま先立ちと着地を数回くり返すだけでも十分です。
原因⑤脳のエネルギー不足
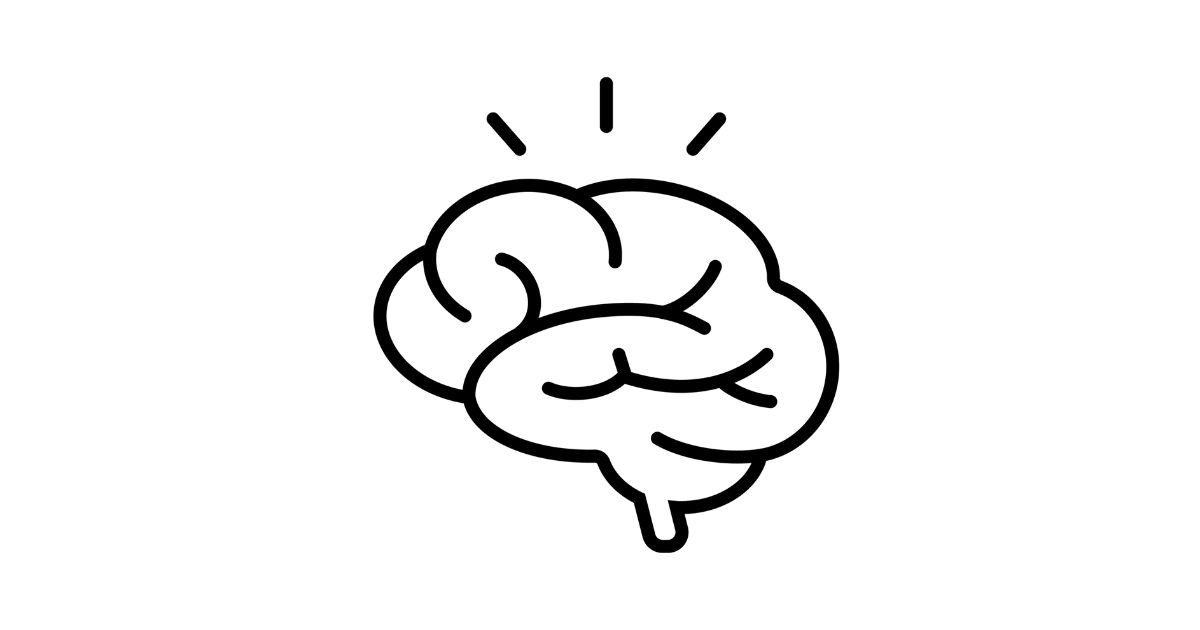
脳は一日に大量のエネルギーを消費しており、その主なエネルギー源はブドウ糖です。
そのため朝食を抜いたり、極端なダイエットをして栄養が偏っていたりすると、脳が必要なエネルギーを確保できず、眠気や倦怠感が現れます。(参考:J-STAGE「食品成分と脳機能の研究動向」)
また、甘いものだけでエネルギーを補給すると、血糖値が急激に上昇した後に急降下し、かえって眠くなります。
脳を効率的に働かせるためには、バランスの良い食事を心がけ、適度に栄養補給することが重要です。
間食をとるなら、ナッツ+ヨーグルトのようにたんぱく質や食物繊維を含む小さめのセットにして、甘い飲料は学習の直前に大量摂取しないのがオススメです。
原因⑥体温の上昇や体内時計の乱れ
人間の体は一日の中で体温やホルモン分泌が変動するリズムを持っています。(参考:厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「体内時計」)
特に午後は体温が徐々に下がる時間帯であるため、自然と眠気が訪れやすくなります。
また、夜更かしや昼夜逆転生活を続けると体内時計が乱れ、昼間に強い眠気を感じやすくなります。
原因⑦勉強内容への拒否反応・興味の欠如

苦手な科目や興味の持てない分野に取り組むと、脳は面白くないと感じて集中できなくなり、眠気につながることがあります。
例えば、数学が苦手な人が公式をひたすら暗記しようとしても、脳が退屈を覚えて眠気が強まります。
この場合は勉強方法を変えたり、学ぶ目的を再確認したりすることが効果的です。
原因⑧リラックスモードになる学習環境
部屋が暖かすぎたり、照明が暗すぎたりすると、脳はリラックスモードに入り、自然と眠気を感じます。
さらに、ベッドやソファなど快適すぎる環境で勉強すると、体が休息の態勢に切り替わりやすくなります。
逆に、周囲が騒がしすぎても集中が途切れ、疲れから眠くなることもあります。
勉強中に眠くならないための予防策
眠気を感じるのは自然な生理現象ですが、日常生活や学習習慣を見直すことで大幅に減らすことができます。
この章では、勉強中に眠くならないための予防策について解説します。
予防策①十分な睡眠時間を確保する

勉強中の眠気を防ぐためには、日常的にしっかり眠ることが欠かせません。
一般的に高校生や大学生であれば7〜8時間の睡眠が理想とされており、夜更かしや睡眠不足を続けると、日中の集中力が低下します。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」)
また、記憶の定着には睡眠が重要であり、しっかり睡眠を取ることで、結果的に成績向上も狙えます。(参考:精神保健研究通巻54号「睡眠と記憶に関する近年の知見」)
休日に寝だめするのではなく、毎日同じリズムで睡眠をとることを意識しましょう。
予防策②規則正しい生活習慣を整える
不規則な生活を送っていると体内時計が乱れ、昼間でも強い眠気に襲われやすくなります。
予防策として朝はしっかり起きて朝日を浴び、三食を決まった時間に食べることで体のリズムを整えましょう。
また、夜遅くまでスマホやパソコンを使うと、ブルーライトが睡眠を妨げます。就寝1時間前はデジタル機器を避けましょう。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」)
予防策③適度な運動習慣を取り入れる

運動不足が続くと血のめぐりが落ちて体が重くなり、日中のぼんやり感や眠気につながりやすくなります。ウォーキングや軽いストレッチ、ゆるいジョギングなど、続けやすい動きを日々のリズムに組み込みましょう。
また、食後に10~15分ほどの軽い歩行を入れると、食後の血糖の上がり方を穏やかにでき、食後のだるさ対策としても相性がよいことが報告されています。
運動はストレスを和らげ、夜の睡眠の質を底上げする効果も期待できます。就寝直前の激しい運動は避けつつ、日中~夕方の適度な運動を習慣にするとよいでしょう。
予防策④バランスの良い食生活を心がける
食事内容が偏っていると、血糖値の急激な変動や脳のエネルギー不足を招き、勉強中に眠気を感じやすくなります。
特に炭水化物に偏った食事は眠気を誘発しやすいため、たんぱく質や野菜を組み合わせるなどしてバランスを意識しましょう。
食べ方の工夫も効果的です。野菜やたんぱく質を先に、炭水化物を後にすると、食後の血糖の上がり方が穏やかになりやすいことが示されています。
間食を取る場合はナッツやヨーグルトなど、血糖値が緩やかに上がる食品を取り入れるのがオススメです。
予防策⑤集中しやすい環境を整える

勉強する環境によって、眠気の出方は大きく変わります。部屋の温度が高すぎるとリラックスして眠気を感じやすくなるため、適度に空調を調整することが重要です。
オフィス研究では、およそ22℃前後が最も安定し、23~24℃を超えると集中が落ち始めるという報告があります。(参考:日本建築学会環境系論文集「室温の違いが作業効率に及ぼす影響」)
また、照明が暗いと目が疲れて集中力が落ちるため、机には十分な明かりを確保しましょう。読書やノート作業に適した光量は、机上で300~500ルクスとされています。(参考:文部科学省「学校環境衛生基準」)
音は静かすぎても気になるものですが、基準としては室内45dB以下を目安にするとよいでしょう。環境音アプリで小さく自然音を流すか、気が散る騒音には耳栓・ノイズキャンセリングを活用すると効果的です。(参考:文部科学省「学校環境衛生基準(騒音)」)
予防策⑥勉強方法を工夫して興味を持てるようにする
退屈なやり方が続くと、どうしても脳への刺激が弱くなり、眠気が出やすくなります。対策ポイントは見るだけ・読むだけの作業を減らして、手と口と頭を同時に動かすことです。
例えば、教科書をただ眺めるのではなく、音読しながら自分の言葉で要約し、思いついた疑問を余白にメモしていくと、理解が深まりやすくなるだけではなく、眠気防止にも効果的です。
言葉とイメージの両方を使うことで、記憶の手がかりが増え、興味も持続しやすくなります。
また、単調さを避けるために、科目やタスクをローテーションさせるのも効果的です。計算→用語暗記→読解→再び計算、のように似すぎない作業を25~40分ごとに入れ替えると、脳の同じ部位ばかりを酷使せずに、飽きずに続けられます。
眠くなったときの対処法
どんなに予防しても、勉強中に眠気が訪れることはあります。そのときに即効性のある対処法を知っておけば、眠気を引きずらず効率的に学習を続けられます。
この章では、眠くなったときの対処法について解説します。
対処法①短時間の仮眠を取る
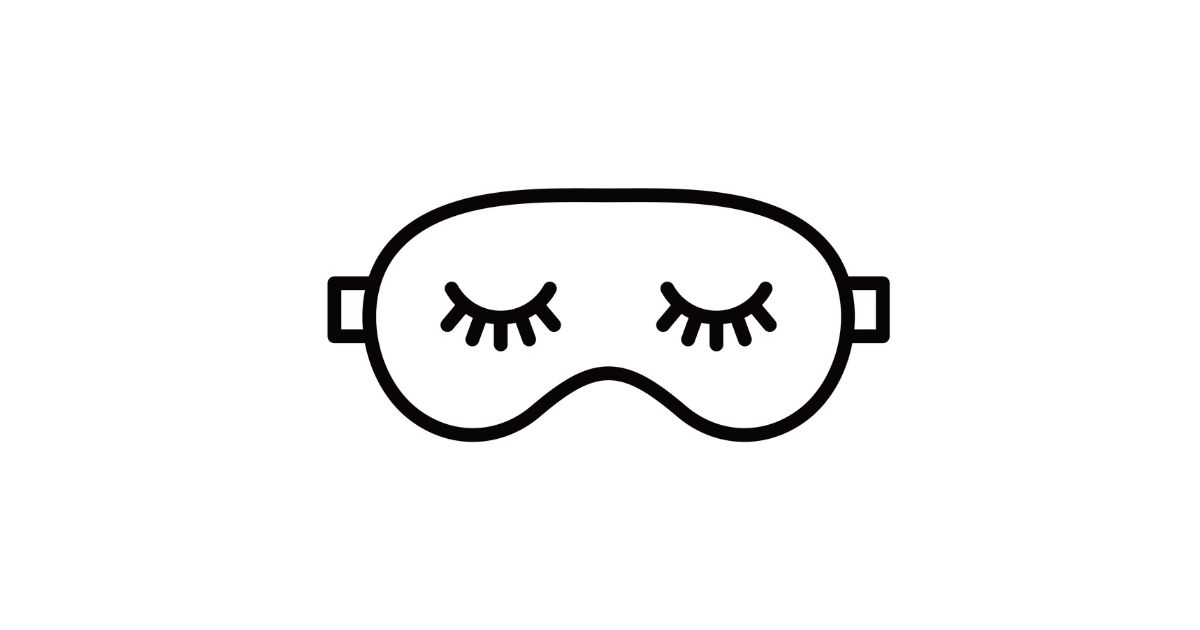
強い眠気を我慢しながら勉強を続けても、効率は上がりません。その場合は軽く目を閉じて10〜20分程度の短い仮眠を取るのが効果的です。短時間の睡眠は脳をリセットし、再び集中力を高めてくれます。(参考:厚生労働省「良い睡眠の概要(案)」)
ただし、30分以上寝ると深い睡眠に入り、起きたときに逆にだるさを感じるので注意が必要です。
対処法②ストレッチや軽い運動で体を動かす
体を動かすと血流が良くなり、脳に酸素が行き渡って眠気が軽減されます。
肩を回したり、立ち上がって軽く屈伸をするだけでも効果があります。勉強中に眠くなったときは、思い切って数分間体を動かすことを習慣にしましょう。
対処法③洗顔や歯磨きでリフレッシュする

顔を冷たい水で洗ったり歯磨きをしたりすると、自律神経が刺激されて眠気が軽減されやすくなります。
特に歯磨きは口の中がスッキリするため、眠気だけでなく気分転換にも効果的です。勉強の区切りごとに取り入れると集中が持続しやすくなります。
対処法④軽い刺激やクールダウンでひと息入れる
強い眠気には魔法の一手はありませんが、軽い刺激で気分を切り替えられることはあります。
例えば、手のひら・前腕・こめかみ周りをやさしくもみほぐす、耳の周りを軽くマッサージする、といった程よい刺激は短時間のリフレッシュに役立ちます。
また、暑さでぼんやりしているときは、首すじやわきの下を冷たいタオルで数分冷やすと、体の熱が下がって頭がスッとすることがあります。とくに夏場や運動後は相性がよい方法です。
対処法⑤カフェイン飲料を飲む

コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインは脳を覚醒させる作用があります。眠くなったときに摂取すると一時的に眠気を抑えられます。(参考:国立精神・神経医療研究センター「カフェインと睡眠」)
ただし、飲みすぎは胃腸への負担や夜の睡眠への影響につながるため注意が必要です。特に子どもはカフェインへの感受性が高いため、取り入れる前に摂取量をチェックしておきましょう。
カナダ保健省によると、4歳~6歳の子どもは最大45mg/日、7歳~9歳の子どもは最大62.5mg/日、10歳~12歳の子どもは最大85mg/日(355ml入り缶コーラ1~2本相当)までと注意喚起されています。
また、13歳以上の青少年については、一日当たり2.5mg/kg 体重以上のカフェインを摂取しないことが推奨されています。(参考:厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~」)
対処法⑥場所や環境を変える
同じ場所に長時間いると脳が環境に慣れ、眠気が出やすくなります。
そこで図書館やカフェ、自習室など場所を変えるだけで気分が切り替わり、集中しやすくなります。
特に家で勉強して眠くなりやすい人は、外に出て環境を変えてみましょう。
対処法⑦換気して空気を入れ替える

人がいる部屋では二酸化炭素(CO₂)が少しずつたまっていき、集中しづらさやぼんやり感、さらに眠気の原因になります。
ときどき外気を入れて入れ替えるだけでも、頭がすっきりしやすくなります。一定の間隔で窓を少し開けて通り道を作り、数分だけでも外気を入れてみましょう。
また二酸化炭素計があるとタイミングが分かりやすく、1000ppmくらいを超えたら換気、900ppm台まで下がったら閉めるといった運用がしやすくなります。
天気や季節の影響で窓を開けにくい日は、換気扇やレンジフードを短時間まわす・扇風機で窓(またはドア)方向へ風を送るなどでも代わりになります。
対処法⑧勉強内容や教科を変える
同じ科目を長時間続けると脳が単調さを感じ、眠気を引き起こします。
その場合は教科や内容を切り替えて新しい刺激を与えると、再び集中できます。
暗記科目に疲れたら計算問題に取り組むなど、勉強の種類を工夫しましょう。
対処法⑨声に出して勉強する・人と会話する

音読したり、友人に口頭で説明したりすると、受け身の読みより脳がよく働き、眠気が出にくくなります。
また、暗記は声に出して要約→本を閉じて思い出すの小テストを繰り返すと定着しやすく、区切りごとに数十秒の立ち歩きやストレッチを挟むと切り替えがスムーズです。
声を出して読むと視覚だけでなく聴覚も同時に使うため、情報を多角的に処理でき、理解や記憶の効率が高まります。
以下のコラムでは、授業中に寝ない方法について詳しく解説しています。本記事の対処法と併せてご活用ください。
まとめ~自分に合った眠気対策を見つけて学習効率を高めよう~

勉強中に眠くなるのは誰もが経験する自然な現象ですが、その原因や背景を理解することで対策が可能です。
大切なのは自分に合った方法を見つけ、無理なく継続することです。眠気を上手にコントロールして、効率の良い学習を目指しましょう。
このコラムが、勉強に集中できる助けになれば幸いです。
Q&A 勉強中に眠くなる原因を教えてください。
不登校の子どもが勉強しない理由を知りたいです。
以下が考えられます。
- 睡眠不足や睡眠の質の低下
- 疲労やストレスの蓄積
- 食後の血糖値変動
- 座りっぱなしによる血流の低下
- 脳のエネルギー不足
- 体温の上昇や体内時計の乱れ
- 勉強内容への拒否反応・興味の欠如
- リラックスモードになる学習環境
詳細については、こちらで解説しています。
眠くなったときの対処法はありますか?
以下が考えられます。
- 短時間の仮眠を取る
- ストレッチや軽い運動で体を動かす
- 洗顔や歯磨きでリフレッシュする
- 軽い刺激やクールダウンでひと息入れる
- カフェイン飲料を飲む
- 場所や環境を変える
- 換気して空気を入れ替える
- 勉強内容や教科を変える
- 声に出して勉強する・人と会話する
詳細については、こちらで解説しています。