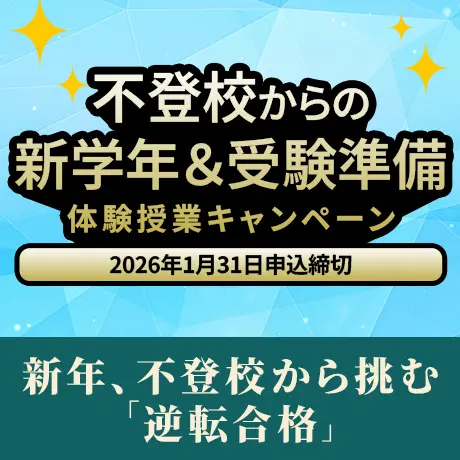浪人しても成績が伸びない人へ 今からできる見直し対策を解説

こんにちは。生徒さん1人ひとりの悩みに寄り添う、完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
- 浪人しても思うように成績が伸びない…。
- 頑張っているのに結果が出なくて、自分には向いていないのかも…。
そんなふうに思っていませんか?
浪人生の中には、焦りや自己否定の気持ちを抱えながら日々勉強に取り組んでいる人がたくさんいます。
でも、成績が伸びないときこそ、自分の勉強法や生活習慣を一度立ち止まって見直すチャンスです。
このコラムでは、浪人しても成績が伸びない理由と成績が伸びる浪人生の特徴、見直すべきポイントについて解説します。
一歩ずつ前に進むためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
私たちキズキ共育塾は、成績が伸び悩んでいる浪人生のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
浪人しても成績が伸びない人は多い?

「浪人しても成績が思うように伸びない…それって自分だけ?」と不安になる方は少なくありません。
でも、実はこの悩みを抱えている浪人生は、決して少数派ではないのです。
独立行政法人大学入試センターの調査によると、令和7年度大学入学共通テストの志願者数は以下のとおりです。(参考:独立行政法人大学入試センター「令和7年度大学入学共通テストの志願者数等について」)
- 全体の志願者数:49万5171人(前年度比+3257人)
- 現役生(高等学校等卒業見込者):42万5968人(+6434人)
- 既卒者(浪人生):6万4974人(−3246人)
- 浪人生の割合:約13.1%(前年度より減少)
浪人生の減少傾向は、浪人しても成績が上がるとは限らない、浪人はリスクがあるという不安が広がっている現れともいえます。
つまり、成績が伸び悩んでいるのは自分だけではないということです。多くの浪人生が同じように悩み、壁にぶつかっているのです。
結果が出ない時期であっても、改善のヒントは隠れています。自分を責めるのではなく、いまの勉強法や生活スタイルを見直すタイミングと捉えることが大切です。
浪人しても成績が伸びない主な理由
この章では、浪人しても成績が伸びない主な理由について解説します。
理由①目標が曖昧で覚悟が足りない
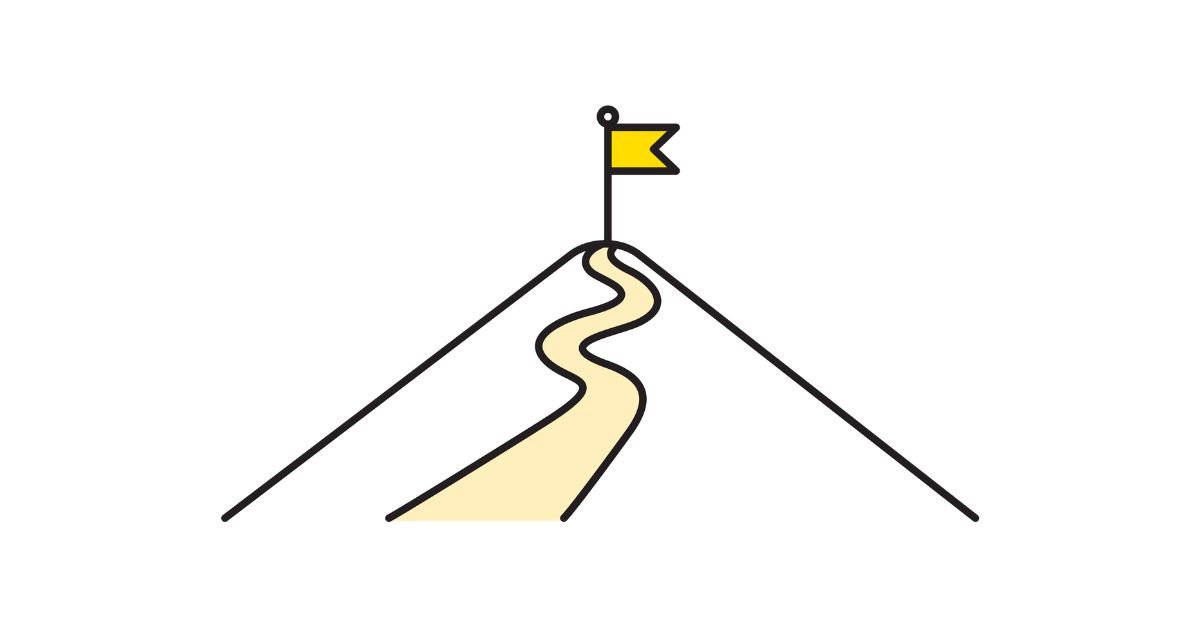
1つ目の理由は、目標が曖昧で、勉強のモチベーションが続かないことです。/p>
浪人中は毎日長い時間、1人での勉強が続くため、何のために頑張っているのかが見えなくなると、気持ちが折れやすくなってしまいます。<
実際、心理学の研究では、家族のサポートや関心の強さが、浪人生のやる気や進路への関心に大きく関わっているとされています。(参考:こころの健康「大学受験浪人生における家族の凝集性 ― 同一性地位判定尺度と教育的進路態度尺度の分析を中心に―」)
- 家族の関わりが深い場合、進路への関心度や計画性、やる気が高まりやすい
- 受験の話が出にくい場合は目標がぼやけ、モチベーションが下がりやすい傾向
これは、本人の性格ではなく、環境の影響による自然な反応です。だからこそ、まずは今できる小さな目標を決めてみてください。
一歩ずつ進んでいる自分を認めることが、浪人生活を前向きに支える力になります。
理由②現役時の失敗を分析できていない
2つ目の理由は、現役時の失敗をきちんと振り返れていないことです。
浪人生活は、時間をかけて勉強すれば成果が出るとは限りません。現役時にうまくいかなかった理由を見つめ直さないまま進めると、同じつまずきを繰り返す可能性があります。
失敗をうやむやにしたままでは、自分に合ったやり方や必要な努力の方向も見えにくくなります。
浪人生活を意味あるものにするためには、なぜ現役時にうまくいかなかったのかを自分なりに整理することが大切です。
理由③勉強の自走力が身についていない
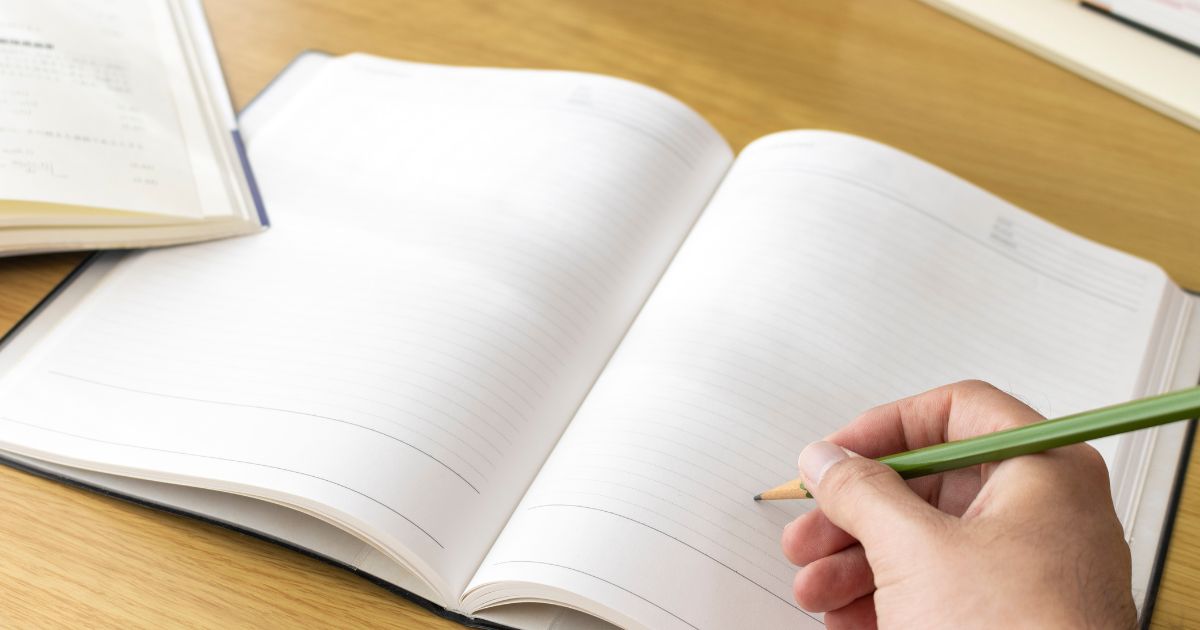
3つ目の理由は、自分で勉強を進める力がまだ身についていないことです。
浪人生は、受験に向けて使える時間が現役生より多いぶん、自分で学習のペースを決める必要があります。
実際、浪人を決めたばかりの時期は、まだ時間があると感じて気が緩んだり、少しくらい休んでも大丈夫と思ってしまったりする人が少なくありません。
浪人生活では、学校や塾だけに頼らず、自分で時間を管理し、学習の流れを作っていく力が求められます。
その力がまだ十分に育っていないと、努力が思うように積み重ならず、結果にもつながりにくくなるでしょう。
理由④予備校任せで受け身になっている
4つ目の理由は、予備校任せで受け身になっていることです。
授業を受けているだけで勉強した気になってしまい、自分で考えて取り組む姿勢が育ちにくくなることがあります。
予備校での授業が知識を教わる場所に終始すると、学習した内容が実際にどれだけ理解できているのかが分からないままになってしまいます。
また、授業をこなすことで安心感が生まれ、「ちゃんと勉強しているはず」と思う浪人生も少なくありません。
受け身の姿勢が続くと、学んだ内容を使いこなす力がつきにくく、思ったように成績に反映されないこともあります。
予備校や塾に通うことは決して悪いことではありませんが、それだけに頼りすぎると、自分から学ぶ力が育ちにくくなるという落とし穴があるのです。
理由⑤メンタル管理ができていない

5つ目の理由は、メンタル管理ができていないことです。
浪人生活は一人で過ごす時間が長く、自分と向き合う日々が続くため、不安や孤独を抱えやすくなります。
特に、身近に話を聞いてくれる人がいないと、感情をうまく整理できず、心が不安定になる可能性が高いです。
心理学の研究では、家族の関わりの強さが、浪人生の心の安定に影響を与えることが報告されています。(参考:こころの健康「大学受験浪人生における家族の凝集性 ― 同一性地位判定尺度と教育的進路態度尺度の分析を中心に―」)
今の自分が「うまく気持ちを保てない」と感じているなら、それは甘えではなく、必要なサインかもしれません。
成績が伸びる浪人生の特徴
この章では、成績が伸びる浪人生の特徴について解説します。
特徴①目的意識をもって浪人している

1つ目の特徴は、目的意識を持って浪人していることです。
Studyplusトレンド研究所の調査によると、現役時代に合格した大学があったにもかかわらず、浪人を選んだ人は約5割弱にのぼります。(参考:Studyplusトレンド研究所「浪人生の5割弱が現役時代に合格した大学があったと回答、浪人理由は『第一志望へのこだわり』~大学全入時代の浪人生活の実態を調査~」)
つまり、「進学できる大学があったけれど、それでも納得できる進路を目指したい」という強い目的意識を持って浪人を選んだ人が多いということです。
こうした浪人生は、とりあえず浪人という姿勢ではなく、自分の意思で目標に向かって再挑戦している自覚があります。
その覚悟の強さが、日々の勉強の質や継続力にも表れやすく、結果として成績の伸びにつながっていると考えられます。
特徴②自習時間を安定して確保している
2つ目の特徴は、自習時間を安定して確保していることです。
浪人中に成績が伸びる人は、授業を受けるだけで満足するのではなく、日々の自習を大切にしています。授業で得た知識を、自分の手で何度も確認し、定着させていく過程があるからこそ、学力がついていくのです。
実際、予備校や塾に通っていても、授業を受けっぱなしにしているだけでは、成果につながりにくいことがあります。
大切なのは、学んだ内容を自分で振り返り、どれだけ理解できているかを確認する時間を日々しっかり確保できているかどうかです。
授業と自習をバランスよく組み立て、コツコツ積み上げていける浪人生ほど、成績が伸びやすいといえるでしょう。
特徴③模試結果を分析し、戦略を修正している

3つ目の特徴は、模試結果を分析し、戦略を修正していることです。
成績がなかなか伸びない浪人生の中には、模試を受けて終わりにする人もいます。点数や判定だけを見て安心したり落ち込んだりして、なぜ間違えたのか、どこが苦手なのかを振り返らないまま次に進むこともあるでしょう。
一方で、成績を着実に伸ばしている浪人生は、模試をきっかけに自分の弱点を把握し、勉強の優先順位や方法を調整しています。
成績を伸ばす浪人生は、「どの科目が不安定か」「どの分野に時間をかけるべきか」などの視点を持ち、計画を立て直す習慣があります。
模試をただの確認ではなく学び直すためのヒントが詰まった材料として活用している人ほど、次の一歩につなげやすいといえるでしょう。
特徴④伸びやすい科目を優先して対策している
4つ目の特徴は、伸びやすい科目を優先して対策していることです。
浪人して成績を伸ばす人は、どこから手をつければ効率よく点数が上がるかを冷静に見極めています。比較的短時間で伸ばせそうな科目から、着実に対策していく傾向があります。
例えば、現時点で得点が低い教科ほど、ちょっとした工夫や取り組みで目に見えて点数が上がることがあります。80点を90点にするよりも、20点を30点にする方が結果が出やすい、というのはよく知られた例です。
「全部やらなきゃ」と焦るのではなく、得点アップに直結しやすい科目に集中するという判断が、学習の効率と成果につながっているのです。
特徴⑤不安や悩みを一人で抱え込まない

5つ目の特徴は、不安や悩みを1人で抱え込まないことです。
浪人生活では、学習の成果がすぐに見えない焦りや周囲との比較から、不安を感じやすくなります。
心理学の研究によると、家族との心理的なつながりが強い受験生は、将来の目標に向けた自己投入意欲や計画性、自律性のスコアが高い傾向があるとされています。(参考:こころの健康「大学受験浪人生における家族の凝集性 ― 同一性地位判定尺度と教育的進路態度尺度の分析を中心に―」)
つまり、悩みや不安を共有できる人がいると、精神面が安定するだけでなく、やるべきことに集中する力や計画を実行する力も高まりやすくなるのです。
一方で、孤立した状態が続くと、目的を見失いやすく、モチベーションの維持も難しくなるでしょう。
学力が伸びる浪人生には、環境や感情を自分1人で抱え込まず、必要な支えを得ながら自分をコントロールできているという共通点があります。
浪人生活で成績が伸びないときに見直したい3つのポイント
この章では、浪人生活で成績が伸びないときに見直したい3つのポイントについて解説します。
ポイント①生活リズムを整える

1つ目のポイントは、生活リズムを整えることです。
浪人生活では学校のような決まった時間割がないため、生活が乱れやすくなります。生活リズムの乱れは集中力の低下や気分の浮き沈みにも影響し、結果的に学習効率に影響を与えます。
特に、自宅で勉強している浪人生は、意識的に1日の流れや1週間のスケジュールを組み立てることが大切です。
図書館やカフェなど、開館時間が決まっている場所を利用すれば、自然と起床時間や勉強を始める時間も固定されやすくなります。また、適度な運動やバランスの取れた食事、質の良い睡眠も生活リズムを整える要素です。
いきなり完璧を目指すのではなく、朝同じ時間に起きることや夜にスマホを見ないといった、小さな習慣から少しずつ整えていくのがおすすめです。
ポイント②メンタル状態を安定させる
2つ目のポイントは、メンタル状態を安定させることです。
Studyplusトレンド研究所が実施した調査によると、浪人生・浪人経験者・仮面浪人生のいずれにおいても「孤独」が浪人生活のつらさとして最も多く挙げられました。(参考:Studyplusトレンド研究所「浪人生の5割弱が現役時代に合格した大学があったと回答、浪人理由は『第一志望へのこだわり』~大学全入時代の浪人生活の実態を調査~」)
浪人期間はどうしても1人で過ごす時間が増え、周囲との関わりが薄れやすいため、自然と不安や孤独を感じやすい時期でもあります。
メンタル面の不安定さは、浪人生活におけるよくある課題であり、放っておくと集中力や学習意欲にも影響を及ぼします。自分の気持ちの揺れを責めるのではなく、「こういう時期だからこそ揺れるのは自然なこと」と捉えるのが大切です。
気持ちを安定させる環境づくりを意識していくことが、結果的に成績にも好影響をもたらすでしょう。
ポイント③スケジュールを見直す

3つ目のポイントは、スケジュールを見直すことです。
浪人生活では、自分自身で時間の使い方をコントロールする必要があります。勉強に追われる日々が続くと、つい休むことに対して後ろめたさを感じるときもあるでしょう。
例えば、この日はラーメンを食べに行く、映画を観る、友人と会うなど、楽しみにできる予定を先に決めておくと、1週間の勉強にもメリハリが生まれやすくなります。
スケジュールの見直しは、単なる時間管理ではなく、モチベーション維持にも直結する大切な工夫です。休むことを甘えと捉えず、戦略的な選択として上手に取り入れていきましょう。
浪人生についてよくある2つの質問
この章では、浪人生についてよくある質問を紹介します。
Q1.浪人が辛いのは普通ですか?
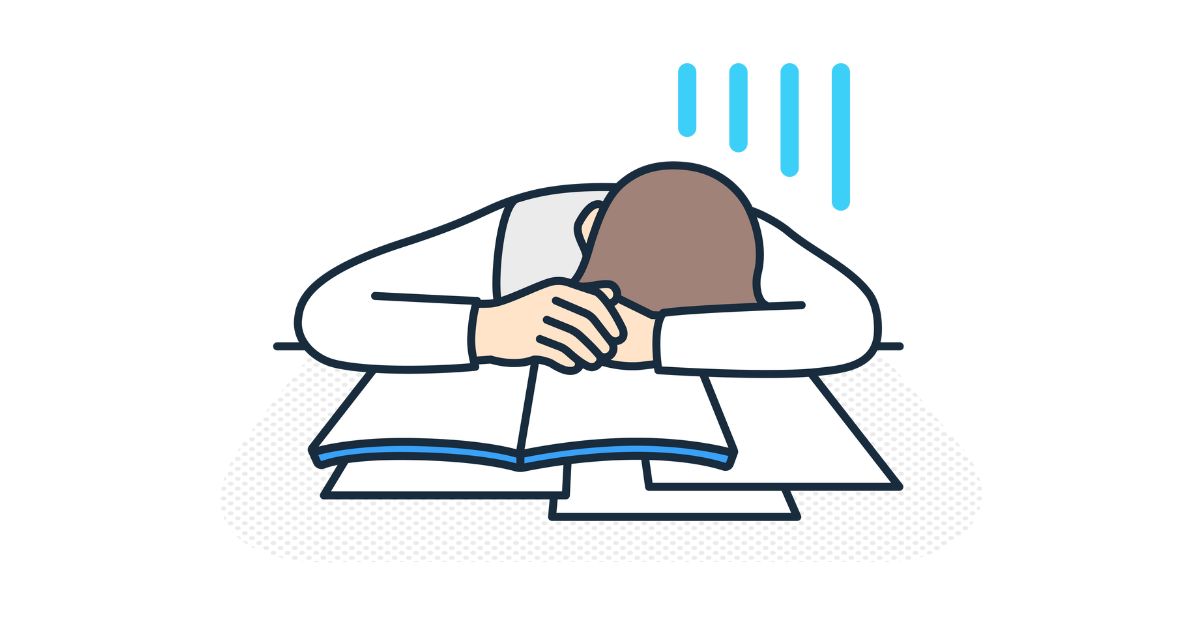
浪人生活が辛いと感じるのはごく自然なことです。
Studyplusトレンド研究所が行った調査によると、浪人生活で最も苦労した点として挙げられた内容は以下のとおりです。(参考:Studyplusトレンド研究所「浪人生の5割弱が現役時代に合格した大学があったと回答、浪人理由は『第一志望へのこだわり』~大学全入時代の浪人生活の実態を調査~」)
- 孤独を感じた人:約17%
- 成績の伸び悩みに悩んだ人:約11.2%
しかし、浪人生の約7割が「浪人して良かった」と回答していることから、浪人生活の中で感じる困難は、自分を成長させる経験にもなり得ます。
もし今、辛さを感じているのならば、それは本気で取り組んでいる証拠です。焦らず、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
Q2.浪人中は学習塾・予備校に行くべきですか?
浪人中に塾や予備校に通うべきか悩む方もいるかもしれませんが、予備校に通っている浪人生は多数派です。
Studyplusの調査によると、浪人生の約74.9%が塾や予備校を利用しているという結果が出ています。(参考:Studyplusトレンド研究所「浪人生の5割弱が現役時代に合格した大学があったと回答、浪人理由は『第一志望へのこだわり』~大学全入時代の浪人生活の実態を調査~」)
塾や予備校を活用することで、生活リズムを整えやすくなり、模試や授業を通じて自分の実力を客観的に把握できるといったメリットがあります。
また、分からない部分をすぐに質問できる環境があることも、精神的な安心につながるでしょう。
まとめ:浪人中に成績が伸びないなら、やるべきことを整理しよう

浪人生活で成績が伸び悩むと、不安や焦りが募り、どうしたらいいか分からなくなることもあるでしょう。
そんなときこそ、「伸びないのは努力が足りないから」などと自分を責めるのではなく、「今のやり方に何か見直すべき点があるのかもしれない」と一歩引いて状況を整理することが大切です。
生活リズム・メンタル・学習計画は、いずれも日々の積み重ねであり、気づかぬうちに崩れていることもあります。
成績が思うように伸びないのは、あなたの力が足りないからではなく、伸びるための土台が整っていないだけかもしれません。
気づいたときが変わるチャンスです。焦らず、自分の状態を見つめ直すところから、もう一度はじめてみましょう。
このコラムが、浪人をしていて成績が伸びずに悩んでいるあなたの助けとなれれば幸いです。
Q&A よくある質問