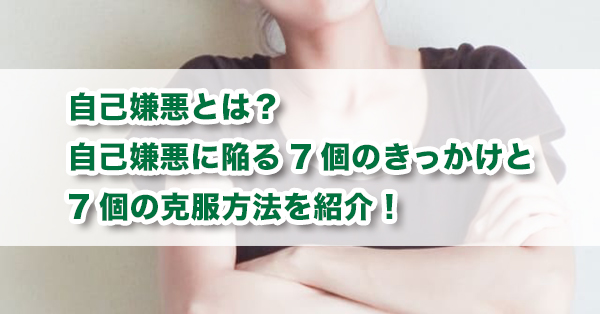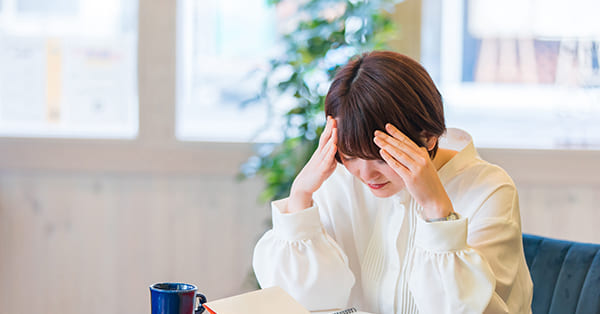サボり癖をなくしたいあなたへ 原因や改善方法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートするキズキ共育塾です。
このコラムを読んでいるあなたは、以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか?
- サボり癖が治らなくて困っている
- サボることが多いと感じている
サボり癖がある人は、意志や心の弱さが原因だと考えがちですが、その他にもサボり癖の原因はあります。
そして、サボり癖の原因や特徴を知ることで効果的な改善方法が見えてきます。
このコラムでは、サボり癖の原因や特徴、サボり癖が引き起こす注意点、サボり癖の改善方法について解説します。
ほんの少しあなたの行動を変えるだけで、サボり癖が治るかもしれません。
ぜひ最後までお読みください。
私たちキズキ共育塾は、サボり癖に悩んでいる人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
サボり癖とは?

サボり癖とは、本来やるべきことを後回しにしたり、ついダラダラと過ごしたりする習慣のことです。
勉強や仕事、家事など、日常のさまざまな場面で「あとでやればいいや」と先延ばしにするため、結果としてやるべきことがたまります。
誰でも一度は経験するものですが、サボりを繰り返していると自分自身に対する信頼感が低くなり、自己嫌悪やストレスの原因にもなります。
サボり癖を治すために大切なのは、まずその正体を知り、あなたの行動パターンを見つめ直すことです。
サボり癖の6つの原因
この章では、サボり癖の原因について解説します。
原因①モチベーションが低い
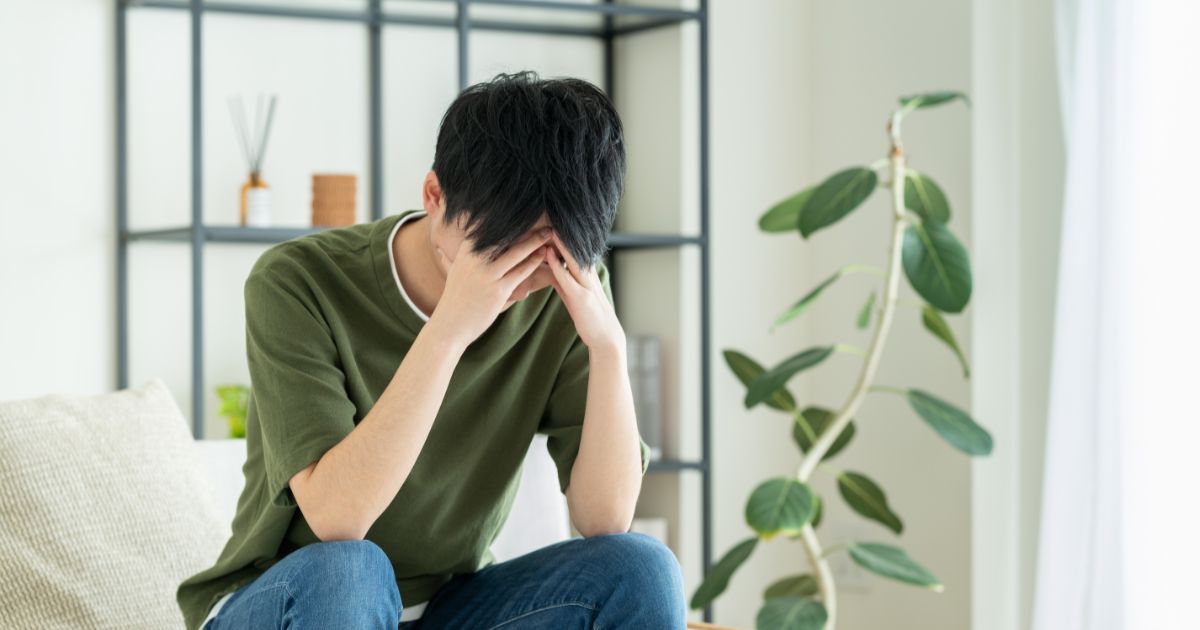
サボり癖の大きな原因のひとつが、モチベーションの低下です。
「やらなきゃいけない」と頭ではわかっていても、心が動かないと行動に移すのは難しいのです。
目標が曖昧だったり、目標を達成しても得られるメリットが見えにくかったりすると、自然とやる気は下がります。
日々の疲れやストレスの影響で、エネルギー不足になっている場合もあり、モチベーションが低い状態が続くと、何事にも無気力になりがちです。
原因②目標設定ができない/しない
明確な目標がないと、人は行動の方向性を見失いがちです。
「何をどこまでやればいいのか」がはっきりしていないと、モチベーションを持てず、結果的にサボる原因になります。
目標が漠然としていたり、大きすぎたりすると、達成までの道のりが見えないため、取り組む前にやる気を失う可能性があります。
原因③自己評価が高すぎる/低すぎる
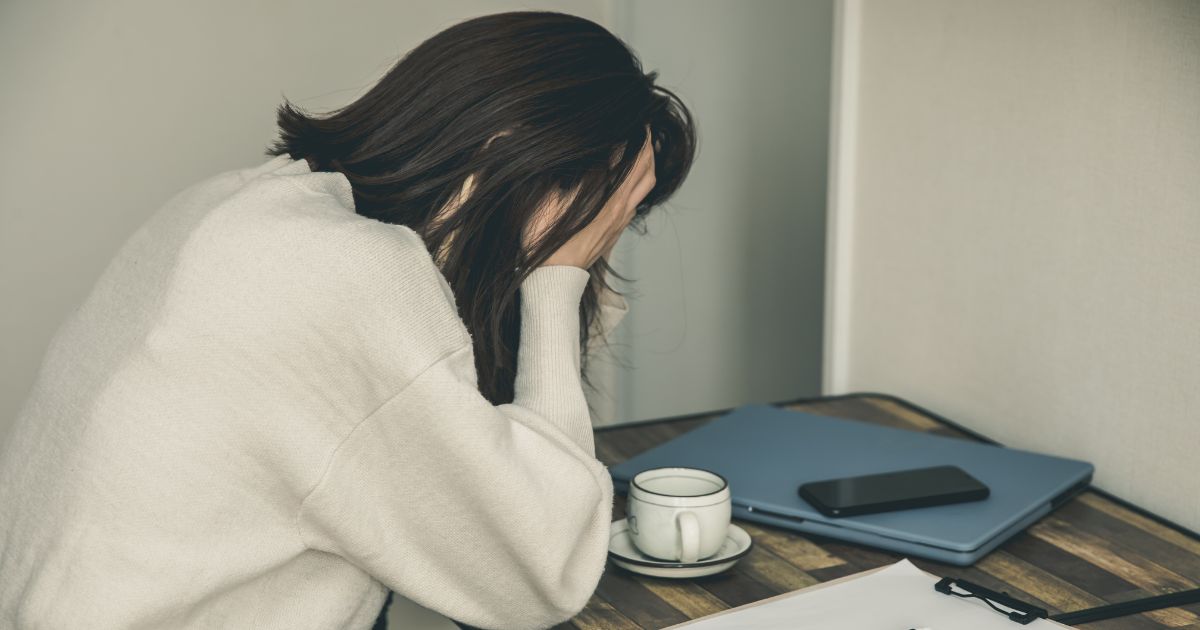
自己評価のバランスが崩れていると、サボり癖につながることがあります。
自己評価が高すぎる場合、「自分ならすぐできる」「本気を出せば大丈夫」と油断して、先延ばしにすることがあります。
反対に、自己評価が低すぎると「どうせ自分には無理」と感じ、手を付ける前からやる気を失う傾向があります。
どちらも行動を妨げる要因となり、結果的にサボる習慣を強めることになります。
原因④精神的・身体的な疲れ
サボり癖の背景には、心や体の疲れが隠れている場合も少なくありません。
人間関係や仕事、生活の忙しさなどで疲労がたまっていると、集中力ややる気が下がります。
サボり癖は、ただの怠けではなく、休息が必要なサインかもしれません。
原因⑤生活習慣や勉強リズムの乱れ

生活習慣や勉強のリズムが不規則だと、集中力ややる気が落ちやすくなり、サボり癖が強まる原因になります。
寝る時間や起きる時間がバラバラだったり、食事や運動の習慣が乱れていたりすると、心と体のバランスが崩れ、日中のパフォーマンスも低下します。
また勉強も、やったりやらなかったりと不定期だと、やるべきことを先延ばしする癖がつきやすくなります。
原因⑥学習・仕事環境の問題
学習や作業をする環境が整っていないと、集中力が続かず、ついサボることがあります。
周囲がうるさかったり、スマホやテレビなどの誘惑が多かったりすると、やる気はあっても気が散ります。
また、机や椅子が使いにくい、部屋が散らかっているなど、物理的な不快感も集中を妨げるので、サボり癖の原因になります。
サボり癖がある人の6つの特徴
この章では、サボり癖がある人の特徴を紹介します。
特徴①完璧主義

サボり癖がある人の中には、実は完璧主義の傾向が強い人がいます。
一見、真面目で努力家に思えますが、「完璧にやらなければ意味がない」と自分にプレッシャーをかけすぎるあまり、初めの一歩を踏み出せなくなるのです。
「どうせ完璧にできないなら、やらない方がマシ」と考えて行動を後回しにすることがあり、サボり癖があるように見られがちです。
特徴②マイナス思考
サボり癖がある人の中には、マイナス思考が強い傾向の人もいます。
「どうせやっても失敗する」「自分には無理だ」というように、ネガティブな考えが先行し、行動する前から諦めがちです。
やる気が起きないのは、能力がないからではなく、物事を悪い方向にばかり考えているからかもしれません。
特徴③言い訳が多い

サボり癖のある人は、何かと言い訳をして行動を後回しにすることもよくあります。
「今日は忙しかったから」「やる気が出ない」「時間がない」など、もっともらしい言い訳を並べて、自分を正当化するのです。
言い訳をすることで一時的には気が楽になりますが、やるべきことが積み重なり、後で自分を苦しめる結果になりやすいです。
特徴④楽観的で危機感が薄い
楽観的な性格は、ポジティブで良いように思えますが、サボり癖につながることがあります。
楽観的な人は「なんとかなる」「まだ大丈夫」と考え、つい行動を先延ばしにする傾向があります。
期限が迫っても焦りを感じにくいため、気づいたときには手遅れということも。
さらに危機感が薄いと、「どうせ何とかなるから」と自分を律する力が弱くなり、やるべきことを後回しにする癖がつきやすいです。
特徴⑤現実逃避している

サボり癖がある人の中には、やるべきことから目をそらして現実逃避するタイプもあります。
勉強や仕事などのプレッシャーが大きいと、ついスマホを見続けたり、動画やゲームに没頭して「今は考えたくない」と逃げの姿勢になることが多いです。
現実から目を背けても状況は変わらないどころか、むしろ問題は大きくなるばかりです。
現実逃避が習慣化すると自己嫌悪やストレスが増える悪循環に陥る可能性もあります。
特徴⑥面倒くさがり
「面倒くさい」が口癖になっている人も、サボり癖がつきやすい傾向にあります。
始める前から「大変そう」「時間がかかりそう」と考え、実際に手をつける前にやる気が失われるのです。
特に難しい勉強や時間がかかる仕事などは、ハードルが高いと思いやすく、面倒くさいと感じて取り掛からなくなります。
サボり癖がもたらす注意点
この章では、サボり癖がもたらす注意点について解説します。
注意点①自己嫌悪・罪悪感

サボり癖が続くと、「またやってしまった…」という自己嫌悪や罪悪感が蓄積します。
一度や二度ならまだしも、繰り返すことで自分自身に対する信頼感が薄れ、「どうせ自分なんて」とネガティブな思考に陥りがちです。
このようなサボり癖からくる自己嫌悪や罪悪感が、やる気や集中力の低下をもたらすだけでなく、生活全体に悪影響を及ぼすこともあります。
注意点②成長する機会を失う
サボり癖があると、目の前の課題やチャレンジに本気で取り組む機会が減ります。
本来なら新しいスキルや知識を得られるチャンスを、自分で遠ざけている状態です。
小さな努力の積み重ねが成長につながるものですが、サボることで成長の継続性がなくなり、あなたの可能性を狭めていきます。
また、努力や挑戦から得られる達成感や成功体験を感じることが少なくなり、自信を持てなくなることもあるでしょう。
注意点③周囲からの信頼や評価の低下
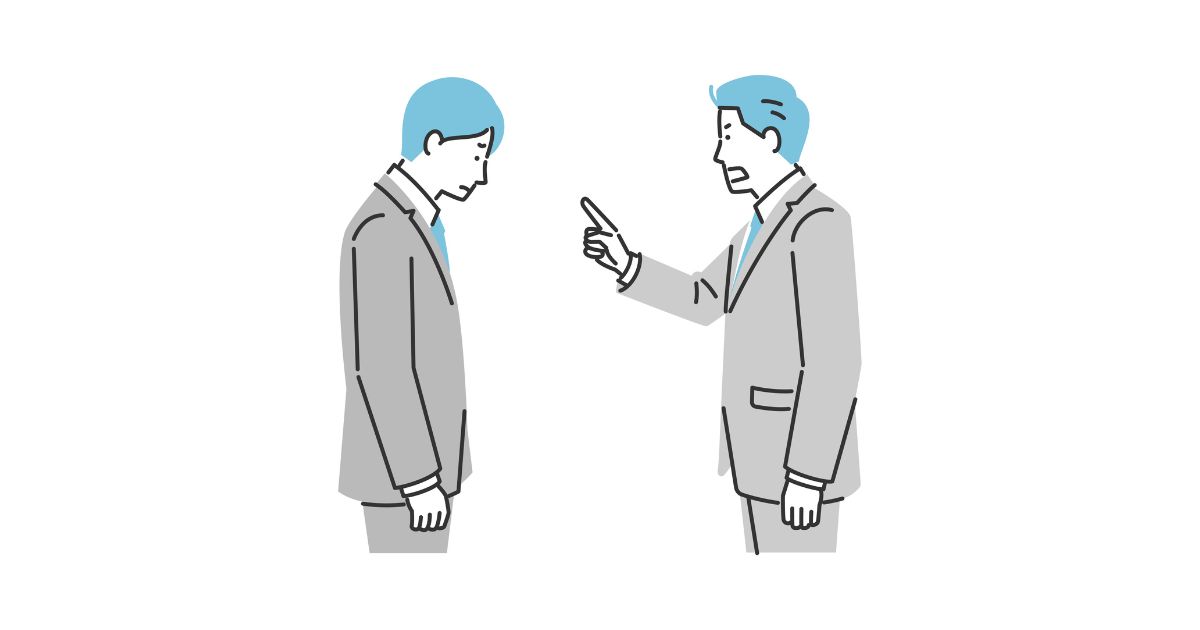
サボり癖が続くと、周囲からの信頼や評価に影響が出てきます。
「頼んでもやってくれない」「やる気が感じられない」などと思われて、仕事や人間関係でチャンスを失うこともあります。
学校など集団で動く場面では、他人に迷惑をかけているという意識が強くなり、あなた自身にもプレッシャーがかかります。
その結果、新しい役割を任せてもらえなかったり、人間関係がぎくしゃくしたりと、悪循環に陥るリスクが高まります。
注意点④将来の選択肢が狭まる
サボり癖が続くと、経験や実績を思うように積むことができず、将来の選択肢が狭くなる可能性が出てきます。
あとから「やっておけばよかった」と後悔しても、過ぎた時間は戻りません。
例えば、学校での授業や宿題をおろそかにすると、学力が伸びずに希望の進路を選べなくなることがあります。
部活動や委員会などでも積極的に関われないと、人間関係や経験の幅が狭まりがちです。
努力を避けるクセがつくと、新しい環境に踏み出す勇気も持ちにくくなり、あなたの可能性を狭める結果になります。
今の選択が未来の選択肢を左右することを忘れてはいけません。
注意点⑤セルフネグレクトへの可能性

サボり癖が深刻になると、自分自身の管理すらおろそかになる場合があります。
食事や睡眠、掃除、身だしなみなどの日常生活の基本すら放置する状態が続き、いわゆるセルフネグレクトに陥るリスクも含んでいます。
心身の健康に悪影響が出るだけでなく、社会とのつながりも薄れていき、孤立感が強まる可能性もあります。
サボり癖の改善方法
この章では、サボり癖の改善方法について解説します。
改善方法①やるべきことを書き出して見えるようにする

サボり癖をなくすために大切なのは、まず何をすればいいかをはっきりさせることです。
頭の中だけで考えていると、やるべきことがごちゃごちゃになり、「あとでいいや」と後回しにしがちになります。
そこでおすすめなのが、やることを紙やスマホのメモアプリに書き出すことです。
以下のように、具体的にリスト化しましょう。
- 提出課題のワークを3ページ
- 英単語テストの勉強を30分
- 友達への返信タイムを30分
書き出すことで、頭の中が整理されて行動に移しやすくなります。また、終わったらチェックをつけることで達成感も得られます。
やるべきことを見えるようにするだけで、気持ちが前向きになる効果もあります。
改善方法②期限を決める
サボり癖を改善するには、いつまでにやるかを明確にするのが効果的です。
「テスト勉強を始める」ではなく、「今週土曜までに英語の単語50個を覚える」というように、具体的な期限を設定しましょう。
人は締め切りがあると集中力が高まりやすくなります。
また、期限を決めて勉強や仕事に取り組むと、テストや締め切り直前に焦るのを防ぐことができます。
期限が遠すぎると逆にやる気が出ないことがあるので、なるべく短めに、例えば1週間以内などと期限を決めるのがポイントです。
スマホのカレンダーや付箋を活用し、すぐにやる癖をつけていきましょう。
改善方法③目標を小さく設定してごほうびを用意する

「やる気が出ない」「面倒くさい」と感じるのは、目標が大きすぎることが原因かもしれません。
そんなときは、目標を小さく分けて取り組んでみましょう。
「数学の問題集を1冊やる」ではなく、「今日は5ページだけやる」という感じです。
達成しやすい小さな目標をクリアするたびに、「終わったらスマホ10分OK」など、自分にごほうびを用意するとやる気をキープしやすくなります。
小さな達成感を積み重ねることで、「やればできる」という自信も育っていきます。
改善方法④「明日やろう」を無くし、すぐにやる
「明日やればいいや」と思って後回しにしてしまうと、結局ずっと手をつけないまま…なんてこと、ありませんか?
サボり癖を改善するには、思いついたらすぐやる癖をつけることが大切です。
課題を出されたら「5分だけ手をつける」など、ハードルを下げてよいので、即行動するようにしましょう。
初めの一歩を踏み出すと、意外とそのまま進められることも多いです。
すぐやることは、サボり癖を改善する一番の近道。明日ではなく、今動く意識を持ってみましょう。
改善方法⑤日記で振り返りを習慣化する
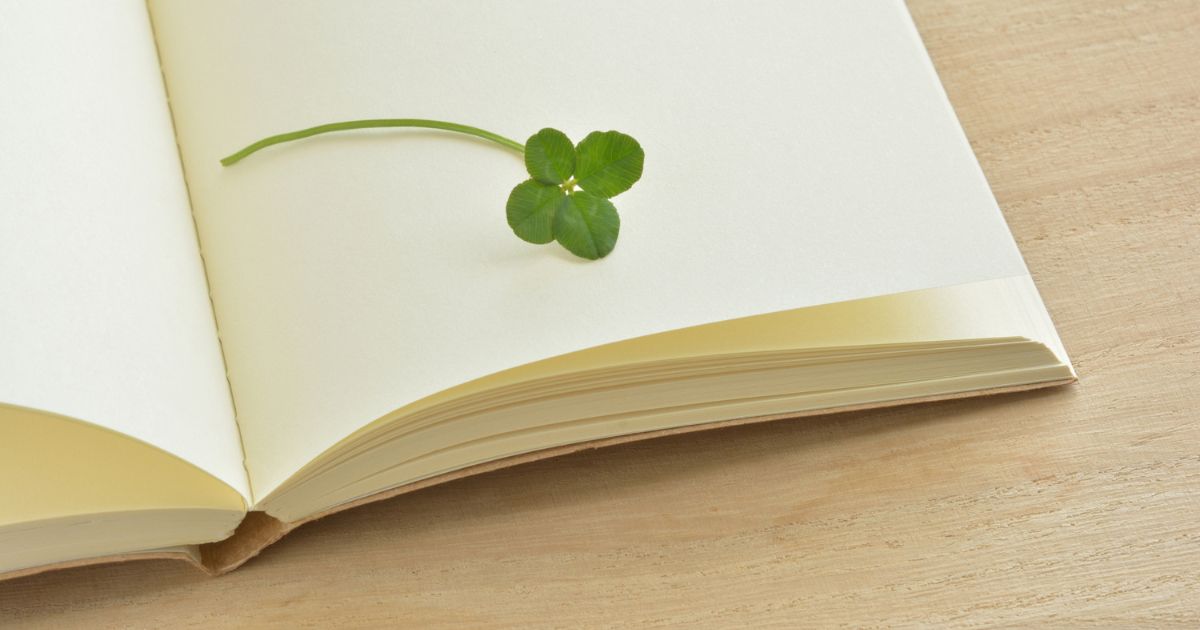
サボり癖を直すには、あなたの行動を振り返る習慣も大切です。
おすすめは1日5分の簡単な日記です。
例えば、以下のようなことをノートやアプリに書いてみましょう。
- 今日やったこと
- うまくできたこと
- 次にやりたいこと
あなたの努力が見える化され、達成感ややる気アップにつながります。
また、「今日はちょっとサボっちゃったな…」と振り返ることで、次の日からの改善にもつながります。
100点満点の完璧を目指す必要はなく、続けることが一番のポイント。
自分自身と向き合う時間が、サボり癖を少しずつ減らしてくれます。
改善方法⑥周囲とのコミュニケーションを大切にする
ひとりでサボり癖を克服しようとすると、途中で挫折することがあります。
そんなときは、家族や友達、先生など信頼できる人とコミュニケーションをとるのがオススメです。
例えば、「明日までに英語の課題やるって決めた!」と友達に宣言したり、「最近やる気が出ない」と家族や先生に悩みを話したりするだけでも、気持ちがスッキリして前向きになれます。
人に話すことで「やらなきゃ」という意識も高まるでしょう。
ひとりで抱え込まず、周囲の協力を得ながらサボり癖を改善していきましょう。
改善方法⑦十分な休息をとる

サボり癖の裏には、実は疲れやストレスがたまっていることもよくあります。
心や体が限界に近づくと、やる気が出ず、ついダラダラするのは自然なことです。
だからこそ大切になるのが、意識的に休む時間を作ることです。
夜はスマホを早めにやめてぐっすり寝たり、週末は好きなことをしたりして、自分なりのリラックス方法を取り入れてみましょう。
しっかり休むことで集中力が回復し、行動に移す心も軽くなります。
頑張ることも大事ですが、休むことも大切にして無理しすぎないようにしましょう。
改善方法⑧やる気が高まることをする
やる気が出ないときは、無理に始めようとしてもなかなか動けません。
そんなときは、まずあなたのやる気スイッチを押しましょう。
あなたの気分が上がることを取り入れるのがオススメです。
- お気に入りの音楽を聴く
- 成功している人の動画を見る
- 朝シャワーを浴びる
- 軽くストレッチする
- 体を動かす
- 好きな文房具を使う
気分が変わると自然と心が前向きになり、勉強などを頑張るきっかけになります。
あなたに合ったやる気を高める習慣を見つけて、うまく活用してみてください。
改善方法⑨生活リズムや環境を整える

サボり癖を改善するには、毎日の生活リズムや環境を見直すことも大切です。
不規則な睡眠や食事、散らかった机などは、集中力ややる気を下げる原因になることがあります。
まずは、朝決まった時間に起きる、勉強前に机の上を片付けるなど、小さな習慣から整えていきましょう。
勉強に集中できる静かな場所を確保したり、スマホを別の部屋に置いたりして、環境を少し整えるだけでもサボり癖を改善する効果があります。
環境が整うと、自然と気持ちも前向きになり、心地よい生活リズムが行動の土台をつくってくれるはずです。
まとめ:できることから始め、サボり癖を治していこう

サボり癖は、単なる怠けではなく、やる気や自己評価、生活習慣などさまざまな要因が複雑に絡み合って生じます。
そのため、自分を責めすぎず、原因や特徴を理解することが大切です。
今回ご紹介した改善方法を少しずつ実践していくことで、習慣や思考に変化が生まれ、サボり癖の克服につながります。
「変わりたい!」と思ったその気持ちこそ、改善への第一歩です。
あなたのペースでできることから焦らずに取り組んでいきましょう。