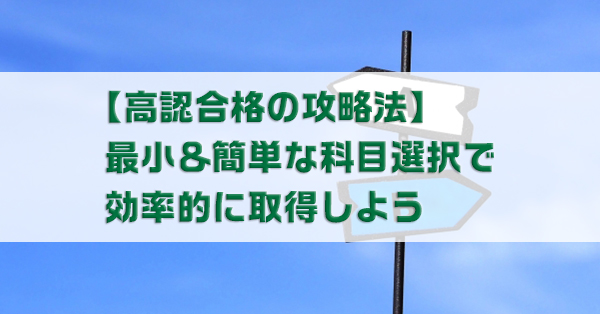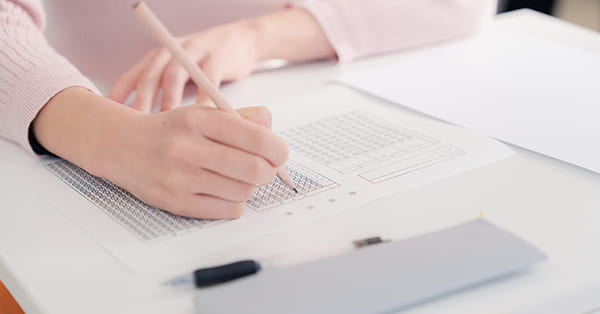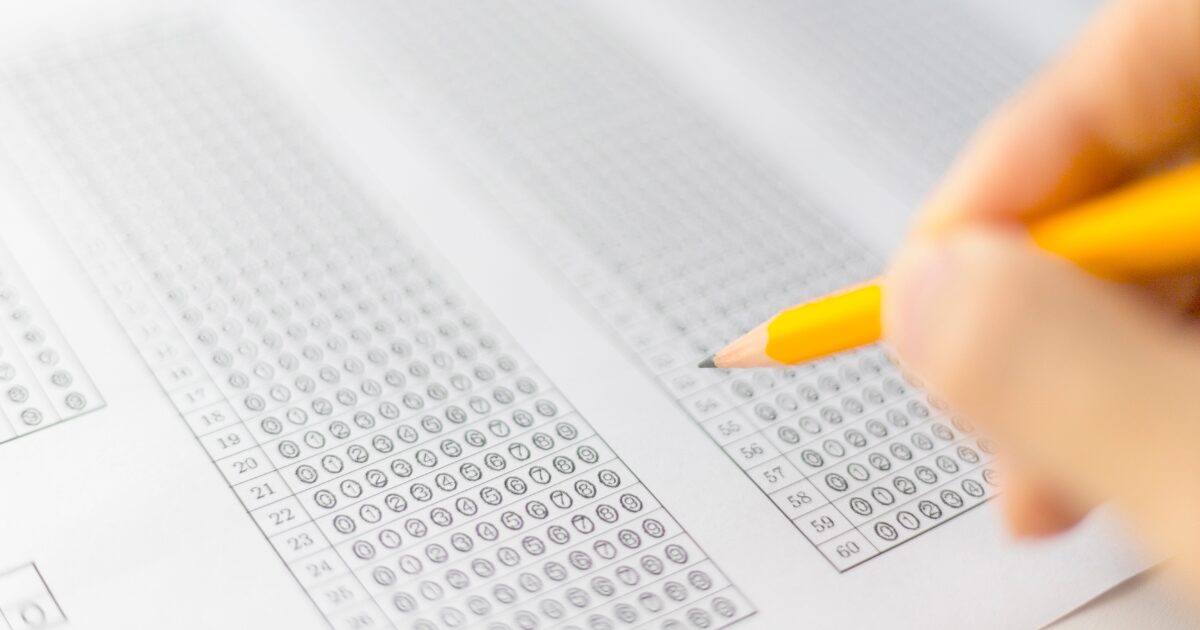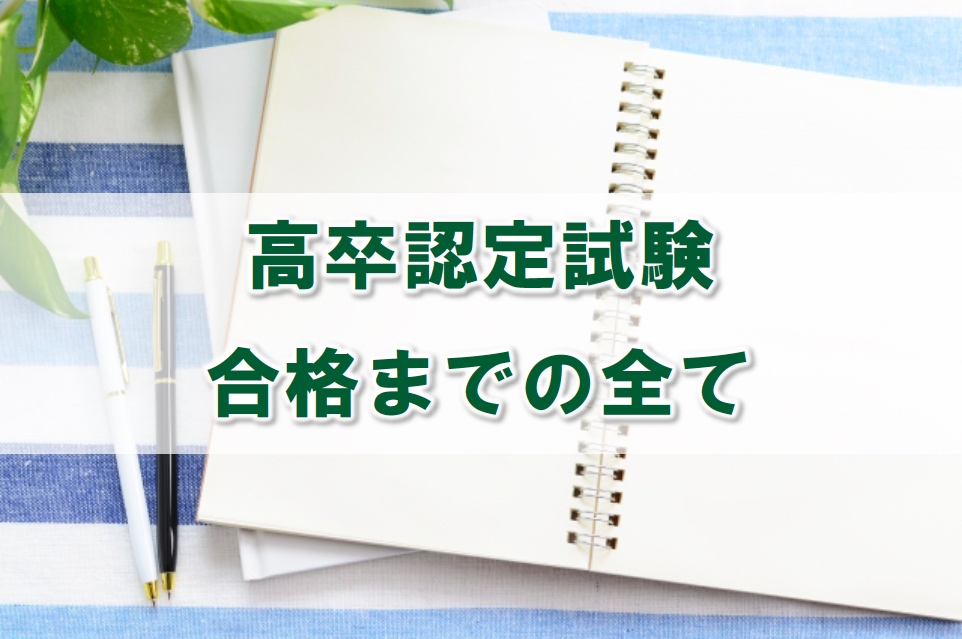高卒認定試験とは? 内容、メリット、受験までの流れを解説
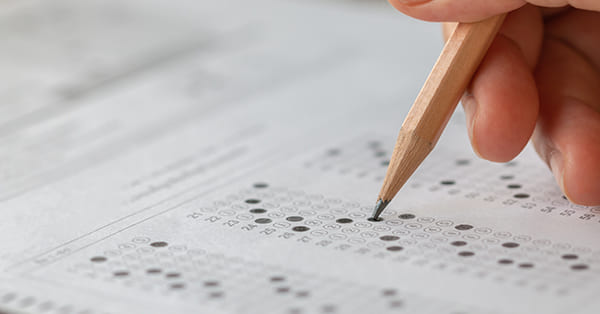
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
高卒認定試験という言葉を何となく知ってはいても、具体的な試験内容やどんなメリットがあるのかなど、細かな点をご存じない人は多いと思います。
このコラムでは、高卒認定試験の概要やメリット、受験までの流れについて解説します。
試験科目や受験料の他に、難易度や合格ラインといった多くの人が気になる詳細についても徹底解説します。高卒認定試験について網羅的に知りたいという人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
私たちキズキ共育塾は、高卒認定の取得を目指している人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
高卒認定試験とは?

この章では、高卒認定試験の概要や受験資格、受験料・費用などについて解説します。
高卒認定試験を攻略するには、まず概要を知る必要があります。特に日程や費用、免除科目などは気になる人も多いので、チェックしておきましょう。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」、文部科学省「参考 高等学校卒業程度認定試験Q&A」)
高卒認定試験の概要
高卒認定試験(正式名称:高等学校卒業程度認定試験)は、文部科学省が実施する高校を卒業した人と同等以上の学力を認定する試験のことです。正式名称を高等学校卒業程度認定試験と言い、高認とも呼ばれています。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」)
合格者には、大学・短大・専門学校の受験資格が与えられるほか、一部の国家資格や公務員試験の受験が可能になります。
つまり、高校中退などで最終学歴が中学校卒業(中卒)になった人や、何らかの事情で高校進学を断念して社会に出た人などが、改めて「大学に進学したい」と思ったときに利用できる試験です。
高卒認定試験の受験資格

高卒認定試験は、「その年度で満16歳以上になる人のうち、大学入学資格のない人」が受験できます。
ここで言う「大学入学資格がない人」というのは、以下のような学校を卒業していない人、また以前に高卒認定試験や大検(大学入学資格検定)に合格したことがない人を指します。
- 高校
- 中等教育学校
- 高等専門学校(高専)
- 専修学校高等課程
より簡単に言うと、中卒の人、高校を中退した人、高校在学中の人などが対象です。
なお、以上の学校に所属しているが不登校となっている状態でも、高認は受験可能です。
高卒認定試験の受験料・費用
受験料は、高卒認定に必要な受験科目数によって異なります。
| 受験科目数 | 受験料 |
|---|---|
| 7科目~10科目 | 8,500円 |
| 4科目~6科目 | 6,500円 |
| 1科目~3科目 | 4,500円 |
なお、免除科目については、受験料はかかりません。
この受験料は、特に若い受験生にとって、きっと安い金額ではないと思います。願書を送るときまでに、親御さんなどに相談をした上で、必要な受験料を支払う準備をしておきましょう。
高卒認定試験の試験科目・免除科目と合格要件〜2024年変更点更新〜

高卒認定を取得するためには、全部で8〜9科目の試験に合格する必要があります。
合否は科目別に判定され、必要な全ての科目で合格すると「高卒認定資格」取得となります。
2024年度からの試験科目・合格要件は、以下のとおりです。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験における試験科目、合格要件、出題範囲の変更等について」 )
| 教科 | 試験科目 | 合格要件 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 必須 |
| 数学 | 数学 | 必須 |
| 英語 | 英語 | 必須 |
| 地理歴史 | 地理 | 必須 |
| 歴史 | 必須 | |
| 公民 | 公共 | 必須 |
| 理科 | ・科学と人間生活 ・物理基礎 ・化学基礎 ・生物基礎 ・地学基礎 |
以下の①②のいずれかが必修 ①科学と人間生活を含む2科目 ②科学と人間生活以外の3科目 |
ちなみに、1回の試験で全ての科目に合格する必要はなく、全ての科目で合格するまで何回でも受験可能です。
そして、一度合格となった科目はその後ずっと有効で、再度試験を受ける必要はありません。
また、高校での勉強の進み具合(=取得単位数)によっては、受験を免除される科目もあります。
特に、高校で2年生以上まで進級した人には、免除科目が発生する場合があります。
高卒認定試験に向けて勉強される前に、確認しておきましょう。
自分に免除科目があるかどうかを知るには、まず在籍している(していた)高校の取得単位を確認した上で、免除要件と照らし合わせる必要があります。
免除に必要な単位数などは、文部科学省が公表している「免除要件」で確認してみてください。(参考:文部科学省「免除要件」)
さらに、学校の単位以外にも、以下の検定で各1級(特A級)や2級に近い合格実績があると、受験が免除になる科目があります。(参考:文部科学省「知識及び技能に関する審査(技能審査)の合格による免除要件」)
- 歴史能力検定
- 実用数学技能検定
- 実用英語技能検定
- 英語検定試験
- 国際連合公用語英語検定試験
なお、実際に科目免除を申請するためには、受験願書とあわせて「単位修得証明書」を提出する必要があります。在籍していた高校に前もって発行をお願いしておきましょう。
出願までの流れは、こちらの章を参考にしてください。
また、全ての科目で免除要件を満たしていても、最低1科目は受験して合格する必要がある点には注意しましょう(逆に言うと、1科目だけ合格すれば全ての科目で合格扱いになる人もいるということです)。
高卒認定試験のスケジュール・試験日程
高卒認定試験は、毎年2回実施されています。
実施の1回目は夏(8月初旬)、2回目は秋(11月初旬から中旬)です(※詳細な日程は年によって異なるので、受験を考えている方はしっかり確認しましょう)。
参考として、2023年度(令和5年度)の年間スケジュールは以下のとおりです。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」)
| 第1回試験 | 第2回試験 | |
|---|---|---|
| 受験案内・願書の配布開始 | 4月3日 | 7月18日 |
| 出願の受付 | 4月3日〜5月8日 (消印有効) |
7月18日〜9月8日 (消印有効) |
| 試験日 | 8月3日・4日(木) | 11月4日・5日 |
| 結果通知 | 8月29日発送予定 | 12月5日発送予定 |
出願書類・受験案内は、文部科学省や各都道府県の教育委員会の窓口、インターネット、電話を通じて取り寄せることができます。
しかし、取り寄せには少し時間がかかります。試験日程に備えて勉強することも大事ですが、事前に出願の日程はしっかりと確認しておきましょう。
特に1回目の申し込みは、出願の期限直前にゴールデンウィークを迎えることがあります。
郵便や受付窓口が閉まっていると、出願方法の確認や出願申請書の郵送ができない日もあるので注意しましょう。
また、1回目と2回目の試験を連続して受験する場合、2回目の出願は、1回目の試験の結果が通知されたすぐ後に締切となります。
1回目の結果がよくないと、2回目を受験するためのモチベーションが湧きづらいかもしれません。ですが、ここでも気持ちを切り替えてすぐに出願準備をすることをオススメします。
なお、1回目・2回目ともに、出願してから試験までは大体2か月から3か月ほどの時間があります。
勉強する期間は十分にあるため、計画を立てて前向きな気持ちで臨むようにしましょう。
高卒認定試験の時間割

高卒認定試験は、例年「9:30~17:30」の時間帯で、休憩を挟んで行われます。
参考として、令和5年度(2023年度)の時間割は以下の通りです。(参考:文部科学省「時間割」)
| 1日目 | 2日目 | |
|---|---|---|
| 1時間目 (9:30〜10:20) |
物理基礎 | 倫理 |
| 2時間目 (10:50〜11:40) |
現代社会または政治 経済 |
日本史A、日本史B、 地理A、地理Bいずれか1科目 |
| 3時間目 (12:40〜13:30) |
国語 | 世界史Aまたは世界史B |
| 4時間目 (14:00〜14:50) |
英語 | 生物基礎 |
| 5時間目 (15:20〜16:10) |
数学 | 地学基礎 |
| 6時間目 (15:20〜16:10) |
科学と人間生活 | 化学基礎 |
時間割を参考にして勉強計画を組み立てることもあるでしょう。時間割は重要な情報なので、必ず確認しておくことをオススメします。
高卒認定試験の受験者数・合格者数
高卒認定試験は、ここ数年で例年約2万人以上が受験をし、そのうち約8000人が合格(8~10科目全科目合格)しています。
また、受験者には、不登校などの事情で学校に通えない人、やむを得ない事情で高校中退をした人など、様々な背景を持った人がいます。
ちなみに、2022年度(令和4年度)の最終学歴別の出願者数の内訳では、高校を中退している人が約47.6%(9354人)と半数近くを占めています。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験パンフレット(一般用)」)
| 受験時の最終学歴 | 割合(人数) |
|---|---|
| 中学校卒業 | 14.6%(2,867人) |
| 高校中退 | 47.6%(9,354人) |
| 全日制高校在学 | 13.4%(2,643人) |
| 定時制・通信制高校在学 | 18.9%(3,722人) |
| 高専中退 | 0.8%(159人) |
| その他 | 4.6%(908人) |
2022年度(令和4年度)度第2回試験の合格者の年齢分布は、以下のとおりです。(参考:文部科学省「令和4年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」)
| 年齢 | 合格者の人数 (全合格者中の割合) |
|---|---|
| 16歳~18歳 | 2426人(約58.2%) |
| 19歳~20歳 | 526人(約12.6%) |
| 21歳~25歳 | 351人(約8.4%) |
| 26歳~30歳 | 224人(約5.4%) |
| 31歳~40歳 | 395人(約9.5%) |
| 41歳~50歳 | 191人(約4.6%) |
| 51歳~60歳 | 44人(約1.1%) |
| 61歳以上 | 8人(約0.2%) |
合格者の年齢の内訳は、16歳〜18歳の人、つまり一般的には高校生の年齢の人2426人を中心として、幅広い年代で構成されています。
なお、合格者の平均年齢は22.2歳、同最高年齢は80歳です。多様な背景を持つ人が、高卒認定試験を受験していることがわかります。
補足:高卒認定試験と大学入学資格検定の違い
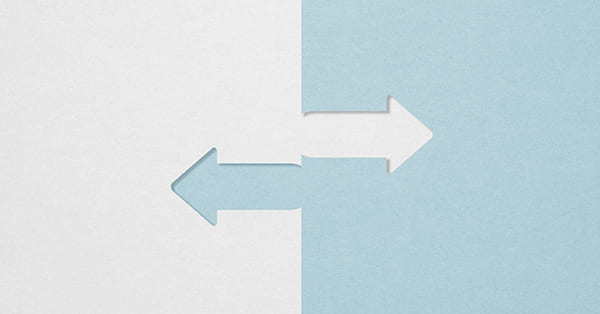
大学入学資格検定は、合格することで大学入学資格を得ることができる、高卒認定試験開始以前の検定試験です。大検とも呼ばれています。
2004年度(平成16年度)末に、大学入学資格検定は廃止になりました。大学入学資格検定の方が馴染みがあるという人もいるかもしれません。
しかし、大学入学資格検定から高卒認定試験に切り替わる際に、厳密には以下の違いが生じています。
- 9科目の試験科目が8~9科目に(2024年変更後)
- 必修科目の家庭と選択科目の簿記、保健が廃止
- 英語が必修科目として追加
- 高校等に在籍している人も受験可能
したがって、大検は単に高卒認定試験の以前の名前というわけではなく、内容も多少異なったものになっています。
高卒認定試験の難易度と合格ライン

高卒認定試験に合格するためには、高校1年生レベルの学力があれば充分だと言われています。なぜなら、試験の範囲は、基本的には1年生で習う内容だからです。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験_試験科目・合格要件・出題範囲」)
また、各科目の合格点はおよそ40点とされているため、満点を目指す必要はありません。なお、正式な合格ラインは公表されていませんが、通説としてそのように認識されています。
そのため、基礎的な学力を固めたり、科目ごとにきちんと過去問を解いたりと、基本的な対策を丁寧にすれば合格は可能です。
大学受験などに比べると、簡単な試験であると言えるでしょう。
しかし、文部科学省の発表によると、全科目の合格率は、ここ最近40%台となっています。2022年度(令和4年度)では、約46.4%でした。(参考:文部科学省「令和4年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」)
合格率が低い原因として考えられるのは、高卒認定試験の科目数が多いことです。科目数が多いことで、勉強が間に合わない科目が出てくることがあるのです。
また、通信制高校などで教科の単位を取得するために、一部の科目のみを受けた人がいるのも理由の一つでしょう。
ただ、一度合格した科目は、その後も合格扱いになります。そのため、次の高卒認定試験を受ける時は不合格だった科目に集中して勉強できるのです。
なお、高卒認定試験の成績が大学受験の出願時にチェックされることがあります。推薦入試や総合型選抜入試での大学受験を考えている場合は、なるべく高得点を目指してみましょう。
最終学歴は高卒?高卒認定試験と高卒資格の違い

高卒認定試験に合格したら、最終学歴は高卒になると思っている人もいるかもしれません。
実際には、高卒認定試験に合格しても、最終学歴は中卒のままです。
高卒認定試験は、あくまでも高校卒業程度の学力があることを認定する試験であり、厳密には学力を証明する資格です。
一方、高卒資格(高校卒業資格)は、全日制高校・定時制高校・通信制高校などの高等学校において、卒業要件を満たした人に与えられる資格です。
つまり、高卒認定試験に合格しても、高校を卒業していなければ、履歴書などの学歴欄に高等学校卒業と記載することはできません。
高卒認定試験に合格しただけでは、就職活動などで募集条件が高卒以上と設定されている求人には原則応募できないため、注意が必要です。
ただし、資格試験や公務員・民間企業の採用試験などでは、高卒認定試験の合格を高卒と同様に扱うところもあります。
いずれにせよ、高卒認定試験人生の選択肢が広がるため、取得を目指して損はない資格と言えるでしょう。具体的に気になる求人があるならば、その求人を公開している企業に確認してみてください。
高卒認定試験に合格するとできること4点
高卒認定試験に合格することで、できることを4点紹介します。
①大学・短大・専門学校の受験資格が得られる

高卒認定試験に合格すれば、高校を卒業していなくても、大学・短期大学・専門学校の受験資格が与えられます。
これは、何らかの事情があって高校を卒業していない人にとっては、うれしいポイントでしょう。たとえ高校を卒業できていなくても、大学・短大・専門学校へ通いたいという思いをあきらめる必要はないのです。
中卒からの大学受験については下記コラムで解説しています。興味がある方はぜひ読んでみてください。
ただし、大学・短期大学の受験が可能になるのは、18歳になる年度からです。高卒認定試験に早く合格した場合でも、18歳になる年度までは大学受験をすることはできません。
専門学校は必ずしもこの限りではないため、各学校に問い合わせて確認をしてみましょう。
なお、高卒認定試験合格を経て大学・短大を受験するときは、高卒認定試験の「合格証明書」または「合格成績証明書」の提出が必要です。
各書類は、文部科学省に申請すると、何枚でも発行できます。発行の際は、1通あたり250円の手数料と、枚数に応じた郵送料が必要です。
また、高卒認定試験の全科目に合格しておらず、残りの科目を高校の取得単位で免除する予定の場合は、「合格見込成績証明書」が必要です。
高校での取得単位によって、高卒認定試験の受験を免除された科目がある場合は、「高校による成績証明書」が必要な場合もあります。
高卒認定試験を経て大学・短期大学を受験するときは、忘れないようにしましょう。
②高校で高卒認定の合格科目を単位認定してもらえる場合がある
通信制高校や定時制高校の一部では、高卒認定試験の合格科目を単位として認定している場合があります。
基本的に単位制の高校は「卒業には○○単位の取得が条件」となっているので、高卒認定試験の合格科目を単位認定してもらえると、卒業に必要な単位数が減ります。
そのため、卒業までに4年間の在籍が必要な定時制高校でも、高卒認定試験に合格することで、3年間で卒業できることがあるのです。
単位認定が可能かどうかは、前もって各学校の担当窓口で確認してみましょう。申請の際には高卒認定試験の「合格証明書」などが必要になるため、発行手続きは早めに進めておくのがオススメです。
③一部の国家資格や公務員試験を受験できる

高卒認定試験に合格すると、一部の国家資格や公務員試験の受験資格が得られます。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験の合格を高等学校卒業と同等とみなしている採用試験、国家資格一覧」)
一例は、以下のとおりです。
- 公務員試験(一般職や税務職員など)
- 国家資格(幼稚園・小学校教員、保育士など)※別途実務経験などが必要な場合あり
また、地方公務員の採用でも、「高卒扱い」で試験を受けられる場合があります。
ただ、大学受験同様に、試験ごとに必要な提出書類や受験可能となる年齢が設定されている場合がありますので、実際に受験を考えている方は要項をきちんと確認しましょう。
④高卒資格が必要な民間企業に就職できる場合がある
先述したように、高卒認定試験合格は「高卒資格」とは異なります。
しかし、「高卒(見込み)」が応募条件の民間企業であっても、高卒認定試験を取得しておくと就職できる場合があります。
応募条件を定めるのは、原則として企業側です。そのため、「高卒(見込み)」の捉え方は企業によって変わります。
就職を視野に入れている方は、高卒認定試験に合格していることを企業に伝えてみるといいでしょう。
高卒認定試験を受けるメリット4点
高卒認定試験に合格しても、最終学歴は「高卒」とはなりません。
そのため、高校卒業に比べて高卒認定試験は、「あまりメリットがない」と考える人もいます。
しかし、高卒認定試験は、そもそも「何らかの事情で高校を卒業していない(できなかった)人」を対象にしているため、高校卒業とは一概に比較できるものではありません。
それに、高卒認定試験には、高卒認定試験なりのメリットがあります。
この章では、そうした高卒認定試験を受ける以下4つのメリットを紹介します。
メリット①不登校や中退からでも合格を目指せる

1つ目のメリットは「不登校や中退からでも合格を目指せる」です。
先述したように、高卒認定試験の受験者数には、不登校の学生さんや高校を中退した方が少なくありません。
実際に、私たちキズキ共育塾からも、不登校・中退を経験後に大学受験を目指して高卒認定試験を受け、合格した生徒さんがたくさんいます。
実例はこちらの章で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
高校のように、数年に渡って学校へ通い続けたり、一般的な集団授業に付いていったりするのが難しいという生徒さんも一定数います。そのような生徒さんにとっては、高卒認定試験合格から大学を目指せることはメリットと言えます。
メリット②試験慣れできる
2つ目のメリットは「試験慣れできる」です。
高卒認定試験に合格した後、大学受験を受ける方もいるでしょう。
高卒認定試験にしろ大学受験にしろ、問題を解く時間が決まっています。そのため、時間内に回答を記入しなければなりません。
普段から時間を意識して勉強していても、本番特有の緊張感のせいで、時間内に問題を解き切れなかったということはよくあります。
これは、試験慣れしていないことが一つの原因です。何事も初めて経験するときは、緊張して本来の力を出しにくいものですよね。
高卒認定試験を一度経験していると、大学受験のときに余裕が生まれやすくなります。試験の流れや休み時間の過ごし方などを経験していれば、落ち着いて臨めるでしょう。
大学受験を受ける方にとって、試験という形式を経験できるのは大きなメリットと言えます。
メリット③高校に通い直すよりも費用がかからない

3つ目のメリットは「高校に通い直すよりも費用がかからない」です。
文部科学省の調査によると、2021年度(令和3年度)の全日制高校における、1年当たりの学習費総額平均は以下のようになっています。(参考:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果を公表します」)
- 公立高等学校…51万2971円
- 私立高等学校…105万4444円
全日制高校に再入学して卒業を目指すと、それなりの費用が必要です。
一方、高卒認定試験の場合、自力で勉強を進められるのであれば、基本的には参考書や問題集の代金と受験料しかかかりません。
高卒認定試験対策塾に入って指導を受けるとしても、多くの場合は月謝単位での授業料の支払いになるため、再入学をするよりは安く済むと考えられるでしょう。
メリット④複数回に分けて受験できる
4つ目のメリットは「複数回に分けて受験できる」です。
高卒認定を取得するためには、全部で8〜9科目の試験に合格する必要があります(2024年変更後。免除科目がある場合を除く)。
ですが、1回の試験で全科目に合格する必要はありません。
複数回に分けて、受験したい科目だけを受験することができます(=1回合格した科目は、ずっと合格扱いになります)。
「今年の1回目の試験で5科目を受験して、2回目の試験で残りの4科目を受験する」などの、勉強・受験スケジュールの分割も可能です。
また、1度目の試験で複数科目を受験して不合格の科目があった場合、2度目はその科目に絞って勉強できます。
高卒認定試験の申し込みの流れ
高卒認定試験の申込の流れについて、順を追って、詳細を見ていきましょう。(参考:文部科学省「令和5年度 第2回高等学校卒業程度認定試験受験案内」 、文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」)
流れ①出願書類(受験案内)の入手

高卒認定試験を受験するためには、文部科学省に出願書類を提出しなくてはなりません。そのため、まずは出願書類(受験案内)を入手しましょう。
出願書類(受験案内)の入手方法には、以下の2つがあります。
- パソコンおよびスマートフォンで資料請求を行う(インターネット申し込み)
- 配布施設に直接取りに行く
パソコンおよびスマートフォンで資料請求を行う(インターネット申し込み)の場合
文部科学省が認証している「テレメール資料請求受付サイト」から必要項目を入力して申請を出すと、発送からおおよそ3〜5日以内に資料が届きます。
請求の際は215円の送料とともに、別途手数料が必要です(速達を利用する場合は600円)。
また、速達対応期間は例年数日程度と短く、年によって異なりますので、文部科学省のウェブサイトで必ず確認するようにしましょう。
配布施設に直接取りに行く場合
出願書類(受験案内)は、文部科学省と各都道府県の教育委員会で配布されます。
都道府県によっては、各市区町村の窓口で配布している場合もあります。
具体的な配布場所や市区町村での配布については、各都道府県の教育委員会に問い合わせてみましょう(受付時間は平日の9時〜17時が多いです)。
連絡の際は、まず教育委員会に電話をかけてみましょう。電話番号が分からなければ、都道府県庁の代表番号にかけて、教育委員会に繋いでもらったり番号を教えてもらったりしてみてください。
流れ②必要な書類を集める
出願書類(受験案内)を入手した後は、出願に必要な書類を確認して集めましょう。
必要な書類は、出願書類フローチャートから確認可能です。順番に質問に答えていけば、自分に必要な書類が分かるようになっています。
出願に必要な基本的な書類は、以下の4つです。
必須書類
- 受験願書・履歴書
- 収入印紙(受験料にあわせて印紙が異なる)
- 写真2枚(4cm×3cm)
- 住民票又は戸籍抄本(本籍地記載のあるもの)
さらに、以下の場合には、追加で書類が必要になります。
過去に合格科目がある場合や、試験科目の免除を申請する場合
- 科目合格通知書
- 試験科目の免除に必要な書類(単位修得証明書等)
「合格通知書や免除に必要な書類に記された氏名」と「現在の氏名」が異なる場合
- 氏名、本籍の変更の経緯がわかる公的書類
市役所へ足を運んだり高校へ申請したりと、書類を集めるには多少時間がかかります。余裕を持って早めに確認しておきましょう。
流れ③受験科目・免除科目の確認

必要書類の確認にも関わってきますが、受験科目・免除科目の確認も必要です。自分がどの科目を受験するのか、免除できる科目はあるのかをチェックしましょう。
受験科目と免除科目については、こちらでご説明したとおりです。全科目合格を目指している方は、どの科目を選択すればいいのか確認しておきましょう。
効率的な科目選択については下記コラムで詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
免除科目については、入学年月日や所持している資格によって細かく定められています。免除要件に記載されているので、一度確認してみてください。
流れ④特別措置の申請(希望者のみ)
身体上の障害などで特別措置を希望する場合は、「高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書」及び「医師の診断・意見書」の提出が必要です。(参考:文部科学省「身体上の障害等にかかる特別措置」)
特別措置の対象者は以下のとおりです。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 肢体不自由
- 病弱
- その他(精神疾患を含む)
申請後は審査が行われ、認められると「特別措置の決定通知」が送付されてきます。受験当日に、受験票と併せて持っていくようにしましょう。
細かい措置内容は、「身体上の障害等にかかる特別措置」から確認できます。(参考:文部科学省「身体上の障害等にかかる特別措置」)
流れ⑤出願書類の提出

書類のテンプレートを入手したあとは、実際に必要事項を記入して提出します。
書類の中には、提出の際に「開封厳禁」とされるものもありますので、ご注意ください。
なお、受験願書・履歴書は、案内に従って黒の鉛筆で記入します(ボールペンなど不可)。
試験会場は各都道府県で1か所です(東京都は年により2か所になる可能性があります)。どの会場(都道府県)で試験を受けるかは選択できます。
お住まいによっては、居住地とは別の都道府県の会場の方がアクセスしやすい場合もあるでしょう。出願の際には、どこで受験するかもしっかり検討しましょう。
記入が済んだら、提出後も確認ができるようにコピーを取っておくのがオススメです。
受験料は、受験科目数に応じた金額の収入印紙を郵便局などで購入し、願書の『受験料(収入印紙)貼付欄』に貼り付けます。
必要書類の記入・準備が済んだら、不備が無いかを確認の上、郵送(簡易書留)で出願し、受験票などの到着を待ちます。
郵送には時間がかかります。繰り返しにはなりますが、書類の取り寄せ・記入、郵送には、問い合わせも含めて、スケジュールに余裕を持って行うことをオススメします。
流れ⑥受験票受け取り・内容確認
出願が受け付けられると、文部科学省から特定記録郵便で受験票などが送られてきます。ウェブサイトに記載されている期日までに届かない場合は、速やかに連絡してみましょう。
文部科学省から送られてくる書類は、以下のとおりです。
- 受験票
- 受験科目決定通知書
- 試験会場案内図及び注意事項
記載内容など、特に以下の項目を注意して見てみましょう。
- 氏名(漢字を含む)、生年月日に誤りがないか
- 受験願書で選択した受験希望科目が記載されているか
- 受験願書で選択した試験会場が記載されているか
- 受験願書で選択した試験会場の案内図が入っているか
もし誤りがあった場合は、すぐに文部科学省に問い合わせてください。
また、当日になって焦らないよう、試験会場と注意事項は事前に把握しておきましょう。
高卒認定試験当日について
続いては、試験当日についてのお話をします。
試験当日は、「試験会場」と「持ち物」の確認が大切です。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」)
①試験会場

試験当日は混雑が予想されるので、余裕を持って家を出発するようにしましょう。
万が一、試験当日に自然災害や事故など、本人の過失によらない公共交通機関の不通や遅れに遭遇したときは、試験会場にすぐに連絡を入れることが大切です。
状況に応じて、試験時間延長や再試験等の措置を受けられる可能性がありますので、希望は捨てないようにしましょう。
②試験当日の持ち物
試験当日は、必要な持ち物を整理した上で、忘れ物がないかを確認するようにしてください。
送られてくるもの
- 受験票
- 受験科目決定通知書
- 試験会場案内図
- 特別措置の決定通知(希望者のみ)
自分で用意するもの
- 鉛筆・消しゴムなどの筆記用具
- 時計(携帯電話・スマホは試験中に使用できません)
- 弁当・お茶などの飲食物
- 参考書などの勉強道具
なお、「受験票」は当日忘れても、会場で再発行できます。(参考:文部科学省「3 試験の出願について」)
決して慌てず、まずは係りの方に相談してみてください。
試験当日は、不測の事態が発生する可能性を見越して、早めの行動を心がけるようにしましょう。
高卒認定試験に向けてどうやって勉強すればいい?
高卒認定試験に向けて勉強を始めようと思ったとき、どのスタイルで勉強すればいいか分からない方もいるでしょう。
勉強のスタイルとしては、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれのメリット・デメリットを紹介するので、自分に合った勉強スタイルを見つけてみましょう。
①独学
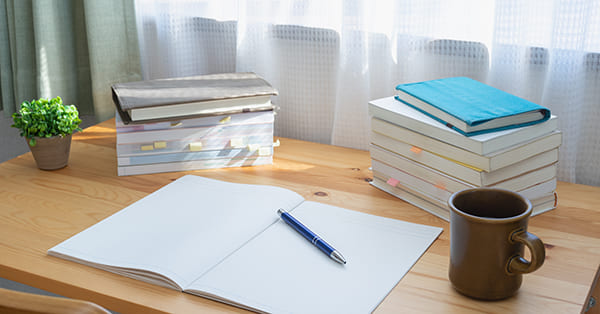
独学は文字通り、自分の力で勉強するスタイルです。独学のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | ・費用を抑えられる ・自分のペースで勉強できる |
|---|---|
| デメリット | ・テキストや勉強法が自分に合っているか分からない ・分からない問題を質問できない |
何より、費用を抑えられるのが一番のメリットです。文部科学省のウェブサイトには、過去数年分の試験問題と正答が掲載されています。これらは無料で閲覧可能です。(参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験問題(高卒認定試験) 解答・過去問題」)
また、市販の参考書も1000〜2000円台のものが多く、塾や予備校に通うよりは費用がかかりません。
しかし、独学だと相談できる相手がいないため、分からないところを質問できません。そもそも、解いているテキストや勉強の仕方が自分に合っているのかと不安になる方もいるでしょう。
そのため、独学は勉強の仕方を分かっていて、自分で計画を立てて進められる方にオススメの方法です。
勉強に慣れておらず、サポートしてもらいながら進めていきたい方は、塾や予備校に通って勉強できた方が安心です。
自分のタイプを考えてみて、まずは独学か塾に通うかを検討してみてください。
②オンライン学習塾
オンライン学習塾は、インターネットを活用して勉強するスタイルです。オンライン学習塾のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | ・家にいながら学習できる ・効率的に学習できる |
|---|---|
| デメリット | ・パソコンなどの準備が必要、・緊張感が出にくい |
オンライン学習塾は通学の必要がないので、家にいながら勉強できるのが最大のメリットです。あまり外に出たくなかったり、家の近くに塾や予備校がなかったりする状況でも指導を受けられます。
ただ、インターネットを使うので、パソコンやネット環境などの準備は必要です。また、家で勉強することになるため、緊張感がなく身が入りづらい方もいるかもしれません。
そのような場合は、オンライン学習塾を検討してみるといいでしょう。
③通学制学習塾

通学制学習塾は、塾や予備校などの教室に通って授業を受けるスタイルです。通学制学習塾のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | ・対面で授業を受けられる ・分からないところはすぐ質問できる |
|---|---|
| デメリット | ・教室までの移動が必要 ・近くに塾や予備校がないと受けられない |
通学制学習塾のメリットは、対面で授業を受けられることです。緊張感が出るほか、目の前で見てくれることにより、細かい言動も察知してくれます。
また、目の前に先生がいることで、すぐに質問しやすい点もメリットと言えるでしょう。
しかし、教室までの移動が必要になるので、家から遠い場合は親御さんの協力が必要不可欠です。通える範囲に塾や予備校がない場合は、通信制学習塾を検討するといいでしょう。
高卒認定試験突破には対策塾がオススメ 対策塾のメリット3点
高卒認定試験を突破するには、対策塾の利用がオススメです。
対策塾では、単に高卒認定試験の合格を目指すだけでなく、その後の大学受験までフォローしてくれたり、勉強面以外のアドバイスを得られたりなど、メリットがたくさんあります。
この章では、具体的な以下3つのメリットを紹介します。
メリット①経験豊富なスタッフが受験科目の選定や相談に乗ってくれる

対策塾に通うメリットの1つ目は、「経験豊富なスタッフが受験科目の選定や相談に乗ってくれる」ことです。
これまで解説してきた通り、高卒認定試験は取得単位による科目免除など、受験生の現状によって試験内容が変わってきます。
受験勉強の計画を立てる際に、そうした内実に合わせて対策をすれば、より効率的に合格へ向けた勉強ができるはずです。
しかし、一人でそうした計画を立てるのは、なかなか難しいのが実際のところです。経験豊富な先生に計画を立ててもらえると、安心して勉強に臨めるでしょう。
また、高卒認定試験の対策実績がある塾では、これまでの生徒さんの悩みに応えてきた講師が勉強面だけでなく、精神的な相談にも乗るなど、手厚くサポートを受けられる点も大きいです。
メリット②試験合格後の進路についても相談できる
「試験合格後の進路についても相談できる」ことも、対策塾に通うメリットです。
受験勉強をするときには、高卒認定試験合格後の進路まで考えた方が、その後の歩みがスムーズになるでしょう。
例えば、「将来、車の設計に関わりたいから大学で機械工学を勉強したい」という人は、大学受験での選択科目を見越して、「物理」を学んでおいた方が後々役に立ちます。
そのため、高卒認定試験での受験科目も、進路にあわせて「物理を選択する」など、しっかりと調整した方がよいでしょう。
また、受験生の方も、将来の目標が明確になっていた方が、勉強に集中できるという面もあると思います。
高卒認定試験の対策塾では、そうした試験合格後の進路相談も受け付けているところが多いです。先生たちが、一人では得られなかった視点を与えてくれます。
さらに、実際の大学・資格受験の際に必要となる証明書類などについてもアドバイスを得られるため、手続き面での不安を解消しやすい点もメリットです。
単に高卒認定試験では終わらず、その後のことまで総合的にフォローが得られる点は、大きなポイントでしょう。
メリット③あなたのスケジュールに合ったカリキュラムを組める

最後のメリットは「あなたのスケジュールに合ったカリキュラムを組める」ことです。
とりわけ、個別指導の対策塾の場合、苦手科目は基礎から、得意科目は演習形式、といった形で、あなたに合ったカリキュラムを組むことができます。
高卒認定試験を目指す人の中には、働きながら合格を目指すなど、より細かな自己管理・時間管理が求められる人もいるでしょう。
そういった方には、特に個別指導の対策塾がオススメです。
中学卒業(または高校中退)後に、勉強から離れていた期間が長かった人は、勉強についていけるか分からないという不安が少なからずあると思います。
そういった面からも、柔軟なカリキュラムを組めることは大きな利点になるでしょう。
高卒認定試験に向けた具体的な5つの勉強法
こちらで、高卒認定試験の「全科目の合格率」は40%台とお伝えしました。
つまり、油断は禁物ということです。
では、受験勉強はどのように進めたらよいのでしょうか?具体的な勉強法は、以下の5つです。
学習の進め方について、ポイントをまとめましたので参考にしてみてください。
勉強法①学習期間は1年間を目安に

まず、学習期間は1年間を目安にしましょう。1年間順調に勉強を進めれば、合格に近づくはずです。もちろん免除の科目が多くなれば、それだけ学習期間も短く済みます。
早い人では数ヶ月の勉強で間に合うこともありますが、基本的には1年間と考えておきましょう。
「来年の試験に向けて」勉強する、というのが大まかなスケジュール感です。
勉強法②得意なところから始めよう
受験勉強を始める際は、少なからず気力を使います。そのため、最初は手を付けやすい科目から始めましょう。
高卒認定試験は合格点が低めなので、いきなり全範囲を習得しようとするのではなく、得意なところで確実に点数を取る、という考え方が大切です。
「得意な科目から」「得意な単元から」地道に基礎力をつけていきましょう。
勉強法③高校1年の教科書を攻略しよう

次に「どんなテキストを使ったらよいのか」ということですが、これは特別なテキストを用意するというよりも、まずは高校1年の教科書を攻略しましょう。
そして、ある程度の学習が進んだら、過去問題に挑戦してみることをオススメします。過去問題は文部科学省のウェブサイトに掲載されているので、どんどん活用しましょう(ただし、著作権の関係で直近2年間の問題は掲載されていません)。
そこでつまづいた所があれば、その単元に戻って改めて学習します。
この「教科書」と「過去問題」の合わせ技でかなりの力がつくはずです。文部科学省の方でも教科書を中心に学習すること、過去問題を参考にすることを推奨しています。
勉強法④参考書は基礎に特化したものを
教科書を一通り終えたら、次は参考書で理解を深めるのもオススメです。参考書を使う場合は、なるべく基礎に特化したものにしましょう。
参考書を購入される場合、必ずしも「高卒認定試験用」でなくても構いません。ポイントは「基礎の習得」を目的としているかどうかです。
こちらの動画では、試験の傾向と対策、そしてオススメの参考書などをご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
勉強法⑤気になる数学は「数学Ⅰ」だけでOK
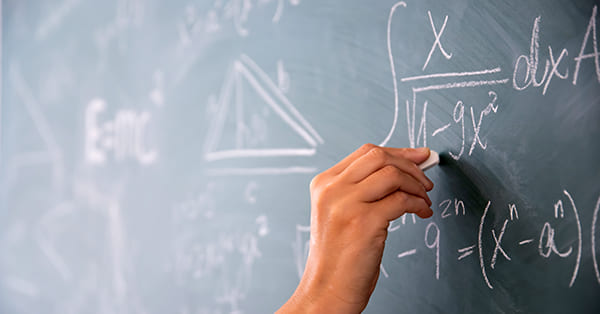
数学は苦手な人と得意な人に分かれやすい科目です。「特に数学だけが苦手で心配」という方も多いのではないでしょうか。
そんな気になる数学ですが、高卒認定試験においては「数学Ⅰ」だけ押さえれば問題ありません。
数学に関しては、過去問題から単元を絞って取り組むのがオススメです。過去問題を見て「自分にもできそう」と思える単元から復習をスタートし、着実に基礎力をつけていきましょう。
高卒認定試験の体験談
実際にキズキ共育塾では、高卒認定試験に何人もの生徒さんが挑んできました。その中で、体験談として語ってくれた例をいくつか紹介します。
高卒認定試験はどんな状況からも目指すことができます。まずは一歩、勇気を出して踏み出してみてください。
体験談①高校中退、高認取得からの大学受験。学んだのは勉強だけじゃなかった

キズキ共育塾では、まずは高卒認定試験の取得を目指すことにして、生物と数学から勉強を始めました。
最初に担当してくれた女性の先生は、ご自身にも高校中退の経験があり、独学で高卒認定資格を取得後、大学に進学したそうです。
その先生の存在自体が私にはとても心強かったし、なかなか人には打ち明けられない悩みも相談しやすかったです。
気分がふさぎ込むときは、ためらわずその先生に話を聞いてもらいました。
ひょんなことで落ち込んでしまい、塾に行く気になれないときもありました。
そんなときでも先生は、スタッフさんを通じて連絡をくれ、私のことを温かく気遣ってくれました。
キズキ共育塾で学び続け、私は高卒認定資格を全科目で取得しました。
体験談②高校を不登校から中退。高認を取得して大学合格。キズキで学ぶうち、「なんとかなる」と思えるようになった
高2の夏に、高校に行けなくなりました。
結局、高校への登校は再開せず、その年の11月くらいに中退しました。
もともと、なんとなく「大学には行きたい」と思っていて、高校中退時点では高卒認定試験の受験を考えていました。
キズキ共育塾では、まずは高認に向けた勉強に取り組みました。
ですが全科目を受験する必要はなく、高校在籍時に取得していた単位の関係で、受験免除科目が結構あったんです。
スタッフさんと相談しながら改めて調べてみると、受験する必要があったのは、世界史(AまたはB)、倫理、政治・経済、地学基礎の4科目だけでした。
そして、18歳になる年度(高校に在籍していたら3年生の年度)の夏の試験に合格し、高認を取得しました。
高認は、もちろん先生の指導のおかげでもありますが、「想像以上に楽だった」というのが実感ですね。
高卒認定試験に関するよくある質問
ここでは、高卒認定試験に関するよくある質問として、以下6つに回答していきます。
気になるポイントばかりだと思うので、ぜひ目を通してみてください。
Q1.高卒認定試験は簡単すぎると言われているけど本当?

A:簡単すぎると感じるかは人によりますが、たしかに合格点は高くなく、1科目およそ40〜50点とされています。そのため、しっかり基礎を固めて臨めば、合格は可能なレベルです。
しかし、「全科目の合格率」は、ここ最近「40%台」となっており、科目数が多いために勉強が間に合わなくなることも考えられます。
決して油断はせず、自分にできる勉強をしっかりこなすようにしましょう。詳しくは、こちらの章をご覧ください。
Q2.高卒認定試験の過去問はある?
A:高卒認定試験の過去問は、文部科学省のウェブサイト「高等学校卒業程度認定試験問題(高卒認定試験) 解答・過去問題」に掲載されています。過去数年分の過去問が無料で閲覧可能です(ただし、著作権の関係で直近2年間の問題は掲載されていません)。
過去問を解くことは、何より一番の受験対策となります。ぜひ有効活用してください。
Q3.高卒認定試験はいつ?日程は?

A:高卒認定試験は、毎年2回実施されています。基本的に実施の1回目は夏(8月初旬)、2回目は秋(11月初旬から中旬)です。
詳細な日程は年によって異なるので、受験を考えている方は自分の目で一度確認してみてください。
日程について詳しくはこちらをご覧ください。
Q4.高卒認定試験の費用は?
A:受験料(費用)は受ける科目数によって異なり、以下のようになっています。
| 受験科目数 | 受験料 |
|---|---|
| 7科目~10科目 | 8,500円 |
| 4科目~6科目 | 6,500円 |
| 1科目~3科目 | 4,500円 |
免除科目の兼ね合いも出てくるので、自分が何科目受けるのかを明確にして費用を計算しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
Q5.高卒認定試験の申し込み方法は?

A:高卒認定試験の申し込みの流れは、以下のとおりです。
- 出願書類(受験案内)の入手
- 必要な書類を集める
- 受験科目・免除科目の確認
- 特別措置の申請(希望者のみ)
- 出願書類の提出
- 受験票受け取り・内容確認
申込時には書類を集めたり記入したりと、思ったより時間が必要です。余裕を持って準備するようにしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q6.高卒認定試験に免除科目はある?
A:高卒認定試験には免除科目があります。高校ですでに単位を取得していたり、資格を持っていたりすると免除になる可能性があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
これを見ればすぐにわかる!高卒認定試験に関する動画のご紹介

最後に、高卒認定試験の概要や対策、科目ごとの勉強方法、オススメのテキストなどの情報をまとめた動画をご紹介します。
高卒認定試験について、知っておくべきことを凝縮した内容になっていますので、ぜひご覧ください。
※2020年に撮影した動画のため、2024年度からの試験科目・合格要件については、こちらをご覧ください。
まとめ〜高卒認定試験を突破すれば可能性が広がります〜

高卒認定試験の詳細から、合格を目指すメリット、対策塾が勧められる理由などを解説してきました。具体的なイメージは掴めましたか?
高卒認定試験の内容理解だけでなく、合格に向けた実際の対策までを考えたとき、すべてを一人でカバーしようというのは、なかなか難しいところがあります。
すでに高卒認定試験に合格した人や、指導実績のある専門の人に頼る方が、勉強を効率的に進められるはずです。
私たちキズキ共育塾のように、対策塾によっては、講師本人が、不登校・高校中退から高卒認定試験を合格して大学進学を果たしている場合もありますので、勉強面以外の悩みにも、より親身になって対応してもらえる可能性が高いです。
ぜひ、一人で抱え込まずに、興味を持った対策塾に相談・問い合わせをしてみてください。
Q&A よくある質問