いじめの定義とは? 具体的な事例や対処法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
いじめに関する報道を見聞きする機会は少なくありません。
あなたは、以下のようなことでお悩みではないでしょうか?
- 自分はいじめられているかもしれない
- どこからどこまでがいじめなの?
- どう対処すればいいの?
このコラムでは、いじめに関してお悩みのあなたや親御さん、現場の教職員に向けて、いじめの定義や具体的な事例、認知する方法、対処法について解説します。あわせて、いじめを防止する取り組みの事例やいじめられている人に向けた相談先についても紹介します。
いじめの定義や事例などを知り、適切に対処できるように記事に目を通しましょう。
私たちキズキ共育塾は、いじめにお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
いじめの定義とは?
いじめとは、学校や職場などの集団内で、特定の個人を肉体的・精神的に苦しめる行為のことです。(参考:三省堂『大辞林 第四版』)
受けた本人がいじめだと思えば、それはいじめです。「これくらい」「遊びのつもりだった」などという言葉に惑わされず、いじめに対する正しい認識が必要です。
残念ながら、現代においていじめは珍しいものではありません。どの学校でも、どの子どもにも起こりうるものです。
いじめがないことはよいことです。ですが、学校や社会がいじめゼロを目標に掲げると、現に起きているいじめを見逃すことに繋がる可能性があります。
重要なのは、「いじめがあるのではないか」という認識に立ち、いじめの予防や対処の検討・実施を進めていくことだと言えるでしょう。
いじめの定義は文部科学省や研究者によって異なります。この章では、文部科学省によるいじめの定義と研究者によるいじめの定義を紹介します。
文部科学省によるいじめの定義

文部科学省は、いじめを以下のように定義しています。(参考:文部科学省「いじめの定義の変遷」、Gov法令検索「いじめ防止対策推進法」、法務省「「いじめ」をなくすために」)
児童生徒等に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒等と一定の人的関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒等が心身の苦痛を感じているもの
(参考:文部科学省「いじめの定義の変遷」)
以上の定義は、2013年に成立したいじめ防止対策推進法の施行に伴うものです。
一定の人的関係とは、主に以下の3つです。
- 学校の内外にかかわらない対人関係
- 学校や学級、部活動内などの関係
- かかわりのある仲間や集団
この3点から、児童生徒がかかわっている仲間や集団から心身の苦痛を伴う行為を受けた場合、学校の内外を問わずいじめと判断されることが分かります。
「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とあるように、いじめの定義の中心を、当事者の被害感にしています。
これは、精神的なダメージやトラウマは外から判断しづらく、また、加害行為を見分けることが困難な場合があるからです。
それゆえ、いじめの形式や特徴を具体的に示さないことによって、教職員の恣意的な判断を避けるよう定義されています。
研究者によるいじめの定義
いじめ研究で有名な森田洋司氏は、いじめを以下のように定義しています。(参考:森田洋司『いじめとは何か?』)
いじめとは、同一集団内の相互作用過程において優位に立つ一方が、意識的に、あるいは集合的に他方に対して精神的・身体的苦痛をあたえることである
(参考:森田洋司『いじめとは何か?』)
こちらもやはり、定義の中心は「当事者の被害感」です。
「集合的に」という文言には、意識的ではないとしても、人々が集まることによって集団心理が働くことがあるという意味が込められています。
こちらで紹介した文部科学省による定義と比べると、「集合的に」という文言のほか、「優位に立つ一方が(中略)他方に対して」という文言も特徴です。
これは、定義した森田名誉教授によると、「同程度の力を持った人同士での喧嘩や口論とは違い、いじめがパワーバランスの不均衡に乗じて起こること」を示しているそうです。
補足①いじめ重大事態

いじめのうち深刻なものを、いじめ重大事態といいます。
いじめ重大事態とは、いじめられている児童生徒の生命や心身、財産などに重大な被害が生じた疑いがあると認められる事態や、一定の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める事態のことを指します。(参考:文部科学省「重大事態の解説(案)」、e-Gov法令検索「いじめ防止対策推進法」、総務省「重大事態の再発防止の取組状況」)
第二十八条
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(参考:e-Gov法令検索「いじめ防止対策推進法」)
いじめ重大事態の事例は、以下のとおりです。
- 殺人・殺人未遂
- 自殺・自殺未遂
- リストカットなどの自傷行為
- 暴行によるケガ、骨折
- 人が見ている前で服を脱がされた、脱ぐことを要求された
- インターネット上での個人情報などの拡散
- 恐喝
- 私物の破損
いじめ重大事態の発生が疑われる場合、学校側は、重大事態の調査の開始が義務付けられています。
また、いじめ重大事態が発生したと認められる場合、学校側は、いじめられている児童生徒とその保護者への報告、文部科学省への報告、重大事態への対処、再発防止のための取り組みなどが義務付けられています。
補足②いじめといじりは違う
いじりといじめは一見似ているように見えますが、本質的に異なるものです。
いじりは、お互いの信頼関係を前提とした友好的なコミュニケーションの一種です。相手が精神的な苦痛を感じる場合は、それはいじめに該当します。
また、いじりのつもりでも、繰り返されることで相手を傷つけ、いじめに発展するケースも少なくありません。相手の表情や態度に違和感があったら、それはいじりの範囲を超えている可能性があります。
周囲の人もいじりであると軽視せず、受け手の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
いじめの定義の変遷
いじめの定義は、時代の移り変わりとともに変化してきました。この章では、いじめの定義の変遷について解説します。(参考:文部科学省「いじめの定義の変遷」)
時代とともにどのようにその定義が変化してきたのか確認してみてください。
1986年(昭和61年)以前におけるいじめの定義

1986年以前におけるいじめの定義は、以下のとおりです。
「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。
(参考:文部科学省「いじめの定義の変遷」)
1986年の定義は内容が限定的なうえ、「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」とされています。そのため、現代ではいじめとみなされるものが、当時としてはいじめとされなかったケースも多くあるとみられます。
1994年(平成6年)におけるいじめの定義
1994年のいじめの定義は以下のとおりです。
「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。
なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
(参考:文部科学省「いじめの定義の変遷」)
1986年の定義と異なるのは以下の2点です。
- 「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」という文言の削除
- 「なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。」という文言の追加
新たに追加された文言は、いじめ対策において現代にも通じる最も重要なポイントです。
2006年(平成18年)におけるいじめの定義

2006年におけるいじめの定義は以下のとおりです。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。 (※)なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
(参考:文部科学省「いじめの定義の変遷」)
1994年の定義と異なるのは以下の3点です。
- 「自分より弱い者に対して一方的に」という文言から「一定の人間関係のある者」という文言への変更
- 「身体的・心理的な攻撃を継続的に加え」という文言から「心理的、物理的な攻撃を受けたことにより」という文言への変更
- 「相手が深刻な苦痛を感じているもの」という文言から「精神的な苦痛を感じているもの」という文言への変更
「一定の人間関係のある者」とすることで、いじめる児童生徒といじめられる児童生徒との関係性が見直されました。これは、どのような関係であってもいじめが起こりうる可能性を示唆しています。
また「心理的、物理的な攻撃を受けたことにより」という文言によって、一過性の行為もいじめと捉え指導の対象とされました。
さらに「精神的な苦痛を感じているもの」では、いじめられた児童生徒の精神的苦痛を適切に把握して解消に務めることが重要だと示しています。
2013年(平成25年)以降のいじめの定義
2013年以降、いじめは以下のように定義されています。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
(参考:文部科学省「いじめの定義の変遷」)
2013年にはいじめ防止対策推進法が施行されたことで、定義が大きく改定されました。
主な変更点は以下の2つです。
- 「インターネットを通じて行われるものも含む」という文言の追加
- 「精神的な苦痛」という文言から「心身の苦痛」という文言への変更
「インターネットを通じて行われるもの」という文言が追加されたのは、WebやSNS上でのいじめが問題視されるようになったためです。
また、「精神的な苦痛」を「心身の苦痛」とすることで、苦痛を感じる度合いや範囲が広くなりました。いじめによる精神疾患の発症や身体的な症状、不登校なども視野に入れていると考えられます。
いじめの具体的な6つの事例
この章では、いじめの具体的な事例について解説します。
事例①悪口や暴言

1つ目の事例は、悪口や暴言です。
本人の見た目や体型に関する悪口や暴言によって、不登校や精神疾患に悩まされるケースが後を絶ちません。
なぜなら、悪口や暴言を言う人にとっては冗談でも、言われた人に深刻な苦痛を与えることがあるためです。
また、そのような発言に対して「やめてほしい」「傷つくから言わないでほしい」と意思表示しにくい人がいます。
そのため、事態が深刻化するまで周囲の人が気づかない可能性があります。(参考:東京都教育委員会「2 悪気のない言葉で、相手を傷付けてしまった事例」)
事例②無視や仲間はずれ
2つ目の事例は、無視や仲間はずれです。
無視や仲間はずれの問題点は、集団が特定の個人に対してそのような行為をしていることです。無視や仲間はずれが起こるきっかけは、主に以下の2つです。
- 空気の読めない言動をするため
- 優秀またはその反対の振る舞いによって本人の存在が気に障るため
無視や仲間はずれにされた人は、周囲から疎外、孤立していると感じて悩みを抱え込む恐れがあります。また、コミュニケーションを取ることに不安や苦痛を感じて、自分のことを話しにくくなる可能性があります。(参考:沖縄県「「仲間はずれ、無視、陰口」 した経験がある・・・・9割」)
学校・クラスで嫌われてると悩んでいるあなたに向けて、その対処法などについて、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
事例③身体的な苦痛を与える行為

3つ目の事例は、身体的な苦痛を与える行為です。
身体的な苦痛を与える行為は、いじめの加害者に傷害罪が適用される可能性もあります。(参考:国立教育政策研究所「いじめと暴力」)
身体的な苦痛とされる行為は、主に以下の4つです。
- 叩く
- 蹴る
- 押す
- 突き飛ばす
暴力を受けた児童生徒のなかには、大人になってもそのトラウマに悩まされるケースがあります。
事例④金品の要求や窃盗の強要
4つ目の事例は、金品の要求や窃盗の強要です。
金品の要求や窃盗の強要の問題点は、計り知れないほどの精神的苦痛を与える可能性があることです。
なぜなら、金品を要求されたとき、子どもは親の財布からお金を盗んだり嘘をついたりして用意することが多いためです。(参考:千葉県「第2章 いじめの理解」)
また、窃盗を強要されたとき、実際に盗めば罪の責任を背負うことになります。金品の要求や窃盗の強要は、被害が拡大したり罪に問われたりする可能性を含む行為です。
事例⑤SNSやネット上での誹謗中傷

5つ目の事例は、SNSやネット上での誹謗中傷です。
SNSやネット上での誹謗中傷の問題点は、顔や名前が見えない相手から攻撃されることです。相手の正体が分からない状態で暴言を吐かれたり不快な画像を送られたりするため、精神的な苦痛を感じます。
また、SNS上で特定の人物を無視したり仲間はずれにしたりすることがあります。
ネット上での交流やコミュニケーションが活発な現代において、ネットいじめは特に問題視されている行為です。(参考:文部科学省「『ネット上のいじめ』から子どもたちを守るために」)
事例⑥精神的な苦痛を与える行為
6つ目の事例は、精神的な苦痛を与える行為です。
精神的な苦痛を与える行為の問題点は、被害の状況を目視で確認しにくいことです。そのため、周囲の人が気づきにくく事態が深刻化する恐れがあります。(参考:法務省「「いじめ」をなくすために 」)
精神的な苦痛を与える行為は、主に以下の6つです。これまでに述べたものを内包するケースもあります。
- 人が見ている前で服を脱がされたり脱ぐことを要求されたりする
- インターネット上での個人情報などの拡散
- 窃盗を強要される
- 金品を要求されたり脅し取られたりする
- 掃除や片付けなどを押しつけられる
- SNSやWebサイトなどで悪口を書かれる
- 無視される
精神的な苦痛を受けた人には、強い不安や抑うつなどから心身の不調をきたし、さまざまな症状に悩まされる可能性があります。
いじめの原因

文部科学省は、いじめの原因として「不満やストレス」を挙げています。(参考:文部科学省「いじめ対策Q&A」)
ほかにも、さまざまな原因があると考えられます。
- 学校(友達・先生)での人間関係
- 勉強ができない・成績が上がらない
- 部活がつらい・周りについていけない
- 親が自分を見てくれない・兄弟姉妹と比べられる
いじめの原因については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
いじめを犯罪と定義しにくい理由

なぜいじめは犯罪として定義されていないのでしょうか?
いじめを犯罪と定義しにくい理由は、いじめをすべて犯罪の観点から扱おうとすることによって、予防や対応が不十分になる恐れがあるためです。
評論家の荻上チキ氏は、以下のように論じています。(参考:荻上チキ『いじめを生む教室 子どもを守るために知っておきたいデータと知識』)
(中略)確かに暴行や恐喝は犯罪であり、こうしたケースについては警察などとの連携を増やしていかなくてはなりません。
(中略)
しかし、いじめには大きく分けて、「暴力系いじめ」と「コミュニケーション操作系いじめ(非暴力系いじめ)」の2つがあります。(中略)
現代日本の場合、大半のいじめは「コミュニケーション操作系いじめ」です。こうしたいじめも、「暴力系いじめ」と同じように「犯罪」として取り扱い、「警察に通報」しさえすれば、解決するでしょうか。いえ、そもそも「犯罪」としての要件を満たさないケースが多いため、難しいでしょう。
(参考:荻上チキ『いじめを生む教室 子どもを守るために知っておきたいデータと知識』)
以上のとおり、無視や仲間外れなどの「コミュニケーション操作系いじめ」は、現行法では犯罪として扱いきれません。
つまり、全てのいじめを犯罪の観点でとらえようとすると、「犯罪ではないいじめ」「犯罪として扱いきれないいじめ」が「いじめではない」として見落とされる恐れがあるのです。
犯罪ではないコミュニケーション操作系いじめは、当事者が被害感を覚えていればもちろんいじめに該当します。また、やがて重篤ないじめへと発展する可能性もあります。
以上のことから、いじめの予防・対策をより万全にするためには、やはり、いじめを犯罪より広い概念としてとらえることが重要だと確認できます。
いじめを正確に認知する4つの方法
この章では、教職員や保護者さんに向けて、いじめを正確に認知する方法について解説します。
前提:重大な事態に至る前に認知する必要がある
いじめを正確に認知することが重要なのは、ささいな出来事をきっかけとして重大な事態に至る可能性があるためです。
いじめ防止対策推進法においては、いじめの事実を確認できたときは措置を講じなければならないと定められています。(参考:Gov法令検索「いじめ防止対策推進法」)
学校が組織としていじめを認知して状況を見守り、適切に指導して解決につなげることが最も重要です。
方法①いじめの定義を理解する
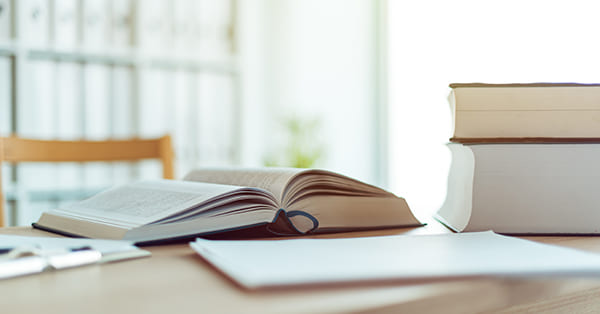
いじめの定義を再確認して、理解を深めましょう。文部科学省による現行のいじめの定義を、4つのポイントにまとめました。
- いじめた人といじめられた人が児童生徒であること
- 両者のあいだに一定の人的関係があること
- いじめた人がいじめられた人に対して心理的または物理的に影響を与える行為をしたこと
- その行為を受けた人が心身の苦痛を感じていること
なかには、物品を隠したり上履きに画びょうを入れたりなど、その行為を行った人物を特定できないケースがあります。
行為者を特定できないケースはいじめの定義の要件を満たしていないものの、学校はいじめとして対応し、問題行動等調査においてもいじめとして取り扱いましょう。(参考:文部科学省「別添 いじめの認知について~先生方一人一人がもう一度確認してください。~ 」)
方法②いじめの認知漏れを防ぐ
いじめの認知漏れを防ぐために必要なのは、法の定義に基づいて、被害を受けた児童生徒の主観を尊重することです。
第三者がいじめかどうかを判断すると、自らの価値観や見方で「これはいじめではない」と考えて認知漏れが発生する恐れがあります。
そのため、被害を受けた児童生徒の主観を尊重し、いじめの認知漏れを防ぎましょう。
以下に、いじめの認知漏れが発生した事例とその理由をまとめています。(参考:北海道教育委員会「02-2 いじめの正確な認知に向けて」)
事例①ある児童が数人から下着を下げられてひどく傷ついた
- 単発的であり既に解決していると判断したため
事例②ある児童がほかの児童の顔を殴った
- 殴られた児童が殴った児童に物品を盗まれたと疑ったことから、一方的な暴力ではないと判断し「けんか」として処理したため
事例③インターネット上で誹謗中傷と共に卑猥な書き込みを拡散させていた
- 悪質かつ緊急の対応が必要と判断し犯罪として対処したため
以上をみると、認知漏れが発生したのは、第三者がいじめの定義を自らの考えに基づいて解釈していたということが分かります。
いじめを正しく認知できるよう、いじめられている児童生徒の主観を尊重しましょう。
方法③いじめられている人の意思を尊重する

いじめられている人の意思を尊重することで、事態の深刻化や被害の拡大を防げる可能性があります。
そのため、いじめられている児童生徒の苦痛や不安を理解し、安心して過ごせる環境を用意しましょう。
安心して過ごせる環境を用意するためには、以下の4つのポイントを押さえてください。(参考:NITS 独立行政法人教職員支援機構「学校におけるいじめ問題への対応のポイント」)
- 本人から話を聞く
- 本人の安全を確保する
- 本人の意思を尊重する
- 本人をサポートする
はじめに、いじめられている児童生徒から話を聞き、「どのような行為を受けたか」「そのときに感じたこと」などについて話してもらいましょう。本人がリラックスして話せるよう、場の雰囲気を穏やかに保ちます。
次に、本人の安全を確保して、学校内で安心して過ごせるようにします。
いじめられている人が自信を回復できるよう、そのようなきっかけがみられたときにはすぐに認め、学校で安心して過ごせるよう積極的にフィードバックの場を設けましょう。
また、学校での過ごし方やクラスメイトへの対応の仕方は本人の意思を尊重してください。
時間をかけてヒアリングし、誘導するような話し方やプレッシャーを与えるような態度は控えます。
最後に、学校内で過ごすときは担任以外の教師とも協力します。声かけをしたり様子をみたりして、周囲とのかかわり方に注意を払いましょう。
方法④組織的に対応する
4つ目の方法は、組織的に対応することです。この項目については、特に教職員が対象です。
いじめに対して組織的に対応することは、初期段階で適切な対策を取り、事態の深刻化を未然に防ぐためにも重要です。
そのため、ささいなことでも注意を払って教職員や保護者さん同士で協力しましょう。
組織的な対応の流れは以下のとおりです。(参考:文部科学省「いじめ防止対策推進法等に基づくいじめに関する対応について 」)
- 情報を集めて教職員同士で共有する
- 指導および支援体制を組む
- 子どもへの指導と支援を行う
- 教職員と保護者さんが連携する
いじめに関する情報を集めるときは、アンケートをとります。
対象は教職員や児童生徒以外に保護者さんや地域住民などです。収集した情報はいじめ対策組織に集約します。むろん、いじめを発見したときはその場でやめさせるべきです。
指導および支援体制は、校長が主体となって以下の人員で組織を構成しましょう。
- 生徒指導担任
- 学年主任
- 養護教諭
- 学級担任
- スクールカウンセラー
- 弁護士
- 警察OB
子どもへの指導と支援は、いじめを行った人と受けた人、周囲の人すべてに対して行ってください。
いじめられている児童生徒への指導内容
- 保護者や親しい友人など信頼できる人たちが寄り添って支える
- いじめから徹底的に守り通す体制を整える
いじめをしていた児童生徒への指導内容
- 自らの行為がどのような影響を与えるかを伝える
- 自らの行為によって負う責任を自覚してもらう
- 不満やストレスを抱えている場合は適切な対応を取る
周囲の児童生徒への指導内容
- いじめを止められなくても周囲に知らせる勇気を持つよう指導する
保護者との連携においては、かかわりのある教職員が中心になります。いじめられている児童生徒、いじめている児童生徒の自宅へ即日訪問しましょう。
家庭訪問の際は、事実関係を伝え、学校とどのように連携していくかを話し合います。
いじめへの対処法
実際に身近にいる子どもがいじめ被害にあっている、いじめにあっていそうだと思われるとき、まわりの大人や学校はどんなことができるでしょうか。
この章では、いじめられている本人やまわりの大人や学校ができるいじめへの対処法を解説します。
対処法①いじめられている本人にできる対処法

大人であっても、一人でいじめを防ぐ・対処するのは困難です。複数人で、組織的に予防・対処をすることが理想的です。
子どもたちも、まわりの大人の振る舞いによって、SOSを発信したり相談したりできるようになります。
それによっていじめの重大化を防ぎ、問題を一人で抱え込むことを避けられます。
具体的な方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
こちらで解説する公的・民間の相談機関を利用することもオススメです。
対処法②親御さんにできる対処法
お子さんがいじめられている場合、場合、お子さんの主体性を尊重しながらスクールカウンセラーや自治体の窓口に相談しましょう。
お子さんがいじめられている事実を打ち明けにくいことがあります。
日常生活を送るなかで以下の3点がみられたときは、学校や本人の友人たちから話を聞いてみてください。
- 小さな傷が不自然に増えた
- ものをなくすことが増えた
- 情緒が不安定になりやすい
この3点以外にも、違和感を覚える言動があったときは同様に情報を集めます。ただし、重要なのはお子さん本人が安心して過ごす場所や時間を確保することです。
解決を焦らず、お子さんの意思を尊重してください。
対処法③学校にできる対処法

2011年に発生した滋賀県大津市でのいじめ事件を受けて、国は、「いじめ防止対策推進法」という法律を制定しました。
いじめ防止対策推進法では、国や自治体などがなすべきいじめの防止・早期発見・対処が明記してあります。
「特定非営利活動法人ストップ!いじめナビ」に所属する弁護士たちは、いじめ防止対策推進法の特色を次のように整理しています。(参考:ストップいじめ!ナビ スクールロイヤーチーム・編『スクールロイヤーにできること』)
- いじめの定義を広くとらえ、早期発見の重要性を強調していること
- これまで教員個人に任されてきた対応を組織的に行うよう求めていること
- PDCAサイクルによる定期的な見直しを前提とした、継続的で効果的な施策の実行が求められていること
- いじめが重大事態に発展した際の対応について特に取り上げ、様々な義務等が明記されていること
この法律の22条では、いじめ防止対策のために組織をつくることが規定されています。そのため、いじめ防止対策推進法第 22 条にもとづく組織のことは、「22条組織」と呼ばれています。
22条組織の窓口となる先生が決められているはずです。まずは、その先生に相談してみるということも可能です。
また、学校によっては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置しているところがあります。
これらは、いじめに関する相談も受け付けているので、子どもが在籍している学校に配置されているかどうかチェックしてみてください。
補足:大人のいじめへの対処法
近年では、大人のいじめ、職場でのいじめも少なくありません。
大人が職場でいじめられたときは、上司や同僚に相談したり文書で報告したりして、組織としての対処を求めましょう。
職場や上司を頼りにくいときは、労働局へ相談することも検討できます。
労働局に協力を求めれば、組織に対して助言や指導をしてもらう制度を利用することも可能です。
ただし、深刻ないじめによって心身ともに苦痛を感じている場合は部署の転換や転職など、環境を大きく変えることを視野に入れておきましょう。
いじめへの法的な対処法3選

いじめへの法的な対処法は、以下のとおりです。(参考:文部科学省「いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について」、東京弁護士会「いじめ問題」)
法的な対処法①いじめ防止対策推進法
- 道徳教育や早期発見のための措置や相談体制の整備
- いじめ防止に従事する人材の確保など
法的な対処法②刑事責任の追及
- 暴力を振るわれた場合は傷害罪
- 威圧されて金銭を脅し取られたときは恐喝罪が成立する可能性がある
法的な対処法③民事責任の追及
- いじめを行った人とその保護者に対して損害賠償を請求できる
いじめを解決するうえで最も重要なのは、いじめられている人の意思を尊重することです。
刑事および民事の責任を追及する際は、いじめられている児童生徒や専門家などと話し合って判断しましょう。
自治体ごとのいじめ防止の事例2選
この章では、自治体ごとのいじめ防止の事例を紹介します。
事例①熊本県教育委員会

熊本県教育委員会では、いじめを防止して早期に対応できるようにリーフレットを発行しています。(参考:熊本県教育委員会「いじめ防止等リーフレット」)
リーフレットに記載されている主な内容は、以下の3点です。
- 教職員向けのセルフチェックシート
- 組織として対応することの重要性
- いじめを早期に発見し対応するときの流れ
教職員向けのセルフチェックシートは、いじめを正しく認知して対応できるよう促します。
また、組織として対応することの重要性を示し、教職員が単独で問題を抱え込まないようにしています。
いじめの初期段階で対応するための流れを把握できていれば、いざというときにスムーズに実行できるでしょう。
事例②東京都教育委員会
東京都教育委員会が推進する、いじめ対策のポイントは以下の6つです。(参考:東京都教育委員会「02_「いじめ総合対策【第2次】の概要」)
- 軽微ないじめも見逃さない
- 教員一人で抱え込まず、学校一丸となって取り組む
- 相談しやすい環境の中で、いじめから子供を守り通す
- 子供自身が、いじめについて考え行動できるようにする
- 保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図る
- 社会全体の力を結集し、いじめに対峙する
また、以下のWebサイトとアプリを通じて、SNSを含むいじめの対策と防止に務めています。
参考:東京都教育委員会「考えよう!いじめ・SNS@Tokyo」
Webサイトとアプリでは、学校やSNS上で起こるいじめやトラブルの事例を漫画形式で示しているため、子どもたちは自分自身の立場と目線で考えられるでしょう。
ほかにも、ストレスチェックおよび都いじめ相談ホットラインにつながるアプリがあり、子どものプライバシーに配慮した対応を取っています。
いじめについて相談できる支援機関4選
この章では、いじめについて相談できる支援機関を紹介します。
子ども用の連絡先も掲載しますので、お悩みの学生さんがいるようでしたら、ご紹介ください。
前提:いくつかの支援機関に相談しましょう
あなたが相談するにしろ、親御さんが相談するにしろ、「頼りにならなかったな」「自分の状況に合わない回答だったな」となる可能性は、残念ながらあります。
そんなときは、心が落ち込むかもしれませんが、決してあきらめず、別の支援機関などを利用するようにしてください。
重篤ないじめについては、警察や司法による対応を求めることも検討すべきでしょう。
なお、いじめの多くは軽易なものが含まれることが多いです。軽易ないじめなどは、現行法では警察が犯罪として取り扱えないものもあるため、意識しておきましょう。
その他の相談先については、以下のコラムで解説しています。是非ご覧ください。
支援機関①24時間子どもSOSダイヤル

子ども用に文部科学省が設置している電話相談です。
- 受付日時:毎日、24時間対応
- 電話番号:0120-0-78310
支援機関②チャイルドライン
18歳までの子ども用の相談窓口です。
- 受付日時:毎日、午後4時~9時まで(12月29日~1月3日を除く)
- 電話番号:0120-99-7777
参考:チャイルドライン
支援機関③子どもの人権110番

子ども用に法務省が設定している電話相談です。
- 受付日時:平日、午前8時30分~午後5時15分まで
- 電話番号:0120-007-110
参考:子どもの人権110番
支援機関④最寄りの警察署や弁護士事務所など
最寄りの警察署、弁護士事務所、いじめ関連の支援機関などもあります。
あなたも親御さんも、決して孤立していません。
ぜひ、積極的に相談先や頼れるところを探してください。
まとめ~いじめには周囲の人と協力して対処しよう~

いじめは、どんな環境でも起こりうることです。
予防・対処のためには、当事者の被害感を基礎にすえて、いじめをより広い概念としてとらえる姿勢が重要です。
また、いじめ防止対策推進法で明示されているように、いじめ問題は、組織的な対応が求められています。
あなたは、決して一人ではありません。
周りの保護者さんも、ご家庭だけで解決しようとせず、学校や支援機関などと協力していきましょう。
1人でも多くの人がいじめから救われることを、祈っています。
さて、私たちキズキ共育塾では、いじめで傷ついた子どもの心と勉強のサポートを行っています。
無料相談も行っていますので、少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。保護者の方だけでのご相談も可能です。
Q&A よくある質問
















