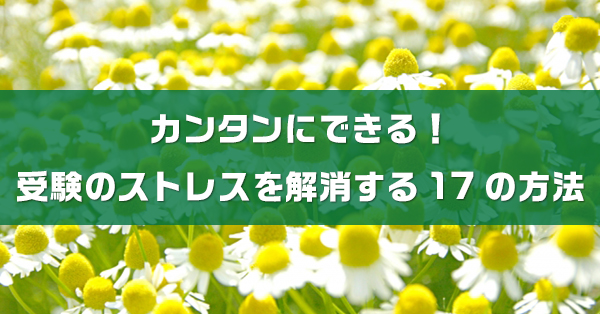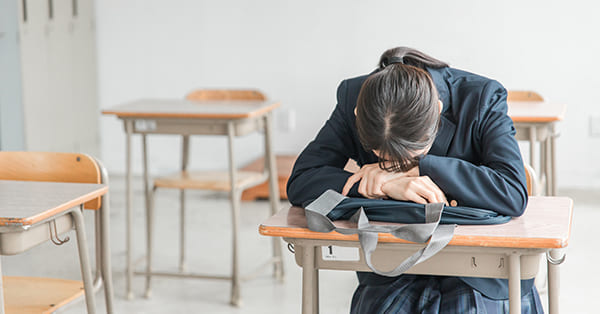受験でボロボロなメンタルになる原因 解決策やサポート先を解説
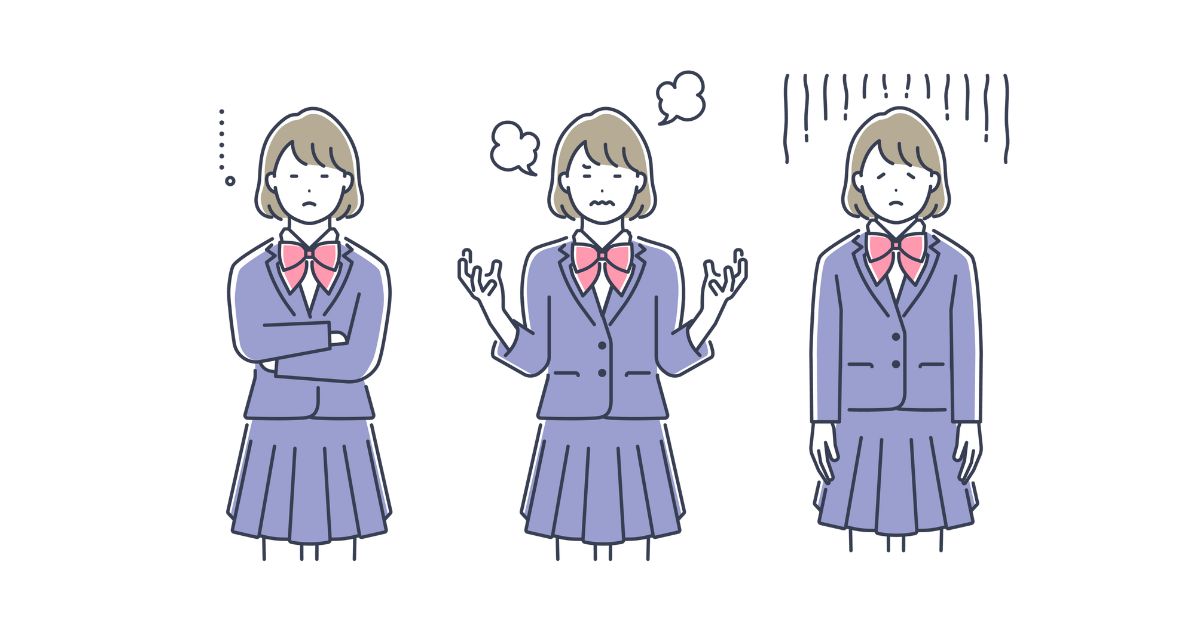
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
受験生のあなたは、「ストレスでメンタルがボロボロ」「頭痛や吐き気を感じるようになった」と違和感を感じていませんか?
受験勉強をしていると、疲労や不安感から心が追い込まれることもあります。
限界までストレスが溜まると、心身の不調から受験勉強に手がつかなくなる場合もあるでしょう。
メンタルがボロボロになる背景には、かならず原因があります。原因を知ることで適切な対処法がわかり、勉強に集中しやすくなるはずです。
そこで、このコラムでは、受験期間中にメンタルがボロボロになる原因や影響、解決策、メンタルを維持しながら勉強を続けるためのコツについて解説します。
あわせて、親御さんができるサポートも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
私たちキズキ共育塾は、不安や悩みにある受験生のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
受験でメンタルがボロボロになる原因
受験の合否は、将来に大きく関わると考える人も多く、そのプレッシャーからストレスを感じることは決して珍しいことではありません。
厚生労働省が行った調査によると、「不安や悩みがある」と答えた小学校5年生から18歳未満のうち、約77%がその内容として「自分の勉強や進路について」と回答しています。(参考:厚生労働省「平成26年度全国家庭児童調査結果の概要」)
つまり、多くの人が不安や悩みを抱えながら、学業や受験勉強に取り組んでいるのです。
この章では、受験でメンタルがボロボロになる主な原因について解説します。
原因①成績が伸び悩んでいる
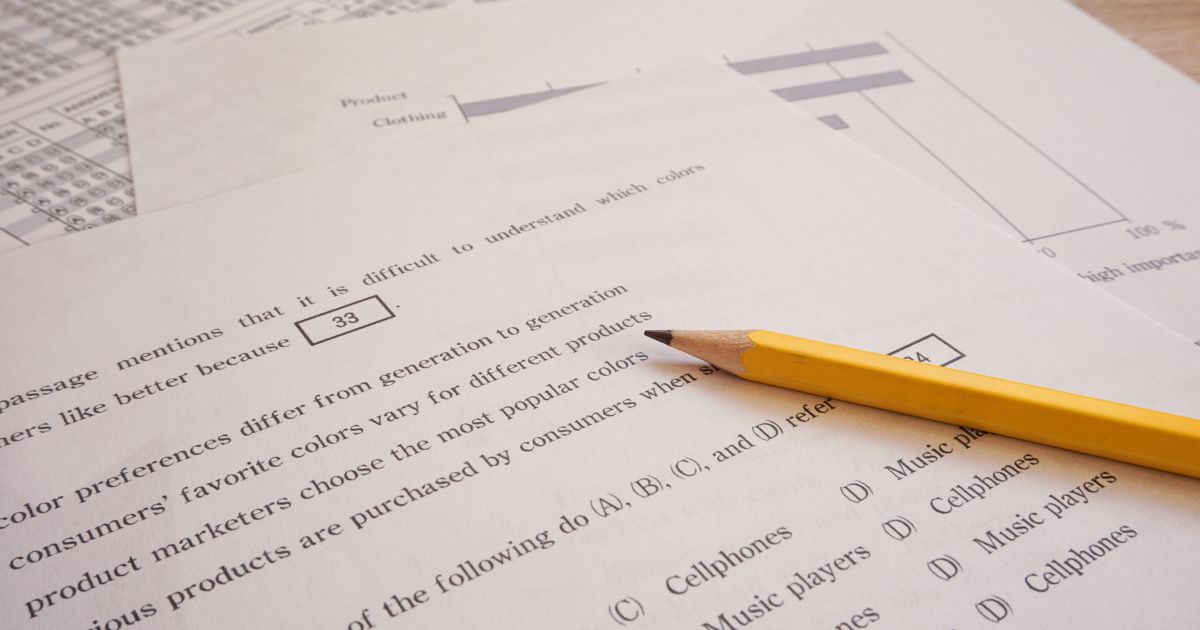
努力しても思うように成績が伸びないと、入試が近づくにつれて焦りや不安が募、その結果としてメンタルに大きな負担がかかります。
また、努力と結果が結びつかないとモチベーションも低下し、勉強そのものが苦痛に感じることもあります。
こうした状態が続くと、精神的な疲労が蓄積し、受験勉強に集中しづらくなる可能性があります。
原因②勉強の仕方が分からない
正しい勉強法を知らないまま学習を続けると、効率が悪く疲労が溜まり、メンタルへの負担も大きくなります。
受験勉強は、量より質が重要です。自分に合ったスケジュールや方法を見つけることが、負担の軽減と成果の向上につながります。
長時間の勉強をしても、結果が出ないことに落ち込んでしまうこともあるでしょう。
原因③十分な休息が取れていない

息抜きや睡眠を削って勉強を続けると、心身の回復が追いつかず、ストレスがさらに蓄積されます。
また、不安から眠れなくなることで、さらに休息が取れないという悪循環に陥ることもあります。
十分な睡眠が取れないと、日中の強い眠気や作業効率の低下、さらには抑うつ状態を引き起こすこともあります。(参考:厚生労働省「健やかな眠りの意義」)
原因④他人と比べている
周囲の成績や進捗と自分を比べることで、自分が劣っているように感じ、メンタルに悪影響を及ぼすことがあります。
比較がモチベーションの向上につながることもありますが、常に他人と比べることは、自己否定に繋がりやすくなります。(参考:樺沢紫苑『精神科医が教える ストレスフリー超大全』)
原因⑤完璧主義

「こうでなければならない」と言った思考にとらわれやすい完璧主義の人は、受験勉強で過度なストレスを感じやすい傾向にあります。
完璧主義は目標達成には有利ですが、達成できなかった時に強い自己否定に陥るリスクもあります。
しかし、完璧主義は必ずしも短所ではありません。高い目標を持ち行動する背景には、能力を向上させたいという思いがあります。(参考:早稲田メンタルクリニック「完璧主義(べき思考)に関する雑感 「「こうでなければ」のハードルが高い」」)
完璧主義のつらさをやわらげる方法については、以下の記事も参考にしてみてください。
原因⑥親や先生の期待が重い
周囲の期待が大きすぎると、それに応えようとして自分の気持ちやペースを後回しにし、メンタルの負担が増してしまいます。
期待に応えられなかったときの落胆や、思った反応が返ってこなかったときのショックも、心を追い詰める原因となります。(参考:あい『『脱』完璧主義! ~ラクに生きるための処方箋~: 疲れたココロとカラダを解放する がんばらない戦略 キンドルカウンセリングシリーズ Kindle版』)
受験中のメンタル不調による影響
メンタルに不調を感じていても、不安や焦りから無理に勉強を続けようとする受験生は少なくありません。
しかし、不調を放置すると心身への影響が大きくなり、かえって受験勉強に集中しにくくなります。
そのため、過度なストレスを自覚することは、心を和らげて受験勉強を継続しやすいコンディションを整えるうえで欠かせないポイントです。
この章では、メンタル不調による主な影響を紹介します。
影響①集中力ややる気が落ちる
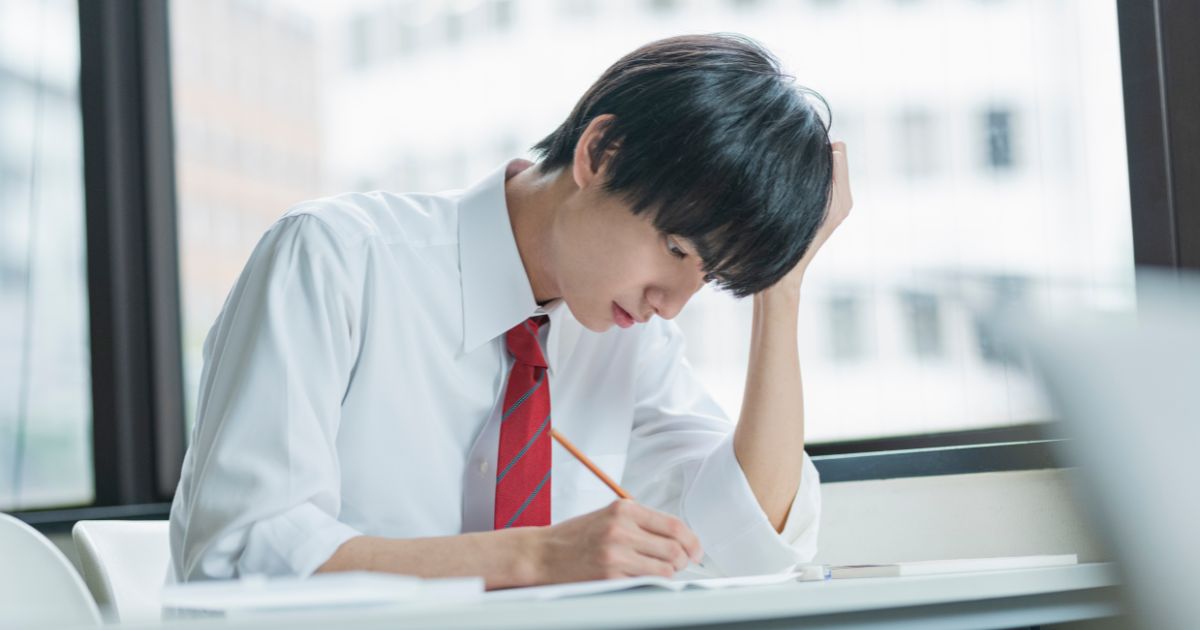
メンタルがボロボロになっているときは、集中力ややる気が落ちて、受験勉強に専念しづらくなります。
ストレスが蓄積すると、集中力や記憶力にも関係する脳の「前頭前野」という部分の働きが弱まることがあります。(参考:東邦大学「ストレスと脳」)
そのため、「やる気が出ない」「集中できない」と感じることは、怠けやサボりではなく、過度なストレスや疲労のサインだといえるでしょう。
影響②身体的症状が出る
強いストレスや生活習慣の乱れが続くと、自律神経のバランスが乱れ、さまざまな身体的症状が現れることがあります。
例えば、以下の症状が見られる場合は、自律神経の乱れを疑ってみてください。(参考:一般社団法人 起立性調節障害改善協会「自律神経の乱れの症状とは?改善方法・原因を現役医師が解説」)
- 寝つきが悪い
- 寝ても疲れが取れない
- 食欲がないのに食べる
- 食べてもすぐにお腹が減る
- 食後に胃がもたれやすい
- 便秘や下痢がある
- 頭痛や肩こりがある
- 手足が冷える
- 皮膚や髪が乾燥する
影響③情緒が不安定になる

ストレスによって自律神経が乱れると、気分の浮き沈みが激しくなり、情緒が安定しづらくなることがあります。
アドレナリンなどのストレスホルモンの影響で交感神経が過剰に活性化し、緊張しやすくなったり、イライラが続いたりすることがあります。
以下のような状態が続いている場合は、過剰なストレスが溜まっているサインかもしれません。(参考:一般社団法人 起立性調節障害改善協会「自律神経の乱れの症状とは?改善方法・原因を現役医師が解説」)
- なぜかイライラする
- 緊張しやすくなる
受験でメンタルがボロボロになったときの6つの解決策
過度なストレスで心身に影響が出ているときは、リフレッシュの時間を取ることが大切です。
受験期間中は、勉強以外に時間を使うことに不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、心身の不調を抱えたままでは集中力が続かず、努力が結果につながりにくくなってしまいます。
適度にリフレッシュすることで、効率よく学習を進めやすくなるでしょう。
この章では、受験でメンタルがボロボロになったときの解決策を紹介します。
解決策①休養を取る

メンタルに限界を感じたときは、まずしっかりと休養を取りましょう。
休養には2つの側面があります。(参考:厚生労働省「休養・こころの健康」)
- 休むこと:心身の疲れを回復させ、活力を取り戻す
- 養うこと:身体的、精神的、社会的な健康能力を高める
心身のバランスを整えるためにも、以下のような工夫をして休養の時間を確保しましょう。
- 疲れているときは勉強を休む日をつくる
- 勉強しない時間帯を設定してメリハリをつける
- 夜更かしは控える
解決策②適度な運動をする
勉強の合間に適度な運動を取り入れましょう。
運動によって分泌されるセロトニンやエンドルフィンには、心の安定やリラックス効果があります。
セロトニンは心身をリラックスさせ、不安や意欲低下を防ぎます。(参考:量子科学技術研究開発機構「セロトニン低下によってやる気が下がる仕組みを明らかに-うつなど疾患の病態理解や治療法開発のための重要な手がかり-」)
エンドルフィンには痛みの緩和や気分を良くする効果があります。(参考:国立消化器・内視鏡クリニック「「幸せホルモン(幸福物質)4つ」ドーパミン・セロトニン・オキシトシン・βエンドルフィンとは?」)
部活動や体育の授業以外でも、日常的に体を動かす習慣を持つことで、メンタルケアにつながります。(参考:運動・身体活動と公衆衛生「運動・身体活動とストレス・メンタルヘルス」)
解決策③質の良い睡眠を取る

睡眠はストレス軽減において非常に重要です。
睡眠によって自律神経が整い、心と身体の回復が促されます。
睡眠不足が続くとストレスホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌され、免疫力や記憶力が低下するおそれがあります。(参考:鎌倉市「【新型コロナウイルス関連】『感染予防の基本と免疫力アップ』で健康づくり」)
特に、夜更かしやスマートフォンの使いすぎは注意が必要です。就寝前にリラックスする時間を確保し、決まった時間に眠る習慣を心がけましょう。(参考:佐野真莉奈・北原祐理・河合啓太朗・下山晴彦「睡眠がメンタルヘルスに与える影響に関する研究動向と今後の展望――交替制勤務者に着目して――」)
解決策④今の気持ちを書いてみる
気持ちが混乱しているときには、頭の中のモヤモヤを文字にすることで整理できます。
ノートや日記に自分の今の感情や悩みを書き出すことで、冷静に自分を見つめ直すきっかけになります。
文章で書くのが難しければ、箇条書きやイラスト、落書きでも構いません。
書き出すことで新たな気づきや解決策が見つかる可能性があります。(参考:厚生労働省「こころもメンテしよう 若者のためのメンタルヘルスブック」)
解決策⑤音楽を聴く

自分の好きな音楽を聴く、または歌うこともリフレッシュに効果的です。
音楽には気分転換やリラックス効果があり、アップテンポな曲は元気を引き出し、ゆったりとした曲は気持ちを落ち着かせる働きがあります。
歌うこと自体もストレス解消につながるため、大きな声を出すことで気分がスッキリすることもあるでしょう。(参考:厚生労働省「音楽を聞いたり、歌を歌う」)
解決策⑥人に相談する
ストレスや不安をひとりで抱えず、信頼できる人に相談しましょう。
悩みは話すことで軽くなることが多く、具体的なアドバイスや気づきを得られることもあります。
親や先生、友人など自分が話しやすい人を頼ってみてください。受験が近づいてストレスを感じやすい時期には、以下の記事も参考にしてみてください。
メンタルがボロボロなときに家族ができる3つのサポート
受験生でお子さんのメンタルがボロボロになっているとき、どのようにサポートすればいいのか悩んでいる親御さんもいるでしょう。
この章では、お子さんを支えるために親御さんができるサポートについて解説します。(参考:こころの耳「ご家族にできること」、あしたのクリニック新宿院 「うちの子は受験うつ?周りができる対策や治療法などをくわしく解説」)
サポート①話を聞き、理解と共感を示す

お子さんの様子がいつもと違うと気づいたら、まずは話をじっくり聞きましょう。
「やる気が足りないのでは?」「考えすぎだよ」と言いたくなるかもしれませんが、お子さんの言葉は否定しないようにしましょう。
また、「まずは数学の基礎固めからやりなさい」「私が高校生の頃はもっと勉強していたよ」といったアドバイスも、今は我慢しましょう。本人が求めていない助言ははかえって逆効果になる可能性があります。
大切なのは、理解と共感を示すことです。
お子さんが感じているつらさや焦りに寄り添い、言葉に耳を傾けましょう。
「受験って大変だよね」「がんばっているね」といった言葉をかけるだけでも、お子さんは心強く感じるはずです。
もし、お子さんがあまり話したがらない場合は、無理に気持ちを聞き出そうとしなくて大丈夫です。
「話したくなったらいつでも聞くよ」と、いつも気にかけて見守っている姿勢を伝えてください。
サポート②十分な休養をとらせる
受験中は、無理に勉強をさせるのではなく、しっかりと休養をとらせることが大切です。
元気を出させようと外出に誘ったり、イベントを計画したりするよりも、まずはお子さんが心と体を休めてほっとできる環境を整えることを優先しましょう。
お子さんが好きなメニューをさりげなく作ってあげたり、静かでゆったりできる時間や空間を作ってあげたりすることもオススメです。
サポート③生活習慣を整えるサポートをする

生活習慣を整えることは、親御さんができるサポートの中でも非常に大切なことのひとつです。
例えば、食事の時間を一定にしたり、朝はカーテンを開けて自然光を入れることで、本人が規則正しい生活を送りやすくなります。
そのためには、家族全体の協力が必要です。お子さんが勉強や就寝している時間帯には静かに過ごすなど、家族内でのルールを共有しておくとよいでしょう。
気持ちが不安定なときだからこそ、こうしたさりげないサポートが大きな支えになります。
メンタルを維持しながら受験勉強を続ける6つのコツ
メンタルが安定してきたら、受験勉強を進めるうえで、過度なストレスを防ぐ工夫を取り入れていきましょう。
そうすることで集中力を持続しやすくなり、学力の向上にもつながります。
この章では、メンタルを整えながら勉強を続けるためのコツを紹介します。
コツ①学習計画を立てる
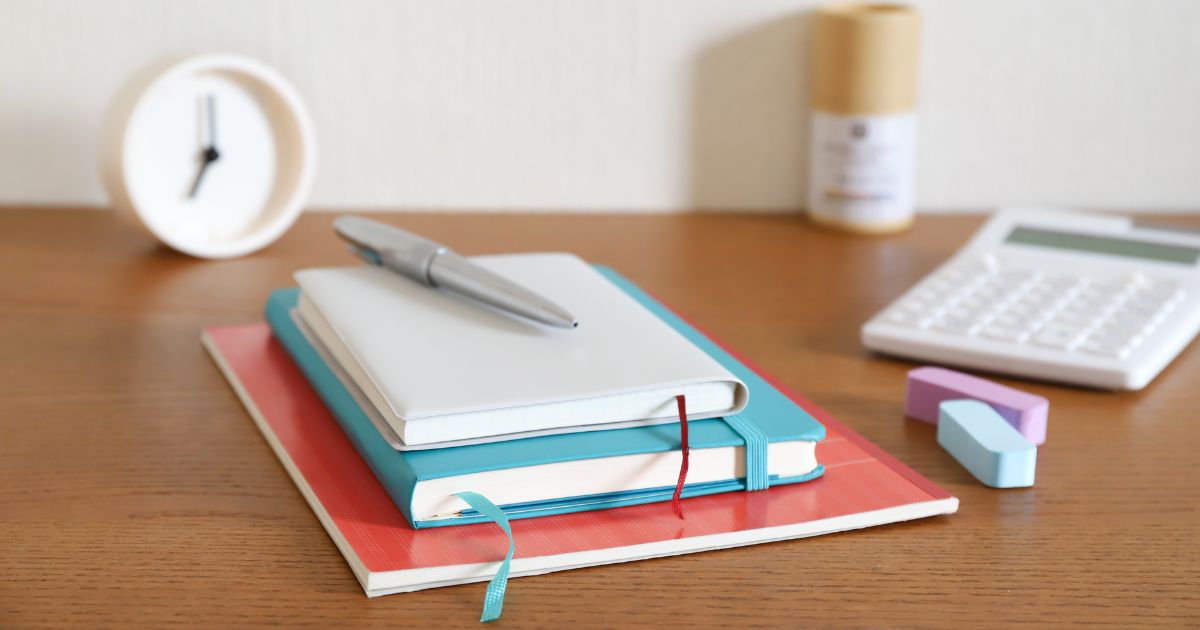
学習計画を立てることで、何をいつまでにやるべきかが明確になり、不安や焦りを減らせます。
入試日程から逆算して計画を立てると効果的です。試験科目や苦手分野を把握することで、勉強内容の優先順位がつけやすくなります。
学習計画を立てる際は、以下の点を整理しましょう。
- 入試や模試の日程
- 試験科目と出題形式
- 現在の学力と目標偏差値の差
- 1日に勉強に使える時間
- 各科目の得意・不得意
注意点は、最初から頑張りすぎないことです。
はじめはリハビリ期間と考え、少しゆるめの目標を設定するのがオススメです。慣れてきたら、徐々に勉強時間や学習量を増やしていきましょう。
コツ②学力が伸び悩んでも落ち込まない
受験勉強では、期待どおりに学力が伸びない時期もありますが、必要以上に落ち込む必要はありません。
伸び悩んでいるときは、「正しく理解できていない」「勉強方法が合っていない」といった原因があるかもしれません。
これは、つまずきポイントに気付き、改善するチャンスとも言えます。
以下の点を整理して、改善に活かしましょう。
- 正しく理解できていない単元や分野
- 間違えやすい問題の傾向
- 学習内容のかたよりの有無
誰にでも伸び悩む時期はあります。焦らず冷静に現状を分析し、学力向上につなげていきましょう。
コツ③日々の努力を振り返る
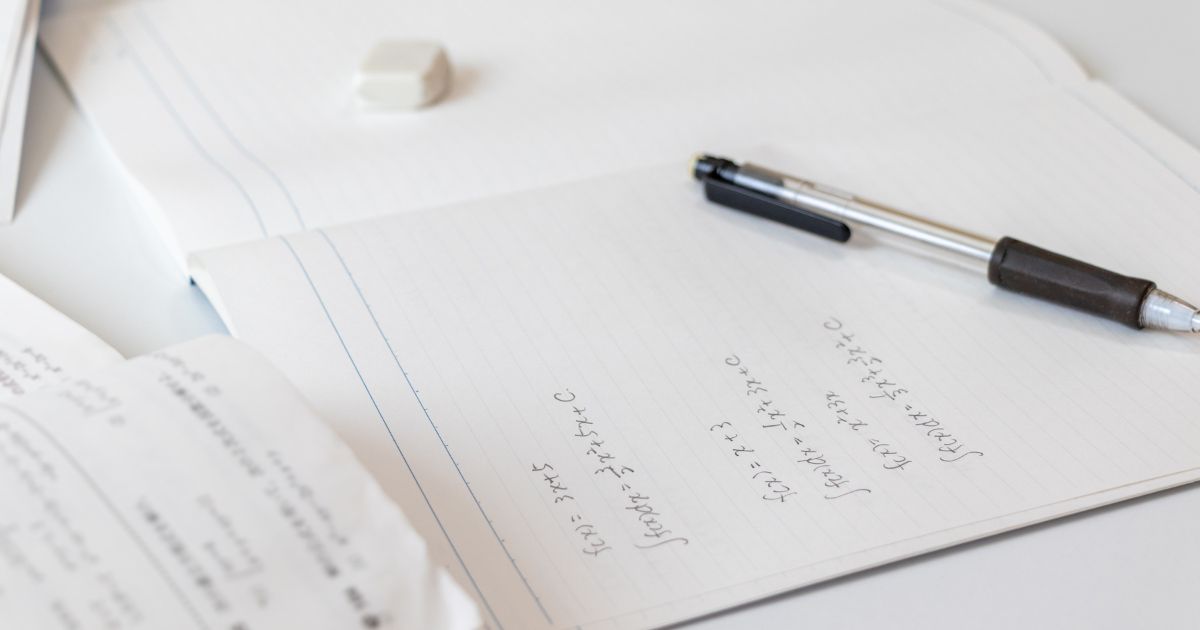
努力を振り返ることで、モチベーションを維持しやすくなります。
普段はテストや模試の結果に一喜一憂してしまうかもしれませんが、「集中できる時間が増えた」「問題を解くスピードが速くなった」といった小さな成長にも目を向けてみましょう。
以下のような習慣を取り入れるのがオススメです。
- ノートやアプリで学習時間・内容を記録する
- 1週間や1か月おきに成果を整理する
- 小さな「できた」を探す
最初は成果を感じづらく、くじけそうになる日もあるかもしれません。しかし、合格はこうした小さな努力の積み重ねの先にあります。自分の成長をしっかり認めてあげましょう。
コツ④こまめに休息をはさむ
勉強中は、合間に短い休憩をとることも大切です。
集中力の持続時間は個人差があります。ずっと集中し続けるのは難しく、無理に続けても効率が落ちてしまいます。
オススメは「ポモドーロ・テクニック」という方法です。
- 25分集中したら5分休憩
- これを4セット繰り返したあと、15〜30分の休憩をとる
このように短い休憩を挟むことで、集中力を保ちやすくなり、学習効率も高まります。(参考:森田ゆき『賢い人の質と速さを両立させる時短100式』)
必ずしもこの時間設定にこだわる必要はありません。自分の集中力や疲れ具合に応じて、柔軟に休憩を取り入れてみてください。
コツ⑤受験後の理想を想像する

モチベーションが下がったときは、受験後の理想の姿を具体的に思い描いてみましょう。
これは「メタアウトカム」と呼ばれる脳科学的アプローチで、自分の目標を達成したあとに得られる感情やメリットを想像することで、やる気を引き出す効果があります。
モチベーションが下がったときは、以下のような質問に答えてみましょう。(参考:NLP-JAPAN ラーニング・センター「脳をやる気にする!心理学でモチベーションを高める9つの方法」)
- 目標を達成すると、さらに何が得られる?
- 目標達成によって、どんな可能性が広がる?
- この目標を達成する意義や意味とは?
ただし、理想を想像するだけで満足してしまわないよう注意が必要です。
大切なことは、実行に移すこと。日々の生活リズムを整えて、学習スケジュールに沿って着実に取り組むことが欠かせません。
コツ⑥受験経験のある人の話を聞く
受験に不安を感じたときは、経験者の話を聞いてみましょう。
ひとりで頑張っていると、壁にぶつかったときの乗り越え方がわからず、悩みを抱えやすくなります。
経験者の話を聞くことで、同じような状況をどう乗り越えたかという具体的な方法や考え方を学べます。
また、効率的な勉強方法のヒントやモチベーション維持にも役立つでしょう。
以下のような方法がオススメです。
- 学校の先生に相談する
- 塾講師に話を聞く
- 志望校のオープンキャンパスで在校生と話す
ひとりで悩まず、周囲の知恵や経験を上手に活用することで、前向きに受験勉強を進められます。
受験でメンタルがボロボロになったときの相談先
つらさや困りごとが解決できないときは、適切な相談先を見つけることが大切です。
この章では、不眠やうつなどこころの悩みがあるときに頼れる相談先を紹介します。
相談先①保健所、保健センター

全国の保健所や保健センターでは、不眠・うつなど、こころの病気に関する悩みのほか、家庭内暴力やひきこもり、不登校など、思春期に関する問題の相談も受け付けています。
医師などの専門家に相談できる場合もあります。「病院の受診はハードルが高いけれど、誰かにに話を聞いてほしい」という場合は、まず連絡してみましょう。
参考:保健所、保健センター
相談先②精神保健福祉センター
こころの健康に関する相談のほか、精神医療やアルコール、薬物の問題、思春期・青年期の相談にも対応しています。
医療が必要かどうかを判断する助けにもなり、近隣の医療機関を紹介してもらえる場合もあります。受診を迷っているときは、ぜひ活用してみましょう。
相談先③こころの健康相談統一ダイヤル

こころの問題について、本人はもちろん、親御さんなど周囲の人も相談できる公的な窓口です。
国や自治体が運営しているため、相談は無料で、秘密も守られます。なお、一部通話料がかかる場合があります。
電話をかけると、最寄りの公的な相談機関につながります。
- 番号:0570-064-556(おこなおう まもろうよ こころ)
ただし、NTTコミュニケーションズが定める通話料が発生します。通話料割引サービスや携帯電話の無料通信枠は適用されません。また、相談対応の曜日・時間は、都道府県によって異なります。ご注意ください。
こころの健康相談統一ダイヤルのほかにも、さまざまな電話相談窓口があります。気軽に相談してみましょう。
相談先④キズキ共育塾・キズキ家学
私たちキズキ共育塾では、不登校・ひきこもり・中退からの学び直しを支援し、これまでに8,000人以上の卒業生をサポートしてきました。
「登校がむずかしい時期でも、キズキ共育塾には通えた」「学び直しで自信がついた」という声も多くいただいています。
学力にブランクがある人や、家庭だけでは解決が難しい人に向けて、学習指導だけでなくメンタル面や生活面での支援も行っています。
以下のようなニーズにも対応可能です。
- 勉強の習慣をつけたい
- 一人では勉強が続けられない
- 気持ちに寄り添ってほしい
キズキ共育塾・キズキ家学では、受験ストレスによって勉強が継続できなくなった場合も、スタッフが丁寧にサポートいたします。
LINEや電話での相談も受け付けていますので、まずはWebサイトをご覧ください。
まとめ ~受験でメンタルがボロボロなときは、リフレッシュと学習方法の工夫を取り入れよう~
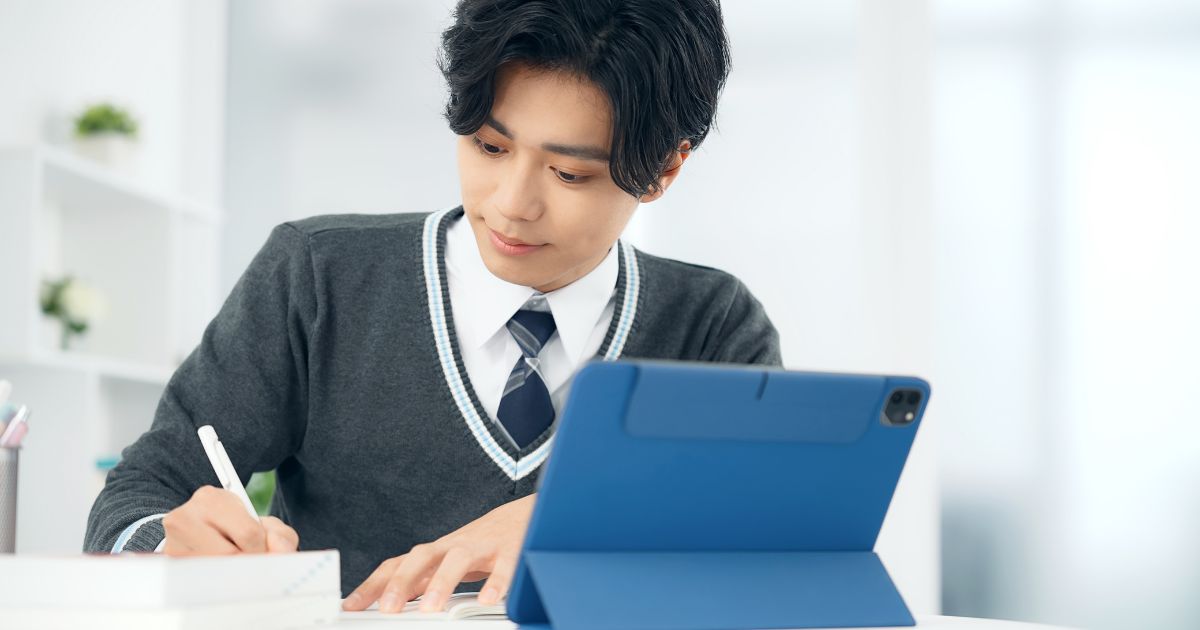
受験で大きなストレスを感じるのは、決して珍しいことではありません。心の調子が一時的に崩れるのも、当然の反応です。
ただし、その状態を放置してしまうと、心身の不調によって勉強が手につかなくなるおそれもあります。
まずはリフレッシュの時間を取り入れ、ストレスや疲労をやわらげることが大切です。
そして、ひとりで悩まず、相談できる環境を見つけることも忘れないでください。
キズキ共育塾はこれまで、受験や学習に悩む多くのお子さんと親御さんをサポートしてきました。
お子さんの勉強や受験について、少しでも気がかりなことがあれば、ぜひお気軽に、あなたの思いをお聞かせください。