発達障害で宿題をしない子、その理由、親ができる7つの対応、5つの接し方
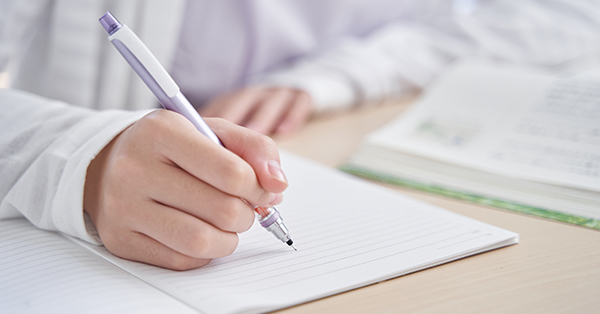
こんにちは。発達に特性のある生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、「発達障害があって、宿題をしないお子さん」のことで疑問や不安を抱えていませんか?
- 発達障害がある子どもに宿題をさせるには?
- 宿題をしない子どもに接するときの注意点は?
このコラムでは、発達障害が原因で宿題をしない子どもへの対応と、接するときのポイントについて解説します。
宿題をしない子どもの対応に悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでみてください(診断を受けておらず「うちの子は発達障害かもしれない」という親御さんにも役立つ内容です)。
※ただし、ご紹介する対応などは、あくまでも例です。実際のあなたのお子さんに向いた対応などは、「発達障害のある子どもの、宿題(勉強)」に詳しい塾やサポート団体に相談することで、具体的に見つかります。
私たちキズキ共育塾は、発達に特性のあるお子さんのための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
宿題をしない子どもは発達障害が原因のこともあります
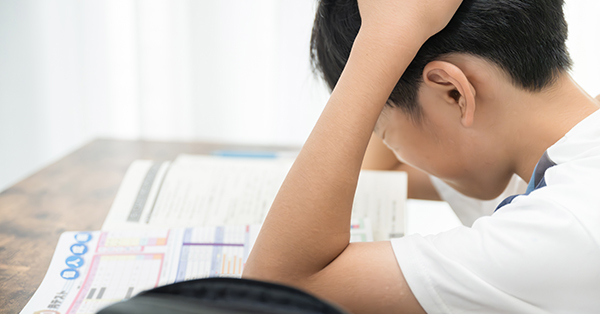
子どもが宿題をしないこと自体は珍しいことではありません。しかし、そもそも宿題に取り組むことができない、もしくは取り組むのが困難な子どももいます。
そのような場合、発達障害の特性が影響している可能性があります。
発達障害とは、脳の機能の特性によって生活面や学習面に困難がある状態のことです。
つまり、発達障害がある子どもは、意志の弱さや努力不足のせいではなく、生まれつきの特性のために宿題に取り組めていない可能性があるということです。
ただし発達障害だからといって、誰もが宿題をできないわけではありません。工夫しだいでは自然と宿題をできるようになりますので、ご安心ください。
ちなみに私たちキズキ共育塾にも、発達障害が原因で宿題をすることに困難を感じている生徒さんが通塾しています。
発達障害があるお子さんがいる人や、宿題をしない子どもの発達障害を疑っている人は、ぜひお気軽にご相談ください。
発達障害が原因で宿題をしない子どもの心理
発達障害が原因で宿題をしない子どもに対応するときは、特性だけでなく、本人の気持ちも理解しておくことが重要です。
この章では、発達障害の特性と子どもの心理について解説します。
ただし、発達障害だからといって、以下に解説する特性・心理がすべてあてはまるとは限りません。性格も特性も子どもによって異なるという点に、ご留意ください。
ADHDの場合
ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害、Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)とは、不注意性や多動性・衝動性の特性から日常生活などに困難が生じる発達障害の一種のことです。
ADHDの特性は大きく、以下の2つの特性に分けられます。
- 不注意性:忘れ物やケアレスミスが多い、注意散漫、整理整頓・管理が不得意
- 多動性・衝動性:落ち着きがない、気が散りやすい、後先考えず行動する
また、ADHDのある子どもは、以下のような心理から宿題を避けている可能性があります。
- 他にやりたいことがあって宿題に意識が向かない
- 宿題を始めたけどいつのまにか別のことに集中していた
- 何から手をつけていいかわからないから後回しにしよう
- 得意な教科以外に手を付ける気になれない
ADHDのある子どもの特徴・困りごとについては以下のコラムで解説していますので、ぜひご覧ください。
ASDの場合
ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。
ASDがある子どもに見られる特徴は、以下のとおりです。
- 相手の身振りや表情の意味、意見・気持ち、発言の意図・意図などを察しづらい
- コミュニケーションの齟齬が生じやすい
- 自分の考えと別の可能性を想定しづらい
- 相手の立場に立って考えることが苦手
- 比喩や冗談を理解しづらい
- こだわりが強い
- 興味関心の範囲が狭い
- 一つのことに集中しすぎる
- 興味関心のない領域に関する知識が著しくない
また、ASDのある子どもは、以下のような心理から宿題を避けている可能性があります。
- 設問の意図がわからなくてどうしたらいいかわからない
- 課題が抽象的でどう取り組んでいいかわからない
- 興味のない教科の宿題を進める気にならない
- 宿題の出方が変わって混乱している
ASDのある子どもの特徴・困りごとについては以下のコラムで解説していますので、ぜひご覧ください。
LD/SLDの場合
LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害、Learning Disorder/Specific Learning Disorder)とは、読む・書く・計算する・推論するなど、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。
LD/SLDは症状別に、以下の3つの種類に分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
症状は1つとは限らず、複数が併存していることもあります。
LD/SLDのある子どもは、以下のような心理から宿題を避けている可能性があります。
- 音読の宿題が出たけど上手に読めないからやりたくない
- 綺麗に字が書けないから提出物を見られるのが恥ずかしい
- 基本的な計算ができないから算数の宿題をやりたくない
LD/SLDのある子どもの特徴・困りごとについては以下のコラムで解説していますので、ぜひご覧ください。
補足:感覚過敏・疲労の影響が大きい子どももいます
感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚の五感の一部、または複数からの刺激を過度に感じることで、苦痛や不快感が生じている状態のことです。(参考:イルセ・サン・著、枇谷玲子・訳『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』、岡田尊司『過敏で傷つきやすい人たち HSPの真実と克服への道』)
発達障害がある人は、感覚過敏も併存することがあります。ASDがある人に多いとされていますが、ADHDの場合にも現れることがあります。
もしお子さんが帰宅後も疲れた顔でぐったりしているようであれば、感覚過敏の影響が大きいのかもしれません。
感覚過敏の場合、通学中や学校生活のなかで、人混みや生徒の大きな声にさらされることが強いストレスになっている可能性があります。
疲労が溜まりやすいので、宿題をする余力が無くても不思議ではありません。
感覚過敏が疑われるときは、まずは専門医の診断を受けてみてください。
そのうえで学校の先生に相談し、症状を緩和できる道具の持ち込みや、環境調整をお願いすることをオススメします。
ADHD・ASDと感覚過敏の関係については、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジのコラム「ADHDと感覚過敏の関係 対策を解説」で解説しています。よかったら読んでみてください。
発達障害が原因で宿題をしない子どもへの7つの対応

この章では、発達障害が原因で宿題をしない子どもへの対応を7つ解説します。
対応①特性に合った学習環境を整える
お子さんの特性に合わせて学習環境を調整しましょう。
特にADHD・ASDのある子どもの場合は、以下を意識してください。
- ADHD:
勉強部屋を整頓して刺激になる物を視界に入れないようにする
スマートフォン、タブレット、ゲーム機などを別の部屋に置く - ASD:
話し声や物音が届きにくい静かな部屋で勉強させる
イヤーマフやノイズキャンセリング機能の付いたヘッドフォンを使う
また、ADHDのある子どもは、宿題をする場所を1つに絞らず、お気に入りのカフェをはしごするのも良いでしょう。
家庭で集中しやすい環境を作れない場合は、学校の図書室や近所の図書館に通うのもオススメです。
対応②特性をカバーする教材・勉強道具を使う
最近では発達障害のある子ども向けに、様々な教材やデジタルツールが売られています。
具体的には、以下のような教材・勉強道具が挙げられます。
- 文字の形を触って覚えられる凹凸のある教材
- 音と文字を結びつける音声付き教材
- 行間の広さや文字の大きさを調整できる教材
- 点線で示された文字をなぞる練習帳
- 書き順がイラストで示された教材
- の大きさが異なるノート
特に、LD/SLDのある子どもの場合、特性をカバーできる勉強道具を取り入れたことで学習上の困難が解消される例は多いです。
LD/SLDのある小学生に役立つツールは以下のコラムで解説されていますので、ぜひご覧ください。
対応③宿題の整理・スケジューリングを手伝う
発達障害のある子どもは、段取りが苦手な傾向があります。そのため、親御さんが率先してスケジューリングを手伝ってあげましょう。
夏休みなどの長期休暇には宿題が多く出されるため、早めに整理することが特に大切です。
予定を立てるときのポイントは、以下のとおりです。
- 宿題を片付けるのに必要な時間を逆算してざっくりとした予定を立てる
- Googleカレンダーなどのアプリを利用する
- スケジュールが実現可能かを再度考えなおす
段取りが苦手な子ども向けの対策は、キズキ共育塾の代表・安田祐輔の著書『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本』で詳しく解説されています。試験勉強に役立つコツも書かれているので、ぜひ読んでみてください。
対応④宿題の量・出し方を先生に相談する
学校の先生によっては、子どもの特性に合わせて宿題の量や出し方を変えてもらえることがあります。
読字障害や算数障害など、お子さんの発達障害の特性を具体的に伝えながら相談するのがポイントです。
ただし、先生の状況や教科の種類によっては、宿題の変更を願い出てもすぐに対応することが難しい場合もあります。
そのため、日頃から担任の先生に障害特性のことを共有しておくとよいでしょう。
対応⑤発達障害に理解のある学習塾に通わせる
発達障害に理解のある学習塾に通うのもオススメです。
学習塾によっては、特性に合わせた勉強面のアドバイスだけでなく、メンタル面のフォローも得られます。
学習塾を選ぶときは、必ず以下の点を確認しましょう。
- 発達障害への専門的な知識があるか?
- オーダーメイトの指導をしているか?
- 親も子どもも相談しやすいか?
- 居心地のよい環境か?
- 通い続けやすいか?
ちなみに、私たちキズキ共育塾でも発達障害のある生徒さんに、特性に配慮した完全個別指導で授業を行っています。よかったら気軽にご相談ください。
発達障害のある子どもの塾選びのコツは以下のコラムで解説していますので、ぜひ参考にしてください。
対応⑥宿題への取り組み方を変える
発達障害の種類しだいでは、宿題への取り組み方を変えるのも効果的です。
- ゲームの要素を持ち込んで遊びながら取り組む
- タスク単位ではなく20分ずつ小分けにして片付ける
- 宿題を5つ終えたら文房具を買えるなどポイント制を導入する
特にADHDのある子どもには、成果に応じた報酬を用意することがモチベーションの維持に有効と言われています。(参考:榊原洋一『最新図解 ADHDの子どもたちをサポートする本』)
宿題へのハードルを下げることができますので、お子さんの特性に合った宿題への取り組み方を考えてみてください。
対応⑦家族で協力する姿勢を見せる
発達障害のある子どもが独力で宿題に取り組むのは困難です。
特に低学年の場合はまだ特性への自己理解が不十分なので、どうすればいいかわからず、不安を感じることが多いです。
そのため、家族みんなでサポートする姿勢を示して、安心させることを優先しましょう。
いつでも相談できる環境を作ることが子どもの成長には大切だということを、忘れないようにしてください。
宿題をしない子どもに接するときの5つのポイント

この章では、宿題をしない子どもに接するときのポイントについて解説します。
ポイント①抱え込まずに先生や専門家に支援を求める
発達障害が原因で宿題をしない子どもに対して、このまま勉強をしなかったらどうしようと不安になる親御さんもいると思います。
そういう人ほど、専門家や学校の先生に話をしてみてください。
特性理解や有効な支援策の検討など、発達障害のある子どもの支援には、専門的な知見が必要な場面がどうしても出てきます。
周囲の助けを借りながら、みんなでサポートするという意識を忘れないようにしましょう。
ポイント②強制せずに誘導する
宿題をしない子どもに宿題を強制しても、状況の好転に繋がることは少ないです。
それよりも、自然と宿題に意識が向くように誘導することが大切です。
特に以下の3点を意識してください。
- 宿題に集中できるように環境調整をする
- きょうだい・家族で一緒に勉強したり本を読む
- 勉強に対して苦手意識を持たせないように注意する
自発的かつポジティブな気持ちで机に向かえるようなサポートを心掛けましょう。
ポイント③宿題を終えたら必ず褒める
勉強への意欲を保つためには、子どもを褒めることが不可欠です。
発達障害のある子どもは勉強面に困難を抱えやすく、学習能力に自信が持っていないことが多いです。なので、宿題が終わったら必ず褒めてあげてください。
頑張ったところを具体的に指摘してあげると、より効果的です。
宿題に取り組む姿勢を評価することで、次も同じようにやればいいんだという安心に繋がります。
ポイント④達成感を得られる工夫をする
褒める以外にも、達成感を与える方法はたくさんあります。
- 自分で目標を決めて挑戦するように促す
- 達成できたらちょっとしたご褒美を与える
- 簡単で得点しやすいテストを受けさせてみる
- きょうだいや友だちと問題を解く早さを競争する
発達障害の特性やお子さんの性格(負けず嫌いかどうかなど)を考慮しながら、達成感を得られる工夫を取り入れてみてください。
ただし、勉強が嫌いになっては元も子もありませんので、無理のない範囲で行うことが大前提です。
ポイント⑤感情的にならない
宿題をしない子どもに接するときには、感情的にならないように注意してください。
発達障害がある子どもは、宿題をしなくてはならないという自覚はあっても、特性の影響で取り組めずに悩んでいる場合が多いです。
そんなときに感情的に叱られると、自己肯定感が低下し、心理面に悪い影響を与えるかもしれません。
また、本人の頑張りだけではどうにもならない問題もあります。
それらを理解したうえで、環境調整やツールの使用など、合理的な解決策を探しましょう。
発達障害の相談先・窓口
発達障害のある子どもがいる親御さん向けの相談先・窓口は、以下のとおりです。
- 発達障害者支援センター
- 教育センター
- 精神保健福祉センター
- 発達障害の検査ができる医療機関
- 発達障害に理解がある塾・家庭教師・フリースクールなど
公的機関・塾ともに無料で相談できる窓口はたくさんあります。まずは、お電話などで問い合わせてみることをオススメします。
なお、発達障害に限らず様々な困りごとを抱えている人のための無料の相談先は以下にまとめてありますので、興味のある人はご覧ください。
まとめ:発達障害があって宿題をしない子も、サポートしだいで勉強・宿題をできるようになります
発達障害のある子どもは、宿題をしたくてもできずに悩んでいることが多いです。
そんなときに宿題を強制したり叱ったりしても、宿題に対して苦手意識が付きやすくなるだけでしょう。
大切なのは、専門家の意見を聞きながら、お子さんの特性に合った環境を整えて、誘導することです。
ご家族・学校の先生・学習塾の講師などと相談しながら、お子さんが安心して宿題に取り組める環境を作ってあげてください。
私たちキズキ共育塾も、発達障害のある子どもを完全個別指導で支援しています。
宿題をしない子どものことでお悩みの人は、ぜひ気軽にご相談ください。












