発達障害とアスペルガー症候群の違いとは? 発達障害の種類を解説

こんにちは。発達障害のある生徒さんを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
あなたは、発達障害やアスペルガー症候群、ASDといった言葉を聞いたことはありますか?
「うちの子は発達障害かも」と心配して、このコラムを読んでくださっている方もいるかもしれません。
発達障害は幼児から大人まで、すべての年代で現れるものです。
明確な要因や治療法は、まだ見つかっていません。それぞれの特性を個性と受け入れ、周りが支えることが重要です。
しかし、発達障害の特徴や正しい情報は、まだ世間に浸透しているとは言い難いのが現状です。偏見や誤解によるすれ違いから、心にダメージを負う子どもも少なくありません。
このコラムでは、キズキ共育塾および筆者自身の知見に基づき、発達障害の定義や特徴、教育制度や支援機関などのサポートのほか、身近な人に心がけてほしい対処法などについて解説します。
私たちキズキ共育塾は、発達障害のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。
目次
発達障害とは?
この章では、最新の発達障害の基本について、解説します。
発達障害の概要〜脳機能の発達に関する障害〜
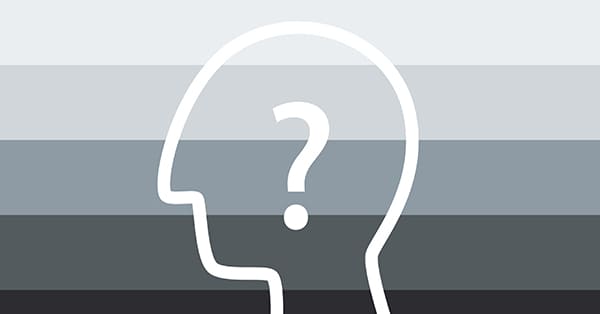
発達障害とは、日常生活や社会生活、学業等においてみられる機能障害を指す言葉のことです。その原因ははっきりとはわかっていませんが、脳の機能的な問題が引き起こしているとされています。
発達障害には、ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)やADHD(注意欠如・多動性障害)などの種類があります。
同じ診断名でも、子どもの個性や発達の状況によって、多彩な症状があらわれるのが発達障害の特徴です。
遺伝的な要素が関連する場合もありますが、発達障害は生まれつきの特性で、育て方やしつけの問題ではありません。
一般的に乳幼児から幼児期に特徴的な症状が現れますが、近年、大人になってから問題が顕在化する、大人の発達障害も話題になっています。(参考:厚生労働省「発達障害」)
また、最近では、吃音やチック症、読み書き障害なども、見落とされやすい発達障害の症例として注目されています。(参考:厚生労働省「発達障害」)
発達障害の定義
アメリカ精神医学会(APA)がまとめた診断基準「DSM-5」では、発達障害は神経発達障害(神経発達症、Neurodevelopmental Disorder)とも表記されます。
これには知的障害や学習障害を含む、以下の7つが該当します。(参考:医学書院『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「発達障害」)
- 知的障害(知的能力障害)
- コミュニケーション障害
- ADHD(注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)
- LD/SLD(学習障害/限局性学習症)
- DCD(発達性協調運動障害)
- チック症
これらの項目は、日本においても法令または日常的に発達障害の一部として扱われることも多い症状です。
近年では、医学的な現場で発達障害という単語を使わないこともあるそうですが、一般的に使用されるシーンでは、神経発達症と発達障害はほとんど区別されていないと考えてよいでしょう。
日本の法令では、医学的に最新の用語や定義が反映されていないものもあります。
例えば、発達障害者支援法における発達障害の定義は、以下のとおりです。
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
(参考:文部科学省「特別支援教育について」 )
国内の発達障害の研究は、まだまだ発展途上です。定義や名称、分類などは、今後も少しずつ変わっていくのかもしれません。
「アスペルガー症候群」は「ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)」へ
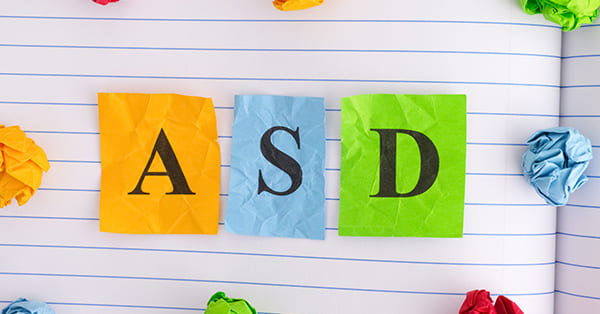
自閉症やアスペルガー症候群という言葉や特性は、2013年に発表されたアメリカ精神医学会(APA)の診断基準「DSM-5」ではすでに使われていません。
これまで自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群などと呼ばれてきた症例は、現在ではASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)に統一されています。(参考:厚生労働省「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」 )
このコラムではわかりやすさを重視し、従来の発達障害やアスペルガー症候群などの用語も、必要に応じて併用しています。
種類①ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)
ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)は、多くの遺伝的な要因が複雑に関与して起こる生まれつきの脳機能障害です。その症状は非常に多様ですが、人口の約1%がASDに該当するとも言われます。
DSM-5では、主に以下の症状が、自閉症スペクトラムの定義とされました。(参考:医学書院『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「発達障害」)
- 社会的なコミュニケーションに持続的欠陥がある
- 固執やこだわり、感覚刺激に対する過敏さ、または鈍感さなどの反復的な様式が2つ以上ある
- 発達早期から、上記の症状が存在している
- 対人関係や学業的・職業的な機能が障害されている
- これらの障害が、知的能力障害や全般性発達遅延ではうまく説明できない
ASDには多くの特性がありますが、その中でも下記の2点がASDの条件として挙げられます。
- 社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥
- 行動、興味、または活動の限定された反復的な様式
ASDでは、多くの場合、言語やコミュニケーションの障害が認められます。程度には個人差がありますが、乳児期早期から他者と関心を共有することが苦手で、社会性が低いのも特徴です。
また、感覚にも問題を抱えているほか、こだわりが強く、切り替えが難しいのもASDの特性です。集団行動が求められる場面などに、1人だけ違うことを始めるのはそのためです。
他に、感覚過敏(光や音や刺激への敏感さが目立つ)、発達性協調運動障害(不器用さが目立つ)などの特性がある人もいます。
一方で、ASDの子どもは、興味の対象(電車や絵など)の方が人間より好きなわけではありません。彼らも家族や友達との交流を望んでいるのですが、多くの人の考え方や振る舞い方がよく理解できないのです。
大勢の人の中にいるとき、彼らは火星人の中に放り込まれたように感じていると言われています。(参考:厚生労働省「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」)
種類②ADHD(注意欠如・多動性障害)
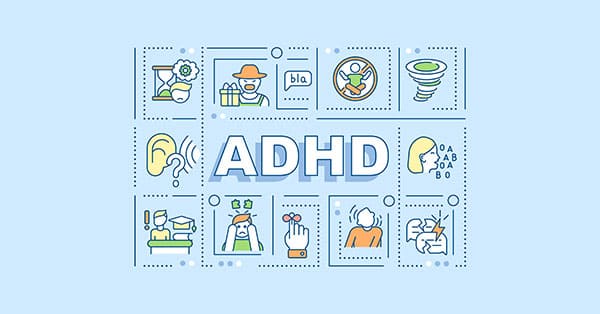
ADHD(注意欠如・多動性障害)の主な特徴として、下記の2点が挙げられます。
- 不注意…忘れ物やケアレスミスが多く、確認作業を苦手とする
- 多動・衝動性…気が散りやすく、貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない
学齢期の小児では、約3〜7%程度が該当すると考えられています。
ADHDの子どもは、脳内の前頭葉や線条体と呼ばれる部位のドーパミンという物質の機能に障害があると言われています。また、「DSM-5」におけるADHDの診断基準は、以下のとおりです。(参考:医学書院『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「発達障害」)
・以下の2点が、同程度の年齢の発達水準に比べて強く認められる
1.活動に集中できない、気が散りやすい、物をなくしやすいなどの不注意
2.じっとしていられない、静かに遊べない多動衝動性
・症状のいくつかが、12歳以前より認められる
・家庭や学校などの2つ以上の状況において、障害となっている
・対人関係や学業的・職業的な機能が障害されている
・その症状が、統合失調症などの他の精神疾患ではうまく説明されない
ADHDの診断は、行動上の特徴に基づいて行われます。神経・身体疾患や虐待、不安定な子育て環境などが要因で、子どもがADHDによく似た症状を引き起こすケースもあるようです。
「うちの子はADHDかも」と思ったら、まずは専門医に相談し、きちんと診断を受けましょう。(参考:厚生労働省「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
種類③LD/SLD(学習障害/限局性学習症)
LD/SLD(学習障害/限局性学習症)とは、特定の分野で理解や習得が著しく困難な発達障害の一種です。以前はLD(学習障害)と呼ばれていました。
学習障害とは、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く・話す・読む・書く・計算する・推論する、といった学習に必要な能力のいくつかに困難がある状態です。
LD/SLD(学習障害/限局性学習症)では、読む・書く・計算する、の分野で理解や習得が著しく困難な場合を表します。
学習障害には、一人ひとりの認知の特性に応じた対応法が重要です。ADHDやASDなどを伴う場合には、これらの特性にも配慮する必要があります。家庭や学校、医療関係者が連携し、総合的な支援を行いましょう。
LD/SLD(学習障害/限局性学習症)では、字が汚い、漢字が覚えられない、繰り上がりと繰り下がりが理解できない、などさまざまな症状が現れますが、特に小児期に生じる特異的な読み書き障害は、発達性ディスレクシアとして知られています。
一般的な子どもでも、学習の程度には個人差があります。LD/SLD(学習障害/限局性学習症)がどうかの診断は、必ず専門家に依頼しましょう。(参考:厚生労働省「学習障害(限局性学習症)」 )
発達障害が生活に及ぼす影響
子どもには、生まれ持った特性があります。発達障害の子どもはその特性の個性が強く、社会的活動が困難な状態に陥りやすくなります。
発達障害の特性が生活に及ぼす影響について、まとめました。
もちろん、発達障害がある場合でも、その特性のあらわれ方は様々です。あくまで一例として、参考にしてみてください。
影響①コミュニケーションが難しい
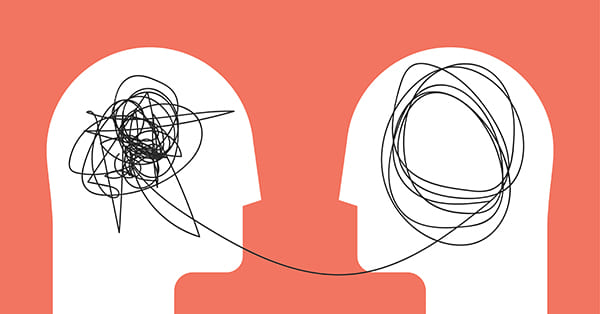
発達障害の特性によっては、相手がなにを考えているかわからないという子どももいます。
そのため、発達障害のない子どもとのコミュニケーションの齟齬が生まれ、お互いをいじわるをする子と思っていることもありえます。
発達障害の種類別に、友達とトラブルになりやすい特性を確認しましょう。
ASDのトラブルになりやすい特性
- 独特のこだわりがあり、周りの友達に合わせて言動を調整しにくい
- 自分の好きなことや得意分野のことばかりを話すため、友達と会話が噛み合わない
ADHDのトラブルになりやすい特性
- 友達とのすれ違いや喧嘩が大きな問題に発展して、友達が離れていく
- 忘れっぽかったり、キレやすかったりすることで、友達から足手まといだと思われる
LD/SLDのトラブルになりやすい特性
- 目で見た文字や文章を読むのが苦手
- 正確に聞いたり伝えたりすることができず、友達との会話にすれ違いが生まれる
発達障害の子どもにも、発達障害のない子どもにも、悪気はありません。ただ、世界の見え方が違うだけなのです。
コミュニケーションをとる前に、それぞれの特徴を知り、自分と違うことを受け入れる準備をしておく必要があります。
発達障害の子どもの友達づくりについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
参考記事:キズキ家学「発達障害の子どもの友達作りのために、親ができる11の方法」
影響②環境に馴染みにくい
発達障害の特性から、環境やルールの変化を受け入れることが難しい傾向にあります。
特定の環境や事物に強いこだわりを持つASDの子どもだけでなく、忘れものやうっかりが多いADHD、計算や識字能力に課題を抱えるLD/SLDの子どもたちも、周りに溶け込むことが難しい場面もあるでしょう。
発達障害の子どもたちは、それぞれ異なる特徴を持ちます。そのため、一人ひとりにあった支援を必要とします。子どもたちのケアは、周りの人たちや環境の整備から始めなくてはいけません。
発達障害は、特別な病気ではありません。生まれながらの特性です。多様な特性のある人が、ともに暮らせる環境づくりは、発達障害のない人にとっても住みよい社会をつくることにつながります。
発達障害のある人も、発達障害のない人も、ともに楽しく過ごすためのルールや設備を整え、みんなが過ごしやすい環境を整えていきましょう。
影響③うつ病や神経衰弱状態を引き起こすこともある

発達障害においては、その特性が引き起こす直接的なトラブルとともに、周囲の無理解による二次障害も深刻な問題です。
発達障害の特性による悩みは、適切な支援を行うことで、ある程度軽減されます。
ところが発達障害による特性で子ども自身が困っているにもかかわらず、𠮟りつけたり一般的な価値観の下で教育しようとしたりすると、ストレスから不登校やうつ病を引き起こす可能性があります。
親御さんにしてみれば、「ほかの子どもと同じように育ってほしい」と思うこともあるでしょう。そして、大勢の子どもたちが過ごす教育現場では、一人ひとりに対応するのは難しい場面もあるかもしれません。
しかし、本当に困っているのは子ども自身です。自分自身が受け入れられず、特性上難しいことを強いられた結果、精神を病んだり、できることまでできなくなったりすることもあります。
発達障害の子どもを支援する最大の目的は、二次障害を防ぐことです。まずは子どもができることを認め、できないことはどうすればよいか、一緒に考えてあげてみてくださいね。(参考:本田秀夫・監修『発達障害がよくわかる本』)
発達障害のある子どもの現状〜支援が必要な子どものほとんどが、学校での支援を受けていない〜
文部科学省は、支援が必要と考えられる児童・生徒が学校でどう過ごしているかを調査した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」を公表しています。(参考:文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)について」)
その結果、支援が必要と考えられる子どもたちのほとんどが、学校での支援を受けずに過ごしていることが明らかになりました。
次は「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」から、発達障害が疑われる児童・生徒の現状について見ていきましょう。
なお、本調査における児童・生徒の困難の状況は学級担任等による回答に基づいて判断されています。専門家の診断によるものではありませんので、ご留意ください。
「学習面、各行動面で著しい困難を示す」男子の割合は、女子の約2倍

学級担任等が回答した内容から、「学習面、各行動面で著しい困難を示す」と判断された児童生徒のうち、男子は女子よりも2倍近く多くなりました。
小学校と中学校では、発達障害が疑われる児童・生徒は男子が全体の約12.1%である一方、女子は全体の約5.4%に留まります。
高等学校でも男子は約2.8%、女子では約1.5%です。
『新版 発達障害に気づいて・育てる完全ガイド』でも、男女比は3~4対1であることが指摘されています。(参考:黒澤礼子『新版 発達障害に気づいて・育てる完全ガイド』)
小学校では約8.8%の児童が「学習面または行動面で著しい困難」あり
学校種別で「学習面又は行動面で著しい困難を示す」と判断された児童・生徒数の割合は、小学校が約8.8%と最も高くなりました。
学年では小学校第1・2学年が最も多く、ともに約12%です。高等学校ではどの学年も約2%程度でした。
本調査で「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とは、聞く・話す・読む・書く・計算する・推論する、のひとつ、あるいは複数で著しい困難を示す場合を指します。
「行動面で著しい困難を示す」とは、不注意、多動性-衝動性、あるいは対人関係やこだわり等について問題があるケースです。いずれの数字も、年代があがるにつれて低くなる傾向が見られました。
発達障害の診断では、行動面での困難も大きな判断材料になります。学校種別の「学習面又は行動面で著しい困難を示す」、「学習面で著しい困難を示す」、「行動面で著しい困難を示す」、「学習面と行動面ともに著しい困難を示す」の割合は、以下のとおりです。(参考:文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」)
小学校・中学校
- 学習面又は行動面で著しい困難を示す:約8.8%
- 学習面で著しい困難を示す:約6.5%
- 行動面で著しい困難を示す:約4.7%
- 学習面と行動面ともに著しい困難を示す:約2.3%
高等学校
- 学習面又は行動面で著しい困難を示す:約2.2%
- 学習面で著しい困難を示す:約1.3%
- 行動面で著しい困難を示す:約1.4%
- 学習面と行動面ともに著しい困難を示す:約0.5%
通級による指導を受けている児童は約1割

同調査では、校内委員会において、現在、特別な教育的支援が必要と判断されている子どもの割合は、次のようになっています。
校内委員会において、現在特別な教育的支援が必要と判断されている児童・生徒
- 小学校・中学校:約28.7%
- 高等学校:約20.3%
しかし、実際に学校内で何らかの支援を受けられている児童生徒の割合は、以下の割合にとどまっています。
特別支援学級などに通級して指導を受けている児童・生徒
- 小学校・中学校:約10.6%
- 高等学校:約5.6%
「授業時間内に教室内で個別の配慮・支援を行っている」児童生徒
- 小学校・中学校:約54.9%
- 高等学校:約18.2%
このように、支援が必要な子どもたちのうち、多くの児童・生徒が、学校での支援を受けられずにいるのです。
こうした子どもたちへの支援不足には、教員の人手不足や環境整備の遅れも指摘されています。
教育現場では、教員の過剰労働も深刻です。発達障害のある子どもたちの支援は、学校だけでなく、専門家のサポートを活用することも検討しましょう。
子どもに発達障害があるとわかったときの対処法〜治療法はないけれど対処は可能〜
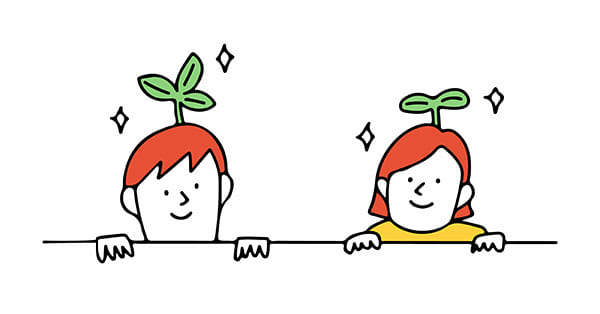
発達障害には、明確な治療法はありません。特性を緩和する薬もありますが、基本的には子どもが過ごしやすいように支え、環境を整備することが大切です。
最適な対処方法はそれぞれ異なりますが、この章では、厚生労働省が公開しているADHDの対処方法などを例に、子どもに発達障害がわかったときに意識してほしい、対処法のポイントを解説します。
前提:発達障害は、その子の個性
発達障害は個性と言われても、すぐには受け入れられないことがあるかもしれません。多くの人にできることができないために、苦労することもあるでしょう。残念ながら、差別的な意識を持っている人もいます。
しかし、どんな子どもにも特別な素質があります。誰もが人より好きなことや苦手なこと、極端なこだわりを持っています。
発達障害の子どもは、それが人よりも目につきやすいだけです。
社会で生活するために訓練する必要はありますが、子どもが悪いわけではありません。もちろん、親のしつけや育て方の問題でもありません。
発達障害の子どもの気持ちは、親御さんにも理解しにくいことがあります。それでもできる限り子どもの世界に寄り添い、共感を示してあげてください。
幼少期に自分は変わっているから人に受け入れられないという経験をすると、子どもの人生観に大きな影が残ります。
「自分は人と少し違うけれど、受け入れられる存在なのだ」と実感できるよう、周りが受け入れる姿勢を見せてあげることが、彼らを支える第一歩となります。
対処法①専門家や支援機関への相談
自分の子どもに発達障害があるとわかったら、まずは専門家に相談することが大切です。
多くの場合、親御さんは教育や医学の専門家ではありません。病院や支援団体の助言を受け、子どもにとって最適な環境づくりをともに考えましょう。
発達障害のある子どもは、家庭だけではなく、学校・地域のサポートや専門家の助言を受けて、みんなで子どもを支えていくことで、より生きやすくなっていきます。
それほど支援が難しくないお子さんの場合でも、突発的なトラブルが起こらないとは限りません。どんな支援機関があり、どんなサポートが受けられるのかは、事前に確認しておきましょう。
こちらで相談できる支援機関を紹介します。
対処法②環境への介入
周りの環境を、子どもが過ごしやすいように整える方法です。机の位置や掲示物を工夫し、集中が保てるように整えます。また、勉強時間を短く区切り、集中できなくなる前に休憩をはさむのも効果的です。
また、忘れ物がどうしても治らないお子さんには筆箱やお財布を蛍光色のものにして、目につく場所に置くという工夫をしている親御さんもいらっしゃいます。
生活や勉強で必要となる情報やスキルを丁寧に教えて、成功体験を積ませることが大切です。
対処法③行動への介入
子どもが好ましい行為をしたときにご褒美をあげることで、行動を変える方法もあります。トラブルになりやすい行動を抑制できたことを褒めることで、子どもが「取るべき行動」を学ぶトレーニングです。
場面ごとに適切な行動を取る訓練を積むことで、子どもは特性があっても人とコミュニケーションを取れる方法を学びます。
この行動変容に関しては、ペアレントトレーニングとして、保護者が子どもへのかかわり方を学ぶトレーニングも知られています。(参考:厚生労働省「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」)
補足:その他の対処法
そのほか、発達障害の子どもへの接し方のポイントは以下のとおりです。
- 頭ごなしの説教や体罰は禁止
- ぶれない態度で善悪の基準を教える
- 指示は短く、はっきり、具体的に
- 視覚的な手掛かりを重視する
- 新しいことや変化が苦手⇒事前に予定を知らせる
- 追い詰めない。干渉し過ぎない
自分にどんな特性があるのか自覚することで、人との関わり方を意識できることもあります。必要に応じて、本人にも自身の特性を伝えましょう。
発達障害の子どもの支援機関

発達障害のある子どもは、福祉的・教育的な支援を受ける権利があります。
生活面ではその子にあった合理的配慮や療育を受けることが、教育面では特別支援教育を受けることが可能です。また、就職面でも国や自治体の支援が受けられる場合があります。(参考:本田秀夫・監修『発達障害がよくわかる』)
そのほか、発達障害の悩み事を相談できる施設や機関には、以下のようなものがあります。
- 市区町村の障害福祉課
- 発達障害者支援センター
- 保健所・児童相談所
- 小児科・児童精神科
- 学校のスクールカウンセラー
- 発達障害(神経発達症群)の支援を行うNPO法人
- 児童発達支援センター
- 精神保健福祉センター
- 子育て支援センター
- 子供家庭支援センター
また、文部科学省のサイトでは、障害の発見や相談・支援にかかわる主な機関とその役割が紹介されています。
環境や状況に応じて、利用しやすい機関を利用しましょう。
発達障害に関するQ&A5選
発達障害があるとわかったら、不安に感じることや心配なことも多いはずです。
この章では、発達障害に関するQ&Aをまとめました。
Q1. 学校やクラスに馴染めないときは、どうしたらいい?

発達障害のある子どもは、特性上、お友達とトラブルになることも少なくありません。
集団の中で生活するためには、相互の努力が必要です。相手が特性について理解し、本人が人との関わり方を学ぶことで、コミュニケーションがとれるようになります。
どうしてもクラスになじめないときは、特別支援学級や特別支援学校に通うこともひとつの方法です。特性に合った支援を受けることで、安心して社会に出る訓練を積むことができます。
Q2. 発達障害に関する教育制度が知りたい
発達障害の子どもの教育制度については、以下のような選択肢があります。
- 通常学級
- 通常の子と同じクラスに通う
- 通級
- 通級による教育という教育をしている通級指導教室に通う
- 特別支援学級
- 特別支援学校
どの学級・学校に通うかは、本人や保護者の意向を聞き、障害の程度を踏まえ、合意形成のうえで、最終的には教育委員会が決定します。(参考:文部科学省「就学相談・就学先決定の在り方について」 )
Q3. 我が子の発達障害を、周囲に公表するべき?

お子さんの発達障害を周囲へ公表すべきかどうかは、一概には言えません。周囲の理解度や環境によっては、公表しないほうがよい場合もあります。
一方で、周囲のサポートや支援を得るためには、特性について理解してもらう必要があります。支援機関の専門家に相談し、子どもにとって最適なタイミングを図りましょう。
Q4. 発達障害の診断を受けることに抵抗があるのですが…
発達障害の現れ方は、人によって差があります。普段の生活の中でお子さんが特に困っていないようであれば、わざわざ発達障害の診断を受ける必要はないかもしれません。
お子さんの性格や、特性の強さによっては、ちょっと落ち着きがないという程度で受け入れられている場合もあるからです。
その反面、発達障害の検査を受けることで、お子さんの状況を正しく理解することにもつながります。また、障害者手帳の交付には専門機関の診断が必要です。
公表するかどうかと同様、発達障害が疑われる場合には、まず専門家のアドバイスを受けてみることをおすすめします。
Q5.大人の発達障害とは?

幼少期に顕在化することの多い発達障害ですが、大人になってから見つかることもあります。会社や社会にうまくなじめず、病院を受診して初めて、障害があることがわかるのです。
大人の発達障害では、子どものころに支援を受けられなかったために、二次障害を発症しているケースも少なくありません。
大人の発達障害にも、就労支援や職場定着の支援が受けられます。こちらも専門家に相談してみましょう。
私たちキズキでも、キズキビジネスカレッジ(KBC)という就労移行支援を行っています。
就労支援を利用することで、自分の特性や悩みについてスタッフと一緒に相談しながら、より自分に合った就職を実現することができます。
ご相談は無料です。気になる方はぜひ問い合わせをしてみてください。
まとめ〜専門家や支援団体に相談し、みんなでお子さんを支えましょう〜

発達障害は、脳の機能障害です。親御さんの育て方や幼少期の経験に問題があるわけではありません。生まれ持った特性として、一生付き合っていくものです。
社会のルールは、人々が気持ちよく過ごすために作られています。
しかし、発達障害のお子さんは、気持ちよく過ごす環境が人とは違うことがあります。そのために、社会のルールを理解するのが難しいのです。
彼らを支援することは、お互いに気持ちよく過ごす環境づくりの一部です。家庭だけ、親御さんだけで抱え込む必要はありません。
ぜひ、スクールカウンセラーや医療機関、市区町村などの専門家・支援者を頼ってください。
専門家・支援者を頼ることで、お子さんはもちろん、保護者であるあなたも、生きづらさを解消することにつながります。
あなたとあなたのお子さんがよりよく過ごすために、お役に立てれば幸いです。
さて、私たちキズキ共育塾は、一人ひとりの生徒さんに寄り添う個別指導塾です。
生徒さんには、発達障害の診断を受けた方や、診断を受けてはいないけれどその傾向が見られる方がたくさん通っています。
私が過去に担当した生徒さんの中には、たとえば、次のような方がいらっしゃいました。
- 登場人物の関係が理解できないため、文章の読解ができない
- 必要なものを手帳やスマホに記録しても、どうしても忘れ物をしてしまう
- 解けない大問にこだわり、飛ばして別の問題に進むことができない
キズキ共育塾では、そのような生徒さんと講師が一対一で、その生徒さんに合った学習方法や進路選択をしていきます。
また授業では、勉強のみならず、生活や進路についても相談ができますし、雑談もできます。
お子さんの発達障害と勉強や発達将来と進路などについてお悩みでしたら、お気軽にご相談ください(ご相談は無料です。また、保護者様のみのご相談も受け付けております)。
なお、キズキビジネスカレッジ(KBC)は、発達障害のある人の就労を支援していますので、就労についてのお悩みはこちらにお気軽にご相談ください。
Q&A よくある質問












