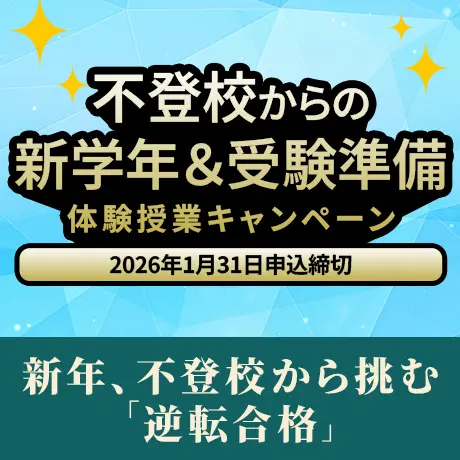勉強を好きになる方法 環境づくりの工夫を解説
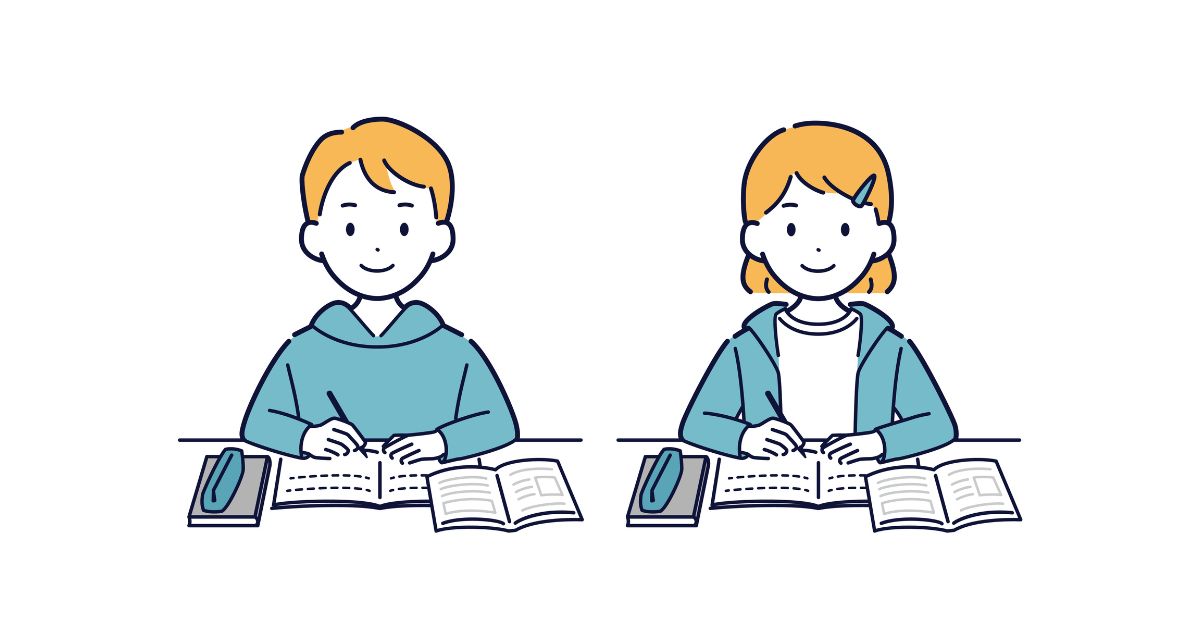
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾、キズキ共育塾です。
このコラムを読んでいるあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 勉強を始めてもすぐに疲れて、続けるのがつらい
- 「やらなきゃ」と思うのに机に向かうのが嫌で仕方ない
お子さんの学習を支えたいが、どんな声かけや関わり方が良いのか迷っている
このコラムでは、勉強嫌いになる原因や勉強が好きな人に共通する特徴について解説します。
あわせて、勉強を好きになる効果的な方法や学習を支える環境づくりの工夫、周囲のサポートの仕方についても紹介します。
勉強が苦手で悩んでいる人や、その支援をしたい人の一助になれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、勉強が苦手ない人のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
勉強嫌いになる5つの原因
子どもが勉強を嫌いになる背景には、理解不足や思い込み、環境的要因など、さまざまな理由があります。
この章では、勉強嫌いになる5つの原因について解説します。
原因①学習内容の難化や理解不足

学習が進むにつれて内容が難しくなると、基礎が不十分な場合に理解が追いつかなくなります。
理解できない時間が増えると、勉強そのものが自分に向いていないと感じやすくなり、嫌悪感や自己否定感につながります。(参考:「「子どもの生活と学びに関する親子調査 2022」結果速報」)
原因②勉強はつまらないという思い込みや失敗への恐怖
勉強は退屈だという思い込みや、テストの失敗への恐怖心が勉強への抵抗感を強めます。
心理学的研究では、失敗体験の積み重ねにより学習性無力感が生じ、努力しても成果が出ないと感じるようになることが知られています。(参考:「学習性無力感とは何か「もう頑張っても無駄だ」と感じる方へ」)
こうした感情が、新しい課題への挑戦にも消極的になる要因になります。
原因③集中できない環境や親の態度など周囲の影響

学習環境は、子どものモチベーションに大きく影響します。
例えば、テレビやスマートフォンが常に近くにある環境では、集中力が途切れやすくなります。
また、親が「勉強しなさい」と命じるだけでは逆効果になり、学びへの関心が低下することもあります。(参考:「中学生の学習意欲を高める大人の言葉・態度に関する調査研究」)
原因④習慣化されておらず勉強が生活に根付いていない
日々の中で勉強が習慣化されていないと、勉強を始めるたびに大きなエネルギーを必要とし、継続が難しくなります。
国立教育政策研究所の調査では、家庭で学習習慣がある子どもほど、学習意欲が高い傾向にあると報告されています。(参考:「平成26年度全国学力・学習状況調査の結果」 )
原因⑤勉強より楽しいことが多く優先度が低い

ゲームやSNS、動画視聴など、すぐに楽しめるコンテンツが身近にある現代では、勉強の優先順位が下がりやすくなります。
しかし、娯楽にはストレス解消の効果もあるため、無理に排除するのではなく、勉強とのバランスを意識することが大切です。
勉強好きな人に共通する5つの特徴
勉強を楽しめる人には、いくつかの共通点があります。
この章では、勉強好きな人に共通する特徴について解説します。
特徴①好奇心と探究心が旺盛で、知ることを楽しむ

新しいことを知るのが楽しい、疑問を持つと自分で調べたくなるといった好奇心や探究心の強さは、学びを前向きに捉える原動力になります。
実際、好奇心が強い子どもは学びに向かう力が強い傾向にあるとされています。(参考:「学習指導要領の構造化を進めるに当たっての諸論点」)
特徴②小さな目標を立てて達成感を積み重ねる
1ページ解いた、昨日より速く問題を解けた、という小さな目標を達成することで、自然と勉強が楽しくなります。
これはスモールステップ法と呼ばれ、継続的なモチベーションの維持に役立ちます。(参考:「スモールステップ方略が目標達成に及ぼす影響」)
特徴③負けず嫌いで友達との健全な競争を楽しめる

勉強好きな子どもは、友達との競争をポジティブに捉える傾向があります。
点数で競い合う、問題を出し合うといった行動の中で、刺激し合いながら成長することを楽しめます。(参考:「義務教育に関する意識に係る調査概要・集計結果」)
特徴④継続して取り組む習慣がある
勉強好きな子どもは、やる気や気分に頼らず、日々少しずつ取り組む習慣を身につけています。
こうした習慣は、自動化された行動として定着しており、学習の継続につながります。
特徴⑤学びをポジティブに捉えられる

学びを点数のためではなく、自分の世界を広げる機会と捉えられる人は、勉強に前向きな姿勢で取り組むことができます。(参考:「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」 )
学びの意味を理解し、自分ごととして捉えることで、長期的に意欲を維持しやすくなります。
勉強を好きになる効果的な方法
学習意欲は、環境や学び方によって変化します。だからこそ、正しいアプローチを取り入れることが大切です。
この章では、勉強を好きになる効果的な方法について解説します。
方法①目標を細分化し、達成基準を明確にする
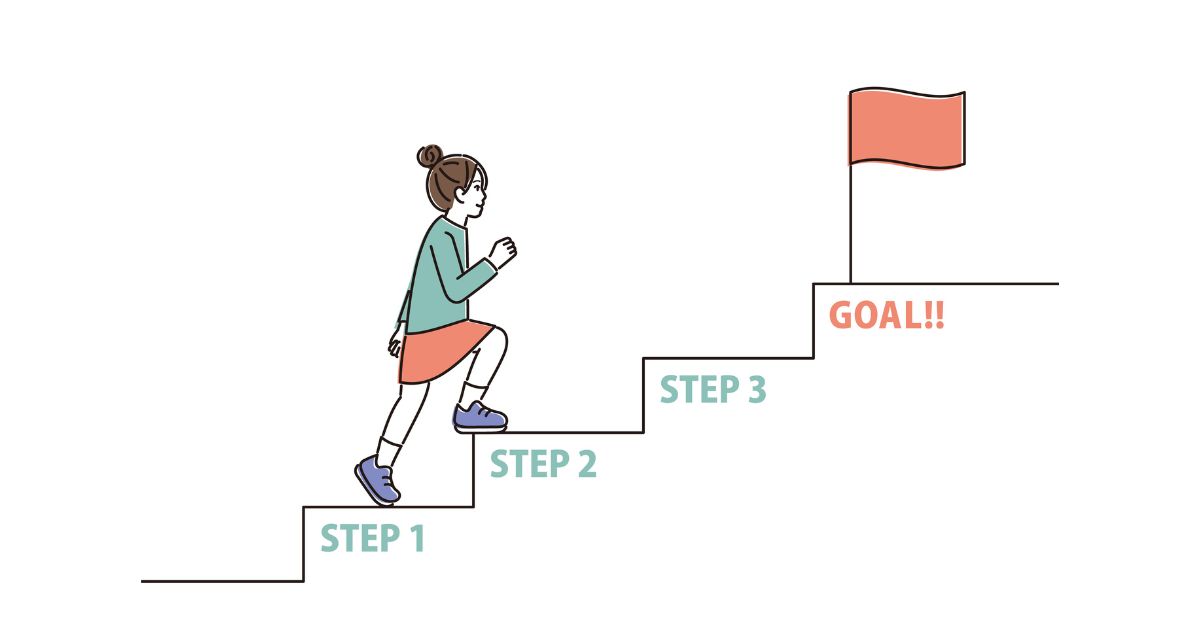
大きな目標だけでは、途中で挫折しやすくなります。そのため、目標は細かく分けて取り組むのが有効です。
例えば、今日は漢字10個を覚える、1問だけ復習する、といった小さな目標を設定すると、達成するごとに達成感が得られます。
こうした小さな成功体験の積み重ねが、自然と学習意欲を高めてくれます。
方法②わからないところを確認し、繰り返し学習する
わからない部分を理解しないまま進めると、自信を持てなくなり、勉強への苦手意識が強まります。
そのため、理解が不十分な箇所では一度立ち止まり、繰り返し学習することが大切です。
同じ問題を何度も解く中で、できたと感じられる瞬間が生まれ、自信につながります。
勉強は一度で理解するものではなく、繰り返しによって定着するものだということを意識しましょう。
方法③テストをゲーム感覚で解き、やり直しで理解を深める

テストに対して苦手意識を持つ人は少なくありませんが、見方を変えると、学びを深めるよい機会になります。
周囲と比較するのではなく、前回より点数を上げる、解くスピードを上げるといった小さな目標を設定すると、テストがチャレンジの場となり、モチベーションの維持に役立ちます。
さらに、やり直しを重視することで、理解をより深めることが可能になります。
方法④ICTやアプリ、動画教材を活用する
スマートフォンやタブレットを活用したICT学習は、紙の教材に比べて取り組みやすさや楽しさを感じやすいという特徴があります。(参考:文部科学省「ICT学習」)
動画教材で視覚的に理解したり、アプリでクイズ形式の問題に挑戦したりすることで、学びが遊びに近づき、抵抗感が減っていきます。
方法⑤夢や将来の目標と勉強を結びつける
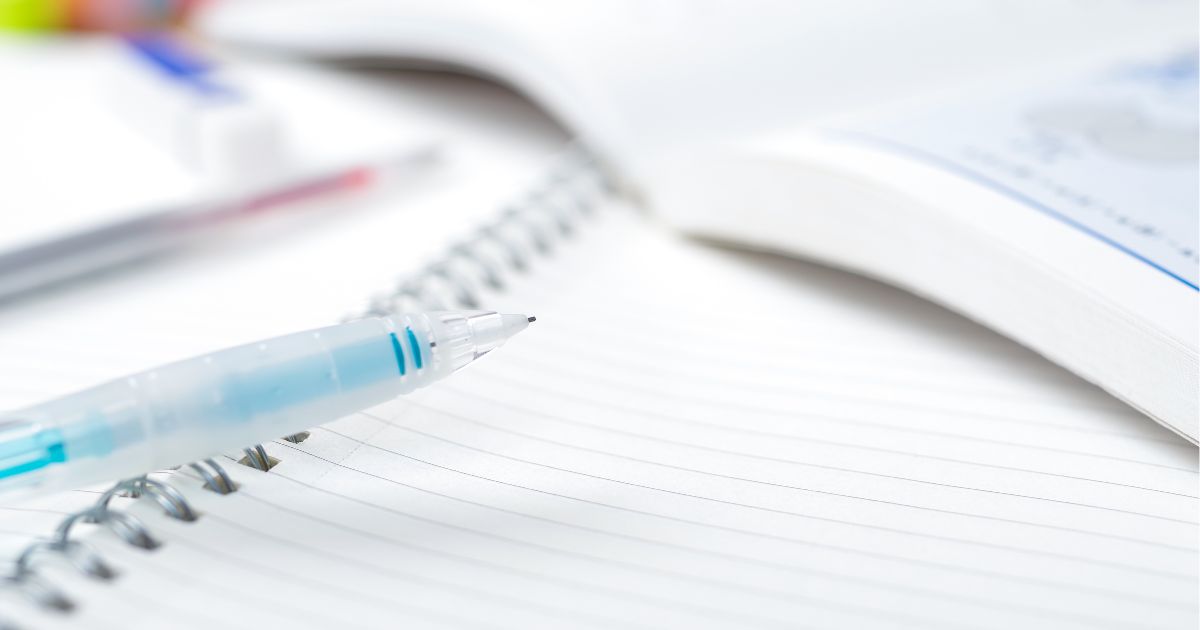
「なぜ勉強しなければいけないの?」という疑問を持ったままでは、意欲を維持するのが難しくなります。
将来の夢や目標と勉強を関連づけることで、自分にとって必要な学びだと実感しやすくなります。
例えば、将来行きたい学校がある、就きたい職業があるなど、具体的な将来像とつなげると、学習へのモチベーションが自然と生まれます。(参考:「「学習意欲に関する調査研究」概要」)
学習を支える環境づくりの工夫5選
勉強を習慣にするためには、学習内容だけでなく、学習に取り組む環境を整えることが非常に重要です。
この章では、学習を支える環境づくりの工夫について解説します。
工夫①勉強に適した静かで整理された空間を用意する
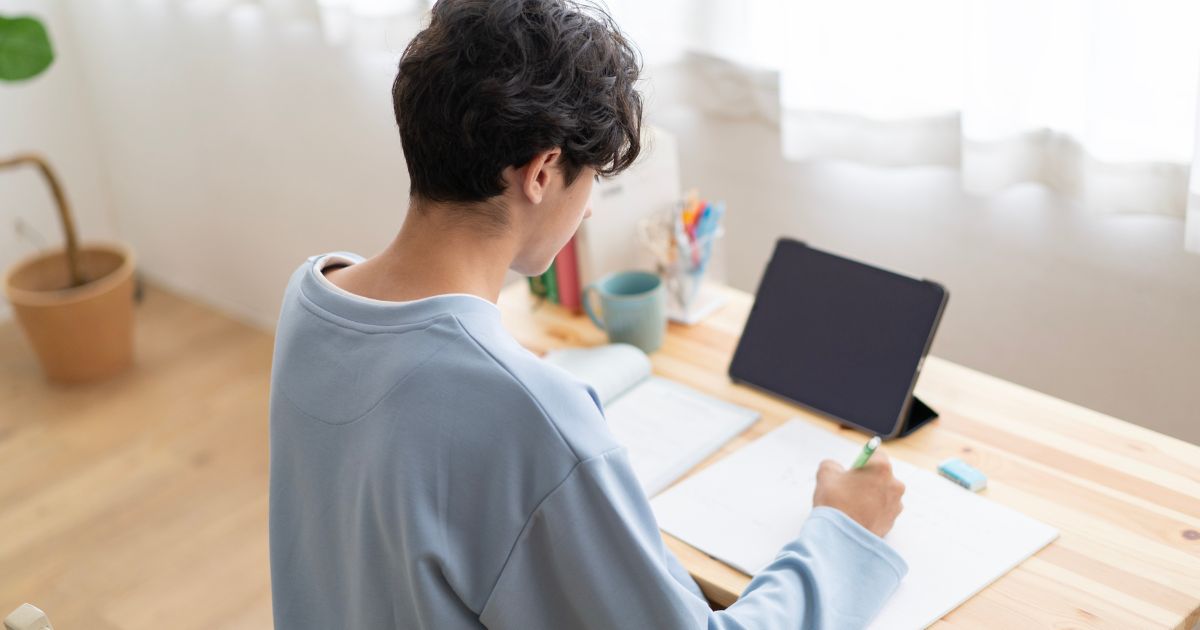
勉強を習慣化するには、まず静かで集中しやすい空間を整えることが大切です。自分で選んだ落ち着いた場所で学べる環境は、学習意欲を引き出します。
例えば、机の上は必要なものだけを置き、周囲の騒音やテレビ、スマートフォンの影響をできるだけ減らしましょう。
室内の明るさや温度も、集中のしやすさに関係します。また、家族や友達と一緒に学習に取り組む時間を作ったり、学習量を少しずつ調整したりすることで、学習への負担を軽減できます。(参考:「学校環境と学習意欲の関係性に関する研究」 )
工夫②学習場所に選択肢を与えて自分で選ばせる
学習場所を1つに固定する方法もありますが、複数の環境を用意し、その中から本人が選べるようにするのも効果的です。
例えば、自分の部屋、リビング、図書館、カフェなど、学習内容や気分に応じて場所を変えることで、新鮮な気持ちで取り組むことができます。自分で選んだという感覚が、主体性とモチベーションを高めてくれるでしょう。
工夫③家族や友達と一緒に勉強する時間を作る

一人での勉強は孤独を感じやすく、集中力が続かないことがあります。そのようなときは、家族や友達と一緒に勉強する時間をつくるとよいでしょう。
親子でのリビング学習や、友達同士の勉強会は、互いに刺激を受けながら学べるため、継続しやすくなります。
わかったという体験を共有することが、学習の達成感にもつながり、勉強を前向きな体験として定着させるきっかけになります。
工夫④勉強量をスモールステップで調整する
はじめから大量の勉強を課すと、子どもはストレスを感じやすくなります。そのため、まずは5分だけや1ページだけなど、小さな目標から始めてみましょう。
少しずつ成功体験を積むことで、勉強へのハードルが下がり、自然と取り組む姿勢が育っていきます。
慣れてきたら、徐々に勉強時間や内容を増やしていくことで、無理なく習慣化が目指せます。
工夫⑤勉強するタイミングを本人に決めさせる

大人から勉強時間を一方的に決められると、子どもはやらされていると感じ、学習への抵抗が強まることがあります。
そこで、勉強するタイミングを自分で決めてもらうことで、主体性と責任感が育ちやすくなります。
もちろん、生活リズムが乱れないように大人が見守ることは必要ですが、最終的な判断を本人に委ねることで、自律的な学習習慣を身につけやすくなります。
子どものためにできる周囲の大人のサポート5選
子どもが勉強を嫌いになるか、好きになるかは、親や教師など周囲の大人の関わり方が大きく影響します。
この章では、周囲の大人ができるサポートについて解説します。
サポート①「なぜ勉強するのか」を一緒に考える

勉強の目的が曖昧なままだと、子どもはやらされていると感じやすくなり、学習を苦痛に受け止めやすくなります。
そこで、大人が一緒に勉強の必要性について話し合い、学ぶ意味を伝えることが大切です。学習内容と将来の夢や日常生活を結びつけて話すと、理解しやすくなります。
例えば、「この漢字を覚えると本がもっと楽しく読めるよ」「計算が得意になると、お金の管理ができるようになるよ」といった言葉かけが有効です。(参考:「「学習意欲に関する調査研究」概要」 )
サポート②努力や成長を具体的に褒める
テストの点数や結果だけではなく、勉強に取り組んだ過程や努力の様子に注目し、丁寧に褒めましょう。
「昨日より計算が速くなったね」「漢字の形がきれいに書けるようになったね」といった、具体的な声かけがポイントです。
結果だけを評価されるとプレッシャーを感じやすくなりますが、努力を認められることで自信が育ち、学習意欲の向上につながります。
サポート③勉強を強制せず寄り添う

「勉強しなさい」と一方的に命じられると、子どもは反発心を持ちやすく、学習に対するモチベーションが下がる原因になります。
そのため、強制するのではなく、寄り添いながら自発的に取り組めるような雰囲気作りが大切です。
例えば、「今やる?それとも少し休憩してからにする?」と選択肢を与えることで、子ども自身が決める姿勢を促すことができます。
サポート④過去の自分との比較で成長を実感させる
他の子どもと比べるのではなく、過去の自分と比較することで、成長の実感が得やすくなります。
「前より丁寧に書けるようになったね」「昨日より計算ミスが減っているね」など、変化や進歩に気づかせる言葉がけが効果的です。
小さな変化を積み重ねることで、自信や達成感が育ち、勉強に前向きな気持ちが生まれやすくなります。
サポート⑤大人自身が学びを楽しむ姿を見せる

子どもは、周囲の大人の姿勢や行動から多くを学びます。大人が学ぶことを楽しんでいる姿を見せることは、子どもの学習意欲にも好影響を与えます。
例えば、読書をしている姿や趣味の資格取得に取り組む様子を見せると、学ぶことは大人になっても楽しいものと自然に伝えられます。
また、親子の会話の中で自身が知ったことなどを共有すれば、学びが日常に根づき、子どもの関心を引き出すきっかけにもなります。
子どもの学習を支援するサービスの活用法3選
勉強に苦手意識を持っている子どもでも、適切なサポートを受けることで、学習に前向きになれることがあります。
特に第三者による支援は、家庭内だけでは補いきれない部分をカバーできるため、有効な手段のひとつです。
この章では、学習を支援するサービスの活用について解説します。
活用法①学習塾を利用する

学習塾では、基礎固めから受験対策まで、幅広い学習内容に対応した指導が受けられます。
プロの講師による体系的なサポートは、勉強のやり方がわからない子どもにとって大きな助けになります。
また、塾に通う友達の存在が刺激となり、学習習慣を身につけるきっかけにもなります。
特にキズキ共育塾では、勉強に苦手意識がある人に対して、学習面だけでなく、メンタル面のサポートにも力を入れています。
活用法②オンラインライブ授業や個別指導を取り入れる
近年は、オンラインを活用した学習サービスも充実しています。
自宅にいながらリアルタイムで授業を受けられるほか、録画で好きな時間に復習できる点が特徴です。
また、マンツーマンの個別指導であれば、自分のペースで理解を深めることができ、集団授業についていくのが難しい子どもでも安心して学べます。
活用法③習い事を通して勉強とつながる楽しさを知る

学習塾以外にも、習い事を通じて学びの楽しさを体感する方法があります。
例えば、スポーツや音楽、美術などの習い事では、集中力・継続力・達成感を得られる機会が多くあります。
こうした経験が、学ぶことは楽しいという前向きな感覚につながり、勉強への意欲も高まりやすくなります。
まとめ~小さな工夫を積み重ねて苦手なイメージをなくそう~

勉強嫌いの背景には、学習内容の難しさ、環境の問題、周囲の関わり方、本人の思い込みなど、さまざまな原因が複雑に絡んでいます。
一方、勉強を楽しめている子どもには、学びを前向きに捉える姿勢や、小さな成功体験を積み重ねる習慣が共通しています。
学習の苦手意識は、日々の小さな工夫やサポートによって、少しずつ和らげていくことができます。焦らず、自信を持てる体験を増やしていくことが大切です。
このコラムが、勉強に対する苦手意識を克服する支えになれば幸いです。
Q&A よくある質問
勉強嫌いになる原因を教えてください。
以下が考えられます。
- 学習内容の難化や理解不足
- 勉強はつまらないという思い込みや失敗への恐怖
- 集中できない環境や親の態度など周囲の影響
- 習慣化されておらず勉強が生活に根付いていない
- 勉強より楽しいことが多く優先度が低い
詳細については、こちらで解説しています。
勉強を好きになる効果的な方法はありますか?
以下が考えられます。
- 目標を細分化し、達成基準を明確にする
- わからないところを確認し、繰り返し学習する
- テストをゲーム感覚で解き、やり直しで理解を深める
- ICTやアプリ、動画教材を活用する
- 夢や将来の目標と勉強を結びつける
詳細については、こちらで解説しています。