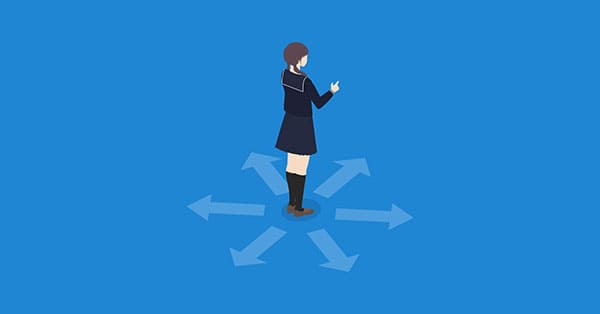ASD(自閉スペクトラム症)のある小学生の特徴 親ができる対応を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
「ASD(自閉スペクトラム症)のある、小学生のお子さん」がいるあなたは、以下のようにお悩みではないですか?
- ASDのある小学生に多い特徴は?
- ASDのある小学生に親ができる対応は?
このコラムでは、ASDのある小学生の特徴や抱えている困りごと、親御さんができる対策の具体例を解説します。
私たちキズキ共育塾は、発達障害のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
ASDのある小学生の特徴
ASDのある小学生には、コミュニケーションや社会的な関わり、こだわりの強さなどの特徴が見られます。
ASDのある小学生に見られる主な特徴は、以下のとおりです。
- 相手の身振りや表情の意味、意見・気持ち、発言の意図・意図などを察しづらい
- コミュニケーションの齟齬が生じやすい
- 会話による意思疎通をうまくできない、会話がかみ合わない
- 「空気が読めない」と言われる
- 一方的なコミュニケーションになりやすい
- 場の状況や上下関係に無頓着
- 他人の発言をそのまま繰り返す
- 人と目線が合いにくい
- 名前を呼ばれても反応しない
- 人に関心がない
- 自分の考えと別の可能性を想定しづらい
- 相手の立場に立って考えることが苦手
- 比喩や冗談を理解しづらい
- 交友関係を広げるのが苦手
- 自分だけのルールにこだわる
- 臨機応変な対応が苦手
- 特定領域の記憶力が優れている
- こだわりが強い
- 興味関心の範囲が狭い
- 好きなことには精通している
- 一つのことに集中しすぎる
- 興味関心のない領域に関する知識が著しくない
- 予定が急変するとパニックになる
ただし以上の特性は、「ASDのあるすべての小学生」に当てはまるわけではありません。個人差が大きい点には注意が必要です。
ASDのある小学生が学校生活で抱きやすい6つの困りごと
この章では、ASDのある小学生が学校生活で抱きやすい困りごとを解説します。
困りごと①授業の内容を理解するのが難しい

1つ目の困りごとは、授業を理解するのが難しいことです。
ASDのある小学生は、聞いたことをそのまま理解するのが苦手なためです。
例えば、授業で複数の指示が出されると、一部しか理解できず、何をすればよいのか分からなくなることがあります。また、話の流れをつかみにくかったり、抽象的な表現を理解しにくかったりするため、教師の指示が十分に伝わらない場合も少なくありません。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと②書くこと・読むことが苦手
2つ目の困りごとは、書くこと・読むことが苦手なことです。
ASDのある小学生の中には、視覚的な情報処理に強みがある子どももいます。そのような特性がある子どもの場合、文字情報の理解や文章の構成が苦手な可能性が考えられます。
例えば、黒板の文字をノートに書き写すのに時間がかかり、指示を聞き逃して、授業についていけなくなる場合があります。また、長文の読解では、文章の要点をつかむのが難しく、理解するまでに時間がかかることもあります。
視覚的な補助や個別のフォローを取り入れると、学習の負担を軽減し理解を深められるでしょう。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと③コミュニケーションのすれ違いが起きやすい

3つ目の困りごとは、コミュニケーションのすれ違いが起きやすいことです。
ASDのある小学生は、他人との意思疎通が難しいことがあるためです。
例えば、会話の流れを理解しづらいため、コミュニケーションが一方通行になりがちです。また、自分の気持ちを言葉で伝えるのが難しいため、周囲とすれ違いが生じる場合もあるでしょう。
円滑にコミュニケーションできるよう、意思疎通のしやすい環境を作ることが大切です。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと④集団行動が苦手
4つ目の困りごとは、集団行動が苦手なことです。
ASDのある小学生は、他人と関わって遊んだり、友達と協力したりなどの行動がむずかしい場合があります。これは、相手の気持ちを察しにくい、こだわりが強い、感覚過敏があるといったASDの特性が関係しているためです。
例えば、友達と協力する必要がある活動で、一人で行動する場合があります。
集団生活に適応しやすくなるよう、周囲の理解とサポートが大切です。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと⑤予定変更や環境の変化にストレスを感じる
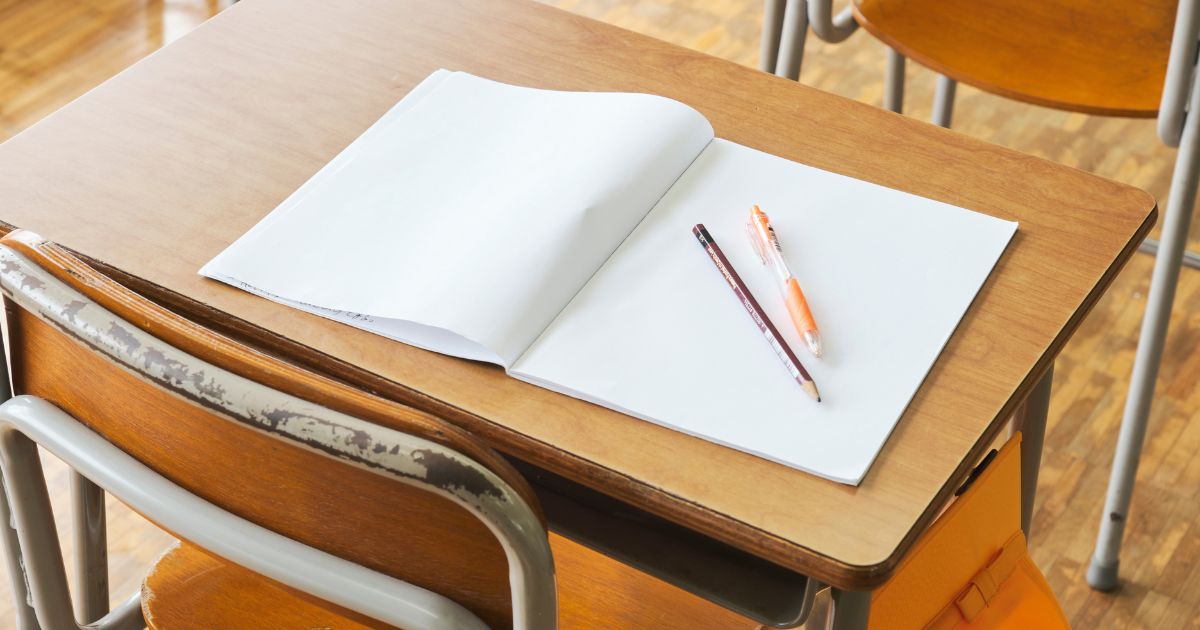
5つ目の困りごとは、予定変更や環境の変化にストレスを感じることです。
ASDのある小学生は、予想外の出来事に適応するのが難しく、強い不安や混乱を引き起こしやすいためです。
例えば、学校の日課が急に変更されると混乱し、落ち着きを失うことがあります。また、入学や進級、転居などの大きな環境の変化では、想像以上のストレスを抱え、学校生活に適応するのに時間がかかる場合もあるでしょう。
安心して過ごせるよう、事前に変化を予告するなど、変化に対する不安を和らげるサポートをするのが重要です。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと⑥特定の手順やルールへのこだわりが強い
6つ目の困りごとは、特定の手順やルールへのこだわりが強いことです。
ASDのある小学生は、同じものや同じやり方へのこだわりがあるためです。いつもと違う状況に直面すると、不安が高まり、強い抵抗やパニックを引き起こすことがあります。
例えば、青い椅子でなければ座れない、決まった順番で遊びをしないと落ち着かないなどのこだわりが見られます。また、日常の動作をルーティンのように繰り返すことがあり、順番が崩れると強いストレスを感じることも少なくありません。
こだわりを無理にやめさせるのではなく、安心できる環境を整えることが重要です。変化を受け入れやすくするために、少しずつ慣れさせたり、代替の手段を用意することで、ストレスを軽減できるでしょう。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
ASDのある小学生が日常生活で抱きやすい5つの困りごと
この章では、 ASDのある小学生が(学校生活に限らず)日常生活で抱きやすい困りごとを解説します。
困りごと①身の回りのことをスムーズに行うことが苦手

ASDのある小学生は、身の回りのことをスムーズに行うことが苦手な傾向があります。
一日の予定を把握するのが苦手だったり、特定の行動にこだわりを強く持っていたりする場合、その特性上、日課や生活習慣を明確にしないと、不安や混乱を感じやすくなるのです。
例えば、朝の支度をする際に、次に何をすべきか分からず時間がかかる場合があります。また、学校での行動でも「授業の後に何をすればいいのか」など、予定が明確でないと落ち着かなくなる場合もあるでしょう。
学校や家庭では、一日の流れが分かるようにスケジュールを提示したり、視覚的に日課を示したりするなどの工夫が必要です。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと②感覚が敏感または鈍感
ASDのあるお子さんは、感覚が人よりも敏感だったり、逆に鈍感だったりする場合があります。
例えば、雑音が苦手だったり、人に触られるのを嫌がることがあります。
また、全ての音が苦手ということではなく、特定の声や雑音のみに強い恐怖を感じるケースなどもあります。
人によって異なる感覚の特性を把握し、刺激の影響を最小限に抑える環境を整えるのが重要です。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと③睡眠リズムが乱れやすい

3つ目の困りごとは、睡眠リズムが乱れやすいことです。
ASDの特性として、状況を認識するのが難しい場合、生活のリズムが崩れやすく睡眠の質が低下する場合があるためです。
刺激に対する過敏性や行動の特異性が影響し、睡眠障害を引き起こす場合もあります。
例えば、夜になっても眠れず、翌朝の起床が遅くなる、日中に眠気が強くなるなどの問題が見られます。また、就寝前のルーティンが変わると不安を感じ、さらに睡眠リズムが乱れることもあるでしょう。
睡眠リズムの乱れを防ぐためには、毎日の生活を規則正しくし、安心できる環境を作るのが大切です。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと④公共の場でのマナーが守りづらい
4つ目の困りごとは公共の場でのマナーが守りづらいことです。
ASDのある小学生は、他人との関わり方やルールの理解が難しく、状況に応じた適切な行動を取るのが困難な場合があります。
例えば、電車の中で大きな声を出す、順番を待つことができない、周囲の人に突然話しかけるなどの行動が見られることがあります。また、他人との距離感をつかみにくく、意図せずマナー違反と見なされる場合もあるでしょう。
公共の場で適切な行動を取れるよう、繰り返し練習すると、少しずつ社会生活に適応しやすくなるかもしれません。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
困りごと⑤注意がそれやすい

5つ目の困りごとは注意がそれやすいことです。
ASDのある小学生は、行動の予測がつきにくく、規制が難しいため、危険を回避する機能が十分に働かないためです。
例えば、授業中に急に立ち上がったり、指示が途中で頭から抜けたりすることがあります。また、集団行動でのルールを理解しにくいため、周囲との協調が難しくなることもあるでしょう。最近では、注意がそれやすいASDの子どもの中に、ADHDを併存しているケースも多いことが知られています。
注意がそれやすい特性は、成長や適切な支援によって改善することが多いです。環境を整え、状況に応じた支援を行うと、集中しやすくなり、行動にまとまりが出るようになるでしょう。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
ASDのある小学生に親ができる5つの対応
この章では、ASDのある小学生に親御さんができる対応を解説します。
対応①視覚的なサポートを活用し、事前に繰り返し伝える

1つ目の対応は、視覚的なサポートを活用し、事前に繰り返し伝えことです。こうすることで、安心して行動できるようになります。
例えば、運動会の練習で時間割が変更された際、その変更にパニックになることがあります。
このような場合、以下の対応が効果的です。
- 変更は前日までに伝え、当日の朝に再度説明する
- 口頭だけでなく、視覚的に情報を提示する
また、必要に応じて、学校側に以下のような配慮を求めることも効果的です。
- 個別に名前を呼んで伝えてもらう
- ノートに変更内容を書いてもらい、後で子どもが(親が)確認できるようにする
ASDのあるお子さんには、口頭だけでなく視覚的なサポートを加え、繰り返し伝えることが重要です。不安を減らしスムーズな行動につなげましょう。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」、独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育推進センター 社会面でのつまずきと指導・支援「予定の変更」)
対応②日常生活のスケジュールをあらかじめ伝えておく
2つ目の対応は、日常生活のスケジュールをあらかじめ伝えておくことです。
ASDのあるお子さんには、生活の流れを分かりやすくすることで、不安を減らし、安定した日常を送れるようになります。
例えば、授業や休み時間の流れを把握しやすくするために、時間割を視覚的に示したり、次の活動を予告することで、混乱を防げるでしょう。また、学校と家庭が連携し、同じルーティンを意識すると、生活習慣の定着をより確実にできます。
ASDのあるお子さんには、事前にスケジュールを伝え、日課を明確にすることで、安心して行動できるでしょう。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
対応③感覚過敏への配慮した環境を整える

3つ目の対応は、感覚過敏への配慮した環境を整えることです。
感覚過敏は、周囲の人には分かりにくく、理解されにくい傾向があります。
聴覚、触覚、味覚などの感覚刺激に対する耐性が低いため、些細なことでも大きなストレスにつながるのです。また、本人が自分のつらさを言葉で伝えるのが難しく、不安や疲労をため込む場合もあるでしょう。
このような場合、以下の支援が効果的です。
- お子さんの様子を丁寧に観察して無理をさせない
- 周囲に感覚過敏の特性を説明して理解を深める
- 「大きな声が嫌」など、本人が自分で伝えられるように支援する
ASDのあるお子さんが無理なく過ごせるよう、周囲の理解を深め本人が自分の感覚の特性を伝えられるようサポートしましょう。(参考:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育推進センター 社会面でのつまずきと指導・支援「過敏性」)
対応④学校と密に連携する
4つ目の対応は、学校と密に連携することです。
ASDのある小学生が安心して生活できるよう、学校と家庭で日常生活の流れを分かりやすくし、生活習慣を定着させると心理的な安定につながります。
例えば、学校で学んだ生活スキルを家庭でも実践できるようにするため、学校と保護者が連携し、具体的な方法を共有しましょう。また、教材や教具を工夫し視覚や触覚などの感覚を活用すると、スムーズな生活習慣の確立をサポートできるでしょう。
ASDのある小学生が安定した生活を送るためには、学校と家庭が協力し、適切な指導方法や環境を整え、生活習慣を確実に身につけられるようサポートしましょう。(参考:文部科学省「Ⅷ 自閉症」)
対応⑤専門機関や療育を活用する

5つ目の対応は、専門機関や療育を活用することです。
ASDのあるお子さんの成長や生活の質を向上させるためには、家庭や学校だけでなく、地域の専門機関や療育サービスと連携すると、いっそう効果的になります。
具体的には、以下のような支援を活用するといいでしょう。
- ソーシャルスキルトレーニング(SST)
- ペアレントプログラム
- 発達障害者支援センターの活用
- 巡回支援専門員によるアドバイス
- ピアサポート
- 主治医や専門医の活用
ASDのあるお子さんが適切なサポートを受けるためには、家庭・学校・地域の専門機関が連携し、継続的に支援を行うことが大切です。また、専門機関の支援を積極的に活用すると、子どもが安心して成長できる環境を整え、家族の負担も軽減するでしょう。(参考:厚生労働省「発達障害者支援施策の概要」)
ASDのある小学生のための具体的な支援ツール3選
この章では、ASDのある小学生のための具体的な支援ツールを紹介します。
ツール①視覚的支援ツール(絵カード)

1つ目の支援ツールは視覚的支援ツール(絵カード)です。
絵カードを使うと、行動のルールや手順を明確にし、何をすべきかを直感的に理解できるようになります。また、言葉だけでは混乱しやすい場面でも、絵カードがあれば視覚的な手がかりとなり、スムーズに行動できるようになります。
例えば、以下のような絵カードがオススメです。
方法①指示カード
「帽子をかぶる」「ここで待つ」「×(やってはいけない)」など、具体的な行動を示すカードです。行動のルールを明確に伝え、適切な行動を促すのに役立ちます。
方法②手順カード
歯磨きやトイレの使い方、着替えの手順など、動作を順番に示すカードです。行動の流れを視覚的に示すことで、子どもが次に何をすべきかを理解しやすくなります。
方法③スケジュールカード
1日の流れや授業の進行など、予定を時系列で示したカードです。子どもが先の見通しを持ちやすくなり、不安を軽減できます。
絵カードは、ASDのある小学生が行動の見通しを持ち、適切なコミュニケーションをとるために効果的なツールになるでしょう。(参考:筑波大学 水野智美「保育者が行う絵カード作成の誤りおよび不適切な使用方法の分類-指示カードの誤りに着目して-」)
ツール②支援アプリ
2つ目の支援ツールは支援アプリです。
支援アプリは、ASDのある小学生の家族が日々の特性を記録し、支援者や学校と円滑に情報共有できるツールです。
ASDのある人への支援においては、成長に伴う多くの情報を記録し、学校・医療機関・支援者に共有する必要があります。支援アプリは、家族が負担なく必要な情報を適切なタイミングで共有できるように設計されています。
支援アプリで主にできることは、以下のとおりです。
方法①成長記録を一元管理
子どもの発達や行動の変化を記録し、振り返りがしやすくなります。
方法②感覚特性の記録と共有
音や光への過敏性など、個々の特性を詳細に記録し、適切な支援につなげられます。
方法③支援者との情報共有機能
学校や医療機関、療育機関とスムーズに情報をやり取りでき、適切なサポートが受けられます。
支援アプリの活用は、家族がASDの特性を無理なく記録・管理でき、家族と支援者の橋渡しとなる便利なツールです。(参考:岩藤百香・小田桐早苗 · 森戸雅子 · 難波知子・三上史哲・武井祐子・宮崎 仁・松本正富 「多職種連携による自閉症児支援アプリの開発」)
ツール③コーピンググッズ

3つ目の支援ツールは、コーピンググッズです。
コーピンググッズとは、ストレスや不安を和らげ、感情を整理・調整するためのツールです。コーピンググッズを活用すると、感情のコントロールが難しい場面でも適切に対応できるようになります。
例えば、以下のようなコーピンググッズの活用がオススメです。
方法①風船スクイーズ
手で握ることで触覚を刺激し、リラックス効果を得られます。
方法②オイルタイマー
ゆっくりとした液体の動きを眺めると、気持ちを落ち着かせるのに役立ちます。
方法③感情表現カード
自分の気持ちを言葉にするのが難しい子どもが、視覚的に感情を伝えやすくなります。
方法④ぬいぐるみやクッション
安心感を与え、リラックスするためのアイテムとしてオススメです。
コーピンググッズは、教室や家庭、職場などさまざまな場面で活用でき、感情コントロールのサポートとして有効です。コーピンググッズの活用で、ASDのある小学生が感情を整理し、不安や混乱を軽減できる助けになるでしょう。(参考:広島県 支援者のための発達障害支援ガイドブック「感情のコントロール」)
ASDのある小学生の学校選びと進学の3つのポイント
この章では、ASDのある小学生の学校選びと進学のポイントについて解説します。
ポイント①ASDのある子どもが安心して学べる環境を選ぶ
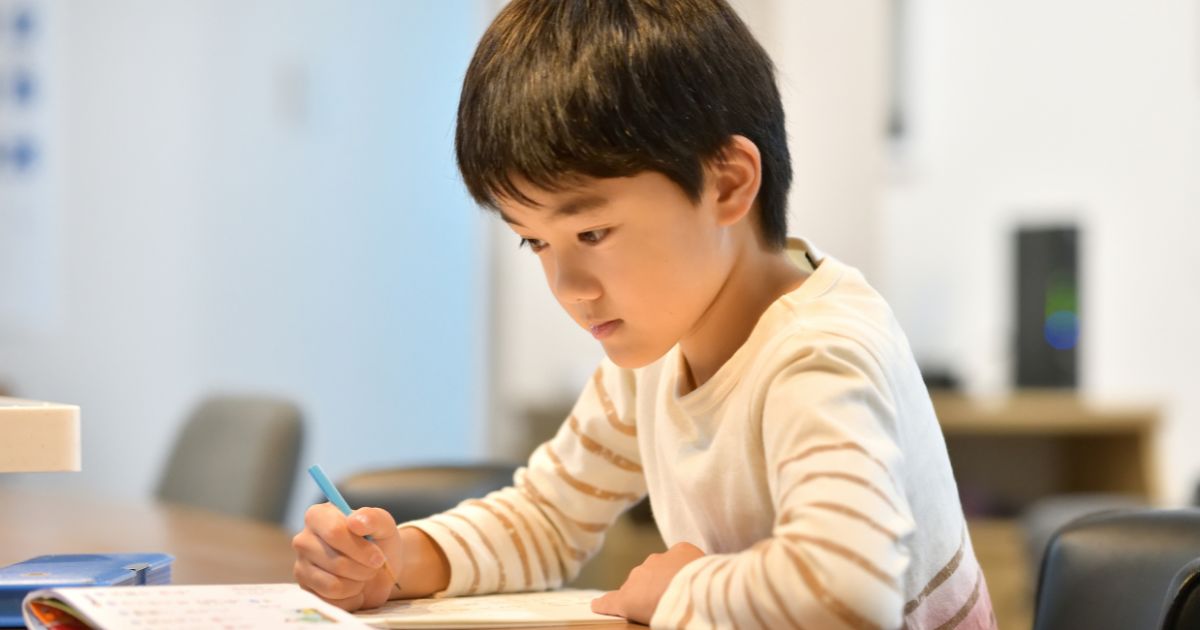
1つ目のポイントは、ASDのある子どもが安心して学べる環境を選ぶことです。
近年、義務教育段階の児童生徒数は減少傾向にある一方で、特別支援教育を受ける児童生徒数は増加しています。
特に、特別支援学級の在籍者数は平成21年(2009年)と比較して約2.1倍、通級による指導の利用者数は約2.3倍に増えており、学習や行動面で支援を必要とする子どもへの対応が進んでいます。(参考:文部科学省「特別支援学級の現状」)
また、通常の学級に在籍しながら学習や行動に困難を示す児童生徒の割合は、医師の診断ではない学校現場の学級担任などの回答に基づくデータによると、小学校・中学校で約8.8%、高等学校で約2.2%です。
ASDのある小学生が安心して学べる環境を選ぶには、特別支援学級や通級指導の活用を含め、学校の支援体制をしっかり確認して検討するのがいいでしょう。
ポイント②通常学級・支援学級の選択肢を検討する
2つ目のポイントは、通常学級・支援学級の選択肢を検討することです。
特別支援教育の選択肢は拡充されており、それぞれの学び方に応じた支援が可能になっています。
特別支援学校では、専門性の高い教育が受けられ、特別支援学級では障害種ごとに個別対応が行われます。また、通級による指導では、通常学級に在籍しながら必要な支援を受けることが可能です。
令和5年時の対象児童数と在籍者数は、以下のとおりです。
- 特別支援学校(対象児童数:約15万人)
- 特別支援学級(在籍者数:約37.3万人、2013年比約2.1倍)
- 通級による指導(在籍者数:約18.2万人、2013年比約2.4倍)
通常学級・特別支援学級・特別支援学校にそれぞれに特徴があり、子どもの特性や支援の必要度に応じて最適な環境を選択することが大切です。(参考:文部科学相 初等中等教育局 特別支援教育課「特別支援教育の充実について」)
ポイント③公立中学校・私立中学校の違い

3つ目のポイントは、公立中学校・私立中学校の違いを理解することです。
公立中学校と私立中学校では、特別支援教育の体制に大きな違いがあります。公立中学校は支援体制が整備されている一方で、私立中学校では特別支援学級や通級指導教室の設置がほとんどなく、支援体制が未整備の学校が大多数です。
文部科学省の2011年度調査によると、公立中学校では特別支援教育コーディネーターの配置が進み、発達障害のある生徒への支援が強化されています。
一方、全国の私立中学校782校を対象とした調査では、特別支援学級を設置している私立中学校はゼロであり、通級指導教室を設置している学校も全国でわずか1校、全体の約0.6%にとどまります。
ASDのある小学生にとって、どのような支援が受けられるのかを事前に確認し、慎重に学校選びをすることが重要です。(参考:文部科学省「特別支援学級の現状」、東京学芸大学連合学校教育学研究科 発達支援講座 教授 髙橋智「私立学校における幼小中高一貫した特別支援教育システムの開発に関する全国調査研究」)
ASDのある小学生の体験談
この章では、ASDのある小学生の体験談を紹介します。
体験談①不登校を経て、自分に合う学びの環境を見つけた体験談

猿渡瑠璃さん(仮名)の娘さんは、高校時代に長期間の不登校を経験し、学習の遅れに不安を感じていました。また、睡眠リズムの乱れやメンタル面の不安定さから、一般的な学習塾に通うことが難しい状況でした。
そんな中で、キズキ共育塾に出会い、ASDの特性や睡眠障害に対する理解がある環境に安心感を抱けたそうです。
現在もメンタル面の影響で欠席や遅刻をすることはありますが、講師の支えのおかげで辞めずに学習を続けることができているそうで、自分に合った学びの環境を見つける大きな転機となりました。
同じような悩みを抱える人にとっても、新しい道を開くきっかけとなるはずです。
小学生のASDに関するよくある2つの質問
この章では、小学生のASDに関するよくある質問を紹介します。
Q1.ASDはどのように診断されるのですか?

ASDの診断は、精神医学会が定めた『DSM-5』の基準に基づいて行われます。診断には、以下の特徴が見られることが必要です。
特徴①社会的コミュニケーションの困難さ
- 対人関係の難しさ
- 非言語的コミュニケーションの問題
- 人間関係の構築が難しい
特徴②限定された興味や反復的な行動
- 同じ動作や行動を繰り返す
- 習慣やルールへの強いこだわり
- 特定の物やテーマに強く執着する
- 感覚の違い
ASDの診断は、これらの特徴が複数の状況で見られることを確認した上で行われます。
ASDの診断基準については、以下のコラムで解説しています。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)とは? 特性や診断基準を解説」
Q2.ASDのある子どもの長所を伸ばすにはどうすればいいですか?
ASDのある子どもの長所を伸ばすには、特性をよく理解し自身に合う進路先を見つけることです。
特に、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
- 相談先を活用する
- 特性を理解し、強みを活かす
- 進路の準備を早めに進める
- 本人の意思を尊重する
- 各進路の特徴を理解する
詳しくは、発達障害のある人の進路選択のポイントについて解説したコラムをご覧ください。
改めて、ASDとは?
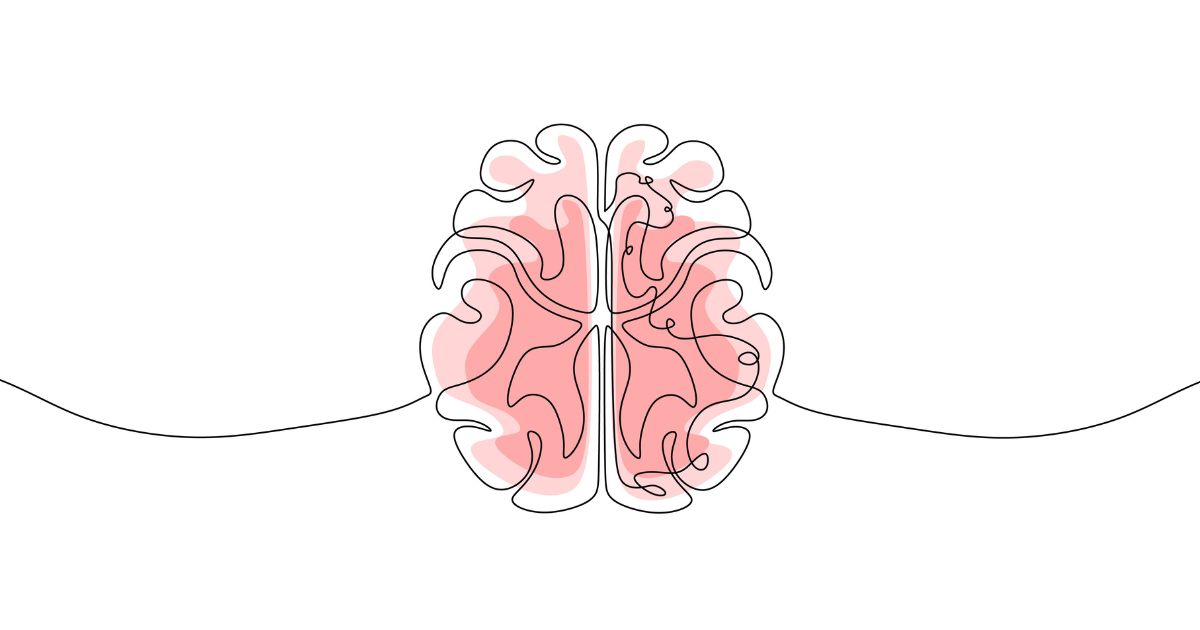
この章では、改めてASDの概要をお伝えします。
ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害、Autism Spectrum Disorder)とは、人とのコミュニケーションなどに困難が生じる発達障害の一種のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、CDC「Autism Spectrum Disorder (ASD) 」、厚生労働省「No.1 職域で問題となる大人の自閉症スペクトラム障害」、福西勇夫、福西朱音『マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド』)
かつて使用されていた以下の診断名・分類は、ASDという診断名・分類に統合されています。
- アスペルガー症候群
- 自閉症
- 高機能自閉症
- 広汎性発達障害(PDD)
それぞれ別の発達障害として、診断基準も異なっていましたが、2013年に行われた『DSM-5』の改訂の際に、厳密に区分するのではなく、地続きの=スペクトラムな障害として捉える現在のASDに変更されました。
ただし、変更前の診断名・分類が、法令や病院、日常会話などで現在も使用されることがあります。また、かつてアスペルガー症候群などと診断された人が、現在のASDという名称を認知していないこともあります。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)とは? 特性や診断基準を解説」
ASDの原因
発達障害の原因は、現在の医学では明確に特定されていません。現在のところ、生まれつきの脳機能の障害が原因であると考えられています。
少なくとも、本人の努力不足や親の育て方、ストレス、環境などが原因ではないことは明らかになっています。発達障害は、原因不明かつ生まれつきのものであり、誰かに責任があるわけではありません。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害とは?生まれつき? ADHD、ASD、LD/SLDを解説」
ASDのある男の子と女の子の違い

ASDは、男の子の比率が高く、男女比は3:1と報告されています。(参考:国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修テキスト」)
ただしこれは必ずしも、発達障害のある男の子の方が女の子より多いということを意味しているわけではありません。
女の子は症状が目立ちにくく、周囲に適応しようと努力するため、発達特性が見過ごされることが多いです。社会的なルールを学びやすく大人しい、真面目と思われやすいため、困りごとが表面化しにくい傾向があります。
表面的には問題がないように見えても、内面では強いストレスを抱えている場合があります。適切な支援を受けるためにも、小さなサインを見逃さず、周囲が早めに気づくことが大切です。
まとめ〜ASDの理解と適切な支援でASDの理解と適切な支援で子どもの可能性を広げよう〜

ASDのある小学生が安心して成長するためには、まず親御さんがASDの特性を理解し、適切なサポートを行うことが大切です。
一人で悩まず、学校や専門機関、学習塾など外部の支援を活用すると、子どもがより良い環境で、長所を伸ばしながら成長できる可能性が広がります。
ASDの特性による困りごとは、子どもにとって大きなストレスになる場合があります。
親御さんは日々の生活の中で子どもの様子をよく観察し、不安や悩みをしっかり受け止めてましょう。子どもと一緒に困りごとを乗り越えながら、安心できる環境を整えてていくのが大切です。
また、子どもの得意なことや興味のある分野を伸ばし、小さな成功体験を積み重ねていくと、自己肯定感の向上につながります。
ASDのある小学生の個性や強みを理解し、親御さんも一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用しながら、お子さんの成長を温かく見守っていきましょう。
Q&A よくある質問