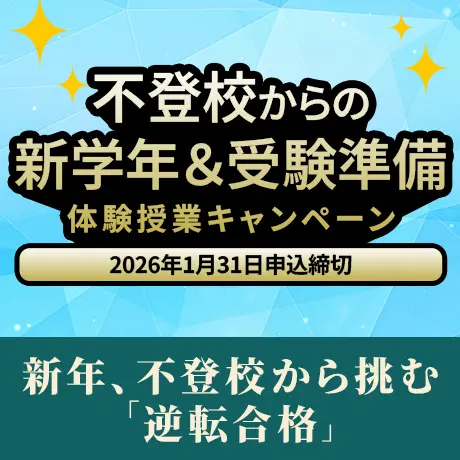情緒不安定なお子さんが心配な親御さんへ 原因や対応方法を解説
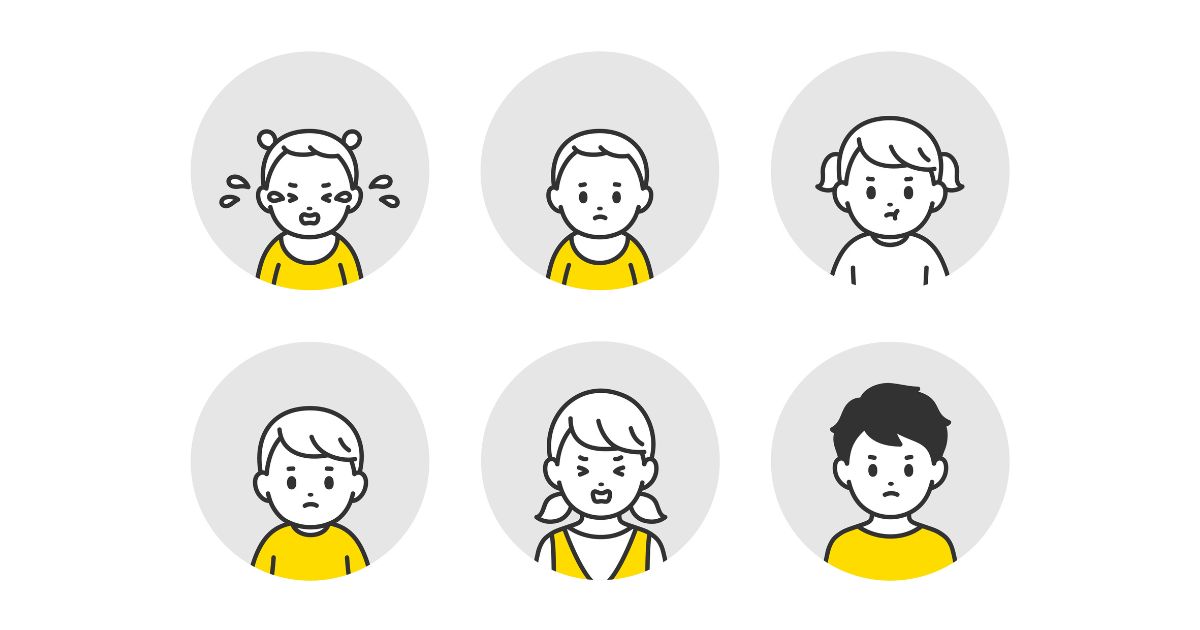
こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。
このコラムでは、お子さんが情緒不安定で心配な親御さんへ、特徴や原因、対応方法などについて解説します。
情緒不安定なお子さんに対してやってはいけないNG対応についてもご紹介しているので、ぜひ最後まで読んでお子さんとよい関係を築くための助けになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、情緒不安定なお子さんのいる親御さんのための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
情緒不安定な子どもの特徴

情緒不安定とは、感情の起伏が激しく、気持ちが落ち着かない状態のことです。
情緒不安定な子どもの主な特徴としては、以下のとおりです。
- ささいなことでイライラする
- 思い通りにならないと癇癪を起こす
- 以前よりも泣くことが増えた
- 以前よりも反抗的になった
- 以前よりも我慢ができなくなった
- 以前よりも不機嫌な時間が増えた
- 以前よりも何かに不安を感じたり、怖がったりするようになった
- 保育園や幼稚園、学校に行きたがらない
- 以前よりもチャレンジしようとしなくなった
- 表情が乏しくなった
これらの項目に多く当てはまる場合は、お子さんが情緒不安定である可能性が高いといえるでしょう。
子どもが情緒不安定になる原因
この章では子どもが情緒不安定になる原因について解説します。
お子さんが感情をコントロールできなくなる理由にはさまざまな背景があるため、まずはお子さんとの生活を振り返り、原因を探ってみましょう。
原因①幼児期で感情を表現する練習が少ない

1つ目の原因は、幼児期で感情を表現する練習が少ないことです。
文部科学省によると、幼児期とは1歳前後〜5、6歳ごろのお子さんを指します。また、この時期の子どもの情緒面での特徴として、以下のような点が挙げられます。(参考:文部科学省「Ⅵ.幼児期の発育発達の特徴」)
- 心身ともに成長が著しい
- 1歳ごろから単語が言えるようになり、1歳後半になると自主性が生まれる
- 3歳ごろになると遊びなどの行動が活発になり、知的好奇心も強くなる
- 2~4歳ごろになると反抗期が始まる
このような成長が著しく、言葉を使い始める時期において感情を表現する機会が少ないと、自分の気持ちを上手に伝えたり、相手の言葉を理解したりするのが難しくなるため、情緒不安定になる要因となり得ます。
原因②両親の関係が不安定
2つ目の原因は、両親の関係が不安定な場合です。
両親の関係と子どもの精神的健康との関連性に関する研究によると、両親が何かしらの葛藤を抱いてお子さんと接している場合に、お子さんの情緒面に影響を与えるそうです。(参考:高橋直美「両親間および親子間の関係と子どもの精神的健康との関連について」)
両親の関係が不安定だとお子さんが不安や恐怖を感じ、情緒不安定さを引き起こすと考えられるでしょう。
原因③親御さんがお子さんの感情を理解しきれていない
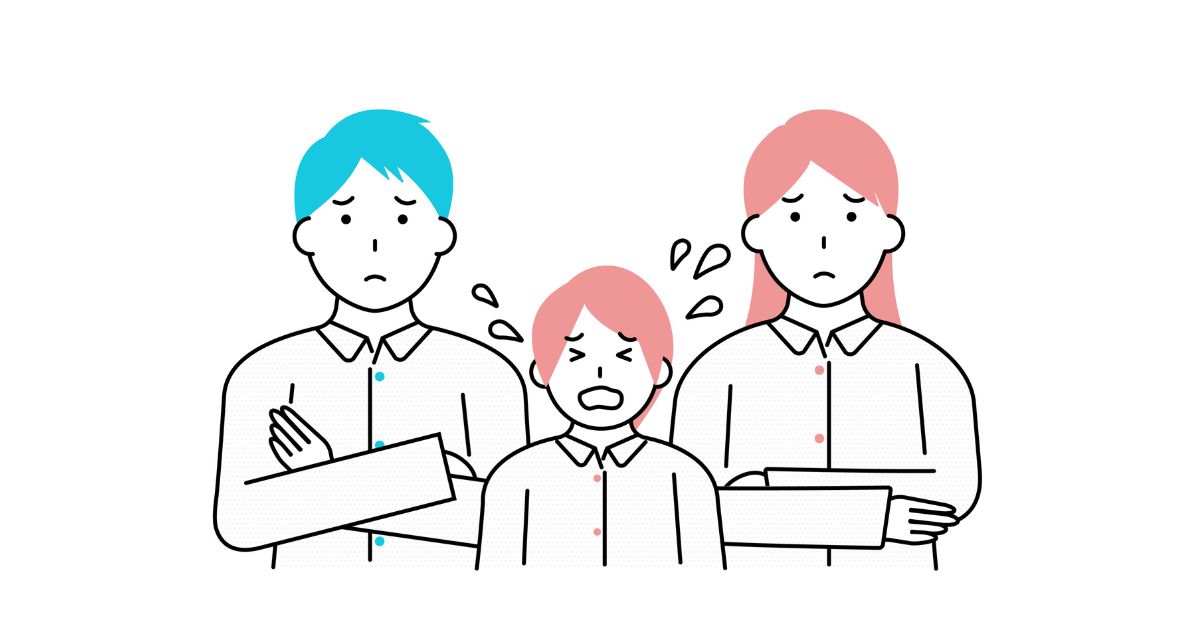
3つ目の原因は、親御さんがお子さんの感情を理解しきれていない場合です。
親御さんがお子さんの気持ちを正しく理解し、適切に対応することは、お子さんが自身の感情を上手に扱うためにも大切なことです。
親御さんがそういった感情表現をうまく理解しきれていないと、お子さんは自分の感情をコントロールするのが難しくなり、情緒不安定になる可能性があるでしょう。
原因④学校環境
お子さんが情緒不安定になる原因4つ目は、学校環境です。
思春期のお子さんであれば学校環境の影響を受けやすい年ごろかと思います。その背景として幼児期や小学生の頃にはそこまで大きく感じなかった勉強のストレスや人間関係が関係します。
中学生や高校生になればそういった問題に敏感になり、周りと学力の差がつかないか、グループの仲間外れにされないかなどの不安が情緒不安定さを引き起こす要因となることが考えられます。
原因⑤生活習慣の乱れ

5つ目の原因は、生活習慣が乱れている場合です。
例えば、食事の場合、食生活の乱れが影響していると考えられます。必要な栄養素が不足すると、神経伝達物質の生成がしづらくなって脳がしっかりと働かず、感情のコントロールが難しくなるといいます。(参考:須藤紀子・澤口眞規子・吉池信男「ストレス負荷時の食事摂取量の変化と必要な栄養素」)
また、睡眠不足が脳の中で情動を司る扁桃体(へんとうたい)に影響を及ぼすという研究結果も報告されています。研究ではネガティブな情動刺激にのみ反応するということも示唆しており、睡眠不足が情緒不安定さを引き起こす要因になると考えられます。 (参考:国立精神・神経医療研究センター「睡眠不足で不安・抑うつが強まる神経基盤を解明」)
ほかにも、ゲームのやり過ぎなどから情緒不安定になるリスクが高まるとも言われています。 (参考:独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター「ゲーム障害について」)
原因⑥電子メディアの影響
6つ目の要因は、電子メディアの影響です。
子どもの電子メディア接触と心身の影響に関する調査によると、3歳から就学前児において視聴時間が3時間を超える子どもは視聴時間が2時間の子どもよりも情緒不安定な面があるとされています。(参考:甲斐鈴恵「子どもの電子メディア接触に関する保護者の意識」)
原因⑦社会情勢の影響

7つ目の原因は、2020年に流行した新型コロナウイルスの流行による危機的状況などの社会情勢の影響です。
直接的な影響はもちろん、その影響による家庭の経済状況・親子関係の変化などが間接的にお子さんの情緒不安定をもたらす要因となる可能性もあるでしょう。
補足:発達障害やその他の病気・障害の可能性も
お子さんが情緒不安定になる原因として、発達障害やその他の病気・障害が影響している可能性があります。
国立特別支援教育総合研究所の研究によると、発達障害が情緒障害と同様の症状を示すことがあることが記載されています。
情緒障害とは、情緒の現れ方に偏りがあったり、その現れ方が激しかったりする状態のことです。自分の意思ではコントロールがきかないため、保育園や幼稚園、学校生活において支障をきたす場合があります。(参考:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所「情緒障害のある子どもへの配慮」)
情緒不安定と情緒障害とでは感情の現れ方や不安定さが続く期間の長さにおいて定義が異なりますが、行動面や対人関係において困難な状態を示しやすい発達障害と情緒不安定さが関連付いている可能性も考えられるでしょう。 (参考:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所「発達障害と情緒障害の関連と教育的支援に関する研究」)
情緒不安定なお子さんに親御さんができる対応
この章では情緒不安定なお子さんに親御さんができる対応について解説します。
対応①お子さんとの関わりを増やす

1つ目の対応は、お子さんとの関わりを増やすことです。具体的には以下の方法を試してみることをオススメします。
- 積極的に話を聞いてあげる
- お子さんの話を理解し、受け入れてあげる
- 親御さん自身が感情をコントロールし、お手本となる
- スキンシップする
お子さんとの関わりを増やすために、まずは積極的にお子さんの話を聞いてあげましょう。お子さんの話を聞いてあげることで、感情を表現する機会にもつながります。
また、話を聞いてあげる際は、「悲しかったんだね。その気持ちよくわかるよ。」などといったように、お子さんの話を理解しようと努め、受け入れてあげることも大切です。
子どもの気持ちに共感し、一緒に言語化することで、ただ感情を表現するだけでなく、自分の感情を認識して、上手に表現する力が身につきます。
その際、親御さん自身が感情をコントロールするそぶりをみせ、お手本になるよう接してみるのもよいかもしれません。
その他の対応としては、スキンシップもオススメです。スキンシップをすることで愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌され、情緒不安定なお子さんの気持ちを落ち着かせる効果が期待できます。(参考:医療法人社団 西宮回生病院「子どもへのスキンシップについて」)
対応②共通の体験や趣味の時間をつくる
2つ目の対応は、共通の体験や趣味の時間をつくることです。具体的には以下の方法を試してみることをオススメします。
- 公園の遊具を使うような親子で協力し合う遊び
- ハイキングといった自然と触れ合うアクティビティ
- ボードゲームやパズルゲームといった頭を使う遊び
- ドッジボールやキャッチボールといった身体を動かす遊び
- 絵を描いたり、粘土を使って物を作ったりといった創造力を養うような遊び
こういった親子遊びは、単なる娯楽としてだけでなく、子どもの情緒的安心感や自尊心にもよい影響を与えると言われています。
対応③安心できる家庭環境をつくる

3つ目の対応は、安心できる家庭環境をつくることです。ここでいう安心できる家庭環境とは、両親の良好な関係を築くことを指します。
小学6年生とそのご両親を対象にした調査によると、父母の仲が良いと感じている子どもは、安心感を抱いている割合が多かったそうです。さらに、日常生活でイライラを感じることも少ないという結果が出ており、両親の関係が、情緒の安定・不安定に影響していることがうかがえます。(参考:群馬県総合教育センター「データでみる父母の仲と子どもとの関係」)
対応④規則正しい生活を送るように促す
4つ目の対応は、規則正しい生活を送るように促すことです。お子さんが食生活の乱れや睡眠不足にならないよう気を付けましょう。
食生活に関しては、バランスの良い食事を与えることを意識しましょう。バランスの良い食事は脳神経を刺激し、イライラとした気持ちを鎮める効果が期待できます。(参考:公益社団法人 千葉県栄養士会「思春期の食事と健康」)
また、睡眠に関しては、成長ホルモンが多く分泌される時間帯に眠りにつくことが大切です。幼児期のお子さんであれば19時、思春期のお子さんであれば22時〜深夜2時には眠りにつけるよう親御さんが促してあげましょう。(参考:奈良県「幼児向け運動・スポーツプログラム」)
対応⑤学校や専門家に相談する

5つ目の対応は、学校や専門家に相談することです。
学校に関連したお悩みの場合、以下が相談窓口として挙げられます。
- 学校内であれば、先生やカウンセラー
- 学校外であれば、都道府県や市区町村の教育センター
また、発達障害に関する相談は、都道府県や指定都市に設置されている発達障害者支援センターもあります。(参考:厚生労働省「こころの相談窓口」)
その他、こころを扱う精神科への受診も選択肢として挙げられるでしょう。
参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害者支援センターとは? 支援内容や利用の流れを解説」
情緒不安定な子どもに対して親御さんがやってはいけないNG対応
この章では、情緒不安定な子どもに対して親御さんがやってはいけないNG対応について解説します。
NG①過干渉する

1つ目のNG対応は、過干渉することです。
過干渉とは、なんらかの対象に対して、一般的な限度を超えて必要以上に干渉したり、行き過ぎた制限をしたりすることです。一般的に、親による子どもに対する過剰な干渉を指す言葉として使われることが多いです。(参考:goo国語辞書「過干渉(かかんしょう)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説」、金子書房『児童心理 2002年9月号 特集:過干渉の親・放任の親』、高橋リエ『気づけない毒親』、おのころ心平『人間関係 境界線(バウンダリー)の上手な引き方』)
お子さんへの過干渉が自信を失わせたり、無気力にさせたりといった情緒に影響を及ぼすと言われています。
子どもをちゃんと育てたいという気持ちは理解できますが、こういった親御さんの心理が場合によってはお子さんの気持ちを不安定にさせる要因にもなり得るため、お子さんの意見を尊重し、行動を縛りすぎないよう気を付けましょう。
NG②親の理想を押し付ける
2つ目のNG対応は、親の理想を押し付けることです。
お子さんが成長するにつれ、親御さんが考えていた育ち方とは違うように感じることがあるかと思います。そういったとき、周りのお子さんと比べて、「どうしてあなたはできないの」などと責めていることはありませんか?
そのように理想を押し付けたり、比較したりするのはお子さんの情緒を不安定にするきっかけにもなるため、控えましょう。
NG③叱りすぎる

3つ目のNG対応は、叱りすぎることです。
特に思春期のお子さんであれば、気持ちを不安定にさせる要因にもなり得るため、必要以上に叱りすぎるのはあまりオススメできません。
理由があり叱りつけようと感じた場合は、叱るのではなく諭す程度に留めておくことをオススメします。
NG④子ども扱いする
4つ目のNG対応は、子ども扱いすることです。
ある程度大人に近づいてきた年齢のお子さんの中には、周囲からは「大人になったね」と言われる一方、家庭内では子ども扱いが止まらず、その間で葛藤を抱く人もいるでしょう。
そのような状況下で、例えば、お子さんの友人の前で「〇〇ちゃん」といった呼び方をされると嫌悪感を示すお子さんもいます。
お子さんが大人に近づいていることを認識し、過度に子ども扱いするのは控えましょう。
NG⑤無関心でいる

5つ目のNG対応は、無関心でいることです。
親御さんの中にはお子さんが成長するにつれ、子どもに近づきすぎるのはやめよう、と無関心でいようとする人もいるのではないでしょうか?
ある程度お子さんの年齢が経っているのであればよいかもしれませんが、お子さんによっては愛情不足や寂しさを感じさせ、情緒不安定になる可能性が考えられます。
無関心でいるのではなく、一定の距離感を保ちつつ、温かく見守るような気持ちでいてあげましょう。
まとめ~まずはお子さんとの会話の時間を増やしましょう~

お子さんの情緒不安定に関して、親御さんとお子さんとの会話を増やすことで解決の糸口が見える場合が多いです。
まだそこまで強く不安定さを感じない場合でも、普段からお子さんと丁寧に向き合う意識を持つことで予防にもつながります。
早期改善のため、お子さんの状況次第では学校の先生や専門の窓口といった専門家への相談も検討してみましょう。
Q&A よくある質問