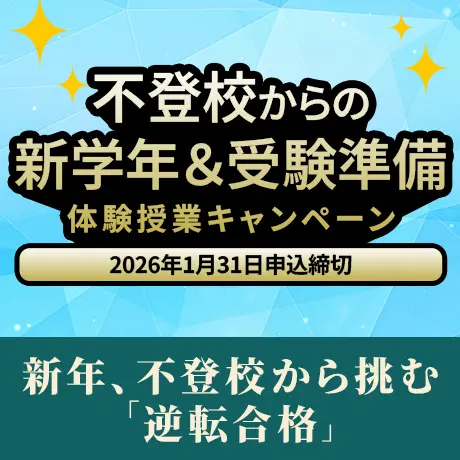勉強疲れを回復する対処法 予防する習慣と環境づくりを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾、キズキ共育塾です。
このコラムを読んでいるあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 勉強を始めてもすぐに疲れて長続きしない
- 勉強そのものに疲れてやる気が出ない
- 勉強疲れしない方法が知りたいけど対処法がわからない
このコラムでは、勉強中に疲れる原因や勉強疲れで現れる症状とリスク、勉強疲れをすぐに回復させる方法について解説します。
このコラムが、勉強中の疲れに悩むあなたや子どもを支えるヒントになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、勉強に疲れている人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
勉強疲れする6つの原因
誰しもが一度は勉強疲れの経験があるでしょう。原因にはさまざまなものがあるため、知っておくことで適切な対処ができるようになります。
この章では、勉強疲れする原因について解説します。
原因①脳の使いすぎによる脳疲労

勉強は頭をフル回転させる作業であり、脳は膨大なエネルギーを消費しています。
長時間問題を解いたり暗記に集中したりすると、情報処理を担う神経回路がオーバーヒート状態になります。これがいわゆる脳疲労で、思考力や判断力が鈍り、集中力が持続しにくくなります。(参考:J-STAGE「脳疲労と脳血流量の関係性」 )
そのため、勉強中は適度に休憩を入れ、脳のリフレッシュを意識することが重要です。
原因②長時間同じ姿勢・座りっぱなしによる身体的疲労
机に向かって勉強を続けていると、気づかないうちに同じ姿勢を長時間維持しています。特に勉強では前傾姿勢や猫背になりやすく、首や肩、腰に負担が集中して血流が悪くなります。
その結果、筋肉のこわばりやだるさが生じ、身体的疲労がたまるのです。
それだけでなく、座りっぱなしでいることは、健康リスクも高めるとされています。こまめに姿勢を変えたり立ち上がったりして、身体を動かしましょう。
原因③目の酷使による眼精疲労

現代の学習は、参考書だけでなくパソコンやタブレット、スマートフォンを使うことも多いため、目への負担が大きくなっています。
長時間文字を追い続けると、ピントを合わせる毛様体筋が疲労し、目の奥の痛みやかすみ目、ドライアイなどの症状を引き起こします。
目が疲れると集中力が落ち、勉強の効率も低下するため、定期的に画面から目を離して遠くを眺めることや、まばたきを意識して目を潤すことが大切です。(参考:公益社団法人日本眼科医会「ギガっこデジたん」)
原因④睡眠不足や生活リズムの乱れ
睡眠は脳と体を休め、学習した内容を記憶に定着させる大切な時間です。
しかし、受験勉強や試験前の追い込みで睡眠時間を削ると、脳の疲労が回復せず、かえって集中力や思考力の低下を招きます。
さらに生活リズムが乱れると、自律神経のバランスも崩れ、体がだるい、気分が安定しないといった不調が現れやすくなります。
なるべく毎日ほぼ同じ時刻に寝起きし、朝は日光を浴びて体内時計を整えつつ、就寝前はスクリーンやカフェインを控えて必要な睡眠時間(約7~9時間)を確保することが重要です。(参考:文部科学省「中高生を中心とした子供の睡眠習慣に関する科学的知見の整理分科会」)
原因⑤勉強が思うように進まないことによる精神的ストレス
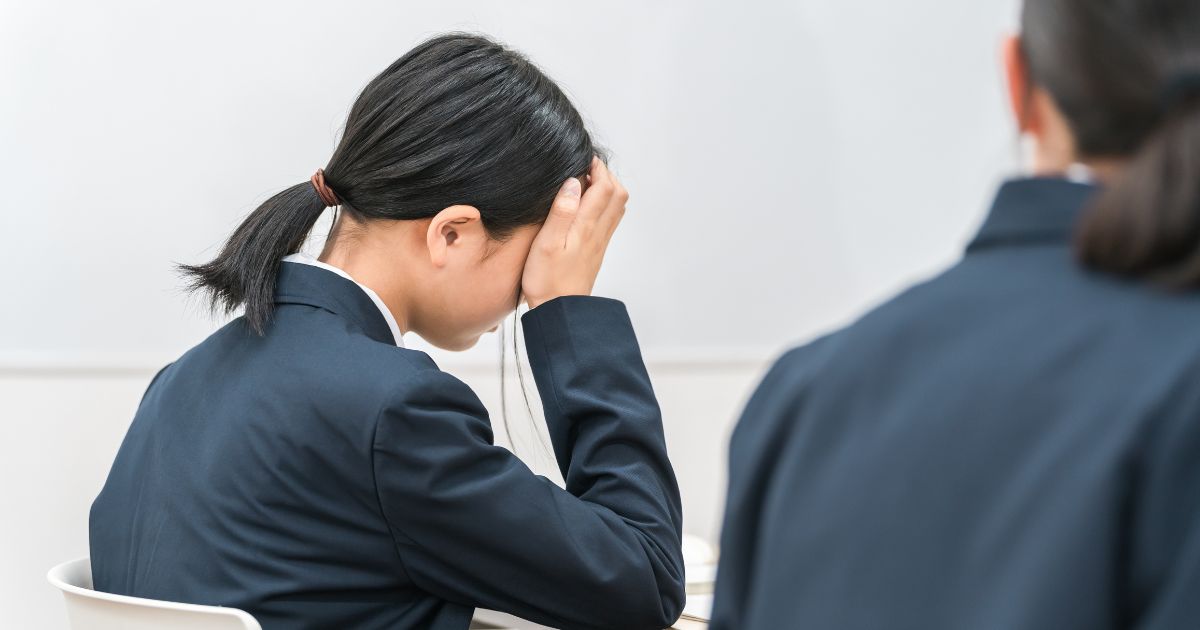
勉強をしていても全然理解できない、計画どおりに進まないという状況は、多くの人が経験することです。
ただ、このような状態が続くと、焦りや不安が募り、精神的ストレスとなって心身の疲れを強めます。
ストレスを抱えた脳は常に緊張状態にあり、エネルギー消費が増加して疲労を感じやすくなります。
原因⑥食事・栄養不足、水分不足
脳はブドウ糖を主なエネルギー源として働いているため、栄養バランスの取れた食事が勉強には欠かせません。(参考:J-STAGE「食品成分と脳機能の研究動向」)
しかし、朝食を抜いたり栄養が偏ったりすると、集中力や記憶力が低下します。
また、水分不足も見落としがちな原因のひとつです。こまめな水分補給と、炭水化物・タンパク質・ビタミンをバランスよく摂ることが、勉強の持久力を高めるカギになります。
勉強疲れで現れる症状とリスク
勉強疲れは放置すると、さまざまな症状やリスクにつながる可能性があります。
この章では、勉強疲れで現れる症状とリスクについて解説します。
リスク①集中力が続かない
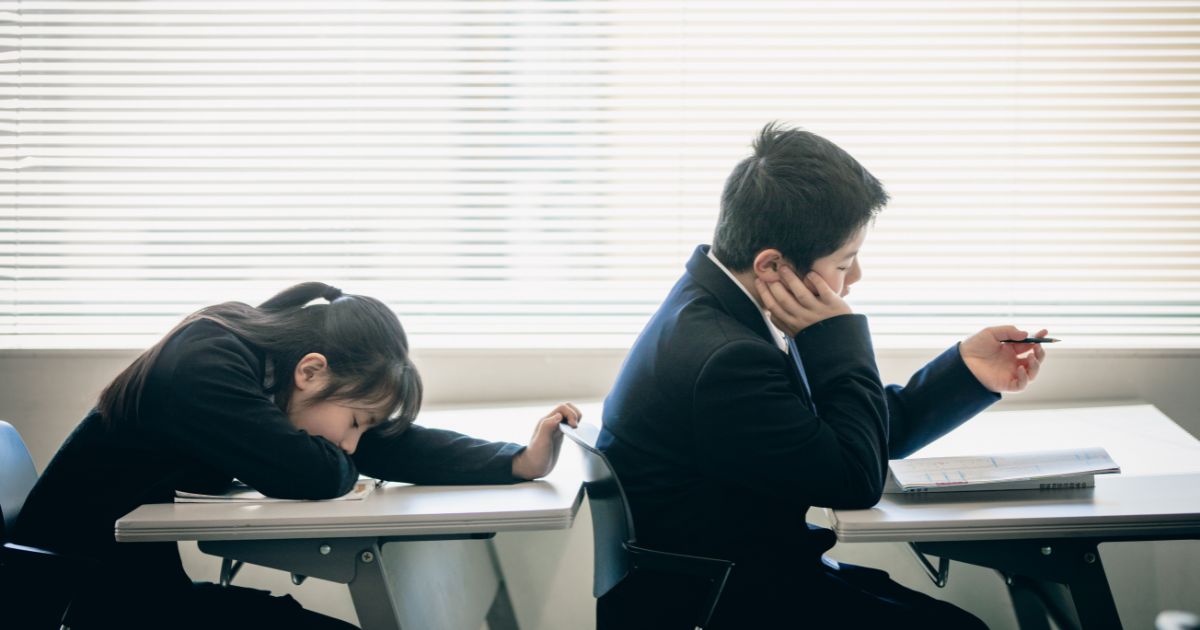
勉強疲れの最も顕著なサインのひとつが、集中力の低下です。脳が疲れていると情報処理がスムーズにいかず、同じページを何度も読み返したり、問題を解くスピードが落ちたりします。
集中できない状態が長く続くと、勉強時間のわりに成果が得られず、頑張っているのに身につかない悪循環に陥る可能性があります。
リスク②やる気が起きない
勉強に疲れると机に向かうこと自体が億劫になり、先延ばしするようになります。
これは単なる怠けではなく、脳や心がオーバーワークになっているサインです。やる気が起きない状態を放置すると、学習習慣のリズムが崩れ、勉強から離れる原因になります。
特に受験勉強や資格取得など長期的な努力が必要な場合、やる気の低下は大きなリスクです。
リスク③イライラやネガティブ思考になる

勉強疲れで脳が疲労してストレスがたまると、ちょっとしたことでイライラしたり、物事を否定的に考えやすくなったりします。
特に長期間ストレスを抱えたまま勉強を続けると、無気力感や自己否定感が強まり、学習の継続自体が難しくなる危険もあります。
リスク④頭痛・目の痛み・肩こり・腰痛などの身体症状
長時間の勉強による疲れは、心だけでなく体にもはっきりと現れます。代表的なのが頭痛や目の痛み、肩こりや腰痛です。
特に前傾姿勢や同じ姿勢を続けることで血流が悪くなり、筋肉が硬直して痛みを感じやすくなります。眼精疲労が加わると、頭痛や吐き気を伴うこともあります。(参考:厚生労働省「腰痛予防対策」)
こうした身体症状を放置すると、勉強だけでなく日常生活にも支障が出る恐れがあります。
リスク⑤食欲不振や肌荒れ、不眠など生活面への影響

勉強疲れが強まると、自律神経のバランスが乱れ、生活面にも悪影響が出てきます。代表的なのが食欲不振や胃腸の不調、肌荒れ、不眠です。
特に夜遅くまで勉強して生活リズムが乱れると、睡眠の質が低下して疲労が蓄積しやすくなります。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」)
体調が不安定になると学習効率はさらに下がり、悪循環に陥るため、日常生活の乱れも勉強疲れのリスクとして意識する必要があります。
リスク⑥学習効率の低下や成績不振
勉強疲れを抱えたまま学習を続けても、効率は上がりません。
脳が疲弊している状態では新しい知識を覚える力が弱まり、理解にも時間がかかるため、結果的に同じ範囲を何度も学習することになります。
その影響は成績不振にも直結し、思うような成果が出ずにさらにストレスを抱える悪循環を招きます。
勉強疲れを回復する対処法
勉強疲れを感じていても、受験や試験前など、どうしてもやめられない瞬間もあるでしょう。
この章では、勉強疲れを回復する対処法について解説します。
対処法①短時間の仮眠・休憩をとる

疲れを感じたときに最も効果的なのが、短時間の仮眠や休憩です。特に15〜30分程度の仮眠はパワーナップと呼ばれ、脳の働きを回復させる効果があります。(参考:J-STAGE「昼寝の功罪とパワーナップ」)
眠りすぎると逆にだるさが体に残るため、アラームを活用して短時間に留めることがポイントです。
机に突っ伏して目を閉じるだけでも脳はリフレッシュできるため、疲れを感じたら無理に続けず、休憩を挟む習慣をつけましょう。
対処法②軽いストレッチ・運動・散歩で血行を良くする
勉強中は同じ姿勢が続くことで血流が悪くなり、体のだるさや眠気が強まります。そこで効果的なのが、軽いストレッチや散歩などの体を動かす習慣です。
肩を回したり、首を伸ばしたりするだけでも血流が改善し、脳に酸素が届きやすくなります。
外に出て少し歩くだけでも、日光を浴びながら新鮮な空気を吸えるため、気分のリフレッシュ効果も高まります。(参考:野田市「冷え症の解消~ストレッチのすすめ~」)
対処法③深呼吸で気分を切り替える

作業に行き詰まってイライラしたり落ち込んだりしたときは、ゆっくりした呼吸でいったんリセットしましょう。
大きく息を吸い、ゆっくり吐き出すことで心拍や筋のこわばりが落ち着き、気分の高ぶりが和らぎます。
対処法④糖分やカフェインを適切に摂取する
勉強中の疲れや眠気を和らげるには、脳のエネルギー源となるブドウ糖(糖分)を適度に摂るのが効果的です。特にチョコレートやフルーツなど、吸収が早い食べ物は短時間で集中力を回復できます。
また、コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは眠気を抑え、注意力を高める働きがあります。ただし、過剰に摂取すると心拍数の上昇や夜の睡眠への悪影響が出るため、少量を勉強前や休憩時に摂る程度に留めるのがポイントです。
カナダ保健省によると、4歳~6歳の子どもは最大45mg/日、7歳~9歳の子どもは最大62.5mg/日、10歳~12歳の子どもは最大85mg/日(355ml入り缶コーラ1~2本相当)までと注意喚起されています。
また、13歳以上の青少年は、一日当たり2.5mg/kg 体重以上のカフェインを摂取しないことが推奨されています。(参考:厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~」)
対処法⑤音楽・アロマ・自然音などで脳を癒す

音楽や香りを利用したリフレッシュ法も勉強疲れには有効です。集中力を高めるクラシック、リラックス効果のある自然音は、脳を優しく刺激し疲労感を和らげます。
また、アロマではラベンダーやペパーミントなどが人気で、気分を落ち着け、頭をすっきりさせる作用があります。(参考:J-STAGE「脳疲労と脳血流量の関係性」、東邦大学「アロマと嗅覚、そしてストレス」)
五感を心地よく刺激することで、自律神経のバランスも整いやすくなり、再び勉強に向かう意欲を取り戻せるでしょう。
対処法⑥勉強場所を変える・環境をリフレッシュする
長時間同じ場所で勉強を続けていると環境に慣れ、集中力が落ちやすくなります。そんなときは、図書館やカフェ、自習室など別の場所に移動することで気分を切り替えることができます。
環境が変わると脳は新しい刺激を受け取り、自然と集中しやすくなります。また、部屋の換気や机周りの整理整頓といった小さな工夫でも効果はあります。
対処法⑦人と話す・笑うことでストレスを和らげる

勉強疲れは、一人で抱え込むと精神的なストレスが大きくなります。そんなときは家族や友人と会話をしたり、一緒に笑ったりするだけで気分が軽くなるものです。
笑うことは脳内でストレスホルモンを減らし、リラックス効果をもたらすことが科学的にも確認されています。気分転換を兼ねて積極的にコミュニケーションを取り入れましょう。(参考:岡山大学「健康における笑いの効果の文献学的考察」)
勉強疲れを予防する習慣と環境づくり
日々の習慣の改善や勉強に適した環境を作るだけでも、疲れを予防して効率的に勉強できるようになります。
この章では、勉強疲れを予防する習慣と環境づくりについて解説します。
予防策①規則正しい生活リズムと十分な睡眠を確保する

勉強疲れを防ぐ基本は、毎日の生活リズムを整えることです。夜更かしや不規則な生活は自律神経を乱し、集中力や記憶力を大きく低下させます。
逆に、決まった時間に寝て起きる習慣があると体内時計が安定し、日中のパフォーマンスが上がります。
特に睡眠は、学んだ内容を記憶に定着させる大切な時間であり、十分な睡眠が取れていないと学習効果そのものが半減するため注意しましょう。(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」、文部科学省「中高生を中心とした子供の睡眠習慣に関する科学的知見の整理分科会」)
予防策②バランスの良い食事と水分補給で脳を支える
脳はブドウ糖をエネルギー源として働くため、栄養バランスが乱れると学習効率が落ちます。
そこで、ご飯やパンなどの炭水化物に加え、魚や肉、卵などのタンパク質、野菜や果物からビタミン・ミネラルを摂ることで、脳が安定して働ける状態になります。
また、水分不足は血流を悪化させ疲労感を強める原因になるため、勉強中はこまめに水やお茶を飲みましょう。(参考:山梨県「~朝ごはんで生活リズムを整えよう~」)
予防策③サイクル学習法を取り入れる

長時間の詰め込み勉強は効率が悪く、疲労も蓄積しやすくなります。そのため、25分勉強して5分休憩するポモドーロテクニックのようなサイクル学習法を取り入れるのが有効です。(参考:中村聡史研究室「カウントダウンを用いたタスク促進手法に関する研究 」)
短時間で集中することにより脳の負担を減らし、定期的に休憩を挟むことでリフレッシュできます。また、学習した内容を一定間隔で繰り返す分散学習を組み合わせると記憶の定着率が高まります。(参考:J-STAGE「分散学習の有効性の原因」)
予防策④学習環境を整える
勉強に集中するためには、学習環境の質が大きく影響します。机の上が散らかっていると視覚的な情報が多すぎて脳が疲れやすくなり、部屋の照明が暗いと目に負担がかかります。(参考:J-STAGE「学校環境と学習意欲の関係性に関する研究」)
整理整頓された机、適度な明るさの照明、快適な椅子や机の高さなど、環境を整えることで無駄な疲労を防げます。
また、温度や湿度も集中力に関わるため、季節に応じてエアコンや加湿器を活用すると効果的です。
予防策⑤勉強の前後にストレッチや軽い運動を習慣化する

机に向かう前に軽く体をほぐしておくと、血流が改善され、脳への酸素供給がスムーズになります。
さらに、勉強後にストレッチを行うことで、肩や腰のこりを和らげ、疲労を翌日に持ち越しにくくなります。
勉強は座りっぱなしになることが多いため、運動不足から体が硬直しやすいのも問題です。ストレッチや軽い筋トレ、ラジオ体操のような簡単な動きでも十分効果があるので、毎日の習慣として取り入れましょう。
予防策⑥メリハリをつけ、休憩を計画的にとる
疲れを感じたら休むのではなく、あらかじめ休憩を計画に組み込むことが勉強疲れを防ぐポイントです。
前述のサイクル学習法や、自分の集中力に合わせた休憩を設定し、余裕を持って休みましょう。
休憩中はスマホを触るよりも、目を閉じる、軽く体を動かす、外の空気を吸うといった方法がより効果的です。
予防策⑦スマホやSNSとの付き合い方を工夫する

勉強中についスマホを手に取ると、集中が途切れるだけでなく、情報やブルーライトの影響で余計に疲れる恐れがあります。
勉強時間は通知をオフにしたり、別の部屋に置いたりすることで、ながら見を防ぐのがオススメです。また、休憩時間にスマホを長時間使うと逆に疲れが取れにくくなるため、使用時間を意識的に区切りましょう。
予防策⑧勉強の目的を振り返り、小さなご褒美でモチベーションを維持する
勉強を続けるモチベーションが下がると、疲労感は一層強くなります。そこで効果的なのが、勉強の目的を定期的に振り返ることです。
志望校に合格したい、次回のテストで成績を上げたいといった目標を思い出すことで、学習意欲が蘇ります。
さらに、達成感を味わうために、問題集を1章終えたら好きなお菓子を食べるなどの小さな楽しみを組み込むことで、精神的な負担が軽くなり前向きに取り組めます。
まとめ~疲れと上手に付き合って効率的に勉強しよう~

勉強疲れは誰にでも起こる自然な現象です。しかし、疲れを無視して長時間机に向かうと、学習効率が落ちるだけでなく、心身の健康にも影響が出ます。
そのため、疲れを感じたら即効対処法で回復させること、そして日常的に予防策を取り入れることが大切です。
今日から少しずつでも休憩の取り方や学習環境を整える工夫を取り入れ、疲れと上手に付き合いながら勉強する習慣を作っていきましょう。
このコラムが、勉強疲れを解消して、効率的に勉強できるようになる助けになれば幸いです。
Q&A よくある質問
勉強疲れする原因はありますか?
以下が考えられます。
- 脳の使いすぎによる脳疲労
- 長時間同じ姿勢・座りっぱなしによる身体的疲労
- 目の酷使による眼精疲労
- 睡眠不足や生活リズムの乱れ
- 勉強が思うように進まないことによる精神的ストレス
- 食事・栄養不足、水分不足
詳細については、こちらで解説しています。
勉強疲れを回復する対処法を教えてください。
以下が考えられます。
- 短時間の仮眠・休憩をとる
- 軽いストレッチ・運動・散歩で血行を良くする
- 深呼吸で気分を切り替える
- 糖分やカフェインを適切に摂取する
- 音楽・アロマ・自然音などで脳を癒す
- 勉強場所を変える・環境をリフレッシュする
- 人と話す・笑うことでストレスを和らげる
詳細については、こちらで解説しています。