受験期に眠れないあなたへ 原因や対処法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾、キズキ共育塾です。
このコラムを読んでいるあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 受験期に夜眠れず、勉強の効率が下がることに悩んでいる
- 睡眠不足による不安や焦りで集中できない
- 眠れないときの対処法や生活習慣の整え方がわからない
このコラムでは、受験期に睡眠の問題と向き合うべき理由や眠れなくなる原因について解説します。
あわせて、眠れないときの対処法や日頃からできるストレス解消法についても紹介します。
このコラムが、受験期に眠れない人の支えになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、受験で眠れなくなっている人のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
受験期に睡眠問題と向き合うべき理由
受験生にとって、質の高い眠りを意識することは勉強と同じくらい大切です。
この章では、受験期に睡眠の問題と向き合うべき理由について解説します。
理由①翌日のパフォーマンスに直結するから
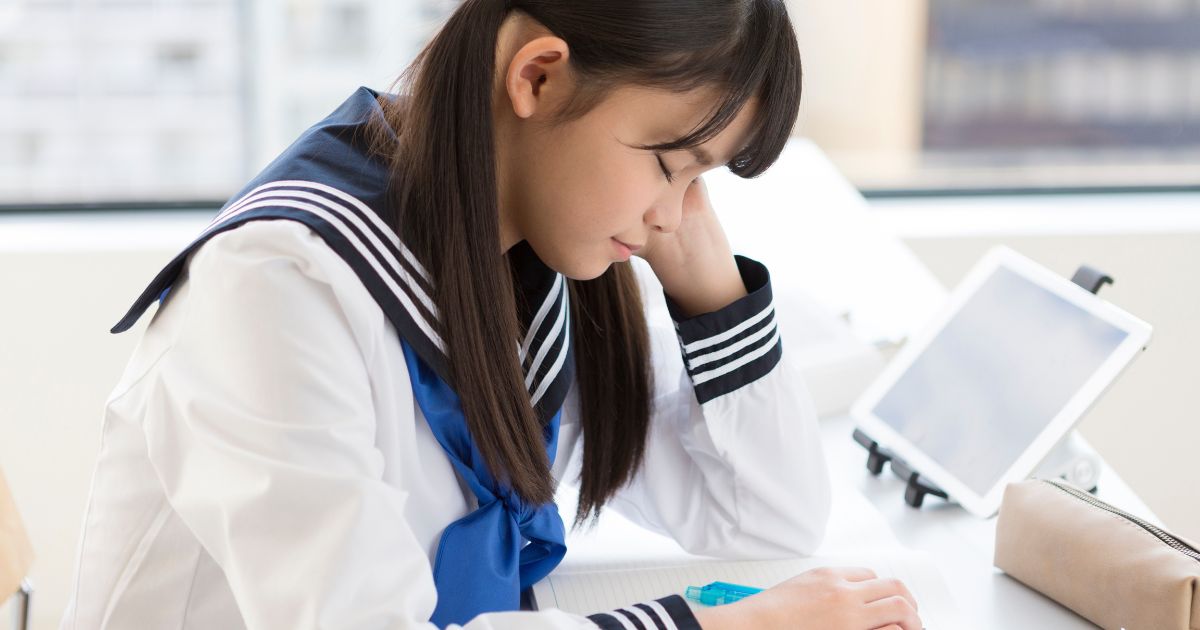
受験期は、一日の学習効率が成果に直結する大切な時期です。しかし、十分な睡眠を取れなければ、集中力や記憶力は大きく低下します。
特に脳は眠っている間に学習内容を整理し、記憶として定着させます。(参考:日本生物学的精神医学会誌 22巻3号「睡眠研究の動向」)
眠れない状態が続くと、どれだけ勉強時間を確保しても覚えたつもりで終わり、本番で知識を引き出せないおそれがあります。(参考:ログミーBusiness「6時間睡眠を5日間続けると、認知機能は“泥酔状態”まで低下 仕事を休めない日本人の「睡眠負債」がもたらす損失」)
つまり、睡眠不足は勉強の質を下げる大きなリスクであり、受験期こそ向き合うべき課題です。
理由②ストレスや不安を増幅させるから
睡眠不足は心の安定にも直結します。十分に眠れないと自律神経のバランスが崩れ、些細な出来事でも強い不安やイライラを感じやすくなります。(参考:PLOS ONE「Sleep debt elicits negative emotional reaction through diminished amygdala-anterior cingulate functional connectivity」)
受験期はもともと緊張感が高まる時期です。そこに睡眠不足が重なると、不安が増幅し、負のスパイラルに陥りやすくなります。
結果として勉強に集中できなくなるため、眠れない問題を軽視せず、早めに対処することが大切です。
理由③本番に向けたメンタル安定につながるから
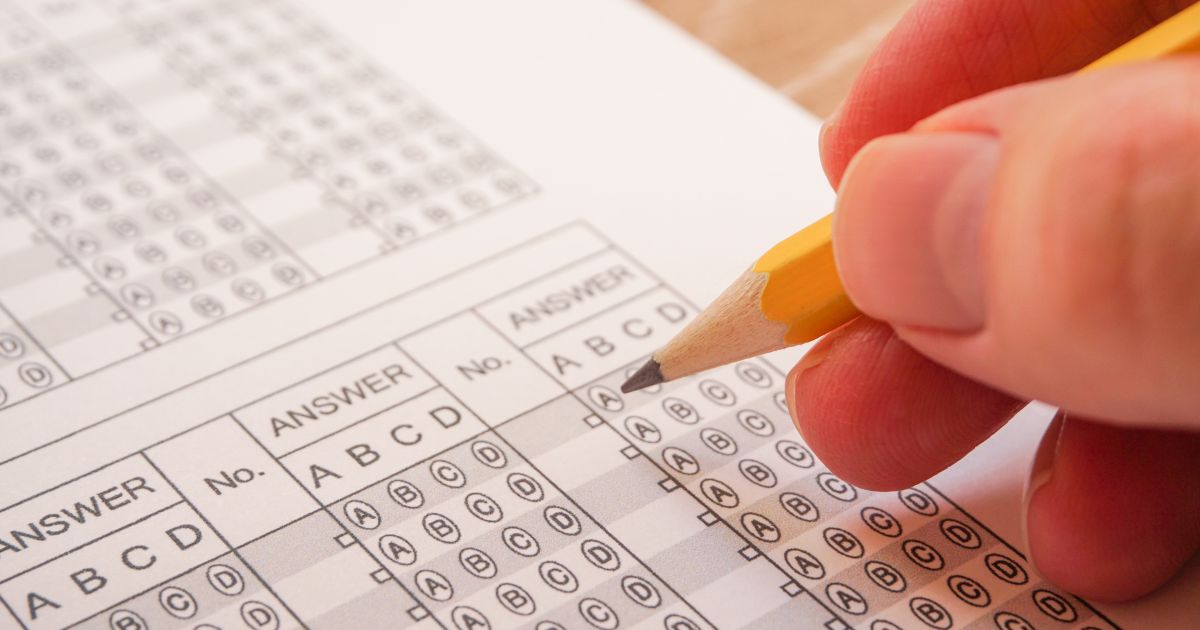
入試本番では、知識だけでなくメンタルの安定も合否に影響します。睡眠不足が続くと心身に慢性的な疲労が溜まり、試験当日に緊張をコントロールする力が弱まります。
一方でしっかり眠れていれば心に余裕が生まれ、難問にも落ち着いて取り組むことが可能です。(参考:厚生労働省「良質な睡眠で心と身体を健康に」)
試験当日に最大限の力を発揮するために、日々の睡眠を整えましょう。
受験期に眠れなくなる原因
受験生の多くが直面する悩みのひとつが、夜になかなか眠れないことです。
その原因には、精神的な要因から日々の習慣までさまざまなものがあります。
この章では、受験期に眠れなくなる原因について解説します。
原因①ストレスや不安

勉強が間に合わない、落ちたらどうしよう、といった受験特有の不安は、多くの受験生を眠れなくさせる大きな要因です。
不安があると、ベッドに入っても頭の中で考えが止まらず、心拍数や呼吸が早まりリラックスできなくなります。
これは交感神経が優位に働くためで、眠気があっても寝付きにくくなります。(参考:全国健康保険協会 富山支部「睡眠実態調査報告書」)
原因②勉強のしすぎによる脳の興奮
睡眠時間を削って勉強を続けると、脳が覚醒した状態になり眠りにくくなります。
特に暗記科目を直前まで詰め込むと、脳は情報を整理しようとして働き続け、布団に入っても頭の中に単語や公式が浮かんできます。
本来であれば、寝ている間に記憶を整理すべきですが、覚醒が続くことでその機能が十分に働かなくなります。(参考:朝日新聞「脳研究者が説く苦手な教科対策は「寝る前に勉強」 昼間はぼーっと」)
原因③生活リズムの乱れ
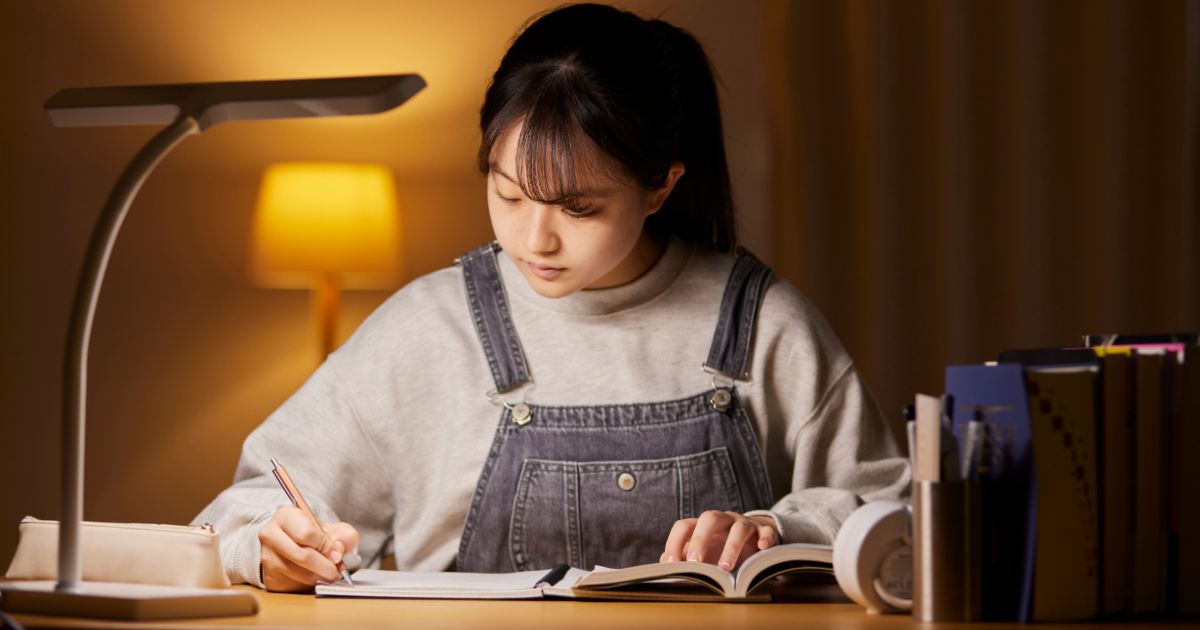
受験勉強のために夜型生活を続けると、体内時計が乱れ、眠れなくなることがあります。
本来、体は朝日を浴びて目覚め、夜に眠くなるリズムを持っています。しかし、夜更かしや朝寝坊を繰り返すと、このサイクルが崩れることになります。(参考:日本神経治療学会「標準的神経治療:不眠・過眠と概日リズム障害」)
原因④運動不足やカフェインの過剰摂取
勉強ばかりで体を動かさないと、体が程よく疲れず眠りにくくなります。睡眠は体の疲労と心の安定がそろうことでスムーズに訪れるのです。(参考:厚生労働省「快眠と生活習慣」)
また、眠気覚ましにコーヒーやエナジードリンクを飲みすぎるのも注意が必要です。
カフェインの作用は個人差がありますが、効果が半減するまで2~8時間かかるため、夕方以降に摂ると夜の眠りを妨げるおそれがあります。(参考:NCNP病院「カフェインと睡眠」)
原因⑤脳の疲労
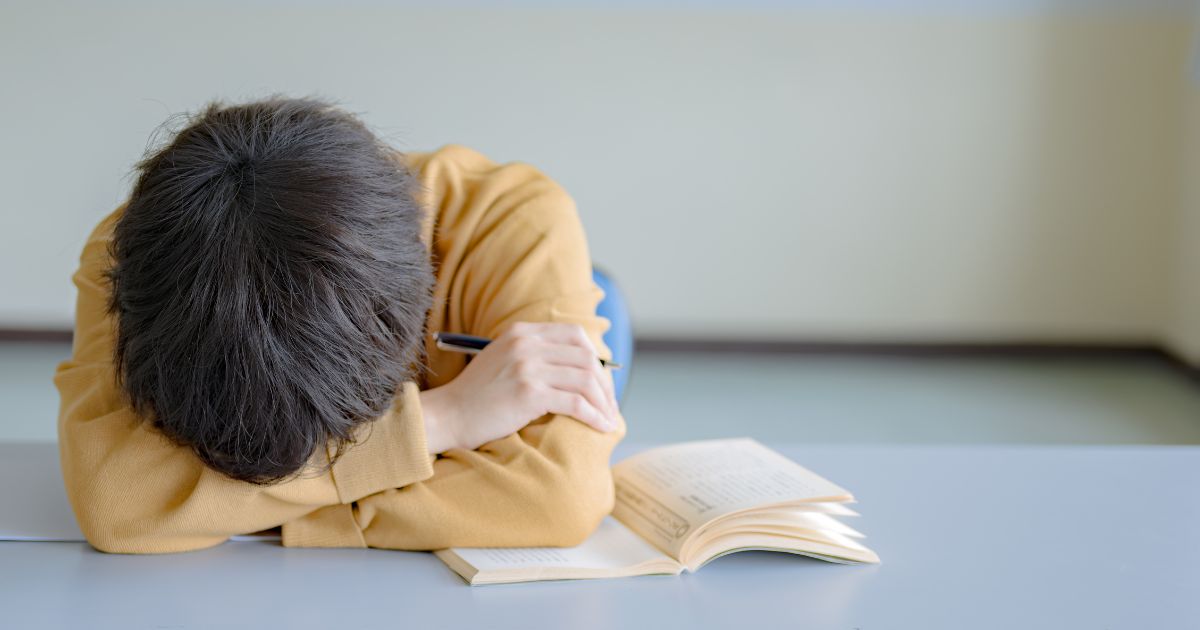
たくさん勉強したのに、疲れて眠れない経験をした人も多いでしょう。これは体よりも脳が疲れ切っているサインです。
脳が過度に疲弊すると交感神経が過剰に働き、体が緊張したままリラックスできなくなります。
その結果、眠気があっても寝付きにくくなり、疲労を翌日に持ち越すことになります。(参考:株式会社FMCC「脳疲労とストレス度 ― 疲労と自律神経機能との関係」)
眠れないときの対処法5選
夜眠れずに悩んでいる受験生に向けて、誰でも実践できる眠りの対処法があります。
この章では、眠れないときの対処法について解説します。
対処法①規則正しい生活を送る

毎日同じ時間に起きて寝るリズムを整えることで、体内時計が安定し眠りやすくなります。
夜遅くまで勉強したくなる気持ちも理解できますが、生活が乱れると結局パフォーマンスが低下します。
そのため、できるだけ起床時間を一定に保ち、朝日を浴びて体をリセットすることが大切です。リズムが安定すれば、夜も自然と眠気が訪れます。
対処法②短時間の昼寝をする
夜に眠れなかった翌日は頭がぼんやりして、勉強に集中できないことがあります。そんなときは15〜20分ほどの短い昼寝を取り入れると効果的です。
短い昼寝は集中力や記憶力を回復させ、午後の勉強効率を高める効果があります。(参考:スポーツ栄養WEB「睡眠時間を11~27%増やすとパフォーマンスが上がる? 系統的レビューからの示唆」)
ただし、長時間寝ると夜に眠りにくくなるため、あくまで仮眠として取り入れましょう。
対処法③白湯を飲む

眠れないときは、温かい白湯を飲むのがオススメです。白湯とは、お湯を50~60℃に冷ました飲み物のことです。
白湯を飲むことで体の内側からじんわり温まり、副交感神経が働きやすくなります。その結果、ストレス解消やリラックスにつながります。(参考:富士薬品「白湯に期待できる効果は?健康習慣に役立つ作り方・飲み方のポイントを解説」)
また、飲む行為そのものに気持ちを落ち着ける効果があり、眠れないときの焦りを和らげます。
対処法④とりあえず目を瞑る
眠らなきゃと焦るほど緊張状態になり、眠気が薄れていきます。そんなときは目を閉じるだけでも回復につながると考え、無理に寝ようとせずリラックスしましょう。
目を閉じて深呼吸をしたり、心地よい音楽を聴いたりするだけでも副交感神経が働きやすくなり、自然に眠気が訪れることも少なくありません。
対処法⑤スマホやパソコンを控える

寝る直前にスマホやPCを使うと、画面から出るブルーライトによって脳が刺激され、眠気が抑えられます。
そのため、最低でも就寝30分前には画面から離れるようにしましょう。その時間をストレッチや読書、日記などに充てると、リラックス効果が高まります。(参考:精神神経学雑誌 第125巻 第1号「生活習慣と睡眠の問題が精神的不調に与える影響についての縦断的分析」)
日頃からできるストレス解消法
睡眠対策には、一時的な工夫に加えて、日常生活の中でストレスをうまく発散しておくことも大切です。
この章では、日頃からできるストレス解消法について解説します。
解消法①適度な運動を取り入れる

受験勉強に集中していると、どうしても体を動かす時間が減りがちです。しかし運動には、ストレス解消と睡眠改善の両方に効果があるのです。
運動で心地よい疲労を感じると、自然に眠気が訪れやすくなります。ウォーキングや軽いストレッチでも十分で、血行を促し自律神経を整える効果があります。(参考:厚生労働省「快眠と生活習慣」)
特に夕方以降に軽い運動を取り入れるとリラックス効果が高まり、夜の寝付きが良くなるでしょう。
解消法②ノートに不安を書き出す
受験期の不安は頭の中で繰り返し浮かび、眠りを妨げます。そんなときはノートや紙に考えを書き出してみましょう。
書くことで頭の中が整理され、不安を客観的に捉えられるようになります。不安を抱えたまま眠るのではなく、書き出してから休むことで気持ちを切り替えやすくなり、寝付きも良くなります。
解消法③短時間でも趣味や好きなことに触れる

勉強一色の生活では、次第に心が疲れていきます。
勉強ももちろん大事ですが、モチベーションの維持やストレス解消には、短時間でも好きなことに触れる時間を持つことが大切です。
例えば、勉強から意識を切り替えて、音楽を聴く、漫画を数ページ読む、絵を描くなど、ちょっとした工夫で気持ちをリフレッシュできます。
まとめ〜眠れる環境づくりの徹底が合格へのカギ〜

受験期に眠れないのは、多くの受験生が直面する悩みのひとつです。
しかし原因と対処法を理解し、日頃からストレス解消や生活リズムの改善を意識すれば、眠りの質は十分に高められます。
しっかり眠れる環境を整えることこそ、合格に向けた大切な準備です。良質な睡眠を味方につけ、本番で本来の力を発揮できるよう備えましょう。
このコラムが、受験で眠れない状況を打破する支えになれば幸いです。








