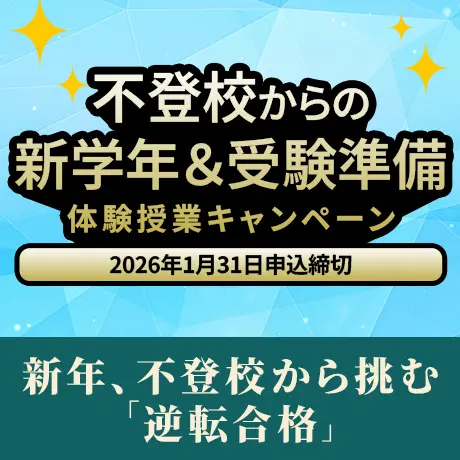高等専修学校とは? 学べる分野や他の学校との違いなどを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートするキズキ共育塾です。
中学生のあなたは卒業後の進路について、以下のような疑問を抱いていませんか?
- 高等専修学校とは何だろう?
- 高等学校や高等専門学校とは何が違うんだろう?
このコラムでは、高等専修学校への進学を検討している中学生に向けて、高等専修学校の概要や学習分野、入学試験の特徴、高等学校や高等専門学校との違いについて解説します。
あわせて、高等専修学校卒業後の進路や高等専修学校に関する支援制度を紹介します。
このコラムが納得のいく学校選びの助けになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、進路選択に悩む中学生のための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
高等専修学校とは?

高等専修学校とは、職業や日常生活に必要な能力の育成と教養の向上を目的とする専修学校の一種で、中学校卒業者を対象とした高等課程を設置する学校のことです。
専修学校では、実践的な職業教育や特定分野でのスペシャリストを育成するための教育、社会での自立を目指した教育が行われています。(参考:文部科学省「未来をひらく高等専修学校」)
高等専修学校には、専修学校の中でも高等学校と並ぶ後期中等教育機関で、普通科目に加え、工業や農業、医療など文部科学省で定められた8つの専門分野があります。
修業年限は主に1〜3年制ですが、定時制高校や通信制高校の場合は、3年以上かかる場合があります。(参考:文部科学省「さまざまな進路と高等専修学校」)
高等専修学校の目的と役割
高等専修学校の目的は、生徒が職業や実生活に必要な能力、または教養を身につけることにあり、多様で個性ある生徒の自立を支える役割を担います。(参考:文部科学省「未来をひらく高等専修学校」)
そのため、社会での自立に向けた実践的な職業教育や特定分野での、スペシャリストを育成するための教育など実務面に重きを置き、多様な学びを提供しています。
また、不登校経験者に対する手厚いサポートを行っていることも、特徴の一つといえます。
全国高等専修学校協会によると、高等専修学校に通う生徒の内、約2割が不登校を経験しているとのことです。少人数教育や不登校経験者の受け入れを行っている点から見ても、その特徴がうかがえます。(参考:全国高等専修学校協会「高等専修学校の実態に関するアンケート調査報告書」)
高等専修学校で学べる分野
高等専修学校では、文部科学省で定められた以下の分野を学ぶことができます。(参考:全国高等専修学校協会全国高等専修学校協会「高等専修学校とは?」)、文部科学省「『未来をひらく高等専修学校』」)
分野①工業:情報処理、IT、自動車、機械、工業技術など

工業の分野では、コンピューターをはじめとしたIT関連の最新テクノロジーに対応できる人材や自動車整備、機械、電気などの技術者を育成します。
IT関連や電気、機械に関する資格試験・検定を幅広く受験できる点が特徴です。
分野②農業:農業、園芸、畜産、造園、バイオテクノロジー、動物管理など
農業の分野では、農業や園芸、畜産などの基礎知識が身に付くほか、栽培や収穫といった実務経験が積めます。
分野③医療:看護、歯科衛生、歯科技工、臨床検査、診療放射線、理学療法、作業療法など

医療の分野では、看護をはじめ、歯科衛生や臨床検査、理学療法、作業療法などの学科を設置しています。
医療分野の学科のほとんどで准看護師養成を行っており、卒業後は准看護師として働く人や看護師を目指して専門学校に進学する人もいます。
分野④衛生:栄養、調理師、製菓、製パン、理容、美容など
衛生分野は、調理系と理容・美容系の2つに分かれます。
調理系の分野では、調理師免許や製菓衛生士免許の取得ができる学科が多数あります。
卒業後は飲食業界へ就職する生徒や、栄養士・管理栄養士の資格を取得するため、専門学校へ進学する生徒もいます。
理容・美容系の分野では理容師、美容師資格が取得できる学科が多くを占めます。卒業してすぐに理容・美容関係の仕事に就くことができる点が特徴です。
分野⑤教育・社会福祉:保育、幼児教育、社会福祉、医療福祉、介護福祉など

教育・社会福祉の分野では、保育や社会福祉、介護福祉などを学びます。
この学科の多くでは介護福祉士を目指すためのカリキュラムとなっており、介護福祉施設や病院への就職を目指せます。
分野⑥商業実務:経理・簿記、旅行・観光・ホテル、会計、経営、医療秘書など
商業実務の分野では、ビジネスのスペシャリストを目指します。
簿記や会計といった経理に関する知識やオフィスワークに必要なパソコンソフトを活用する力が身に付きます。
分野⑦服飾・家政:ファッションデザイン、ファッションビジネス、和洋裁、編物・手芸など

服飾・家政の分野では、服飾系の学校が多くを占めます。
実習を交えながらデザインや仕立て、着付けなど和裁・洋裁の知識や技術を身に付けます。
分野⑧文化・教養:デザイン、音楽、外国語、演劇・映画、写真、公務員など
文化・教養の分野は、大きく分けて文化系と教養系に分かれます。
文化系では、俳優や音楽家など芸能関係の仕事を目指すための授業があり、実際に芸能関係の仕事に就く方から指導を受けられる点が特徴です。
教養系では、国語や数学といった普通科目をはじめ、社会に役立つ教養知識や外国語が学べます。大学へ進学する生徒が多い点も特徴として挙げられます。
高等専修学校の学費
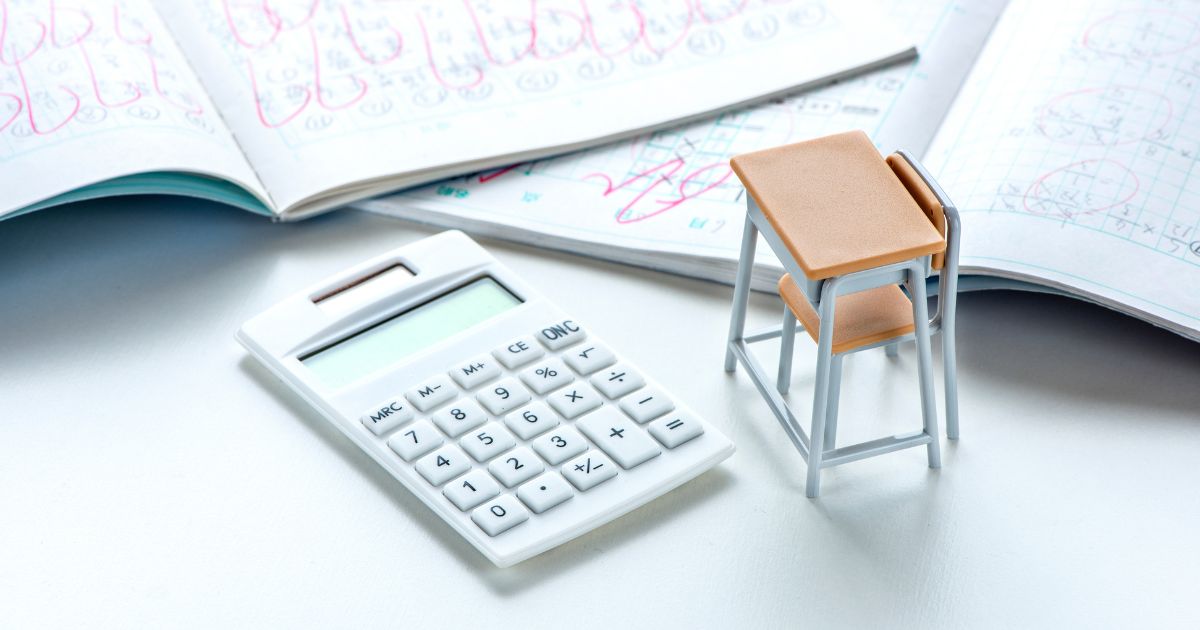
公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会が発表した、2020年度の専修学校各種学校調査統計資料によると、平均学費は93万円です。
また、各分野における最低金額、最高金額を見てみると、最低金額は情報処理・IT分野で約33万円、最高金額は製菓分野で約297万円でした。費用の内訳として、入学金や授業料、実習費、設備費などが含まれます。(参考:公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会「令和2年度 専修学校各種学校調査統計資料」)
高等専修学校の学費は目指す学校や分野により大きく異なり、同じ学科でも昼間・夜間によっても違いがあります。
そのため、WEBサイトを確認するなどして、事前に行きたい学校の学費がいくらなのかを調べておくことをオススメします。
高等専修学校の入学試験の特徴
多くの高等専修学校の入学試験では、高等学校と同様に筆記試験や面接試験を行い、なかには作文を課す学校もあるようです。
入学試験では、中学卒業程度の学力が身に付いていることを求められます。(参考:文部科学省「専修学校 #知る専」、大阪技能高等専修学校「入学案内 生徒募集要項・助成制度」)
学校によって選考方法が異なるため、事前に行きたい学校の試験内容について調べておきましょう。
高等専修学校と高等学校・高等専門学校・専門学校との違い
この章では、高等専修学校と高等学校・高等専門学校・専門学校との違いについて、学校の分類や修業年限、教育内容、学歴、大学入学資格付与の観点から解説します。
高等学校との違い

高等学校は、高等専修学校と同じく後期中等教育機関に分類されますが、修業年限では高等学校が主に3年、高等専修学校は1〜3年となります。
教育内容は高等学校、高等専修学校のどちらでも普通科目を学びますが、高等専修学校で学ぶ普通科目は、就労するために必要な勉強という側面を持ちます。
加えて、高等専修学校では職業に直結する専門科目を中心に学びます。
学歴は、高等学校や教育過程が3年以上の高等専修学校であれば高卒となります。また、高等学校や高等専修学校の中でも大学入学資格付与指定校であれば、大学入学資格が得られます。(参考:文部科学省「未来をひらく高等専修学校」)
高等専門学校との違い
高等専門学校は、高等専修学校とは異なり、高等教育機関に分類されます。修業年限では、高等専門学校では主に5年、高等専修学校は1〜3年となります。
高等専門学校、高等専修学校のどちらも専門分野を中心に学ぶ点に関しては同じですが、高等専門学校では技術者養成を目的とし、高等専修学校では実務教育を目的としている点に違いがあります。
学歴は、高等専門学校では準学士(短期大学と同等の学位)が得られるのに対し、高等専修学校では、教育過程が3年以上の場合は高卒となります。
また、高等専門学校や高等専修学校の中でも大学入学資格付与指定校である場合は、大学入学資格が得られます。(参考:文部科学省「未来をひらく高等専修学校」)
専門学校との違い

専門学校は、高等専修学校とは異なり、高等教育機関に分類されます。
修業年限では、専門学校が主に2年、高等専修学校は主に1〜3年となります。
また、専門学校でも高等専修学校でも実務教育を目的としている点は共通し、どちらも専門分野を中心に勉強します。一方で、専門学校では高等専修学校よりも高度な内容を学ぶイメージです。
学歴は、専門学校では専門士または高度専門士と呼ばれる学位が得られ、高等専修学校は教育過程が3年以上の場合は高卒となります。
また、専門学校や高等専修学校の中でも大学入学資格付与指定校であれば、大学入学資格が得られます。(参考:文部科学省「未来をひらく高等専修学校」)
補足:技能連携制度
技能連携制度とは、通信制高校または定時制高校に通う生徒が、指定された技能教育施設で教育を受けている場合に、その施設で受けた教育を在籍中の学校の教科の一部の履修とみなすことができる制度のことです。技能教育施設は技能連携校ともいいます。
例えば、現在、A高等高校に通う生徒が、技能連携校のB高等専修学校で教育を受けている場合、B校の履修をA校の一部履修とみなすことができるため、場合によっては両校の卒業資格が得られるというケースもあります。(参考:文部科学省「未来をひらく高等専修学校」)
高等専修学校卒業後の進路
全国高等専修学校協会によると、2022年度において、高等専修学校を卒業した生徒の内、就職を選んだ人は全体の約38%を占め、約37%は専門学校、約14%は大学や短期大学等へ進学しているとのことです。(参考:全国高等専修学校協会「令和5年度 高等専修学校の実態に関するアンケート調査」)
大学入学資格が得られる学校や技能連携校から大学、短期大学へ進学する人もいます。
また、就職を選んだ生徒は、学校で学んだ分野に直結した仕事に就くことが全体の約83%と非常に多いです。(参考:文部科学省「職業実践専門課程の実態等に関する調査研究」)
高等専修学校に関する支援制度
この章では、高等専修学校に関する支援制度について解説します。
紹介する支援制度以外にも、授業料軽減助成金など各都道府県で設けられている支援金や支援制度もあります。
気になる人は進学先地域での支援金について調べてみることをオススメします。(参考:公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会「高等専修学校とは」)
支援制度①高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金制度とは、高等学校や高等専修学校など、後期中等教育を受ける所得などの要件を満たす生徒に向けて、授業料を支援する制度のことです。
特徴として、修業年限や大学入学資格付与の有無といった条件を問いません。すべての高等専修学校の生徒が対象となり、親御さんの年収に応じた支援を受けることができます。(参考:文部科学省「未来をひらく高等専修学校」)
支援制度②高校生等奨学給付金制度
高校生等奨学給付金制度とは、低所得世帯を対象に、教材費など授業料以外の教育費において返還不要の支援金を給付する制度のことです。
参考に支援額の目安を記載します。
- 年収が約270万円未満の場合:年間3~14万円
世帯状況により支援額に変動があるため、進学先の学校や高校生等奨学給付金窓口へ最新の情報を確認しましょう。(参考:文部科学省「高校生等への修学支援」)
まとめ~進学先はしっかりと下調べし、後悔のないよう選びましょう~

高等専修学校は、就業を見据えた専門性ある授業を受けられたり、不登校経験者へ手厚かったりと、一般的な高等学校とは異なる特徴があります。
進学先に悩んでいる人は、候補の一つとして高等専修学校を視野に入れてみるのもいいでしょう。
高等学校と比べると学習分野も専門的になるため、自分の進みたい将来を考え、しっかりと下調べすることをオススメします。
Q&A よくある質問
高等専修学校では、何を学べますか?
以下が考えられます。
- 工業:情報処理、IT、自動車、機械、工業技術など
- 農業:農業、園芸、畜産、造園、バイオテクノロジー、動物管理など
- 医療:看護、歯科衛生、歯科技工、臨床検査、診療放射線、理学療法、作業療法など
- 衛生:栄養、調理師、製菓、製パン、理容、美容など
- 教育・社会福祉:保育、幼児教育、社会福祉、医療福祉、介護福祉など
- 商業実務:経理・簿記、旅行・観光・ホテル、会計、経営、医療秘書など
- 服飾・家政:ファッションデザイン、ファッションビジネス、和洋裁、編物・手芸など
- 文化・教養:デザイン、音楽、外国語、演劇・映画、写真、公務員など
詳細については、こちらで解説しています。
高等専修学校に関する支援制度はありますか?