ADHDの子どもの「勉強できない」の理由、効果的なサポート、親にできること

こんにちは。ADHDをはじめ、発達特性のある生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾、キズキ共育塾です。
このコラムを読んでいるあなたは、ADHDのあるお子さんについて、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 興味がないことに取りかかれず、勉強が長続きしない
- 机に向かうのが億劫で、つい後回しになる
- 子どもの学習をどう支えればよいか迷っている
このコラムでは、ADHDの特徴や勉強でつまずきやすい理由について解説します。あわせて、ADHDのある子どもに効果的な勉強法や家庭や周囲ができるサポートについても紹介します。
このコラムが、勉強が苦手なADHDのお子さんと親御さんの助けになれば幸いです。
私たちキズキ共育塾は、発達に特性のあるお子さんのための、完全1対1の個別指導塾です。
10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。
目次
ADHD(注意欠如多動症)とは?
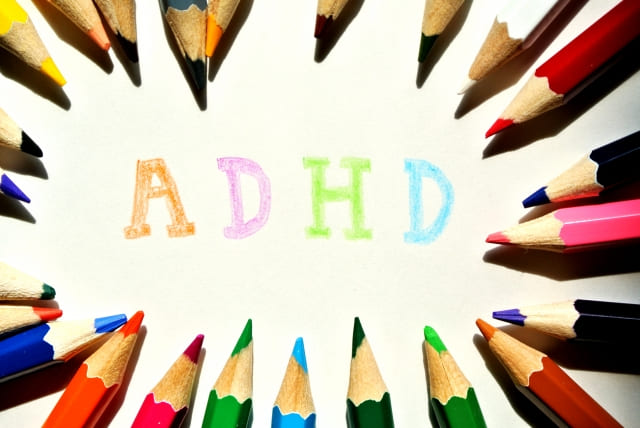
ADHD(注意欠如・多動症)は、集中力や注意の持続、衝動のコントロールに特徴が見られる発達障害の一つです。
ADHDはしつけや性格の問題ではなく、脳の神経伝達の違いによるもので、子どもだけでなく大人になっても続くことがあります。
早期の理解とサポートによって、特性を活かした学び方や生活スタイルを見つけられます。
■参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄・監修『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD─もっとも身近な発達障害』、司馬理英子『ササッとわかる 「大人のADHD」 基礎知識と対処法』、星野仁彦『それって、大人のADHDかもしれません』、国立精神・神経医療研究センター「ADHD(注意欠如・多動症)について」、四天王寺大学 鈴木浩太「注意欠如・多動症に関わる行動指標の包括的レビュー:心理学的特徴と異種性」)
ADHDの基本的な3つの特徴
ADHDは大きく不注意優勢型、多動・衝動性優勢型、混合型の3つに分類されます。
この章では、ADHDの基本的な3つの特徴についてそれぞれ解説します。
特徴①不注意優勢型
不注意優勢型は、集中力の持続が難しく、細かい部分を見落としたり、物をよくなくしたりする傾向があります。
また、授業中にぼんやりする、話を最後まで聞けない、やるべきことを後回しにすることもあります。
このタイプの子どもは一見おとなしく見えるため、周囲から気づかれにくいのも特徴です。
本人も努力が報われないように感じ、自己肯定感が下がりやすくなります。
特徴②多動・衝動性優勢型
多動・衝動性優勢型は、体を動かさずにじっとしていることが難しく、授業中に立ち歩く、会話を途中で遮る、順番を待てないなど、思いついた行動をすぐに取る傾向があります。
これは意図的なわがままではなく、衝動を抑える脳の働きが弱いことが原因です。
多動・衝動性優位型の子どもは、周囲から落ち着きがないと誤解されやすいため、特性を理解した接し方が大切です。
特徴③混合型
混合型は、不注意と多動・衝動性の両方の特徴が見られるタイプです。
集中力の途切れやすさと落ち着きのなさが同時に現れるため、学校生活や友人関係でトラブルが起きやすいこともあります。
ADHDの子どもが勉強でつまずきやすい理由

ADHDのある子どもたちは、知的な理解力には問題がなくても、学習の進め方や集中の持続に困難を感じることがあります。
この章では、ADHDのある子どもが勉強でつまずきやすい理由について解説します。
■参考:国立特別支援教育総合研究所『研究紀要』第44巻、伊藤由美「発達障害のある子どもへの心理的支援をめぐる課題 ―インクルDBの事例の検討から―」、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部「注意欠如・多動症における社会的報酬の報酬頻度が実行機能に与える影響の検討」、神戸大学 教育学研究科「発達障害の理解」、国立精神・神経医療研究センター「“ADHDタイプ”の方の対処策①」
理由①興味のないことに集中できない
ADHDのある子どもは、脳の報酬系と呼ばれる部分の働きに特徴があり、興味のあることには高い集中力を発揮する一方で、退屈な課題には集中できません。
これは意志の弱さではなく、脳の刺激に対する反応の差によるものです。
理由②勉強に取りかかるのが難しい
ADHDのある子どもは「やらなきゃ」と思っていても、勉強に取りかかるまでに時間がかかることがあります。
これは実行機能の働きが弱いためで、行動を起こすスイッチが入りにくいのです。
特に、宿題を前にしても手が止まる、片づけを始めるのに時間がかかるなどの行動が見られます。
理由③注意がそれやすく、最後まで集中できない
授業中に周囲の音や動きが気になるなど、途中で別のことに意識が移りやすいのもADHDの特徴です。
特に教室のように刺激の多い環境では、視覚・聴覚の情報を同時に処理しきれず、注意の焦点を保つことが難しくなります。
その結果、ノートを取り忘れたり、課題の最後までやりきれなかったりといった行動につながることがあります。
理由④宿題や課題のやり忘れが多い
ADHDのある子どもは、覚えていたのに忘れた、やったのに提出を忘れた、といったやり忘れが頻繁に起こります。
これは記憶力の問題ではなく、ワーキングメモリ(作業中の情報を保持する力)が弱いためです。
宿題をメモしても見返すのを忘れる、カバンに入れ忘れるといったミスが起きやすくなります。
理由⑤自己肯定感が低く、やる気が出にくい
繰り返し叱られたり、うまくできないことで注意を受けたりする経験が続くと、子どもは「自分はダメなんだ」と感じやすくなります。
ADHDのある子どもは、特性によって失敗体験が積み重なりやすく、周囲との比較から自己肯定感が下がることがあります。
その結果、勉強そのものへの意欲や関心が薄れることも少なくありません。
ADHDの子どもに効果的な勉強法
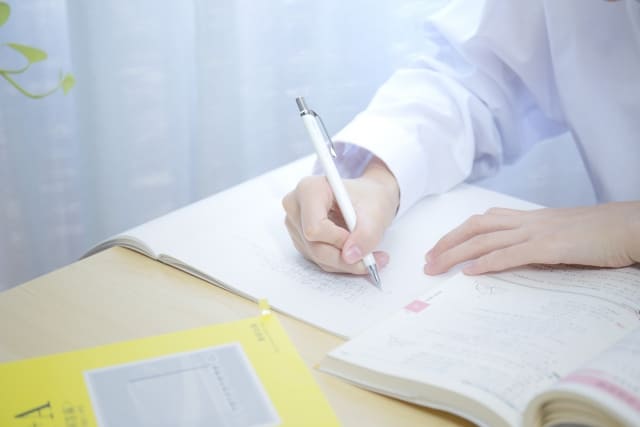
ADHDのある子どもは、一般的な学習方法では成果が出にくいことがありますが、学び方の工夫次第で自信を積み重ねることが可能です。
この章では、ADHDのある子どもに効果的な勉強法について解説します。ただしこれらは、あくまでも例です。実際のあなたのお子さんに効果的な勉強法は、後述する「発達障害に詳しい塾」などを利用することで、具体的に見つかるはずです。
■参考:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育推進センター「注意欠如多動性障害(ADHD)のある子どもの指導・支援」、文部科学省 「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」、J-Stage 特集:心身医学の臨床における発達障害特性の理解 村上佳津美「注意欠如・多動症(ADHD)特性の理解」
勉強法①勉強時間を区切って集中する
長時間の勉強は、ADHDのある子どもにとって集中を保つのが難しい傾向があります。
そこで、例えば20〜30分など短い時間で区切り、間に5分程度の休憩を挟むことで、集中をリセットしながら学習できます。
また、1セット終わったらシールを貼る、タイマーを使う、といった仕組みを取り入れると、ゲーム感覚で続けやすくなります。
勉強法②学習環境を整えて刺激を減らす
ADHDのある子どもは、周囲の音や光、視覚的な刺激に注意が向きやすいため、学習環境を整えることが重要です。
まず、机の上は必要なものだけを置き、静かな場所を選びましょう。テレビやスマートフォンのような集中を妨げる娯楽は、学習環境から遠ざけます。
家で難しい場合は、図書館や塾など静かな環境を活用するのも一案です。環境が整うことで、集中の質が大きく変わります。
勉強法③小さな目標を設定して達成感を積み重ねる
いきなりテストで80点を取るような大きな目標ではなく、今日は漢字3個を覚える、1ページだけやる、といった小さな目標を設定すると、達成感を感じやすくなります。
ADHDのある子どもはできた瞬間の手応えがモチベーションにつながりやすいため、成功体験を日々積み上げることが重要です。
また、成功体験に加えて保護者や教師が小さな努力をしっかり認めることが、やる気の継続につながります。
勉強法④To Doリストでやることを見える化する
ADHDのある子どもは、頭の中で情報を整理したり、順序立てて行動したりすることが苦手な場合があります。
そこで、To Doリストやスケジュール表を使って、何を・いつ・どの順に・やるかを見える化することで、行動の見通しが立てやすくなります。
また、やることを見える化しておけば、保護者や教師もサポートしやすくなるのもメリットです。
勉強法⑤興味や得意を活かした学習スタイルを取り入れる
ADHDのある子どもは、興味を持った分野では高い集中力を発揮するため、その特性を活かし、興味のある内容を勉強に結びつける工夫が有効です。
例えば、電車が好きな子には算数で時刻表を使う、漫画が好きな子には国語の文章を漫画で説明するなど、好きなことを通じて学ぶ仕組みを作りましょう。
こうした能動的な経験が、勉強の苦手意識を和らげ、前向きな取り組みにつながるようになります。
勉強法⑥無理をせず、疲れをためないようにする
ADHDのある子どもは、集中するまでにエネルギーを多く消費するため、長時間の勉強で疲れがたまりやすい傾向があります。
逆に、興味のあることには逆に極端に集中し過ぎて、疲れが出ることもあります。
疲労がたまると、集中力や記憶力がさらに低下し、悪循環を招くため、1日の学習量を詰め込みすぎず、休息やリフレッシュの時間をしっかり確保しましょう。
勉強だけでなく、遊びやリラックスの時間も成長の一部として大切にすることがポイントです。
「ADHDで勉強できないお子さん」に家庭や周囲ができるサポート

ADHDのある子どもが安心して学びに向かうためには、家庭や学校、地域社会など周囲の理解とサポートが欠かせません。
この章では、家庭や周囲ができるサポートについて解説します。
■参考:国立特別支援教育総合研究所『研究紀要』第44巻、伊藤由美「発達障害のある子どもへの心理的支援をめぐる課題 ―インクルDBの事例の検討から―」、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育推進センター「身近な相談機関」
サポート①子どもの特性を理解し、否定しない
ADHDのある子どもは、努力しても失敗を繰り返すことがあります。
しかし、失敗に対して保護者や先生が「なぜできないの?」と叱るよりも、「こういうやり方ならできるかも」と一緒に考える姿勢が重要です。
否定的な言葉よりも、できた部分を認める言葉が子どもの自信を育てます。
特に、ADHDのある子どもは興味のあることに集中力を発揮できるので、周囲は子どもの得意な分野を見つけ、それに対応する学習環境を整えましょう。
サポート②周囲(家族・友人・先生)の理解を得る
ADHDは外見では分かりにくい特性のため、周囲から誤解を受けることも少なくありません。そのため、偏見を減らすには、家族や教師、友人に正しい知識を伝えることが大切です。
学校では担任だけでなく、学年全体で共通理解を持つとより効果的です。周囲が理解者になることで、子どもが安心して自分らしく学校生活を送る環境が整います。
サポート③学校・医療機関・カウンセラーと連携する
ADHDのある子どものサポートでは、家庭だけで抱え込まず、学校や医療機関と情報を共有しながら支援体制をつくることが重要です。
学校では特別支援コーディネーターやスクールカウンセラー、医療機関では発達外来や小児神経科、公的機関では教育委員会や教育センター・特別支援教育センターが相談先です。
必要に応じて心理検査や発達検査を受けることで、支援の方向性が明確になるでしょう。
また、悩みを相談することにより、家族も安心して子どものサポートができるようになります。
サポート④明日の予定や持ち物を一緒に確認する
ADHDのある子どもは、忘れ物や準備のし忘れが多い傾向があります。
そこで、前日の夜には明日の持ち物リストや時間割ボードを確認する習慣をつけることで、安心して1日を始められます。
ただし、保護者がすべてを代わりにやるのではなく、少しずつ自分で確認できるよう導くことで、自己管理力が育ちます。
サポート⑤ADHDに理解のある塾や家庭教師を利用する
最近では、ADHDや発達特性に理解のある学習塾や家庭教師サービスも増えています。
これらのサービスでは、個々の特性に合わせたペースや方法で学べるため、自己肯定感を保ちやすくなります。
塾を選ぶ際は、指導者が発達特性への理解を持っているかどうか、また子どもが安心して話せる雰囲気かを重視しましょう。
私たちキズキ共育塾でも、ADHDに悩む子どもの学習サポートだけでなく、メンタル面のサポートにも力を入れています。
まとめ~ADHDの特性を理解すれば、「勉強できない」は克服できます~

ADHDのある子どもは、集中力や実行機能に課題を抱えながらも、発想力や柔軟性など優れた面を持っています。
そのため、周囲がADHDの特性を理解し、苦手を責めるのではなく、得意なことを伸ばす視点で関われば、子どもの学びに対する意識は大きく変わります。
子ども一人ひとりに合った環境とサポートを整え、安心して成長できる社会を一緒に築いていくことが大切です。
このコラムが、ADHDのある子どもが勉強に対する苦手意識を克服し、自分らしく生活できる支えになれば幸いです。





