自己肯定感を持てず苦しんだ少年期。今悩んでいる人の助けになりたいと考えキズキ共育塾へ

東京外国語大学外国語学部在籍
英語、現代文
小学生のころは勉強も運動も得意な優等生。しかし自分の無個性ぶりにコンプレックスを抱えていた。高校時に「他人と違うことをしたい」と考えオーストラリアへ留学。そこで、「個性は誰にも備わっているもの」と思えるようになる。その後、より新しい環境を求めてケニアへ。「辛いことも、笑いに変えられればそれでよい」という感性を得る。帰国後、二度の海外生活を経て自分が自分を認められるようになったことに気づく。そうした経験から、他者が自己肯定感を持つきっかけになりたいと考え、キズキ共育塾へ。
「普通」が嫌だと思い続けた
「個性的になりたいな…」 小学生くらいのときから、そんなことを考えていました。
当時の私は、勉強が得意で、真面目で、運動会や文化祭などの行事にも積極的に参加するようないわゆる手のかからない子供でした。
中学校ではテニス部で部長を務めたりと、部活にも勉強にも全力を注ぐ優等生。
それでも何故か、そんな優等生を天井から見つめているもう一人の自分がいるような感覚があったんです。
「これでいいのかな…」みたいな。
周囲の人から、「小黒君は勉強も部活もがんばっていて偉いね」と褒められても、「俺は全然ダメなのに…」と考えているようなひねくれ者でした。
私の周囲には魅力的な人がいっぱい居たからかもしれません。
サッカーがめちゃくちゃ上手い爽やか男子Aくん。
いつでも明るく、お笑い芸人の物まねを完璧にこなすムードメーカーBくん。
可愛いのにベイブレードがめちゃくちゃ強いCさん。
羨ましいと思える個性を持つ人々と自分を比較すると、自分は何て個性がなくてつまらない人間なんだとコンプレックスを感じずにはいられませんでした。
自分に自信がなかったからか、小さなことでもクヨクヨと悩んでいましたね。
「魅力的になるためには、何かみんなと違うことをしなければいけない。そうしないと個性的になれない」幼い私には少し荷の重いプレッシャーを抱えていた矢先に、高校受験の季節がやってきました。
先生には地元の進学校への進学を勧められましたが、普通の進学校は嫌だと抵抗し続けたことを覚えています。
それに対して両親が何も言わなかったのは、何となく私の悩みを見透かしていたからかもしれません。
凄い…。
進学校への進学はせず、「よし。これで自分は面白い人間になれるかもしれない」という期待を胸に、静岡県の片田舎では珍しい海外留学のできる高校への進学を決めました。
海外に行って英語を話せるようになりたいというのは周囲を説得するために後付けした理由で、みんながあまりやっていない面白いことができれば何でもよかったんです。
面白い体験をして面白い人間になることができれば、自分と他の人を比較してクヨクヨと悩むこともなくなるだろうと。
初めての海外経験。皆と違うことが当たり前になって
実際に留学に行ってみると、「個性」という言葉に対する意識が変わっていきましたね。
特別な才能もなく、「普通」が嫌だと思っていたんですけど、そもそも「普通」ってなんなんだろうって。
みんなと違うことをしたいという動機で向かったオーストラリアでは、みんなと違うことがもはや当たり前だったこともそう思った大きな一因だったのかもしれないです。
・みんなが当たり前のように話せる英語を話すことができずに苦笑いをされる
・「ごめん」と言いながら手を合わせると、「その手合わせてんのはどういう意味?ジャパニーズカルチャー?」と聞かれる
・職業体験で幼稚園に行くと、子供たちに「目が黒くて面白ーい」と騒がれる
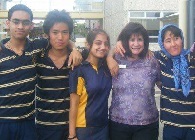
例を挙げたらきりがないですが、留学生活は、自分自身が「多数派ではないからこそ物珍しく見られる」という体験に溢れていました。
そしてそういった体験を積み重ねていく中で、「個性」は自分から見つけ出すものではなくて、生まれながらにしてあるものなのかもしれないと考えるようになりました。
生きていればそれが勝手に「個性」になるというか…。
留学前の私は、周囲の面白い人たちを見て、自分はつまらない人間だと考えてしまっていたんですけど、自分と同じ人間なんてこの世界に一人もいないと気付くことができて、だったら俺も個性的じゃん!って何となく吹っ切れられたんです。
上手く言葉にはできないんですけど…。
膨らみ続けた異世界への興味。単身ケニアへ
新たな環境に飛び込んで、新しい考え方を身につけることができたことが嬉しくて、海外への興味はどんどん膨らんでいきました。
それで大学時代にはケニアにインターンをしに行ったんです。
ケニアでの体験を一言で表すことはとても難しいですが、オーストラリアよりも異世界に来たような感覚が強かったですね。
日本やオーストラリアのようには物質的に恵まれていないからこそ、ケニアには精神的な豊かさがあるように見えました。
大変な状況すら笑い飛ばす強さがあるというか、何でもネタにしてしまうんですよね。
最初は底抜けの明るさに戸惑いましたが、徐々にそれが魅力的に見えていきました。
私のインターン先は田舎の村だったので、オフィスでもよく停電が起きてたんですね。
田舎ではどれだけ天気がよくても急に停電が起きたりするんです。
ある日、私ともう二人のケニア人スタッフでパソコンの作業をしなければならない日があって。
プロジェクト参加者の氏名・性別・年齢といった情報をExcelに打ち込むという圧倒的に面白くない仕事だったんですが、「期限が迫ってきているので早めによろしく」というボスからの指令のもと、3人で黙々と作業をしていました。
確か、3人で500人ほどのノルマでした。私は急な停電で全ての作業が泡と消えることが怖かったので、こまめに上書き保存することをしつこすぎるくらい勧めたんですよ。
作業を初めて3時間くらい経ったころでしょうか。案の定、停電が起きたのです。
すると2人が突然大声を上げて笑い始めました。
「どうした…?」
「やばい。ちょっと待って。保存してない。やばすぎwww」
「…」
上書き保存をすることをあれだけ勧められたのにも関わらず、一度もしていなかったという事実がツボにはまったと言ってずっと笑ってるんです。
さすがに「ふざけんなよ」と不貞腐れていた私に、彼らは「面白かったからいいじゃーん。ネタになったからいいじゃーん」と満面の笑みで言い放ちました。
そこに悪気も全くなく、本当に楽しそうにしているんですよ。
意味不明ですよね。
それでも人間と言うものは不思議なもので順応していくんです。
私が日本に帰国する直前に高熱を出して病院に行ったんですね。
結局ただの風邪だったんですが、鼻水をすすりながら心のどこかでマラリアにかかることを期待していた自分がいたんです。
「マラリアだったらネタになる。笑える」と思ってたんですよ。
何か辛いことや嫌なことがあったときも、後でそれを笑いに変えられればそれでよいっていう考えはくだらないかもしれないですけど、結構面白いですよね。
個性がないことを恐れて、小さなことに悩んでいた自分は、海外での体験を経て少しずつ変わっていきました。
オーストラリアからは「みんなが皆違うから面白い」ということ、ケニアからは「たいていのことは笑っていれば何とかなる」という授業を受けたような気がします。
今となっては。
就職活動を経て。自分自身が知らぬ間に変化していたことを実感
日本に帰国するとすぐに就職活動がはじまりました。
皆が黒髪になり、リクルートスーツを着て、「御社の…」とか言い始める例のアレです。
私自身ももちろん真剣にやっていましたが、どこか楽観的な部分もありました。
「私はこういう人間です」「私はこういうふうに考えます」と伝えた上で、その会社に落ちてしまったらそれはそれでしょうがないし、結局落ち着くべきところに落ち着くだろうとぼんやり考えていたからです。
結局、どこに行っても楽しいと思うようにもしていましたね。
それでも周囲にはその就職活動に悩まされている人も多くいました。
「あの人は○○社に内定したのに、私はダメだった」
「俺は学生時代頑張ったことなど何もない。お前は意識高くていいな」
「XX社の就職偏差値って△△なんだって。私の会社より全然凄い」
こういう弱音や愚痴を聞く機会がとても多かったんです。
比べる必要のないことを比べたり、考える必要のないことを考えたりして悩んでいる友人と話していると、自分自身のことを認めることができなかった昔の自分が思い出されました。
そして、たまたま、私がちょっとした偶然の積み重ねで肩の力を抜くことができるようになっていたことを改めて意識したんですよね。
私が変わったきっかけはたまたま海外にあったのですが、それが必ずしも海外である必要はないと思います。
日本でも海外でも、周りに自分の個性を認めてくれる人や適当に楽しそうに生きている人がいるかによって生まれる違いは大きい。
そしたら自分がきっかけを提供できるような存在になりたいなと考え始めました。
そんなことをぼんやり考えていたときに、キズキ共育塾の代表である安田さんの記事で「やりたいことは、社会的に苦しんでいる人が自己肯定感を持って生きていけるようにすること」という言葉を目にしたんです。
これは面白そうと思ってすぐに応募しました。
自分のことを認めてもらうには
私は講師として初めて半年程度なので偉そうなことは言えないのですが、生徒さんの長所ややる気スイッチを見つける作業は大切にしています。
「私なんて…」「俺なんて…」が「もしかしたらできるかも」「少しがんばってみてもいいかも」と思ってもらえるようには何が必要かという部分ですね。

例えば、「ゲームばっかりやってて英語は何も分からない。ダメだ」と言っている生徒さんに対しては、単に「この単語を覚えて」と言うのではなく、「今から10分間でこの中の単語何個覚えられるかゲームしてみよう」といった方がやる気になってくれるんです。
その方が本人も何となく楽しく勉強できるし、結果的に自分でも単語を覚えられたという自信になりますよね。
そういった自信の積み重ねで生徒さんが以前よりも明るい表情になると、こちらとしても嬉しくなります。
私は経験も浅く、劇的に上手く教えるような技術はないので、些細なことでも楽しみながら自信をつけさせるための工夫は追求し続けていきたいです。
メッセージ
私はたまたま海外での非日常的な経験から、日本で抱いていた悩みを克服することができました。
私にとっての「海外」が非日常的な空間だったのと同様に、不登校や引きこもりの生徒さんにとっては「キズキ共育塾」も物凄く非日常的な空間ですよね。
外出をして、塾に行って、挨拶をして、座って何かを教わるという一つ一つの作業は、誰しもが簡単にできることではなく、彼らからしたら物凄く大きな挑戦の連続だからです。
そして、非日常的な空間に飛び込むことは、物凄く怖いことだからこそ、それだけ可能性を秘めています。
何かを変えようと勇気を振り絞ってくれた生徒さんに対しては責任を持って全力で応えて、自分のこれまでの経験を何らかの形で還元しなければいけないなと日々痛感しますね。
私が彼らの価値観を変えるきっかけを与えるのは、めちゃくちゃ難しいのは事実です。
ただ、しんどいときに「あんなこと言ってる人もいたなぁ」とふと呼吸を落ち着かせることのできるような存在にはなれるのかなと…。
「小黒とかいう適当な奴が何か言ってるなあ、自分でもどうにかなりそう」って思ってもらえれば万々歳です。
生徒さんひとりひとりと向き合いながら、彼らに対して勉強だけではなく何を教えることができるかを追求することは、確かに普通の塾講師よりも大変な仕事かもしれません。
一方で、じっくりと向き合うからこそ、生徒さんに教えることができることも、逆に彼らから教えてもらうこともとても多いですね。
これまでも様々なアルバイトをしてきましたが、これまでとは違った学びをたくさんもらっています。
教えることが好きな人、自らの挫折経験を何かに活かしたい人、ソーシャルビジネスに興味がある人、一般的なアルバイトに飽きた人、動機やきっかけが何であれ得るものは必ずあります。
キズキ共育塾で働くことに少しでも興味を持った方、ぜひ一度足を運んでみてください。
